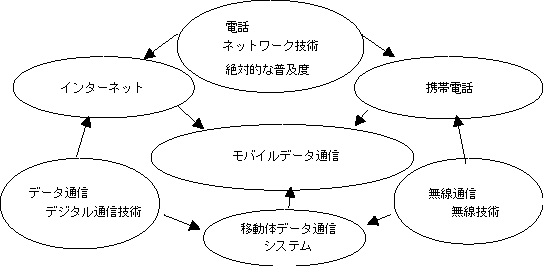
2.1.導入に当たって(モバイル環境に関する事前知識)
(1)モバイルとは
モバイルとは何か、日本語で言えば移動体通信です。つまり一個所に固定せずにどこでも電話をかけたりコンピュータのデータを送ったり受けたりできる仕組みのことです。その中でもモバイルと特に強調する場合は単なる電話ではなくパーソナルコンピュータなどに代表される情報機器を使ってデータをやり取りするシステムを指すことが多いです。
このモバイルを良く理解して更に自由に使いこなすにはまずどんな物とどんな使い方があるかの実際の例を知ることとこのモバイルがなぜ動くのかという簡単なしくみを知ることが役に立ちます。
(2)モバイルの実例
今実際に使われているモバイル機器で皆さんに一番身近なものは携帯電話やPHSでしょう。携帯電話もPHSも大きくは同じしくみと考えて良く従来の電話のしくみの先に無線で通信できる仕掛けを加えたものです。この携帯電話は世の中の技術の進歩につれて次々に新しい仕掛けが導入されて、最初の単なる電話から今は文字データを扱ったりインターネットに接続することができるようになってきました。普及台数も目覚しく日本国内では国民3人に1台くらいまでになってきています。
最近は携帯電話の影に隠れた感じがしますが少し前まで盛んに使われたポケットベルも立派なモバイルシステムです。ポケットベルも最初は単純に呼び出しをするだけでしたが文字情報を送受信できるように進化しました。
携帯電話よりもっと複雑な使い方をされるものにPDA(パーソナルデジタルアシスタント)といわれるものがあります。
PDAはパーソナルコンピュータと基本的なしくみでは同じですが目的を日常のビジネスに必要なものに限定して使い方を簡単にしたものと考えてください。その分機械も小さくなり電池の寿命も延びて携帯機器として使いやすくなっています。PDAではスケジュール表、メモ帳、電話番号帳、などの機能を持ちさらに通信機能を生かしてほかの機械とデータをやり取りしたりインターネットを使ったりすることができます。PDAも最初は文字データを処理するだけでしたが、今はカメラの機能を持って画像情報も扱えるような形に進化しています。
このようにモバイルの機械を見て面白いのはどんどん機能や使い方が進化していくことです。電話機は発明されて以来形や性能は進歩しましたが話をするという機能ではまったく変わりませんでした。しかしモバイルではわずか数年のうちに新しい機能が考えられそれを使った新しい使い方が工夫され、更に新しい使い方が新しい機能を求めるという繰り返しで進化していきます。
これらの新しい使い方は 場合によると世の中のしくみを変えてしまうほどの力を持つこともあります。例えばPDAやモバイルパソコンを使うことで会社の自分の机の上のパソコンを使わずにどこでもいつでも電子メールのやり取りや仕事に必要なデータを扱うことができて携帯電話で連絡もできるとなると、なにも仕事をするのに必ず会社に行かなければならないということがなくなります。どうしても必要な時にだけ会社に行ってあとの時間は自宅やお客様のところで仕事をするようなことも可能になります。
(3)通信について
モバイルに限らず通信という言葉が良く出てきます。通信とは相手に情報を伝えることで広い意味では手紙なども通信ですがここではモバイルに関係する無線通信、ネットワークなどを中心に述べます。
通信では間違いなく相手を探し出してそこだけにつなぐこと(接続)と送りたいデータを能率良く正しく送ること(伝送)の2つが大切な機能になります。
まず接続ですが通信するそれぞれの機械が自分自身の番地(アドレス)を持つことが必要です。モバイル通信では基本のしくみは電話のシステムを使うのでこのアドレスは電話番号になります。長い電話番号は覚えにくいし指定するのに手間がかかるのでインターネットでアドレスは電話番号とは違ったもっと人間に分かりやすい、例えば名前などの意味を持った形であらわされることが多いのです。これらはシステムの内部で電話番号に変換されてから接続されています。電話のように場所が固定される機械のアドレスは例えば東京は03といった場所をあらわす番号と機械の番号を決めてこれを交換機というアドレスを判断する機械が覚えておくことで接続できるようにしています。一方モバイル通信では機械がいる場所が決まりませんからアドレスで場所をあらわすことはできません。このために全部の機械が自分の番号を持っていてモバイルシステムがそれぞれの機械が今どこにいるかを常に監視しておいて接続するときに相手を探し出します。
次に伝送ですがデータの送り方にデジタルとアナログという2つの方式があります。細かなことは省きますがアナログ方式は伝送の能率がデジタル方式より悪く雑音にも弱い欠点があり今は大部分がデジタル方式になっています。デジタル伝送ではデータはパケットと呼ばれる決められた形の固まりに分割されて送られます。パケットには伝送途中で雑音などにより内容が狂うことを防ぐ仕掛けなど伝送されるデータを正しく保つ工夫がされています。また重要なデータに対しては暗号に変換して送る場合もあります。
(4)情報機器のモバイル接続
現在パーソナルコンピュータやPDA等の情報機器をデータ通信に使う場合 これらの機器にモバイル通信の機能が内蔵されているケースは少なく、大部分はデータ通信機能を持った携帯電話あるいはPHSとケーブルで接続されています。中には自分で電話機能を内蔵してモバイル接続機能を持つアダプターもありますがあまり普及してはいません。
2.2.モバイル情報端末の動向
先にも書いたようにモバイルの世界で扱われる情報には音声とデータがありますがここでは主にデータの通信に関して説明します。
(1)モバイルデータ通信の市場
ここでは現在モバイル通信関係の市場の大きさがどのくらいになっているかを説明します。モバイル通信の基礎になる携帯電話台数は全世界で4〜5億台が出荷されています。これは世界中の赤ちゃんから老人まで全部合わせて大体15人に1台という大変な数です。 日本では携帯電話を契約している人や企業の電話を合わせると利用者は5000万人を越えているといわれています。つまり2人に1台になっていることになります。日本で初めて携帯電話が使われたのは1987年頃でこの年の利用数は数十万台ですから10年で100倍近くまで増えた勘定で固定電話の数を追い越す勢いです。一方PHSは550万台、ポケットベルは50万台程度の普及台数になっています。
これだけ携帯電話が普及した結果ほとんどどこでもいつでもモバイル通信が可能な状態になりました。これらの携帯電話やPHSの利用者の内PDAやパーソナルコンピュータとつないだ形でモバイルデータ通信を利用している割合は携帯電話で10%、PHSで30% 程度と推定されていて、合わせて数百万人程度の利用者になります。この数は急速に増加していて2001年には2000万人を越えるのではないかと言われています。
一方モバイル通信に使われる機械の方はパーソナルコンピュータが年間1000万台出荷されていて、その内半分程度がノートパソコンです。PDAは年間300万台近く出荷されています。この内ノートパソコンの20%PDAの30%くらいはモバイルデータ通信に使われておりこの割合は年々増えています。
以上のいわば本格的なモバイルデータ通信に対してiモードに代表される簡易型とでも言うべきデータ通信も急速に増えてきています。
これらの通信は携帯電話を端末にしてインターネットへのアクセス、eメール、天気予報などの情報提供、ゲーム、占いなどの簡単な会話型サービスなど幅広いメニューを揃えていて若い人中心に人気を得ています。また10円メール、ショートメールといわれる電子メールサービスも数十万人の利用者があり専用のポケットボードのような商品も出現しました。現在iモードの利用者は400万人程度、ポケットボードの利用者も数十万人に達しています。これらのモバイルデータ通信利用者を全部合わせると今でも1000万人くらいの人が何らかの形でモバイルデータ通信を使っている勘定になります。
(2)モバイルシステムの歴史
現在のモバイルデータ通信は最初からモバイルデータ通信として発達してきたわけではなくいくつかの重要なシステムが個々に発達し、それらを統合するような形で今のモバイルデータ通信の世界が開けてきました。
モバイルデータ通信の発展相関図
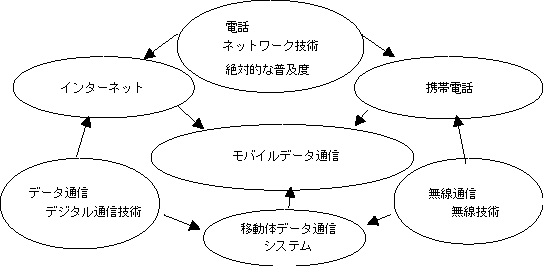
たくさんある電話の技術のうち特に重要なのはネットワーク(通信網)という考え方です。これは沢山の電話が同じ回線網につながれ、通信(通話)をしたいときに相手の番号(アドレス)を指定することで相手を探し出して接続し通信ができること、この時接続された同士以外にはまったく影響を与えず、もちろん通信内容も漏れないことなど網の目のように結ばれた回線を共有して沢山の電話機が間違いなく確実にいつでも通信ができる技術です。データ通信では固定的に設置された通信回線を使います。これは実際には電話回線を使う場合もあります。ここではどんなデータもデジタルデータとして扱います。このデジタルデータを高速でどんなに遠距離でも送ったり、雑音で不良になったデータを検出したり修復するなどの技術はモバイルデータ通信にもそのまま使われます。
無線通信では使用する電波の性質が重要で沢山のデータを送るためには高い周波数が必要になります。この高い周波数を扱うことは難しい技術で無線技術の歴史は周波数への挑戦の歴史でもあります。無線通信の特徴は電波が例えば電話線の中を流れる電流のように閉じ込められずあたりに広がっていくことです。この特徴がモバイルを可能にしているのですが、一方同じ電波を皆んなが同時に使うと混線する欠点があります。つまり電波は同じ周波数を使って同時に沢山の通信をすることは難しいためにその数を制限するなどのルールが必要です。このルールの中で最適の使い方を工夫することになります。携帯電話もその歴史の中で技術の進歩につれて使う周波数が変わってきています。
移動体データ通信システムの発展
早い時期から開発され、計算機システムの保守関係者が使用するなどの業務用に使用されています。これらはデータ専用に設計されているために性能は良いのですが、一方で利用者数が限られるため料金が高くなる難点があるようです。
| 名称 | 特徴 | |
| 1988年 | テレターミナル(日本) | 最初の商用サービス、9600bps |
| 1990年 |
ARDIS(米国) RAM(米、欧) |
モトローラ開発 保守サービス利用 19.2Kbps エリクソン開発 19.2Kbps |
| 1995年 | Ricochet(米国) | 拡散スペクトラム、高速パケット100Kbps |
携帯電話利用のモバイルデータ通信
携帯電話の普及に合わせてパーソナルコンピュータあるいはPDA等の情報機器との接続機能を開発して携帯電話を情報機器の無線データ伝送装置として利用するシステムが現れました。この組み合わせシステムは携帯電話の技術的発達と利用者増加に伴うサービスの拡大で急速に普及し、今やモバイルデータ伝送の主力になっています。
簡単に歴史を振り返ってみます。
| 1990年ころ | アナログ携帯電話接続 |
| 1993年 | デジタル携帯電話 PDC 9.600bps |
| 1996年 | PHS接続 PIAFS 32Kbps |
| 1997年 | DoPa パケット交換 28.8Kbps |
| 1999年 | PHS 64Kbps サービス |
| 1999年 | iモードサービス |
(3)モバイルデータ通信機器の歴史
モバイルデータ通信機器の形態
モバイルデータ通信機器には大きく分けて次のような形態があります。
パーソナルコンピュータについて
1980年代半ばに出現したパーソナルコンピュータは半導体、記憶装置等の部品とソフトウェアの進歩で急速にその容量と速度を向上して当初の初心者や趣味用から業務用へと発展しました。モバイル通信の観点からは1986年に携帯型パーソナルコンピュータであるラップトップコンピュータが出現したことが歴史的転換点になりました。その後小型化が進みノートパソコンと呼ばれるようになりサイズはB5サイズまできています。一方処理能力もデスクトップ型パソコンと比べて実用上は遜色無いレベルに達しています。
| 1970年代 | ミニコンピュータの時代 |
| 1975年頃 |
マイクロプロセッサの発明 マイコンの出現です 8ビットから16ビットへ進化 |
| 1980年代 | パーソナルコンピュータへ発展 |
| 1986年 | ラップトップパソコン登場 |
| 1990年代 | 32ビット化 |
| 小型高性能 | |
| 爆発的普及 | |
| モバイル接続 携帯電話 PHS |
PDAの歴史
PDAは個人の生活、仕事の助けになる小型端末といった機械です。具体的に期待される機能は小型端末にしては盛り沢山で
手書き文字入力
通信機能
携帯に便利な大きさと重量
簡単なユーザ操作画面
- 電池で長時間動作
などで考え様によってはパーソナルコンピュータ以上の機能もあります。
PDAの起源は電子手帳です。電子手帳は日本で1980年代後半から盛んに使われるようになりました。機能的にはメモ、スケジュール、電話番号帳、辞書などたくさんありますが当時の機械は単独で使用される設計でデータ通信はあまり考慮されていません。
1993年に米国アップルコンピュータ社がニュートンという革新的なPDAの構想を発表しPDAの新時代が始まりました。ニュートンの構想では上記の色々な機能に加えて操作を助ける人工知能的な機能も考えられました。この後多くの機械が色々な新しい試みを乗せて出現しましたが結局パーソナルコンピュータとの比較で小さい機械ではあまりややこしい機能は使いにくいとの結論で今は使い勝手のいい機種が使われています。
| 1980年中頃 | 電子手帳 |
| 1993年 |
ニュートン PDAの呼び名定着 |
| 1990年中頃 |
Envoy, MagicLink など HP-LX, ザウルス PalmPilot |
モバイルを考えた時にPDAと携帯電話機能を一体化しようとすることは自然の成り行きといえます。今まで色々と試みられており現在のiモード対応の携帯電話機あるいは後で詳細を説明する次世代携帯電話なども簡易型のスマートフォンに入れることができます。この種の機器の利点は小型軽量で携帯に便利であることですが、その反面表示や入力の能力に限界があることが難点です。このため機能的に電話と電子メールなどの実用的な機能だけに限定されるようです。
| 1994年 | SIMON (米国) |
| Communicator9000(欧州) | |
| 1997年 | Genio (日本) |
| 1996年 | Pinocchio (日本) |
| DataScope (日本) | |
| 1999年 | iモード |
(4)アプリケーションの動向
モバイルデータ通信を用いて実現されるアプリケーションは大きく分けて一般利用者が個人目的で行うコンシューマ向けと事業目的で使用されるビジネス向けがあります。更に最近はこの両方の融合した部分も発展が期待されています。
- コンシューマ向けアプリケーション
電子メール … インターネットと接続することで電子メールが利用されています。パーソナルコンピュータあるいは高機能のPDAを用いる場合は入出力とも十分な機能があるので標準の電子メールが楽に利用可能ですが、携帯電話のように機能に制限がある場合は文字数、文字種を制限するなどある制限条件内での利用となることはやむを得ません。
電子メールに関してモバイルの特質を生かした使い方にプッシュ通信あるいはインスタントメールと言われる使い方が盛んになると考えられます。これは従来の電子メールがサーバに蓄積されて受信者が見に行くことで始めて着信がわかりメールを読めるのに対して、メールが着信するとすぐにサーバがメールを受信者の端末に送り込み、受信者に着信した旨を知らせることでほぼリアルタイムにメールのやり取りができるもので、まさにモバイル通信を生かしたものといえます。このインスタントメール機能は固定設置のパーソナルコンピュータが接続される一般のインターネットでも24時間つなぎっぱなしが常識の米国では普通のサービスになりつつあります。
ホームページ閲覧… インターネット上の各種ホームページ(WWW:World Wide Web)を参照する機能で通信速度の向上とともにモバイル環境でも実用的になってきました。
現在はまだ使用できる通信の速度が十分に速くないために大量の情報を見ることはやや困難ですが、近い将来世界標準として展開される次世代携帯電話IMT2000では速度が大幅に向上しますから動画の伝送も可能になるなど、モバイルだからと我慢する必要はなくなります。どんな応用があるかについては一般のホームページを見る、といった家庭内などの固定機器と同じなのはもちろんですが地図案内、ホテル・レストラン情報、交通機関の時刻表等のモバイルに適した実用情報の利用が盛んになっています。
コンテンツ配信… 音楽、キャラクターのデータなどをデータ通信で端末に取り込んで鑑賞したりするサービスで、通信の速度の向上で実用的になってきました。これから盛んになるアプリケーションです。 決済業務… これからのアプリケーションとして期待されるものに各種支払いの決済があります。例えば物品の購入時に端末を銀行のシステムに接続して自分の口座からお店の口座に代金を振り込むことで買い物が現金なしで行えるようになります。またこの種のアプリケーションの例として株式の売買をモバイル環境で行うことも最近盛んになりつつあります。これらは今後キャッシュレス社会の進展とともにますます増加するアプリケーションです。
ビジネス向けアプリケーション
ビジネス向けアプリケーションは基本的には移動中も会社あるいは客先と情報をできるだけリアルタイムに共有する目的で使われます。
| 電子メール … | これはコンシューマ向けの電子メールと類似していますが、接続先をインターネット以外に会社に設置された社内のネットワークのLANを選択する場合が多くあります。 |
| データベース… | 例えば会社の業務に必要な情報を色々な観点で探しやすく使いやすい形でまとめて記録しておくデータベースと言われるものは会社などの業務上欠かせないものになっています。これもモバイル通信を使ってどこにいても会社に設置されたシステム内のデータベースから業務に必要なデータを引き出すあるいは作業などの結果をすぐにデータベースに書き込むといったことでデータの更新を早くすることができるとデータベースの有効性が増すので積極的に使われています。例えば保険会社の外交員がモバイル端末を持ち歩いてお客の所で保険の契約業務を行うなどは代表的な使い方です。 |
| グループウェア… |
職場で働く人が各種の書類、スケジュール、メモ帳などをシステムに入れておいて皆んなで共有して常に最新のものを活用できるようにすることが行われます。 これは一般にグループウェアと呼ばれる機能です。従来LAN接続されたシステム内で行われていましたが最近はモバイル環境にも拡張されて、いつでもどこでも利用できるようになりました。 |
| 新しい試み… |
電子商取引関連、自販機管理 これからの新しいアプリケーションにはモバイル通信の使い方が単に通話あるいはデータ通信に終わらずにもっと色々な社会活動に直接間接に関わるような使い方が始まっています。これらのアプリケーションは広い範囲に影響を与えて仕事や生活のあり方を大きく変えていくことでモバイルデータ通信の決定的なアプリケーションになると期待されます。これらの期待される応用の一つにキャッシュレスシステムがあります。これは本人認証などのセキュリティ機能と決済限度額などの情報を記憶する機能を備えた携帯電話機にいわば電子財布としての機能を持たせるもので、モバイルデータ通信機能で銀行あるいはカード会社と連携して物品、サービスの購入代金の支払い機能を与え、購入の現場ではレジスターあるいはPOS端末と近距離通信機能(後述)で接続することで切れ目の無い決済サービスを提供するものです。買い物だけでなく電車や劇場の切符手配、病院の診察申し込みなど幅広い使い方が考えられます。 またモバイルデータ通信の面白いアプリケーションとして自動販売機などの管理を行うものがあります。これは自動販売機内に携帯電話の通信機能を内蔵して内部のジュースなどの在庫数、庫内温度などを適宜センターあるいは配達車両に通信することで最適の管理を行うものです。自動販売機のように設置場所の関係で固定的な回線を利用しがたいものには最適の手段です。 |
モバイルアプリケーションの発達段階
実質的には携帯電話としてスタートしたモバイル通信の実用化はいまや単なる通信の枠を超えたアプリケーションの段階を迎えようとしています。
このような発展段階を図式化しました。
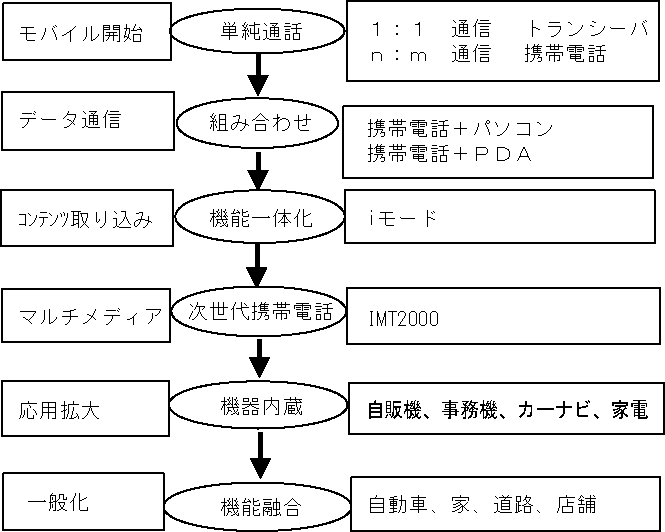
|
|
次へ → |