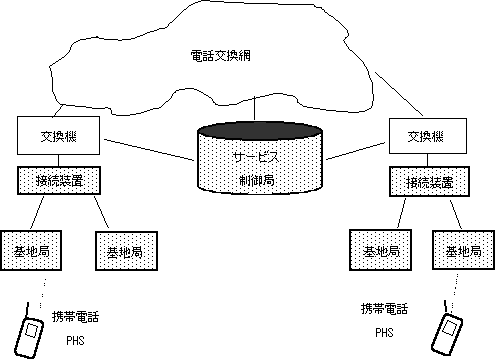
(1)携帯電話、PHSシステムとモバイル利用
携帯電話、PHSシステムの基本的なしくみ
携帯電話、PHS システムのしくみは、基本的に今までの電話システムの先に、電波で通信するしくみを加えたものと考えてください。
下図で網かけの部分が携帯電話、PHSに固有の部分です。
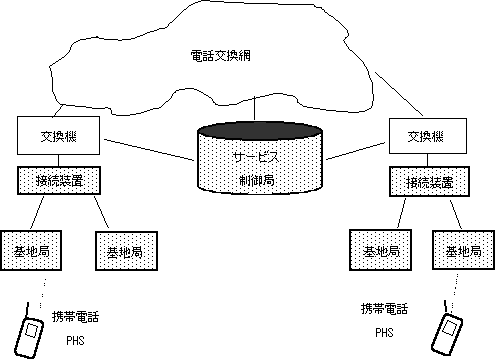
電話網 : 固定電話の通話ネットワークで交換機を多数接続したもの。 交換機 : 通話要求のあった電話機からの宛先番号を解釈して、正しい相手の接続されている交換機へ電話網を経由して回線を接続する。反対に他の交換機から通話要求が届けられた場合は、相手先の電話機を接続して呼び出しを行う。 移動体通信の場合は相手の電話機がどこにあるか固定ではないので、番号をサービス制御局に渡して現在相手がいる場所の基地局までの経路を探させる。一方で通話内容は交換機経由で電話網に渡して相手の基地局につながる交換機まで届ける。 接続装置 : 動体通信の基地局と交換機間の橋渡しを行う。 サービス制御局 : 登録された携帯電話、PHSが今どこにいるかを常に管理する。また通話に伴う料金の計算などを行う。 基地局 : 携帯電話、PHSと電波で通信し電話網のための信号に変換する。基地局は原則として電波の届く範囲でお互いに切れ目が無いように設置される。この電波が届く範囲は携帯電話では数km、PHSでは数100m程度。
端末の位置の検出
モバイル通信では携帯電話などの端末機は移動するので、システムは常にすべての端末がいる場所を把握していなければなりません。このために電源が入っている端末は常に弱い電波を出して基地局に自分のいる場所を知らせています。この情報はサービス制御局に集められて位置情報として管理されます。
ローミング
モバイル通信のサービスは複数の会社が提供しているので、端末のいる場所によっては異なった会社、システムの間を橋渡しすることが必要になります。これはローミングと言われる機能で、国内だけでなく海外とも行われる場合もあります。
機器との接続
携帯電話、PHSをパーソナルコンピュータあるいはPDA等の情報機器と接続するには、データを音声と同じアナログ信号として電話の音声通話機能を用いる場合と、デジタル信号のまま携帯電話またはPHSのデジタル接続機能を使う場合とがありますが、現在は圧倒的にデジタル方式が多いです。接続する場合は情報機器側にアダプタを装着して、ドライバーソフトを入れます。そして携帯話電機とは専用のケーブルで接続します。後述する近距離無線通信が取り入れられた場合はケーブルが不要になり使い勝手が向上します。
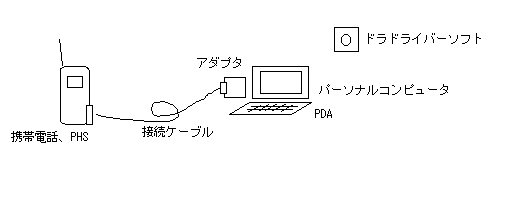
伝送方式
データ伝送には回線交換サービスという一旦回線を接続するとデータの有無に関わらず接続時間で課金されるサービスと、接続時間に関わらず伝送するデータ量に対して課金されるパケット交換サービスの2種類があります。以下にこれらの種類をあげます。
| 速度 | 方式 | システム |
| 9.6Kbps | 回線交換 | 携帯電話 |
| 9.6Kbps | パケット交換 | iモード |
| 28.8Kbps | パケット交換 | 携帯電話 |
| 64Kbps | 回線交換 | PHS |
| 14.4Kbps | 回線交換 | cdmaOne |
| 64Kbps | パケット交換 | cdmaOne |
(2)iモードサービスのしくみ
iモードについて
iモードとは携帯電話にインターネットのホームページを見るブラウザの簡易版を搭載してインターネットのアクセスを可能にしたシステムです。iモードには専用の情報(コンテンツ)を提供するサービスがたくさんあり利用者の人気を集めていて、1999年2月にサービスを開始して年末には300万台に迫る急速な普及を達成し電子商取引(EC)の普及の切り札としても期待されるサービスになっています。
- システム
図の網がけの部分がiモードに固有の部分です。
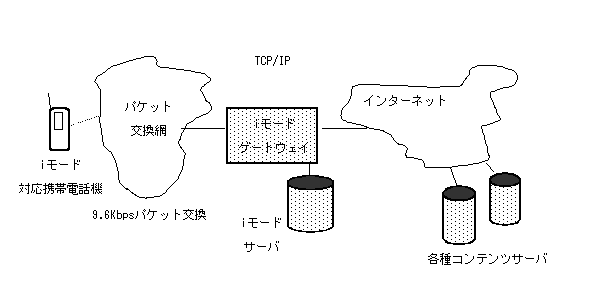
端末
iモードは携帯電話の表示文字数などを多くしてパケット交換機能を持ったハードウェアにWWWブラウザを搭載した端末機を用います。
ブラウザ
インターネットのホームページを閲覧するにはHTMLに対応したブラウザを用いますがiモードサービスではコンパクトHTMLと称する簡易版を採用しています。これは日本のiモード独自の規格で携帯端末の表示の文字数の制限あるいは通信速度を考慮した結果です。このため一般のインターネットのホームページで自由な閲覧ができないのでコンテンツは事実上専用になります。しかしコンテンツを提供する場合は インターネットのホームページを作るのと同じ知識が活用でき、コンテンツ自身も改造可能であることから比較的手軽にiモードサービスに参加できることがメリットになっています。
HTML: Hyper Text Mark-up Language
インターネット接続
パーソナルコンピュータなどをモバイルでインターネット接続する場合は端末がインターネット接続機能を持ち、TCP/IPとい通信手順で接続することが必要ですがiモードの場合はiモードゲートウェイが機能代行を行うので端末は携帯電話のままですみます。
コンテンツサーバ
コンテンツを収納して端末からの要求にこたえるサーバは iモードゲートウェイ接続されるiモード専用コンテンツサーバとインターネット経由でアクセスされる一般のインフォメーションプロバイダのサーバがあります。
サービスの形態
iモードでは3種のサービス形態があります。
| インタラクティブ情報検索… | 特定の情報がほしい時に条件を入力して結果を求める。 |
| プッシュ型情報提供 … | あらかじめ条件を設定しておくとそれに合致する情報が 発生する都度利用者の端末に自動的に送り込む。 |
| 電子メール … | 内容的には通常の電子メールと同様で着信メールを利用者の端末に自動的に送り込む。 |
コンテンツ
iモードを特徴づけるコンテンツは現在合計で4000サイト以上に達しています。これらのコンテンツは取り引き系、データベース系、生活情報系、エンターテイメント系と大別されます。
| 取り引き系 … | 銀行取り引き、証券取り引き、クレジットカード、保険、航空券購入、書籍販売、ホテル予約など |
| データベース系 … | レストランガイド、タウンページ、乗り換え案内、時刻表、料理レシピ、辞書など |
| 生活情報系 … | ニュース、天気予報、株価情報、雑誌、メールなど |
| エンターテイメント系 … | キャラクタ関係、ゲーム、占い、カラオケ情報、写真、音楽など |
料金及び請求
iモードを利用する際の料金は通信料金とコンテンツにかかる料金の2つがあります。通信料金は使用したパケット数に応じてかかりますがコンテンツ利用料は現在使った量に応じた料金ではなく月ぎめの固定料金になっています。この料金のうち通信料金は電話会社から通常の携帯電話料金として請求されますがコンテンツ利用料金はコンテンツあるいは個々のサービス提供会社が自身で請求する場合と、電話会社が請求を代行して電話料金の請求時に併せて請求する場合とがあります。
同種のサービス
iモードサービスは日本のNTTドコモ社のサービスですが同種のサービスにWAPといわれるものがあります。WAPサービスではインターネットにアクセスするのにインターネット標準のHTMLを採用しており世界的な標準に沿っています。このために利用上は便利ですが現在は日本国内ではiモードほどの利用者はいません。
WAP: Wireless Application Protocol
(3)IMT―2000サービスの概要
IMT−2000に関して
IMTは International Mobile Telecommunication 国際携帯電話通信 の略です。つまりIMT2000は2000年から始まる国際携帯電話標準です。IMT2000は国際通信機構 ITU といわれる通信に関する国際標準規格などを協議して決めている、いわば通信の世界の国際連合のような組織が今後の携帯電話の世界統一規格として定めたものです。
以下に書くようにIMT2000の開発の目標は大変意欲的なものです。
:全世界で通用するパーソナルマルチメディア通信
:大容量で柔軟な電波管理
:色々な環境に対応する広範囲の利用可能性
:高速伝送
:安全性
:低消費電力
:経済性
:拡張性
仕様
通信速度は端末の移動速度によって3種類が決められています。
| 屋内(停止) | 2Mbps |
| 低速度移動 | 38.4Kbps |
| 高速度移動 | 14.4Kbps |
速度の非対称性:
インターネットの使い方は一般にデータを要求する上りのデータ量はさして多くなく、対してデータを送ってくる下りは大量のデータを高速で送る場合が多いので、これに対するためにIMT2000では上りと下りの速度が異なる伝送を考えていて、総合的に通信の効率が上ります。
マルチメディアへの対応:
ビデオ映像のようなマルチメディアコンテンツへ対応するためにカラー画像、動画などマルチメディアデータへの対応が可能です。
期待されるサービス
IMT2000のサービスは2001年に日本で開始される予定で、これが世界最初の実用化になります。携帯電話としての利用あるいはパーソナルコンピュータをつなぐなどはもちろん マルチメディア対応が可能なことを生かしたビデオデータ、カラー画像、音楽などのコンテンツ配信、あるいは電話端末にカメラを内蔵することで携帯テレビ電話などが広範囲に利用できるようになります。もちろんインターネットでホームページを見る場合も今より格段に良い表示性能、表示画面寸法、高精細カラーなどにより実用性が大きく向上します。
またIMT2000が国際規格であることから、原則としてどこの国に行っても自分の携帯電話を持っていけばその土地の携帯電話サービスが受けられるようになります。
WCDMAとCDMA2000
IMT2000を実現する具体的手段として本来は1つの方式に統一されるべきですが、現実には日本とヨーロッパが推すWCDMA方式と、米国が推すCDMA2000の統一ができずに2方式になってしまいました。このためアプリケーションは同じながら通信のレベルで2つの方式が併存することになります。今後はどちらかの方式が他を圧倒して統一されることも想定されますが、技術的には両方の方式を1台の携帯電話に持たせてしまうことも考えられます。
(4)IrDA 通信とはなにか
- IrDA
IrDAはInfrared Data Association(赤外線データ協会)の略でここで決めた赤外線を使った近距離通信の方式のことを一般にIrDAと呼んでいます。
赤外線を送受信する素子は赤外線LED(ダイオード)と赤外線フォトダイオードです。
仕様
通信仕様にはV1.0と1.2の2つがありV1.2の方が高速に対応しています。V1.0はパーソナルコンピュータの標準規格であるPC/ATに対応する仕様でV1.2はさらに高性能を目指して決めたものです。
接続される機器がパーソナルコンピュータ、PDA、デジタルカメラあるいはそれらの周辺機器と幅広いので通信速度は2400bpsから最高4Mbpsと幅広くなっています。
通信可能な距離は標準で1メートル以内です。
通信するデータの形はパーソナルコンピュータ間のデータのやり取りなどのためのデータ伝送と、キーボードなどの周辺機器に使うものとがあります。
使い方
仕様上決められている使い方には以下のようなものがあります。
従来のケーブルを経由するシリアル通信とパラレル通信の置き換え用途として、文字データ、オブジェクト交換(データの中身をかまわずに伝送する手順)、スキャナまたはデジタルカメラのイメージデータ、移動通信機器用として決められた特殊な方法により、機器間でデータ通信を行います。
応用例として公衆電話機や飛行機の座席などにも IrDAの機能が付いたものが現れ、例えば電話ボックスに入って自分のパーソナルコンピュータのデータを赤外線を使って送ることもできるようになってきています。
(5)ブルートゥース近距離無線通信とはなにか
ブルートゥースとは
携帯電話、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ゲーム機などをケーブルレスでつなぐ近距離無線通信システムです。これはスウェーデンの携帯電話機メーカが開発の中心となり現在世界で1600社以上の色々な会社がブルートゥースを採用していくことを発表しています。特徴は
:近距離に限定することで送信電力が小さくて、事業用免許を必要としない。
:消費電力が小さく電池が長持ちし軽薄短小の携帯機器に向く。
:電波の性質として雑音に強い。
:世界標準規格を目指している。
特許で使用制限する、あるいは使用料を取るといったことをせずに皆んなが同じ規格でシステムを作り、結果として大きな利用の世界を作る。
さらに世界の各国の政府の電波を管理する部門がブルートゥースが使用する周波数帯の利用を許可して同じ規格で世界中で通用させる。
仕様
| 周波数 | 2.4GHz 帯 | |
| 伝送方式 | 周波数ホッピング、 スペクトラム拡散 | |
| チャンネル | 79チャンネル 1MHz 幅 | |
| 伝送速度 |
最高 1Mbps |
|
|
実質データ速度
|
対称伝送 432.6Kbps 非対称 下り721Kbps/上り 57.6Kbps |
|
| 音声チャンネル | 64Kbps 3チャンネル | |
| 通信可能距離 | 標準10メートル | |
| プロファイルの種類 | プロファイルとはブルートゥースの応用毎にデータのやり取りの手続き等を決めたもので、いくつかの例を挙げます。 | |
|
||
| これらのプロファイルは 例えばIrDAのように従来あったやり方を取り入れて開発の手間を少なくする工夫もされています。 | ||
期待されるアプリケーション
ブルートゥースは免許が不要であること、世界標準として各種の機械に一斉に採用される流れであることから、いずれは身の回りの機器に広く使われることが期待されています。ここではその中から早いうちに実用化されるであろうアプリケーションをいくつか紹介します。
| 携帯電話 … |
ブルートゥースが最初に装備されるのは携帯電話になります。携帯電話メーカは国内も海外も多くのメーカが2000年の内にブルートゥースを載せた携帯電話を出荷開始すると発表しています。当面は携帯電話だけにブルートゥースが載っても使い道はありませんが、以下に説明するパーソナルコンピュータを始め色々な機器にブルートゥースが載せられたときにそれらと接続してモバイルデータ通信をするインフラとして不可欠なものになります。いわば本格的なモバイル通信社会のさきがけとしての役割が期待されます。 データ通信以外に携帯電話の通話機能の面でもたとえば自動車の車内で携帯電話を使う時にヘッドセットと無線接続すると両手での運転を邪魔されずに通話できます。 |
| パーソナルコンピュータ… | パーソナルコンピュータも既に多くのメーカが2000年にはブルートゥースを搭載すると発表しています。まずノートパソコンに載せて携帯電話を使ってモバイルデータ通信をする際に今は必要な接続ケーブルが不用になります。この結果モバイル通信をするときに携帯電話をわざわざ取り出さなくとも10メートル以内であればかばんの中でもポケットでも机の上でもどこにあってもパーソナルコンピュータと接続してモバイル通信ができるようになります。またデスクトップパソコンでもブルートゥースを採用することでキーボードやマウスといった入力機器あるいはプリンタ、スキャナなどの周辺機器をワイヤレスで接続することができて使い勝手が向上します。 |
| デジタルカメラ… | 撮影した結果をパーソナルコンピュータに送り込んだり、あるいは携帯電話で遠隔地の端末に送るなど画像応用のアプリケーションが期待されます。 |
| オーディオ機器… | 携帯電話と組み合わせて音楽コンテンツの配信を受けてそのまま携帯プレイヤーに記憶させる、あるいは再生するときにヘッドセットに無線で送ることでワイヤレスの通信ができます。 |
| 電子商取り引き… | 店舗のレジスター、駅の改札機、街角の自動販売機、ガソリンスタンドなどと利用者が持つブルートゥース端末とデータ通信することで代金の決済が電子的に簡単にできるようになります。 |
(1)インターネットのしくみ
インターネットはどんな仕組みでデータを相手に届けるのか、ここでは一般の利用の仕方について簡単に説明します。今までのデータ通信システムはシステムを作って運用する会社が接続されるすべての端末を管理していました。例えば全世界で1億台の端末があってこれが世界中に散らばっていて毎日多くの端末が接続を止めたり新たに参加してきたりすることを考えるとこれら全部を間違いなく管理して通信ができるように維持することは大変な手間とお金がかかることになります。結果として簡単に誰でも通信に参加できる、あるいは安い料金で通信を行うことが困難で特定の目的の場合に限られるのが現実でした。
ところがここにまったく違う発想のネットワークの仕組みが出てきました。それはあまり大きな規模ではなくとも接続する端末を自分の近くに持つネットワーク同士が相互につながって結果として大きな地球規模のネットワークになってしまうものです。これが簡単に言えば今のインターネットの考え方です。このネットワークは絵に描いてみると世界を覆う蜘蛛の巣のように見えることから World Wide Web(WWW) と呼ばれます。
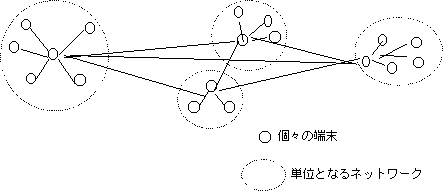
(2)インターネット接続
インターネットでは端末つまり利用者が直接インターネットに接続するのではなく、まずインターネットサービスプロバイダ(ISP)と呼ばれるインターネットの単位となるネットワークの管理者に接続します。この接続には普通は電話網を経由します。
インターネットサービスプロバイダは利用者が希望する相手のアドレスを見て相手が属するネットワークのインターネットサービスプロバイダに回線をつないで利用者が通信をできるようにします。インターネットサービスプロバイダ同士をつなぐ回線はデータ通信線用の高速の回線を使用してルータという装置を使います。これは電話では交換機に相当するものです。
(3)アドレス
インターネットでは端末がすべて自分だけのアドレスを持ってほかと区別できるようにします。これは電話番号と同じ考え方です。このアドレスは実際には数字の列で端末が属するネットワークなどが分かるようになっています。しかし利用者にするとやたらに長い数字の列は何がなんだかわからず覚えることは難しい上に入力するときにも間違えやすくなります。そこで人間に分かりやすい文字で意味があるアドレス名とでも言うものに変換します。このアドレス名はもちろん世界でたった1つだけです。
アドレス名の例は
| http://www.nippon.co.jp | 日本の(jp) 日本という(nippon)会社(co)の ホームページ(www) |
| yamatotakeru@1ban.nippon.ne.jp | 日本の(jp)やまとたけるという人(yamatotakeru)のメールアドレスでnipponというプロバイダの1banという利用者グループ |
このアドレスは皆んなが勝手に付けると同じ名前が出てくるとか世界中のプロバイダに連絡が行き届かず接続ができないなど不都合が起こるので、今はアメリカのアドレスを管理する機関がまとめて管理しています。なお登録は早い者勝ちで希望するアドレス名が既に登録されている場合は別のアドレス名を登録しなければなりません。
またインターネットでは他人のアドレスを使って通信することを防ぐために個人の暗証番号(パスワード)が決められます。
(4)料金制度
インターネットで利用者が負担する料金はプロバイダに払うインターネット接続料金と 端末からプロバイダまでの電話の料金です。インターネット接続料金は インターネットに接続する手数料、各種プロバイダのサービス料金および国内、海外のほかのプロバイダへ接続する手数料と長距離回線使用料などからなっています。インターネット接続料金は自分で遠距離あるいは国際回線を使ってデータ通信することと比較するとプロバイダが沢山の通信をまとめて行っているために大変格安になっています。このあたりがインターネットは国内の電話料金だけで世界中の相手に通信できると言われる理由です。
(5)WWWとeメールのしくみ
WWW自身はインターネットの接続の仕組みを指す言葉ですが、一般にインターネットのサイトあるいはホームページを見る仕掛けをWWWといっています。WWWの使い方などは後でくわしく説明しますのでここではインターネットの主要な目的であるWWWと電子メールについて簡単に述べます。
ホームページはインターネット上で皆に見てもらいたい情報を載せる仕組みです。ホームページは希望すれば誰でも個人でも今は簡単に持てるようになっています。情報を載せる機械をサーバといいますがこれは自分の機械でもいいですし、あるいは契約しているプロバイダのサーバのサービスを使ってもできます。ホームページの情報は一般にHTMLと呼ばれる規則で書きますが、それ以外にビデオ動画などは特定のソフトを使うこともあります。 いままではホームページには文章や絵、動画、音声などをあらかじめ書き込んでおいて希望する人がそれを見たり聞いたりするだけでしたが、最近は同じホームページにアクセス(つないでいる)利用者同士でチャットと呼ばれる文字を用いたリアルタイムのおしゃべりなどもできるようになってきています。
もう一つのインターネットの利用のしかたである電子メールは情報を伝えたい相手を指定して情報を送る仕掛けでインターネットの手紙に相当します。情報の伝達をしたいときに相手のアドレスをつけたメールをプロバイダに送ります。プロバイダはアドレスが指す相手のプロバイダのサーバに(メールサーバといいます)メールを送ります。相手はメールを見たいときにサーバに見に行くことで電子メールが伝達されます。今はメールの本文は文字情報ですが添付書類といってワープロの書類、図表、絵、ビデオなど色々な形の情報を付けて送ることができます。
電子メールは受信者が見に行くことが必要なのですが今後端末が24時間つなぎっぱなしの環境になるとメールがサーバに届くとすぐに端末まで送り込んでくるインスタントメッセージといわれる仕組みが増えるかもしれません。
|
|
次へ → |