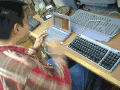

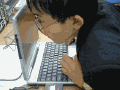
大阪府立盲学校 中島康明
モバイル活用の利点は、いつでも、どこでも、だれでもが必要な情報を入手、活用、伝達できることである。一方で、視覚障害者にとってコンピュータとネットワークの利用は、デジタル化された情報へのアクセスによる新しい学習の可能性を持っている。またインターネットやモバイルの活用は障害者にとっての情報バリアフリーを実現するものとして期待されている。
このことは単に情報の受発信が便利になるということを超えて、健常者と同じ情報に、自らの手でアクセスし、情報をコントロールできる事を意味する。これからの教育においての学習環境を考えたときにパーソナルな情報聴きとネットワークの利用は必須の条件となる。
さらに従来の学習の場は、線でネットワークに接続された端末の前に固定されていた。モバイル環境では自由に移動できる端末が高速でネットワークに接続されることが可能になった。
この実証実験では、情報バリアを克服し、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできる学習環境を構築することをめざして、障害に対応するよう拡張したモバイル端末を、ワイヤレスでインターネット(LAN)に接続して、マルチメディアデータを含む情報をやり取りできる環境を構築し、それによってどのような教育効果が期待されるかを検証した。
2-1
モバイル端末(パソコン)をLANおよび公衆回線への接続用PHS電話機と無線LAN一式
(AIRCONNECTシリーズ 簡単導入パック WLA-PCM2他)
2-2
モバイル端末(視覚障害生徒が使えるように拡張)
a.主に全盲生徒用小型携帯型パソコン(ソニー バイオC1 PCG-C1XE)
音声化ソフト(95Reader)(ホームページ・リーダー
b.主に弱視生徒用ノート型パソコン(シャープPC-PJ2-X4)
画面拡大ソフト(ZoomText(R) Xtra)
音声化ソフト(PC-Talker)
c.主に重複(知的障害)生徒用携帯型パソコン(アップル iBook)
ジャンボエディタ他
d.その他のモバイル端末パーソナルモバイルツール(シャープMI-EX1)
拡大表示機能付き
e.マルチメディアデータ作成用カメラ 2台
シャープインターネットビューカム<VN?EZ1>
その他補助バッテリー等
本校は大阪府立の盲学校として地域における視覚障害者の教育機関として80年以上の歴史を持ち、地域の視覚障害教育のセンター的役割をめざしている。組織的には大きく分けて幼小学部、中学部、高等部(本科、専攻科 4コース、5専攻科)と寄宿舎にわかれる。年齢は3歳から50歳をこえる人までいる。在籍数約200名(18歳以上が3/4)、教員1数十名である。
ネットワークに関しては、平成4年度開設の全国で唯一の情報処理専攻科におけるパソコン通信の利用からダイヤルアップ接続を経て、平成8年度には情報処理科職員室、準備室と実習室をLAN接続しイントラネットの運用を開始した。平成9年度の校内ネットワーク検討会設置、大阪府教育ネットワーク開設(センターへのダイヤルアップ接続)、公式ホームページの開設、平成10年度の校内ネットワーク委員会(ML)設置、OCNエコノミーによる常時接続開始を経て、文部省「光ファイバー網による学校ネットワーク活用研究」の指定をうけ現在1.5MBでインターネットに接続している。
平成11年2月のedドメインの取得とともに現在のドメイン(osakapref-sb.ed.jp)に移行、今年度から、校内ネットワーク利用に関する規定等の整備、視覚障害者関係のメーリングリストの開設、府立高校とのテレビ会議による共同授業を年間通して行いさらに、子供放送局、ETO99等のインターネット活用プロジェクト等に参加するとともに校外も含めた視覚障害者支援技術情報の提供もおこなっている。校内研修会も教員向けから生徒向け、PTA向けへと拡大している。平成12.1末で校内のサーバー5台、接続端末約60台、発行済みアカウント80である。校内LANはコンピュータ実習室(6台)のほか寄宿舎、図書室を始め特別教室、普通教室等あわせて約15箇所に独自で配線している。視覚障害を持つ教員も多数いるが情報化への取り組みについてはむしろ積極的である。
4-1
モバイル端末の設定
各モバイル端末の音声ソフトのインストール、ダイヤルアップ等の設定を視覚障害者自らが設定する。
さらに視覚障害をもつユーザーの立場から各種操作について使いやすさ、操作の可・不可、画面の見やすさ等についての評価をおこなった。
習熟した者であればほとんどすべての設定が自分で可能である。
一部のソフトとハードで音声化等の不具合があった。
4-2
単独行動時の遠隔支援
テレビ会議システムを利用することにより、離れたところからの状況把握、サポートをリアルタイムに行える。このことにより単独行動を支援できる。
校内LANへ無線接続したモバイル端末でテレビ会議を使いながら電波状況の確認、歩行時の利用をおこなった。電波の到達範囲は予想よりも良好で壁越しの廊下、階段、屋外等アンテナが見通せる場所で約50m、壁や床越しは2-3枚(2教室)程度の範囲で利用できた。これにより教室内はもちろん、複数の教室や屋外での同時利用も出来ることが分かった。全盲者は通常足音の反射音も利用しながら歩行するので、歩行しながらのテレビ会議による支援は困難であることが分かった。
生徒の感想文
Subject: 無線Lanの実験
皆さん、こんにちは。
日本で初めて?の実験に参加したIです。
無線Lanで接続されたVAIOを持って、
ネットミーティングを使って、
準備室にいる人と話しながら学校の中を歩きました。
音声もクリアでなかなかいい感じでした。
建物の中では、準備室に近いところでないと使えないようです。
準備室の近くの階段は、2階までなら大丈夫。
二階から降りようとしたところでだめですね。
外に出るとグランドでも大丈夫。
しかしそこまで行く間はだめです。
視覚障害ということからくる問題点もいくつかあります。
いくらパソコンが小さいといっても持って歩いていくのは大変かな?
歩くときに手がふさがってしまうのは不便だと思います。
ヘッドセットを使って会話をするわけですが、
片方でも耳がふさがると、分かっているところでも歩きにくい。
周りの感覚が分かりにくいです。
寒くない日は外でインターネット、
これで決まりですね(笑)。
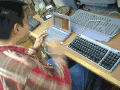
|

|
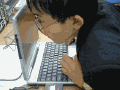
|
4-3
教室におけるモバイルの利用
電源、LAN接続のための線が必要ないことから、端末の自由なレイアウトが可能である。また随時端末の移動が可能であり、移動時も配線に引っかかることによるよる転倒、機器の破損等の危険がないことが確認された。
またデジタル化された教材をネットワークを通じて配受信し共有することで、視覚障害の程度に応じて音声化、拡大、色調変更等をおこない個々に応じて利用しやすくまた確実に情報を伝えることが出来た。
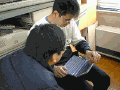
|
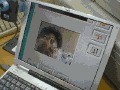
|
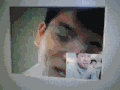
|
4-4
| 屋外での自然観察。画像をメールに添付して送る。 | ||

|
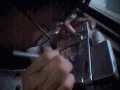
|
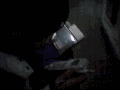
|
| 幼稚部横にて春をみっけました。 T男 | ||
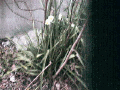
|
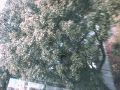
|
|
|
中学部の上からとりました。この嵐が過ぎるといよいよ春です。
|
||

|
|
|
|
元気に遊ぶ子供達 E男
|
||
|
つめた一い F男 |
||
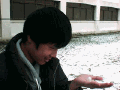
|

|
|
4-5
家庭学習支援
寄宿舎を含む家庭での補習、自主学習、担任への連絡等を電子メールで行った。
長期休暇中等3?30日の期間モバイル機器を貸し出した。
のべ9人。
冬休み中のモバイルプロジェクトよう掲示板への書き込み例
| Reply Delete | No. 23 99/12/31 23:37 | |
| Name | k男 | |
| Title | どんと焼き | |
| Message | 家の近くの神社で毎年行われているどんと焼きの様子を撮ってきました。 | |
| Image |
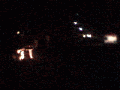
|
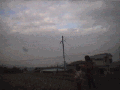
|
生徒からのメール
PHSを使わせていただいてs男
まず、率直な感想としては,自分のようなデスクトップパソコンを使っているも
のにとってこのPHSをつかう送信方法は机の上で簡単にできるのでいいことだと思います。
電話線やLANのあるところまで行かなくてすむので大変焼くにたちました。
また実家に帰るときはこれを使うと楽にメールのやり取りができるのでしょう。
しかし、電話が応答しませんとか、エラーとかが多かったのでつながらなかっ
た。ことが多く勉強をしている間にメールのやり取りがあるのを忘れることもおおかった。
そこで今後、つながり易い送受信ができるのであったら今後も使用したい。
では失礼します。ありがとうございました。
4-6
学校外行事等の取材
校外行事時の報告、連絡、相談
学校教育活動の広報のためのマルチメディアコンテンツの取材、作成、転送
校外学習、出張先、JR、地下鉄の駅を含む多地点でのデータの作成と送受信をおこなった。
あびこ観音まつり、合同就職説明会、情報教育と就労に関するフォーラム等

|

|
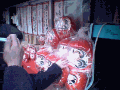
|
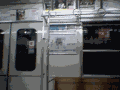
|
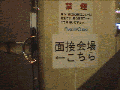
|
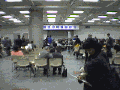
|
文章の作成は長いものは困難であるが短い文章と画像を送信することが出来た。
これにより校外行事時のリアルタイムな報告が可能であった。
長期の休み中もメール等による交流が可能になり生徒の生活実態の把握、学習支援等情報の共有が出来た。
放課後も授業の続きを自主的に学習し、ホームページの作成に取り組むなど学習に対して積極的になった。
モバイルプロジェクトのページ/mo1を参照
適切なハード、ソフトを組み合わせることにより視覚障害者も自らモバイル環境の利用が可能であることが確認できた。
ワイヤレス、マルチメディア、パーソナルな情報ツールのを活用することにより、情報バリアフリーの実現が現実のものとなり、自ら意欲的に学ぶための道具として活用できる可能性が示唆された。
今回は時間の関係もありすでにスキルの相当高い者を対象におこなったが、機器の設定、操作にはある程度の習熟を必要とする。
また機器の発展は日進月歩であり、より身近で誰にでも、いつでも使えるよう環境を整えていくことが必要である。
今後は幼稚部を含む多様な発達段階、障害の状況に応じた活用のノウハウを蓄積し、さまざまな学習場面での検証、実践をすすめたい。
現時点で計画中ものは
遠足、校外学習でのリアルタイム交流 幼稚部、小学部、中学部、高等部
普通教室における授業で、黒板にかわり教材提示、伝達、情報共有して学習のツールとしての利用 中学部、高等部、専攻科
家庭、寄宿舎での自主学習支援 高等部、専攻科
視覚障害者の外出支援
|
|
次へ → |