○グループごとにパソコンを操作しして問題を解決する。
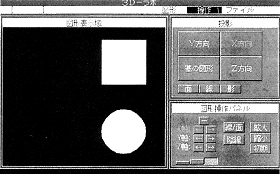
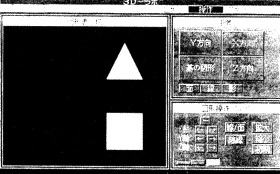
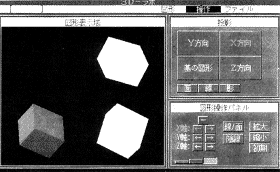
○一斉指導
○真正面と真上の影の組み合わせでなければ,2つの影から正確に形を読み取ることはできないことに気づかせる。
○教師実験で図形を回転させ,そのときの影のようすを観察させる。
| 学 習 活 動 | 活動への働きかけ | 備考 |
| 1.影の形から考えられる立体をできるだけたくさんみつける。 | ○角柱の後ろからOHPで光を当ててスクリーンに影を映し出す 。 | ◎3Dラボ |
| 2.本当の形を確かめる方法を考える。 | ○真上から光を当てた影が必要なことに気づかせる。 | |
| 立 体 の 2 つ の 影 か ら 形 を 読 み 取 ろ う | ||
| 3.学習活動の方法を知る。 | ○ソフトの立ち上げ方,操作方法について実演しながら解説する。 | |
| 4.いろいろな立体について,真正面と真上の影をもとに形を読み取る。
○グループごとにパソコンを操作しして問題を解決する。 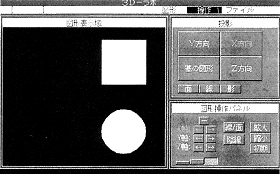 |
○机間指導
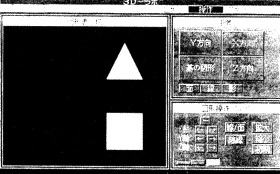 |
|
5.正確に立体を読み取るために必要な光の方向について考える。
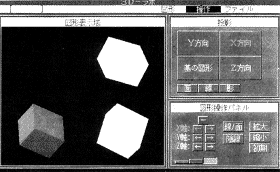 |
○早く終わったグループにはワークシートを配布し,個人解決させる。
○一斉指導 ○真正面と真上の影の組み合わせでなければ,2つの影から正確に形を読み取ることはできないことに気づかせる。 ○教師実験で図形を回転させ,そのときの影のようすを観察させる。 |
|
| 学 習 活 動 | 活動への働きかけ | 備 考 | |
| 1.問題を把握する。 | |||
| 厚 紙 で 三 角 柱 の 名 札 を 作 ろ う | |||
| ○提示された間隔系の三角柱の名札を見る。 | ○用途を明らかにし,制作意欲を高めたい。 | ||
2.課題をつかむ。
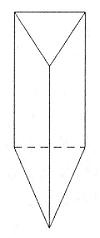 |
○展開図が書ければ良いことに気づかせる。 | 三角柱模型 | |
3.コンピュータの画面を見て三角柱の展開図の構成を考える。
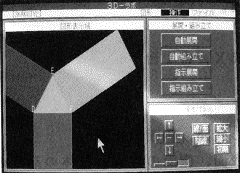 |
○見えない部分について展開されていく様子を思い浮かべることにより,考えるように助言する。
○提示した様々な三角柱の展開図をもとに整理させてもよい。 |
◎3Dラボ
・自動展開により展開する。 あらかじめ拡大しておいたものを用意し,展開すると画面よりはみ出してしまうものを利用する。 また,このソフトは,同じ立体でも2度目は同じ展開図にならない。このことを利用し展開図の多様さにも気づかせたい。 ・理解できない児童のために画面に入る図形も用意しておく。 |
|
4.展開図を考える。
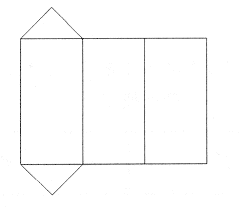 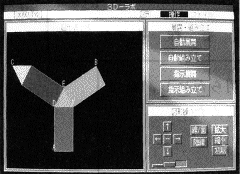 |
○フリーハンドで描かせる
○考えがまとまらない児童には,コンピュータで展開図の概略についての支支援を行う。 ○黒板に発表させ自分の考と比較させる。 ○組み立てられない理由について考えさせる。 |
・組み立てられないものの展開
例 |
|
5.展開図を描く。
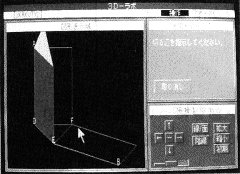 |
○描きやすいものと描きにくいものがあるので技能や取り組みによって,助言や指導をする。
○作業にかかれない児童には,励ましの言葉を与えたり,コンピュータを使って確認をさせる。 |
画用紙
はさみ セロテープ マジック ◎TXT 展開図確認 ソフト (自作) |
|
| 6.組み立てる。 | ○完成品には,自分の名前を入れさせる。 | ||
| 7.まとめる。
三角柱の展開図は,側面の3つの長方形と底面の2つの三角形からできていて,三角形の辺の長さは側面の長方形の辺の長さによって決まる。 |
○様々な展開図の分類を通して,効率的な展開図を作成する必要性を理解させたい。 | ○三角柱の模型
A−展開図の周囲が1番短いもの B−展開図の周囲が1番長いもの |
|
| 8.次時の予告を聞く。 | ○円柱が制作できるか投げかける。 | ||
 平成7年度市販ソフト実践事例集
平成7年度市販ソフト実践事例集