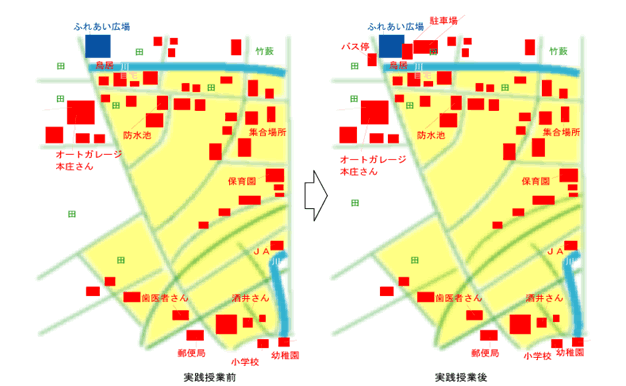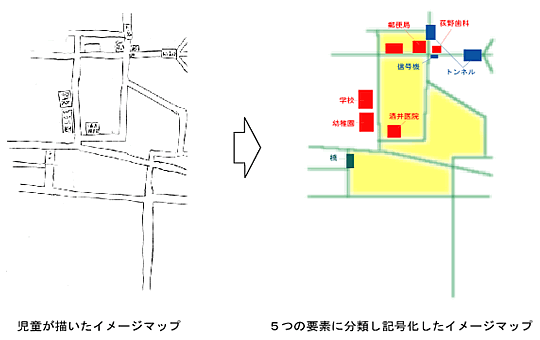
| 6.評価 |
6.2 教育モデルとしての評価(授業の目的達成度評価)
6.2.1 イメージマップ調査による実践授業の評価
ここでは、プロジェクト実施前と実施後の空間認知の度合いを検証すべく、イメージマップ調査を実施した。イメージマップとは「頭の中の地図」のことで、被験者に地域の地図を記入してもらい、空間認知の度合いを測る手法である。調査は進修小学校と熊野川小学校の2校における小学6年生を対象とし、それぞれ授業の始めと終わりに別紙用紙を渡して記入するよう求めた。解析ではイメージマップを「パス」「街区」「ランドマーク」「エッジ」「ノード」の5要素に分け、それぞれ記号化を行い、個別に各要素の変化を把握した(下図参照)。また、全ての児童が描いた要素を合計し、授業の前後で数値比較を行った。
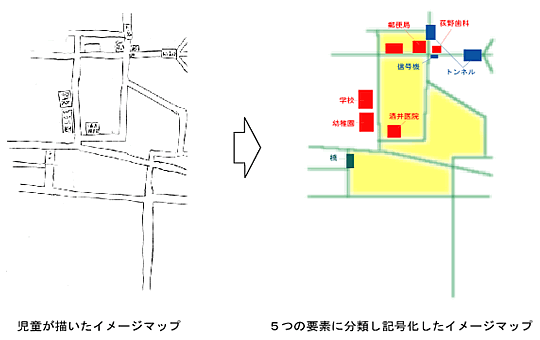
■ 学年全体の評価
下図は進修小学校における児童25名の、イメージマップから抽出した5要素の変化を示す。この図より、全ての児童の情報量は伸びていることがわかる。特に、ランドマークに関わる情報の伸び率が1.55と最も高かった。これは、携帯カメラによる調査では地点を撮影することが多く、また、GISマップの表記も点で示されていることから、点的要素であるランドマークの情報が、児童の地域イメージに多く取り入れられたものと思われる。しかし、一方でパスや街区に関する情報の伸びもそれぞれ1.31、1.43と高かった。点としてのランドマークの情報だけでなく、地域を歩き周りマップで整理することで、地域イメージが領域として拡大したものと思われる。
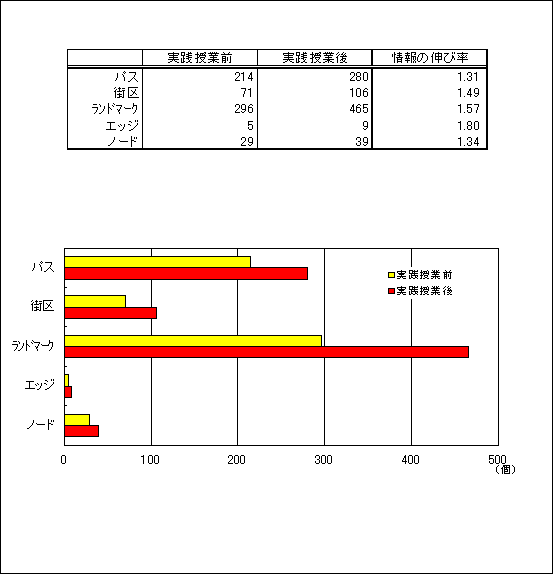
進修小学校におけるイメージマップから抽出した5要素の変化
■ 個人の評価
ここでは、個人イメージの変化のうち特徴的な変化について考察を行う。
(児童E)
児童Eの個人イメージの変化を捉えると、パスが8要素、街区が1要素、ランドマークが19要素と情報が伸びていることが分かる。特に、学校側の橋からパスが伸び、さらに街区を挟んで南部へパスが伸びていることから、児童Eの地域イメージは拡大したといえるだろう。
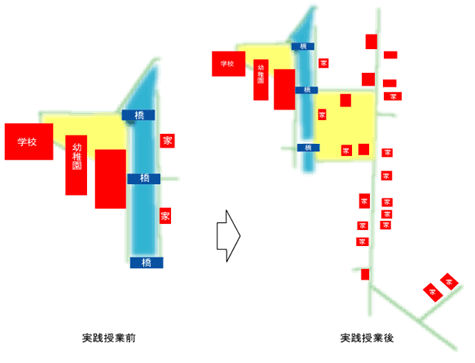
(児童N)
児童Nの個人イメージの変化を捉えると、パスが6要素、街区が6要素、ランドマークが5要素と情報が伸びていることが分かる。特に学校や幼稚園の大きさが、実践授業前後で変化し、また他の建築物との相対的な大きさの関係についても考慮して描かれていることから、数量的な情報の伸びだけでなく大きさの把握も達成されたものと思われる。
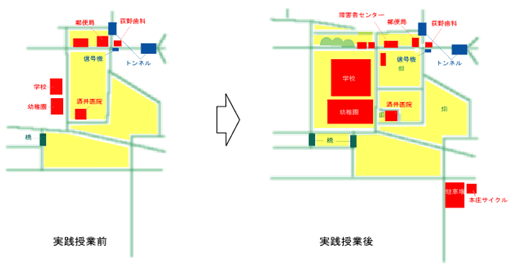
(児童V)
児童Vの個人イメージの変化で特徴的なこととして、ふれあい広場周辺を調査によって、その周辺建物が詳細に記録されていることである。今回の実習によってランドマークに対しての認識が高まったが、特に調査エリアの建物やストリートファニチャーのイメージが強く残ることが伺えた。