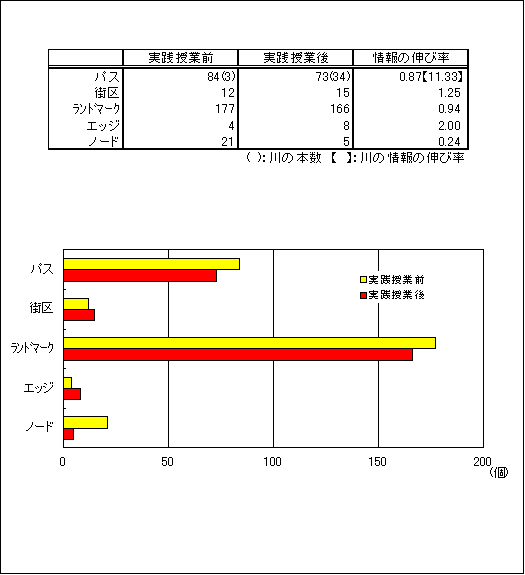
| 6.評価 |
6.2.3 熊野川小学校におけるイメージマップによる授業評価
■ 学年全体の評価
下図は熊野川小学校における児童14名の、イメージマップから抽出した5要素の変化を示す。熊野川小学校では進修小学校と異なり、パス情報の伸び率が0.87、ランドマーク情報が0.94と情報量が減少していることがわかる。一方、川に関する情報量は実践事業前で3本だったにも関わらず、授業後には34本に増加しており、伸び率は11.33と大きな変化が見られた。GISマップを見ながらの交流授業を多くとったことが、広域の地域構造を把握するまでに至ったものと考えられる。
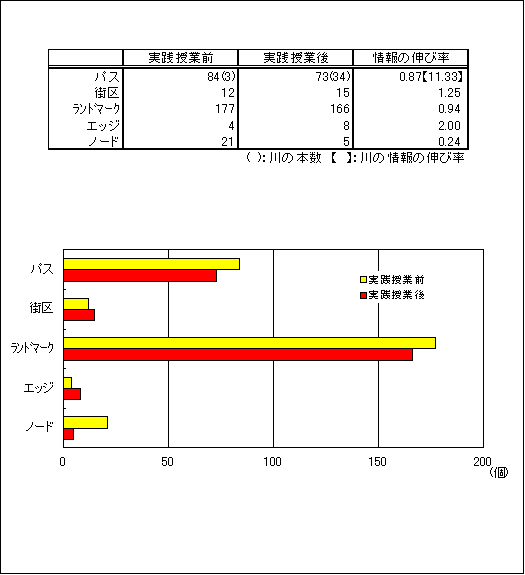
熊野川小学校におけるイメージマップから抽出した5要素の変化
■ 個人の評価
ここでは、個人イメージの変化のうち特徴的な変化について考察を行う。
(児童CC)
児童CCの個人イメージの変化を捉えると、パスが2要素(川:4要素)、街区が1要素、ランドマークが19要素と情報が伸びていることが分かる。特にイメージの領域が県境まで拡大し、河川も正確に描かれていることから、本授業が地域イメージの拡大に貢献したことがわかる。また、友達の家が20カ所描かれているが、これは中山間地域における人間のランドマークに対する認識の特徴と見ることができ、児童にとって友人の家は地域の重要なランドマークとして機能していることが伺える。
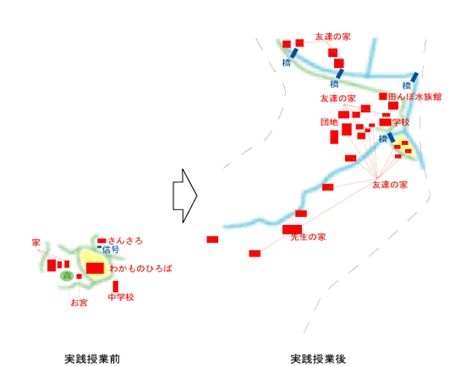
(児童EE)
児童EEの個人イメージの変化を捉えると、パスが5要素減少しているが、ランドマークが8要素増加している。友達の家が11カ所描かれていることから、児童CCと同様に重要なランドマークとして機能していることが伺える。また、遊び場の調査で森での遊びが抽出されたことから、マップ上にも遊び場として活用している森が描かれた。他にも児童GGやKK、LL、MMにも遊び場である山が描かれており、児童の地域イメージの中に遊び場が加わったことから、進修小学校と同様に本授業で扱ったテーマに沿ったエリアが刻まれることが分かった。
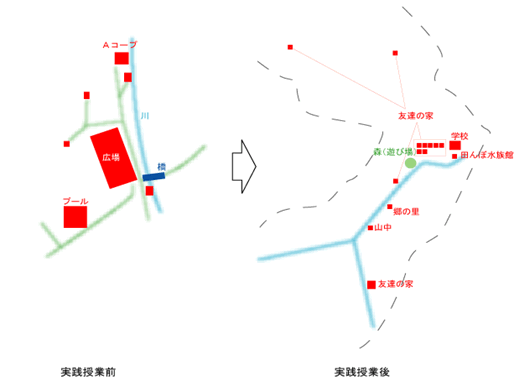
(児童HH)
児童HHの個人イメージの変化を捉えると、実践授業前には描けなかった地図が描けていることが分かる。交流授業などGISマップを活用することで、県境と縦断する河川、ランドマークとしては友達の家など身近な家々が特に認知され、地域イメージを構造化する力が付いたといえるだろう。
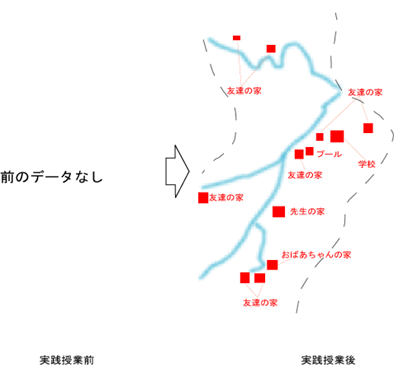
以上のイメージマップ調査から、児童の地域に対するイメージは大きく変化することがわかり、本実践授業は児童の地域認識力の向上に貢献したといえるだろう。
各学校での評価を整理すると、熊野川小学校では、交流授業などGISマップを見ながらの授業を経ることで、児童の地域イメージは河川を軸にして広域に広がることが伺えた。また、ランドマークやパスなどの情報量は減少したが、地域のスケール感に応じた情報量であるといえ、交流授業などGISマップを用いた授業時間を長くとることで、広域の地域イメージの形成が可能になるものと思われる。一方、進修小学校のように広域のマップを見ながら考察する時間が短くとも、自分たちが調査したエリアへの広がりは確認できたことから、空間認知力は向上したといえる。また、空間構成要素の増加だけでなく建築物の大きさを修正するなど、より正確な環境情報を把握する力も付いたものと思われる。
今回の調査によって、ネット社会におけるフワフワした身体感覚ではなく、この2つのツールを用いた身体感覚は、まちが体の一部になるほどのリアルな感覚を伴っていると考えられ、この2つのツールは結果的に地域への愛着心を芽生えさせるものであるといえるだろう。