「酸性雨/窒素酸化物(NOx)調査プロジェクト」
|
学校における教育実践は、その大部分が学校の中に留まってしまう。ネットワークの教育利用は、これを打開する切り札と期待されたが、学校をはじめとする教育機関の体制が整わず、いまだ第一歩を踏み出したばかりである。本プロジェクトは、酸性雨や窒素酸化物の測定を核にして、ネットワークを利用した新しい教育システムを総合的に開発しようとするものである。
本年度の取り組みの概要を表 2-1に示す。
|
表 2-1 本年度の取り組み概要 |
|
作業項目 |
概要 |
|
広げる仕組み作りの推進 |
|
|
広げる仕組み作りのノウハウを収集 |
|
|
全国規模プロジェクト実践マニュアルの作成 |
|
|
ネットワークを利用した新しい教育システムの開発 |
|
これまでプロジェクトは、すべてネットワーク上で行ってきたが、プロジェクトを広げ、深めていくことを考えた場合、ネットワーク上のやり取りのみでは限界がある。そのため、参加校の教師がオフラインで一同に会す「指導者研究会」を開催する。これは、各参加校が、本プロジェクトに参加しつつ地域展開していくためにどのような活動を行っているか、また、活動における留意点・課題等をどのように認識しているか、意見交換したり問題を共有したりすることは重要である。また、専門家による観測の意義や観測方法に関する講義も盛りこむ。このようにしてプロジェクトに対する意識を高めることにより、プロジェクトへの取り組みが活性化、それが波及してプロジェクトが広がっていくことが期待できる。
Webアプリケーションの開発は、本プロジェクトで過去に作成されたものを改良・機能追加することにより行う。これまで本プロジェクトは、30〜40校規模で展開されてきており、Webページ上からデータ登録を行い、データを蓄積する仕組みはできている。生データを蓄積し、授業での活用は教員の創意工夫に任せようと意図したものである。しかし、ネットワークの活用に時間をとられ、教員独自の手で生データを活用することは困難なのが実状である。従って、本年度はデータを授業時にも容易に活用できるよう、データの加工・表示機能を中心に新規開発を行う。また、本年度は参加校を広げることがテーマとなっているため、これまでのようにすべての参加校で観測機器を統一することは困難である。従って、Webページも、多様な参加形態に対応しうるよう、観測機器に応じて柔軟にデータ登録・表示を可能となるように既存登録システムの改良を行った。
本年度の企画では、これまで通り広島大学附属福山中・高等学校が幹事校として、プロジェクトのとりまとめを行い、環境に関する専門家として広島大学からの支援・助言を仰ぐこととしている。また、企業として三菱総合研究所が入り、学校現場のニーズをシステムに反映させたり、三者間の隙間を埋めるための作業を行ったりした。
さらに広げるための仕組みを検討するという意味合いから、参加校の中で独自の活動を行うなど、積極的に取り組んでいる学校をサブ幹事校として選定し、サブ幹事校を拠点とする活動を試行することとした。
このような体制でプロジェクトを遂行していくとともに、よりプロジェクトを深めていくための課題、学校における取り組みを推進するための課題、広げる仕組み構築にあたっての課題などを討議するため、幹事校、サブ幹事校、大学、企業とで推進委員会を組織することにした(図 2-1)。
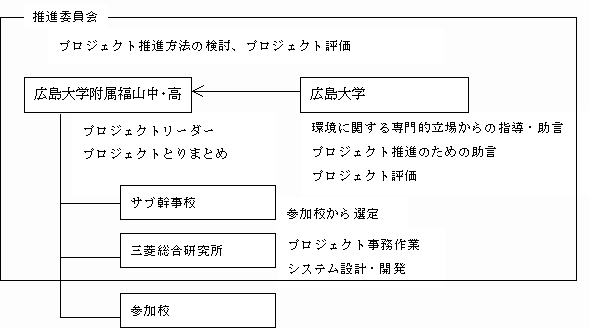 |
|
図 2-1 プロジェクト実施体制 |