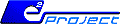 |
→次へ |
|
− 学習者のための情報教育環境に関する調査 − |
→目次へ
4.1.1 インターネット利用環境整備の計画から構築まで
秋田市立小中学校間ネットワーク
「秋田市立小中学校間ネットワーク」(愛称:はばたけ秋田っ子ネット)は秋田市にある小中学校のためのイントラネットである。ドメイン名(edu.city.akita.akita.jp)は秋田市ネットワークのサブドメインであるが、管理運用は秋田市とは別に行っている。
利用対象は市立41小学校(1分校を含む)、21中学校、国立大学病院内院内学級(1学級)、市立病院内院内学級(1学級)。さらに特筆できるのは、私立中学校1校が参加していることである。ちなみに秋田市内には私立小学校はなく、私立中学校はこの1校だけである。国立大学附属学校は大学に接続されているが、インターネット経由で交流しており、市内にある全学校間の連携が図られている。
特徴的なのは、秋田市立学校間ネットワークの企画・構築から管理・運用にいたるまで秋田市の第三セクター「インフォメーションプラザ秋田(略称IPA)」の役割がきわめて大きいことである。秋田市教育委員会はそれらをIPAに全面的に委託するアウトソーシングの形態をとっている。
整備の経過
平成6年、文部省の台数整備計画に基づき、小学校8台、中学校20台のパソコンの整備に着手した。
平成8年になると、教育ネットワーク構築の企画検討が始まった。こねっとプラン(NTT)と「子どもたちにインターネットで夢を送る秋田の会」という地元企業の会からのパソコン寄付があり、この2つのプロジェクトで5校にパソコンが導入された。
企画検討にあたっては、担当者が先進地を視察した(横浜市、箕面市)。
企画当時のシステムの特徴として「テレビ会議システム(フェニックス)」の導入があった。これはISDNを利用するテレビ会議システムであり、過去の調査では「インターネットを利用したテレビ会議システム」という誤解を持った地域があった。しかし、秋田市では「フェニックスはインターネットではない」とはっきり認識しており、『活用の手引き』にもそのように明記されていることは特筆すべきことである。
第三セクターであるIPAにサーバ等のセンター設備を設置し、各学校はIPAにダイアルアップ接続、教育研究所はIPAと専用線接続するというシステムを提案。IPAに対して、サーバ設置・管理・運営を委託する形である。平成9年から「はばたけ秋田っ子ネット」の整備が始まった。提案した時点では、IPAはプロバイダを開業していなかった。
小学校は平成9年7月に工事を開始し、平成10年1月から運用を開始した。また中学校は平成10年7月に工事を開始し、平成11年1月から運用を開始した。
サーバは運営委託先のIPAに設置。学校設置パソコンの保守を含めてIPAに委託している。委託の内容は、設計、設置、調整、工事、運営を含めて「すべて」といってよい。IPAの職員はヘルプデスクもつとめている。このような業務の特殊性から、随意契約になっている。
IPA内の設備は、機種は不明だが、機能的には、ファイアーウォール、外部向けサーバ、内部向けサーバ、コミュニケーションサーバ等を備え、商用プロバイダ(InfoSphere)に接続している。コンテンツフィルタ(WebSence)を利用しているが、その内容は教育委員会で協議して変更している。
各学校内の設備は、1台のWindowsNTサーバ(ファイルサーバ)と3台のクライアントパソコンによる校内LANを構築している。校内の3カ所(職員室、コンピュータ教室、図書室など)にハブを設置し、それぞれ1台ずつのパソコンを配置している。
配置場所は学校が業者と打ち合せて決めた。新しい学校は多目的ホールなど開かれた場所にも設置している。
ISDN回線を使った接続(128Kbps接続)で、その回線はインターネット専用に使用している。学校のネットワークは1セグメントである。
アドレス計画などはIPAに任せている。「教育委員会としては、将来パソコンの台数がいくら増えてもかまわないようにお願いしている」という。
教員の私物パソコンも教育委員会の学校教育課に申請すれば正式に接続を許可している。IPアドレスなどの情報はIPAから教育委員会を通じて学校に通知しているということなので、DHCPにはなっていないと思われる。現在約110台が許可されている。
運用体制
トラブル発生時には学校からIPAに直接連絡をとり、出張で対応してもらっている。平成11年4月〜12月の出張回数は以下の通り。「たった3台ずつのパソコンのトラブルとしては多い」という認識を教育委員会は持っている。※12月は2000年問題対応のために多かった。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
17回 9回 17回 28回 33回 28回 15回 25回 90回
教育委員会は、IPAによるこの出張修理を「訪問研修」として考え、有効に活用している。トラブル対応時に、利用方法に対する相談を受けるなど、研修と同様のことを行っているからである。
学校のインターネット利用に関する統計情報は現在のところ教育委員会は把握していないし、当面は接続時間数を把握する必要性はないと考えている。NTTのi・schoolサービスを利用しているため電話料金が利用時間と比例していない、IPAから利用時間を通知してもらっていない(利用時間による課金はしておらず、異常接続はIPAで対処するため)などの理由による。
4.1.2 インターネット教育利用の進め方について
教員用と生徒用のホームページを分けているイントラネットであり、かつ学校内での接続台数が少ないため、学校事務にも活用している。
平成11年度はCGIによる保健、体育の統計処理サービスを実施。担当教員はLOTUSで入力したデータファイルをWWWのCGIプログラムにしたがってイントラネットにサーバに登録するだけですむようなシステムを開発した。このような、事務合理化向けのCGIシステム作成もIPAとの契約の一部に含まれている。
4.1.3 教育利用のための周辺環境
秋田市教育委員会では「はばたけ秋田っ子ネット」について2つの運用組織を持っている。
「情報教育推進協議会」(略称:情推協)
市教職員の任意団体。情報教育担当主任の情報交換が目的の会合として発足し、平成8年度に現在の形(情報教育担当者の会)に改組した。
平成11年度は研究会を2回開催した。現在の形になってからは、教育委員会も連名(教育長名)で開催の案内を配布している。研究会の内容は、小学校部会は事例発表、中学校部会は操作勉強会がそれぞれ中心になっている。
開催にあたり事前にアンケートをとっているが、メールの使い方や不満点など教育委員会主催の会合では得られないない情報が回収でき、教育委員会の反省材料として役立てられている。
平成12年度は、学期に1〜2回開催に増やしたいという希望を持っている。
「インターネット活用推進委員会」
運用の提言、ガイドラインの見直しなど、「はばたけ秋田っ子ネット」運営方針を決定する。
メンバーは20名程度。会長は秋田大学教育学部教授。構成メンバーは学校管理職、教員(平成10年度の資料ではここまで)。このほか教育委員会から教育研究所所長、学校教育課、学事課に加えてオブザーバとしてIPAも参加する。
年3回ほど開催し、交流学習の成果をまとめて学校に配布するなどの活動もしている。
研修について
研修は秋田市教育研究所が担当している。平成11年度にはコンピュータ研修室に15台のパソコンを整備(10年度までは10台)、次のようなネットワーク関連研修を行った。
研修名 参加者 インターネット初級 61名(各校1名) 特殊学級教員向け研修 44名 授業活用実践のためのコンピュータ活用研修(小学校) 80名(各校2名) ホームページ作成研修(中学校) 24名(各校2名)
このうち授業活用実践のためのコンピュータ活用研修では模擬授業形式を取り入れている。また、これらとは別に教育研究所による自主研修も実施している。
フィルタリング
コンテンツフィルタのWebSenceは当初250ライセンスだったが、教員持ち込み機器などが増えたため現在は1000ライセンスにしている。見たいけれどWebSenceによって見えないサイト、あるいは見えているけれど見えてほしくないサイトに関しては、その都度教育委員会からIPAに連絡してフィルタを更新している。
当初、情報交換に必要なフリーソフトウェアがインターネット経由でダウンロードできないことが問題となった。これはファイアーウォール内のサーバに内部配布用ファイルを置くことで対処した。現在のところ、大きな問題は発生していない。
IPAの存在
IPAは管理職2名、部長、課長、スタッフ4〜5名の小さな会社だが、教育委員会からは絶大な信用を得ている。最初は学校の特殊性を理解していなかったが、最初の2年間で教育委員会は学校の特殊性について細かく説明や指導を行い、それによって理解が進んだという。
学校からはIPAに連絡が行き、IPAで対処できない問題は教育委員会に来るという形である。たとえば、教員のパソコンを校内LANに接続したいという依頼がある。接続方法を知った教員がいない学校からは、IPAに接続依頼が行き、IPA職員が対応する。これはIPA職員が学校を訪問し接続方法を講習するという研修の一種(訪問研修)となっている。
昨年、Happy99ウィルスが発生したが、発見当日にIPAが走りまわって駆除した。このときにIPAの重要性が大きく認知された。
4.1.4 その他
次年度当初予算立案のためのスタッフ会議として「情報教育プロジェクト」を設けている。学校教育課、学事課、総務課の経理・施設の4分担担当者がメンバーで、4月から7月にかけて月に1度のペースで開催する。平成11年度は「中高一貫校」設置の準備がテーマだった。
各分担の問題点、整備時期の調整などを洗い出し、知恵を出し合って調整することで、財政のヒアリングにも備えられる。教育委員会4分担が同じフロアにいるため相互の連絡が密であることが成功の要因であると担当者は考えている。
市役所による学校事務の合理化(市役所のネットワークによる伝票処理事務)にも「はばたけ秋田っ子ネット」を利用する予定。事務用パソコンは2月に整備し、市役所能力開発室による研修が始まっている。対象は栄養職員、事務員の約200名。
小・中学校を結んだ「はばたけ秋田っ子ネット」が完成したので、次はパソコン台数整備に着手する。小学校は多目的教室などへの分散配置方式、中学校はパソコン教室の設備更新(平成12〜13年)を予定。また現在は1校あたり3カ所にハブがあるが、情報コンセントを増やす予定。
秋田市立の高校は現在1校あるが、高校は独自の予算を持っているため、独自にインターネットに接続している。平成12年度に中高一貫校が開校するが、そちらは併設型である特徴を活かし、中高LANを構築する計画である。
【資料】 システム構成図1
システム構成図2
秋田市立小・中学校におけるインターネットの利用に関するガイドライン
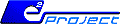 |
→次へ |