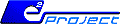 |
→次へ |
|
− 学習者のための情報教育環境に関する調査 − |
→目次へ
4.8.1 インターネット利用環境整備の計画から構築まで
京都市立学校ネットワーク
「京都市立学校ネットワーク」は京都市ネットワーク(city.kyoto.jp)のサブドメインに位置し、京都市情報教育センターが拠点(プロバイダ)となっている。独自ドメインの予定はないが、ktc.ed.jpを予約している。京都市ネットワークとは専用線(1.5Mbps)で接続し、学校とセンターの間は基本的にISDN回線を利用したダイアルアップ接続である。
平成2年度から学校へのパソコン整備を行い、申込制による研修の「夜間講座」をはじめとして継続的に体系的な教員研修を進めてきた。この結果、文部省の平成10年度実態調査 では、パソコンの操作可能な教員は81.2%(全国平均57.4%)、パソコンを使って指導可能な教員は45.3%(同26.7%)と、ともに都道府県・指定都市の中では第1位を占めている。
整備の経過
京都市では教育機器(LL、理科機器、視聴覚機器など)の整備に対する配慮は以前から行ってきたが、教育用パソコンの整備はやや遅れ気味となっていた。まず,台数をそろえるよりもすべての学校にパソコンを導入することを優先し,平成8年度までには全学校に導入した。
平成9年度から小・中学校のパソコン増設を推進する予算が認められ,小学校22台、中学校42台などの整備計画に着手した。平成12年度には全校でこれを完了し、京都市立学校ネットワークにも接続する。
平成10年度には「先進的教育用ネットワークモデル地域事業」(文部省、郵政省)の中で市立学校20校が指定を受け、京都市と京都府下9町が一つの地域として事業を展開することとなり、京都市を核とする地域ネットワークセンターが財団法人京都高度技術研究所に置かれた。
京都市ネットワークをベースにしている
バックボーンに京都市ネットワークがあり、各学校には、京都市ネットワークのアドレス計画の一部を構成するプライベートアドレスを割り当てている。また、ドメイン名も京都市ネットワークから「edu」のサブドメインを割り当てられている。
基本的に各学校は、情報教育センターにISDN回線を使ってダイアルアップで接続(一部専用線接続)している。ただし,先進的教育用ネットワーク整備事業の指定校だけは、情報教育センターと地域ネットワークセンターに接続している。
情報教育センター設立と夜間講座
現在の施設そのものは、もともと高校生の実習を目的に設立された。メインフレーム・パソコンを導入していたが、パソコンが各高校に配備され、情報教育センターでこれを使って実習する必要性が薄れた。
ちょうどその時期に、中学校技術科「情報基礎」の学習に向けてパソコン操作等がカリキュラムの中に組み込まれたことから、施設の有効利用を兼ねて、小学校、中学校の教員を対象とする研修講座に重点を置くようになった。最初の段階から夜間も講座を開設し、内容の充実を図りつつ現在にいたっている。
センター設備について現状のネットワーク関連機器等はファイアウォール、外部向けサーバ、学校用Webサーバ、イントラネット用サーバ、研修用メールサーバ、コミュニケーションサーバ、INS1500×2回線となっている。
- 平成9年5月 京都市とダイアルアップ接続
- 平成9年10月 128Kbpsの専用線接続に変更 WWW、メールサーバを設置
対学校接続用コミュニケーションサーバ(MAX4000)と電話回線(INS1500)を設置
- 平成10年8月 サーバ増強、ファイアウォール設置
- 平成10年10月 高度技術研究所と1.5Mbps専用線に増速
このネットワーク構成については、既存設備を活用しながら予算の許す限り機能アップする方針で設計してきた。
4.8.2. インターネット教育利用の進め方について
メールアドレス
メールアドレスは学校に1つ発行している。専用線接続している学校には、自校のサーバで作成してもらうようにしている。今後、生徒用のメールアカウント、教員用のメールアカウントを要望されたとき、どう対処するかは未定である。
学校ホームページの公開を義務づけている
各学校には学校ホームページの作成・公開を義務づけている。学校の情報を発信し、地域や学校間の交流に役立てることをねらって総合的学習の取組を公開しているところもある。学校がどんなことをしているのかを情報発信していけば、それをもとにしたメール交換などにより、地域や学校間交流に発展していくことも考えられる。
研究指定校などを除いては、授業での直接活用は少ない。どちらかと言えば、教員の教材準備などで資料収集の道具として活用されているケースが多い。
4.8.3 教育利用のための周辺環境
フィルタリングについて
情報教育では、良いも悪いも含めてあらゆる情報を入手できる状態にあるべきで、一方的な情報だけを与えられた子どもは教育されたとはいえないと考えている。情報を取捨選択する能力を培うのも教育課題のひとつである。そのためには、センターが一方的にフィルタで情報をカットするのではなく、各学校で議論される場面を設ける必要があると考えている。
リンクを張る場合について
以前に、幼児ポルノのページから学校のホームページにリンクが張られていると市民から教育委員会に通報があり、情報教育センターで調査したケースがあった。当該ホームページの管理者に連絡をとり、リンクを消してもらったが、これをきっかけに、学校のホームページには「リンクを張る場合は、必ず一声かけてください」という趣旨の掲示をしている。
「ホームページを公開した時点でリンクは自由なはず」というメールも来たが、あえてネチケットとして連絡するよう、学校に掲示する旨の通知をだしている。
ホームページを公開するにあたっての管理組織は,あらゆる面で自主的な対応能力を育成するという視点に立って,校内で組織するように指示している。
研修の機会を多くする
研修の機会をできるだけ多く設定するように努めており、その中心となっているものは次の2つである。これ以外にも、希望者を対象にした「夜間講座」を実施している。
- パソコンの導入時研修
パソコンはレンタル契約により5年に一度更新している。導入・更新時には、導入時研修(2回)を各学校で実施する。これは,各学校の機器を使用して研修するため,高い効果がある。
小学校では、更新時期の異なるパソコンが混在しており、同一校に6年間勤務していると2、3回の研修機会がある。- 指名研修
小学校は採用年数が3の倍数の教員(平成9〜11年度),中学校は採用9、10、19、20年目の教員を対象とした指名研修を夏休みに実施している。
夜間講座の開講時間は午後6時〜8時であるが、実質は9時近くにまで及ぶという。平成10年度は夜間講座の当初計画は26講座であったが、希望者が定員を大きく上回ったので、2倍の52講座に増やして対応した。受講者数はのべ1940名であった。ちなみに京都市の教員総数は6691名である。
「パソコンで何ができるのか」に主題を置き、すぐに役立つ(授業に生かせる)研修になっている。
このような研修の推進と、それを支える情報教育センター職員の熱意が、教員のパソコン操作・指導可能率の向上につながったと考えている。
平成10年度の研修の実施状況は以下の通りである。
研修対象 研修名 講座数 開催
日数のべ
日数参加者数
(のべ人数)小学校 パソコン基礎研究会 6 1 6 242(242) 導入校指導者研修会 1 1 1 68(68) 採用1年目教員研修会 1 1 1 22(22) 導入時研修(10年度導入校) 41 2 82 820(1,640) 中学校 養護学校 教務主任パソコン研修会 1 1 1 27(27) 採用10・20年目教員基礎研修会 5 1 5 169(169) 採用1年目教員研修会 1 1 1 14(14) 導入校指導者研修会(中33校対象) 1 1 1 33(33) 導入校情報基礎担当教員研修会 1 1 1 34(34) 教科別夏季研修講座 8 1 1 283(283) 導入時研修(10年度導入校) 33 2 66 825(1,650) 高校 採用1年目教員研修会 1 1 1 4(4) パソコン基礎研修会 1 1 1 22(22) その他 パソコン新任校長研修会 1 1 1 34(34) 養護教員パソコン研修会 2 1 2 78(78) 養護育成教育パソコン活用講座 1 1 1 37(37) 事務職員・事務員研修会 4 1 4 84(84) 中・指導主事研修会 1 1 1 8(8) 情報教育アドバンスコンクールパソコン活用実践報告会 1 1 1 243(243) 全校種(夜間講座) パソコン入門 52 1〜3 69 1,524(1,940) クリエイティブライター2 Windows95 表計算基礎 パソコンミュージック スーパーYUKI インターネット入門 画像利用 プレゼンテーション入門 ホームページ作成 合計 163 − 254 4,571(6,632)
マスの効果
研修施設は人員的に限界に近く、初心者対象の講座内容は,日頃の職場内での自主的な学習に委ねていきたいという希望を持っている。校内に3人、スキルを持った教員がいれば、日常的な利用の中で技術を身につけやすくなる。
また、校内の1/3の教員が活用し始めれば、相乗効果や教え合いによって、活用度が高まっていくような「マスの効果」があると考えている。
教員の高い操作可能率
操作可能教員が80%を超えている理由については、小学校教員の操作可能率が高いので、それが全体の割合を押し上げていると考えている。中・高等学校では、パソコン操作に関わる教員研修に対して、「自分の教科には不要」と考えている者も多く、教科担任制の弊害も見え始めている。
4.8.4 その他
京都市立学校ネットワークの企画・構築にあたって、京都高度技術研究所からのアドバイスも受けた。また、京都市の職員研修のうちインターネット関係は情報教育センターで行っており、市役所との連携も密である。現在の市長が元教育長であったことにより,予算面でもバックアップを受けている。
学校現場では情報教育分野でそれなりに対応できる先生はいるが、教育委員会事務局の指導主事クラスでパソコンを使える人は少ない。情報操作を基礎に何を指導するかが次の課題である。
先進的教育ネットワーク実証実験システムには期待していたが、応募した時点ではシステム内容がはっきりしていなかった。実情としては、運用面や接続方法において京都市がこれまでに整備した教育ネットワークとの整合性に苦労しているところである。
【資料】 京都市立学校ネットワークシステム図
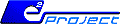 |
→次へ |