本校は普通科の2年、3年に情報コース(各学年約50名)が設置されており、2年時に課題研究の授業が設定されている。この中で環境問題に関する課題研究を行い、校内発表会の中で他の生徒にも環境問題に関心を持たせる。また、化学の学習内容から大気中の窒素酸化物や酸性雨の性質を調べる方法を考えさせ、学習している内容が環境問題に関連していることを気づかせる。さらに、本企画に参加している全国40校の小、中、高校生と同じ調査をするという責任感と連帯感を持たせ、環境問題を身近に感じさせる。
| 2-1 | 教育活動の中での位置づけ(適当なものを選んで下さい) |
(1)プロジェクトを実施した具体的な教育活動 ( 1 )(2)測定を行ったのは誰ですか ( 3 )
- 理科の授業
- 理科以外の授業(教科 )
- クラブ活動(クラブ名 )
- ホームルーム活動
- その他の活動( )
(3)データの送信は誰が行いましたか。 ( 3 )
- 生徒
- 教師
- 生徒と教師の共同作業
- 生徒
- 教師
- 生徒と教師の共同作業
| 2-2 | プロジェクトを教育活動の中で実施するとき、ネットワークの具体的な利用場面。 (1、2、4) |
- データの送信
- 他校のデータの収集
- 他校との交流
- 他のホームページを使った資料の収集
- その他( )
| 2-3 | プロジェクト実施にあたり利用出来たネットワーク環境。該当するものを全て選び、その他のものがある場合は具体的にお書き下さい。 (1、2) |
- ホームページ
- 電子メール
- 電子掲示板
- テレビ電話(CU-SeeMeなど)
- チャット
- その他
本校の課題研究は、週1時間設定されており、1学期は化学の基礎実験と課題テーマ設定を中心に行う。2学期は実験を中心にデータ収集を行い、3学期の前半は課題研究発表会の原稿とそのプレゼンテーション(power pointで作成)の準備、後半はまとめとして課題研究のホームページ作成を行い、最後に評価会を行う。
<年間指導計画>
○1学期(8時間)
| 配時 | 内 容 |
| 1 | コンピュータ基本操作の説明 |
| 2 | 化学基礎実験(溶液の調整) |
| 3 | 化学基礎実験(中和滴定) |
| 4 | 化学基礎実験(溶液の調整) |
| 5 | 化学基礎実験(成分元素の検出) |
| 6 | 課題研究説明と課題テーマの設定 |
| 7 | 課題テーマの設定(インターネットや実験事典等での検索) |
| 8 | 中間発表会(仮課題テーマの設定の動機と目的) |
○2学期(10時間)
| 配時 | 内 容 |
| 1 | 課題テーマの設定(インターネットや実験事典等での検索) |
| 2 | NOやNO2(窒素酸化物)の基礎実験1 |
| 3 | NOやNO2(窒素酸化物)の基礎実験2 |
| 4 | NOx調査(設置場所の決定) |
| 5 | NOx調査(第1回目測定)とNOやNO2(窒素酸化物)の発生実験 |
| 6 | NOx調査(第2回目測定)とNOやNO2(窒素酸化物)の性質 |
| 7 | NOx調査(第3回目測定)とNOやNO2(窒素酸化物)の性質 |
| 8 | NOx調査(第4回目測定)とNOやNO2(窒素酸化物)の性質 |
| 9 | NOx調査(第5回目測定)と酸性雨調査 |
| 10 | NOx調査(第6回目測定)と酸性雨調査 |
○3学期(7時間)
| 配時 | 内 容 |
| 1 | 課題研究発表会資料作成1(power pointで作成) |
| 2 | 課題研究発表会資料作成2(power pointで作成) |
| 3 | 課題研究発表会 |
| 4 | 課題研究ホームページ作成1 |
| 5 | 課題研究ホームページ作成2 |
| 6 | 課題研究ホームページ作成3 |
| 7 | 課題研究の評価会 |
(実験1)NOx調査
| 場所1 | 交通量の多い道路(繁華街の交差点) |
| 2 | 交通量の少ない道路(学校西側道路) |
| 3 | 学校内の植物の多いところ(学校内花壇) |
| 4 | 教室や職員室の中 |
| 5 | 学校内の駐車場 |
| 6 | ショッピングセンターの駐車場 |
| 7 | 紡績工場のそば |
| 8 | 製紙工場のそば |
| 9 | 海(伏木港内)のそば |
| 10 | JR氷見線(ローカル線)伏木駅そば |
NOxカプセル設置場所に関しては生徒と相談しながら、可能な場所を検討し、上記の10 箇所に決定した。この中で注目したのは場所1と6で、交通量が多いため他の場所よりNOxが多いと予想した。また、場所8も製紙工場のそばであるため、これも他の場所よりNOxが多いと考えた。
表1より場所1と6は予想通りであったが、予想に反して場所8の製紙工場のそばよりも場所7の紡績工場のそばの値が大きくなった。このことから製紙工場の煙はそれほどNOx増加に関与している訳ではないことがわかった。また、紡績工場からの煙はほとんどないので、この場所が他より高いNOx値を示した理由は、測定場所7が旧国道と交差しており、朝夕には非常に混雑する道路となることからこのような値を示したのではないかと思われる。他府県のデータと比較しても、交通量の多い首都圏のNOx値は高く、工場からの煙等より車の排気ガスが直接的原因となるように思われる。ただし、首都圏の工場地帯は除く。
表2はNOxの値が比較的高い値を示した測定場所6,7の6回のNOx測定結果である。天候を調べてみると第1回から第3回までは測定の前日まで晴れていたときの値で、第4回から第6回は測定の前日まで天候が悪い日(曇や雨)であったときの値である。この結果からNOxの値は前日までの天候により変化することがわかった。雨が降った翌日の測定値が低くなることから、NOxが水に溶けやすい性質をもつのかを、実際にNOやNO2を発生させてその性質を調べる実験を行った。
|
場所 |
場所1 |
場所2 |
場所3 |
場所4 |
場所5 |
場所6 |
場所7 |
場所8 |
場所9 |
場所10 |
|
第1回 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
第2回 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
第3回 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.3 |
0.2 |
|
第4回 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
|
第5回 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
|
第6回 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
平均 |
0.22 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
0.23 |
0.25 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
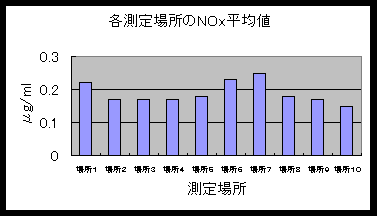
表1
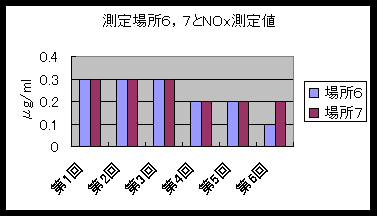
表2
(実験2)NOとNO2の性質希硝酸および濃硝酸にそれぞれ銅片を加え、NOとNO2を発生させる。ここで発生させたNOを空気中のO2と反応させNO2を生成させる。また、はじめに生成したNO2の水への溶解性とその液性について調べた。NOは試験管に希硝酸と銅片を入れ、水上置換で捕集した。このことからNOは無色の水に溶けにくい性質であることがわかった。次にこのNOを空気にふれさせると褐色のNO2に変化し、これに少量の水を入れるとこの褐色が消えた。よってNO2は水に溶けやすく、特有の臭いがあることもわかった。そこで次のような装置(図1)を組み立ててNO2の溶解性と液性を調べてみることにした。
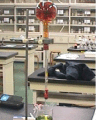 |
 |
| 図1 | 図2 |
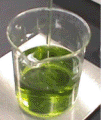 |
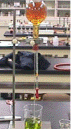 |
| 図3 | 図4 |
 |
|
| 図5 |
これはアンモニアの噴水実験と同様の装置で、アンモニアの代わりにNO2をフラスコに充填し(図2)、ビーカーにはフェノールフタレイン水溶液ではなくBTB水溶液(図3)に入れ替えた。図4からわかるようにアンモニアの噴水のようにはいかないが、NO2でもビーカーのBTB水溶液がフラスコ内に吸い上げられる様子が確認された。図5は図4の上部拡大図であるが、これからもわかるようにNO2が水に溶けて酸性物質(硝酸)が生成され、フラスコ下方部分のBTB水溶液が緑色(中性)から黄色(酸性)に変わった。この実験からNO2の水への溶解性は大きく、酸性雨の原因物質となりうることを確認できた。
(実験3)NO2の温室効果
空気、CO2、NO2のそれぞれを透明容器に入れ、白熱球で10分間照らし、1分ごとに温度の上昇を測定する。(図6)
|
時間 |
0分 |
1分 |
2分 |
3分 |
4分 |
5分 |
6分 |
7分 |
8分 |
9分 |
10分 |
|
空気 |
8.3 |
15.3 |
20.3 |
23.5 |
25.6 |
27.4 |
28.9 |
30.3 |
31.4 |
32.6 |
33.7 |
|
NO2 |
8.3 |
15.2 |
19.6 |
21.9 |
23.5 |
24.9 |
26.4 |
27.8 |
29.1 |
30.5 |
31.8 |
|
CO2 |
8.3 |
18.6 |
25.3 |
29.9 |
33.2 |
35.6 |
37.5 |
39.2 |
40.6 |
42.2 |
43.5 |
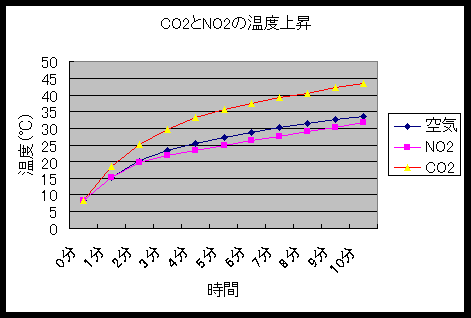
表3

図6
表3から、CO2は空気に比べて温度上昇が大きく、温室効果ガスと考えられるが、NO2は空気よりも温度上昇が少ない。しかし、これは、2NO2 → N2O4+59kJの平衡反応により、NO2が生成したと同時にできるN2O4がNO2にもどるときにまわりから熱を吸収するために温度が上昇しなかったのではないか考えられる。この実験だけではNO2が温室効果をもつかどうかははっきりしなかった。
(1)実践で得られた成果
課題研究では、生徒はおもしろく楽しい実験を選び、とちらかといえば地味な調査は避ける傾向にある。このためデータ収集が遅れがちになるが、定期的にデータを提出する調査に参加することにより、このような心配はなかった。また、化学の既習内容である気体の性質を深く理解することができ、実験方法の検討もできた。実際に実験することで発生させた気体(NO、NO2)が大変有害で危険な物質であることも確認でき、環境問題をより真剣に身近にとらえることができた。
(2)反省・課題
生徒たちは3学期の発表会の資料まとめに時間が取られ、実験内容を深めることができなかった。発表会でも環境問題を他の生徒への啓蒙を含めて、プレゼンテーションして欲しかったが、コンピュータ操作等も不慣れなため、発表内容を覚えるだけで精一杯となった。全体的にNOx調査を中心として実験を進めていったため、酸性雨に関してはデータ不足から課題にできるような実験を考えることができなかった。
(3)今後の実践にあたってのワンポイント・アドバイス
NOxカプセルの予備があれば、比色表と比べるテスト実験を行うことができたのではないか。
(4)このプロジェクト実施に当たって利用した資料・ホームページ等
新化学実験図鑑(講談社)図説化学(東京書籍)
高等学校改訂化学ⅠB(第一学習社)
化学実験テキスト(富山県理化学会)
酸性雨と大気汚染(三共出版)