�Q�D�P�D�Q�D�h�b�o�̋��痝�O��T�v
�@�C���^�[�l�b�g�N���X���[���v���W�F�N�g�i�h�b�o�j�́A�u�J�����_�[�v�u�j���[�X�v�u�n�E�W���O�v���A�𗬃e�[�}�ʂ̂V�̃o�[�`�����N���X���[�����琬�藧���Ă���B���ꂼ��̃N���X���[���ł́A���{���ƊC�O�̊w�Z�̋��t�������Ō𗬂̉^�c�ɂ�����A�w�K�e�[�}�̌��肩��A���k�̊w�K�̎x���܂ł��s���Ă���B
�@���N�x�̍ł��傫�Ȑ��ʂ́A�C���^�[�l�b�g��Ɉ�̃o�[�`�����X�N�[����ݒu���āA���ׂẴN���X���[�������Ă��̊w�Z�Ɉʒu�Â��āA�w�Z���̊Ǘ��̌��ɁA��̑g�D�Ƃ��Ă̌𗬂��s���Ă������Ƃł���B���������w�Z�Ƃ��ẴN���X���[���̑g�D���ɂ�鋤���^�c�ɂ́A���̂悤�ȂS�̂˂炢������B
�w�Z�Ƃ��Ă̍��ی𗬂̗��O���|�m�ɂ��邱�Ƃɂ���āA�Q���Z�̋��t�Ɛ��k�̎Q���ӎ���ӗ~�����߂邱�ƁB
�@
���ꂼ��̃N���X���[���ɏ������鋳�t�Ԃ̌𗬂����������A�Z�p�x���A�N���X���[���^�c��𗬂̃m�E�n�E�̓`���A�e�N���X���[���ɏ������鐶�k�̗����A�𗬂̃e�[�}����@�ɂ��ẴA�C�f�A����������w���i���邱�ƁB
�A
�e�N���X���[���ɏ������鐶�k���݂̃R�~���j�P�[�V���������������邱�Ƃɂ��A���k�̎�̓I�Ȍ𗬂⎩���I�ȉ^�c�̂��������w���i���邱�ƁB
�B �{�v���W�F�N�g�̓������C���^�[�l�b�g�ォ�痝�����₷���Ȃ�A�C�O����̎Q���𑣐i���邱�ƁB
�@���̂悤�Ȃ˂炢�����C���^�[�l�b�g��̉��z�w�Z�́A����܂łɂ��]��Ⴊ�Ȃ��A���H��ʂ��Ă��ꂩ�炻�̉^�c���@����̉����āA���̌��ʂ������邱�Ƃ���ł���B
�Q�D�P�D�Q. �P. �͂��߂�
�X�V�N�x�̃C���^�[�l�b�g�N���X���[���v���W�F�N�g�ł̓I�[�X�g�����A�A�J�i�_�A�؍��A�A�����J�A���{�T�J���̍��ʂ̃N���X���[����ݒ肵�A���ꂼ��̍��̊w�Z�ƌ𗬂��s���`���Ƃ����B����ɂ��ẮA�C�O�S�J���̊w�Z�Ɠ��{�̎Q���Z���ʂ̌𗬂��s���A�{���̖ړI�ł��������f�I�Ȍ𗬂ɂ܂Ői�W���Ȃ������Ƃ������Ȃ��o���ꂽ�B�����ō��N�x�̃v���W�F�N�g�ł́A�e�[�}�ʂɃN���X���[����ݒ肵�A�e�[�}�ɊS�������k�����ꂼ��̃N���X���[���ɎQ������`���Ƃ����B�܂��A��������ĉ^�c���邽�߁A�w�Z�Ƃ��Ă̑̐�����ڎw�����B
����ɍŋ߂̋}���ɐi�݂���C���^�[�l�b�g���̐�������}���`���f�B�A�ʐM�𒆐S�ɑ��l�Ȋ������\�ƂȂ��Ă��Ă���B
�{�v���W�F�N�g���߂���ȏ�̂悤�ȏ�w�i�ɁA�h�b�o�͎��ɂ����鋳�痝�O���������ďo�������B
�Q�D�P�D�Q. �Q. �h�b�o�̋������O
�ȉ��͂h�b�o�̋��痝�O�ł���B
(1) ���ۋ����w�K��ʂ������ی𗬂̐��i
(2) �}���`���f�B�A�𒆐S�Ƃ������̐��i
(3) �o�[�`�����N���X���[����ʂ����q���[�}���l�b�g���[�N�̍\�z
(4) �����w�K�E���Ȃ̃��f������
(5) ���ۃR�~���j�P�[�V������i�Ƃ��Ẳp��w�K
(6) �Q�P���I�ɋ��߂���l�ވ琬
�Q�D�P�D�Q. �Q. �P. ���ۋ����w�K��ʂ������ی𗬂̐��i
�]���A���ی𗬂Ƃ����Έٕ��������⑊�ݗ����ł���A�𗬁A�܂�R�~���j�P�[�V�������̂��̂�ړI�Ƃ�����̂ł������B���������A���^�C���ł̃C���^���N�e�B�u�Ȋ������\�ƂȂ����C���^�[�l�b�g�e�N�m���W�[�̕��y�ŁA�𗬂��甭�W���ċ����w�K�E�������삪�\�Ȋ������܂�Ă����BGuess
What�Ȃǂ̌f���ŁA���̍��̎������f���Ō����Đ�����������AV-Mail�f���ɓ��{���؍���ŏ������݁A�����z���������̎Q���҂������ǂ݁A�R�����g�𑗂�Ȃǂ̊����͍��ۋ����w�K������������̂Ƃ�����B
���N�x�̃v���W�F�N�g�ł́A�܂������ʼn����𐧍삷��Ƃ������ۋ�����Ƃɂ܂Ői�W���Ă��Ȃ��B
�܂����A���r�f�I�̃E�F�u�f�ڂȂǁA�܂����k�����R�ɋ�g�ł�����ƂȂ��Ă��Ȃ��e�N�m���W�[�������Ԃő��݊w�K���s���p�Ȃǂ�����ꂽ�B�����I�Ȋw�Z�����A�܂�o�[�`�����Ȑ��E�ɂ����鋳���Ԃ̋����w�K���i�s���Ă���킯�ł��邪�A��������̃X�e�b�v�ւ̏����Ƃ��Ă̈ʒu�Â��������̂Ƃ�����B
�Q�D�P�D�Q. �Q. �Q. �}���`���f�B�A�𒆐S�Ƃ������̐��i
��p�ꌗ�̍��̃C���^�[�l�b�g���p�ɂ����āA�����ǂ͑傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B�}���`���f�B�A��ʂ����R�~���j�P�[�V������}���`���f�B�A��i�̌����́A����̕ǂ���͂������Ă���B����ʂ����ł͂Ȃ��A���l�ȕ\�����\�ȃ}���`���f�B�A�́A�V���������E�|�p�ݏo���y��Ƃ�����B�}���`���f�B�A����g���邽�߂ɂ́A�R���s���[�^��r�f�I����A�t�@�C������A�C���^�[�l�b�g�Z�p�ȂǏ��Z�p�̏C�����K�v�ƂȂ��Ă���B
�{�v���W�F�N�g�ł́A�Q�����k�����̂悤�Ȕ\�͂�g�ɂ���w�K�̋@��⓮�@�Â������B
�Q�D�P�D�Q�D�Q. �R. �o�[�`�����N���X���[����ʂ����q���[�}���l�b�g���[�N�̍\�z
�h�b�o������N���X���[���ɎQ�����钆�ŁA�Q���҂̕��́A�A�j���摜�A�ʐ^�A�A�C�f�A�Ȃǂ�ʂ��āA�݂��̌��ɐG���ƂƂ��ɁA�l�I�l�b�g���[�N���z����Ă������ƂɂȂ�BDiary�ł́A�j�q���Z�������q�Z��diary�ɏ������݂�������A�I�[�X�g�����A�̐��k�����{��Ōf���Ɏ��ȏЉ�������A����ɓ��{�̐��k���ȒP�ȓ��{��œ�������A���{�̒j�q���k��Guess What�ɊȒP��gif�A�j�����f�ڂ����̂ɑ��؍��̏����k���S���邹��Ȃǂ̂��Ƃ�̒��ŁA�݂����ǂ̂悤�Ȑl�ԂȂ̂����������悤�ɂȂ�B���ꂪ98�N12���ɗ��������؍��̐��k����ˎR�̐��k�ƃt�F�C�X�E�c�[�E�t�F�C�X�̌𗬂�����Ȃǒ��ڌ𗬂ւƔ��W���Ă�������ACU-SeeMe��h�r�c�m�e���r��c��ʂ����𗬂ɂȂ����Ă����B99�N7�����A���Ōv�悳��Ă��鍂�Z�����ۉ�c�����{�����A���O�E����̌𗬂���b�ɁA�o�[�`�����ȃl�b�g���[�N�ƃt�B�W�J���ȃl�b�g���[�N�����ݕ⊮���Ȃ���A�����q���[�}���l�b�g���[�N�ւƐi�݁A�V���ȓW�J�������邱�ƂɂȂ���̂Ǝv����B
�Q�D�P�D�Q. �Q. �S. �����w�K�E���Ȃ̃��f������
�h�b�o������e�N���X���[���œW�J����Ă��鏔�����́A2002�N������{�\��̑����w�K��2003�N�X�^�[�g�̍��Z�u���ȁv�ɎQ�l�ƂȂ�p�C���b�g�I���i�������Ă���BGuess
What��V-Mail�Ȃǂ̌f���ł́A�e�L�X�g�����ł͂Ȃ��摜�≹���E�r�f�I�t�@�C�����f�ڂ��邱�Ƃ��ł��邪�A������s�����߂ɂ́A�����f�ڂ��邩�R���e���c�̋ᖡ�ƂƂ��ɏ��Z�p�⒘�쌠�A�C���^�[�l�b�g�̊댯���ɂ��Ă̒m���E�F���Ȃǂ��K�v�ƂȂ��Ă���B
�@Diary��School Calendar�ł͒Z���e�L�X�g�{�b�N�X�ɓ��e��[�I�ɕ\�����͂���͂��Ȃ��Ă͂����Ȃ����A���̂悤�ȃL���v�V�����I�ȃt���[�Y���l����͂��{����B
�܂�Diary�ł͑����Diary��ǂ݁A���̎������̖͗l��m�邱�Ƃ��ł���ƂƂ��ɁA����̃m�[�g�ɃR�����g���������݁A�o�[�`�����Ȍ������L�ƂȂ��Ă���BSchool
Calendar�ł݂͌��̍��̊w�Z�s����j�Փ��Ȃǂ�m��A����̓��������Ȃ���v���W�F�N�g��i�߂�B�܂��j���[�X�ł́A���{�ȊO�Ƀm���E�F�[��A�����J�̃j���[�X��ǂ݁A����ɂ��Ď����̈ӌ����q�ׂ�B�h�b�o�ł́A���̂悤�ɑ��l�ȃT�[�r�X����Ă���A�Q�����k�́A�C���^�[�l�b�g�̑��l�ȋ@�\�ɂ��Ċw��ł����B�ȏ�̊ϓ_����h�b�o�͑����w�K����Ȃ̎����v���W�F�N�g�Ƃ��Ă̈ʒu�Â��������Ă�����̂Ƃ�����B
�Q�D�P�D�Q. �Q. �T. ���ۃR�~���j�P�[�V������i�Ƃ��Ẳp��w�K
�C���^�[�l�b�g�łǂ����Ă������Ēʂ�Ȃ��̂��p��Ƃ�������̕ǂł���B���̖��ɂ��Ă͖{�v���W�F�N�g�ł��A��ɏq�ׂ��}���`���f�B�A��p������A���{��E�؍���|��\�t�g���g���Ȃǂ��āA���S���y�����鎎�݂��s���Ă���B�������A���ۂɂ͌f���Ȃǂւ̏������݂̑����͉p��ł��邵�A�؍��̐V�����q���ƍ����w�Z�̃n���搶���͐�����悤�ɁA�{�v���W�F�N�g�Q���̗��R�̈�ɉp����w�K�����邱�Ƃ�����B�Q�����k�̒��ɁA�u�i�f���ɏ�������ł��������Ɂj�p��������̂����ʂȂ��Ƃ̂悤�Ɏv��Ȃ��Ȃ����v�ƌ���Ă��鐶�k������Ă��Ă��邪�A����͖{�v���W�F�N�g�̖ړI����������Ă��邱�Ƃ̏؍��ł���B
�Q�D�P�D�Q. �Q. �U. �Q�P���I�ɋ��߂���l�ވ琬
�{�v���W�F�N�g�̂˂炢�ׂ͍����������2.1.2.2.1.����2.1.2.2.5. �̂悤�ɂȂ낤���A���ǂ́A�C���^�[�l�b�g�n�C�E�F�[�ƌ�����C���t���̏�Ŋ���ł���l�ނ̈琬��ڎw���Ă���B���ꂪ�h�b�o�Ƃ������������A��̊w�Z�Ƃ����`���Ƃ��Ă���̂́A�������z���A�n���s���Ƃ��Ă̎��o���������l�Ԃ̈琬���Q�P���I�̐��E�ɋ��߂��Ă���Ƃ����l������{�Ƃ��Đ��܂�Ă�������ł���B
�Q�D�P�D�Q. �R. �T�v
�{�v���W�F�N�g�͈ȉ��̑g�D�E�̐��ōs�����B
�Q�D�P�D�Q. �R. �P. �Z���g�D
�Z���g�D�Ƃ��āA�������A�Z���A�����A�������A�N���X�S�C��u���w�Z�Ƃ��Ă̑̍ق𐮂����B�������̖����͊w�Z�S�̂̉^�c�E�o�c�ʂ�S���A���Ɋw�Z�̕����Â����s���B
�Z���͊e�N���X���[�����X���[�Y�ɉ^�c�����悤�ɑS�̂̓��������Ȃ���A�K�X�A�h�o�C�X��^������A��������B�����͊w�Z�̏��K���Ȃǂ̐���Ȃǂ�S�����ƂɂȂ��Ă��邪�A����͗��N�x�ȍ~�̉ۑ�ƂȂ����B�������i�b�d�b�X�^�b�t�j�͗\�Z�E�o��ʂ�S���B�N���X�S�C�͊e�N���X���[���̃��f���[�^�[�Ƃ��Ă̖�����S�����B
�Q�D�P�D�Q. �R. �Q. �Q�����E�Z�E���k
�Q�����́A���{�ȊO�ɁA�A�����J�i�Q�Z�j�A�I�[�X�g�����A�i�P�Z�j�A�؍��i�P�Z�j�A�m���E�F�[�i�P�Z�j�̂T�Z�A�S�J���B���Ɏ����I�Ȋ����͂ł��Ȃ��������Q����\�����Ă��鍑�E�w�Z�́A��������B���{�̎Q���Z�́A���{���������w�Z�A���M�����w�@�����w�Z�A�_�ˎs�����������w�Z�A��ˎR�w�@�u�������w�Z�A�x�R�����������ƍ����w�Z�A���É��s�����ˏ��ƍ����w�Z�A���Ɍ����_�ˏ��ƍ����w�Z�̂V�Z�B���ɍ��N�x�A�����I�Ȋ����͂ł��Ȃ��������A�Q����\�����Ă���w�Z����������B
���k�̎Q���`�Ԃ́A���{���ł́A�p��i�R�Z�j���Ɓi�Q�Z�j�A�ۊO�����i�Q�Z�j�A�A�����J�ł́A�ږ��q��N���X�A�p��A�e�P�Z�A�I�[�X�g�����A�ł͓��{��N���X�A�؍��͉p��N���u�A�m���E�F�[�͏��ȂƂȂ��Ă���B
�Q�D�P�D�Q. �R. �R. ���p�����T�[�o��
�{�v���W�F�N�g�ɗ��p���Ă���T�[�o�́A�V�P�O�O�Z�v���W�F�N�g�̃T�[�o�R�Z�A�����L�̃T�[�o�P�Z�A�v���o�C�_�̃T�[�o���p�Q�Z�A�v�U�T�[�o�ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A�g�b�v�y�[�W�͒�ˎR�̃T�[�o�ɒu���A�f�U�C���͒�ˎR�̐��k���쐬�A�V�X�e�����͕��������w�Z�̖���L�i�����S�������B
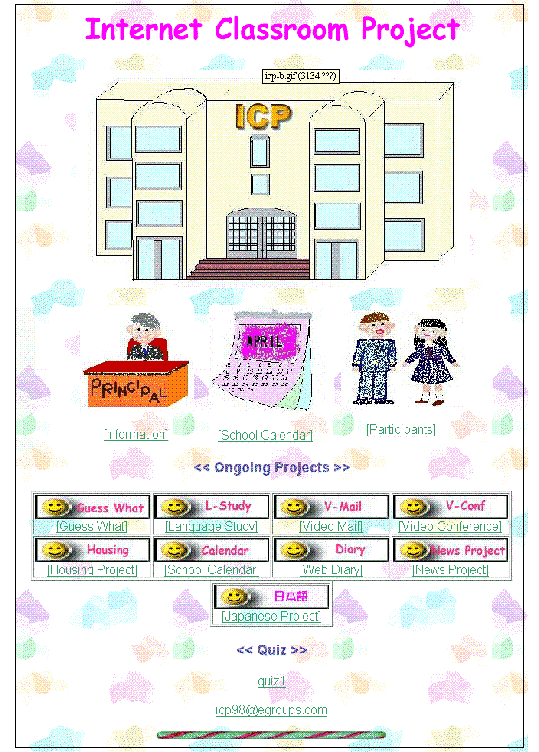
�C���^�[�l�b�g�N���X���[���̃g�b�v�y�[�W
�Q�D�P�D�Q. �R. �S. ���p�����Z�p�E�\�t�g
�f���Ƃ��ẮA�p��ŁA���{��ł�������t���[�i����p�t���[���܂ށj�̌f���\�t�g�𗘗p�ADiary��Visual Basic��p���Đ���a�T������B�r�f�I�t�@�C���́AReal
video�A�e���r��c�́ACU-SeeMe�AISDN�e���r��c�V�X�e���i�t�F�j�b�N�X�~�j�j�Bhtml�t�@�C���쐬�́AFrontPage�APageMIll�A�G�f�B�^�[�ȂǁB�ꕔ�AJavaScript�g�p�B���̑��AGif
Animator�Ȃǂ̉摜�����\�t�g�∳�k�\�t�g�B�Ȃ����_�Ƃ��āAReal Video�t�@�C���͌��݂̂Ƃ���}�b�L���g�b�V���p�̓ǂݏo���\�t�g���Ȃ��A�}�b�N���[�U�̑����A�����J�̊w�Z�œǂ߂Ȃ�������A�Z�p�͕s���Ŋ؍��̈ꕔ�̊w�Z�ł͌����Ȃ������B
�{���ɂ��Ă�2.1.5 ICP�ŗ��p�����c�[���ނŏڍׂ��q�ׂ�B
�Q�D�P�D�Q. �R. �T. �F�V�X�e��
�{�v���W�F�N�g�ł̓Z�L�����e�B�[�̊W����A�ꕔ�f����N���X���[���Ńp�X���[�h�Ń��[�U���m�F����F�V�X�e���𗘗p�����B���̏ꍇ�A�l�b�g�X�P�[�v�ł̓p�X���[�h�ۑ��������Ȃ����߁A����A���͂����߂���Ȃǂ̖�肪�������B
�Q�D�P�D�Q. �R. �U. �T�|�[�g�̐�
�V�X�e���̐v�ɂ������ẮA�ꕔ�̊w�Z�ŃR���s���[�^�N���u�̐��k���S�������ȊO�́A�N���X���[���̒S�C�������������A���[�����O���X�g�̐ݒu���ˎR�̈ꕔ�̃T�[�o�ւ̕s���i���Ȃǂɂ��ẮA�����ǂ̃T�|�[�g�����B
[�O�̃y�[�W��]�@[���̃y�[�W��]