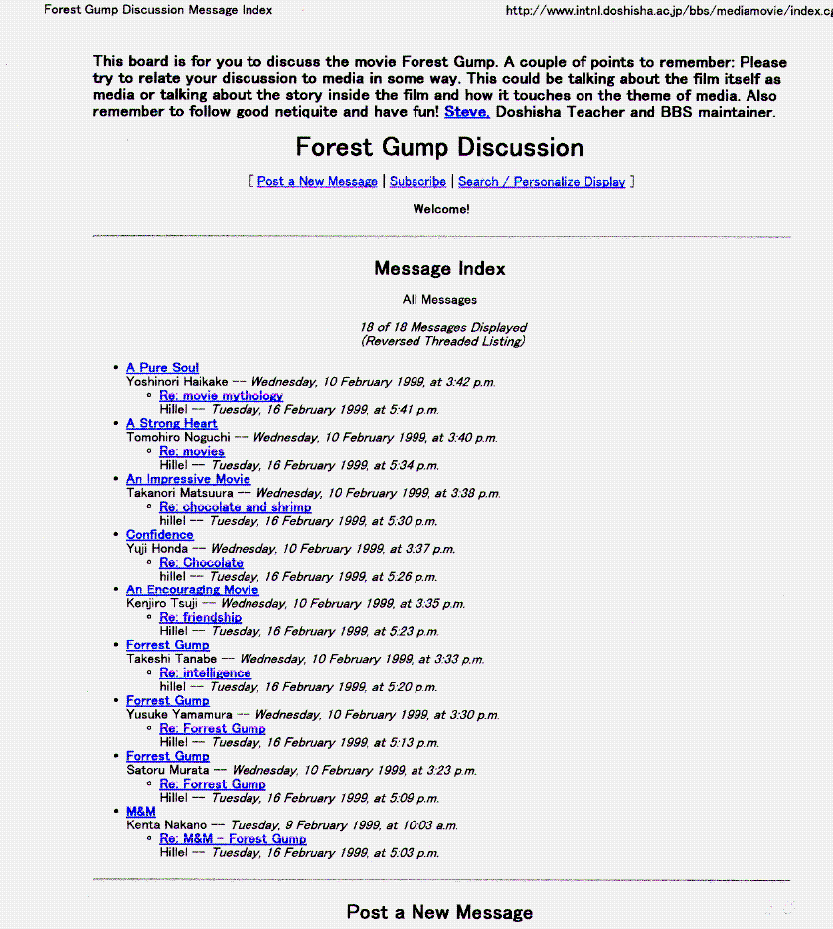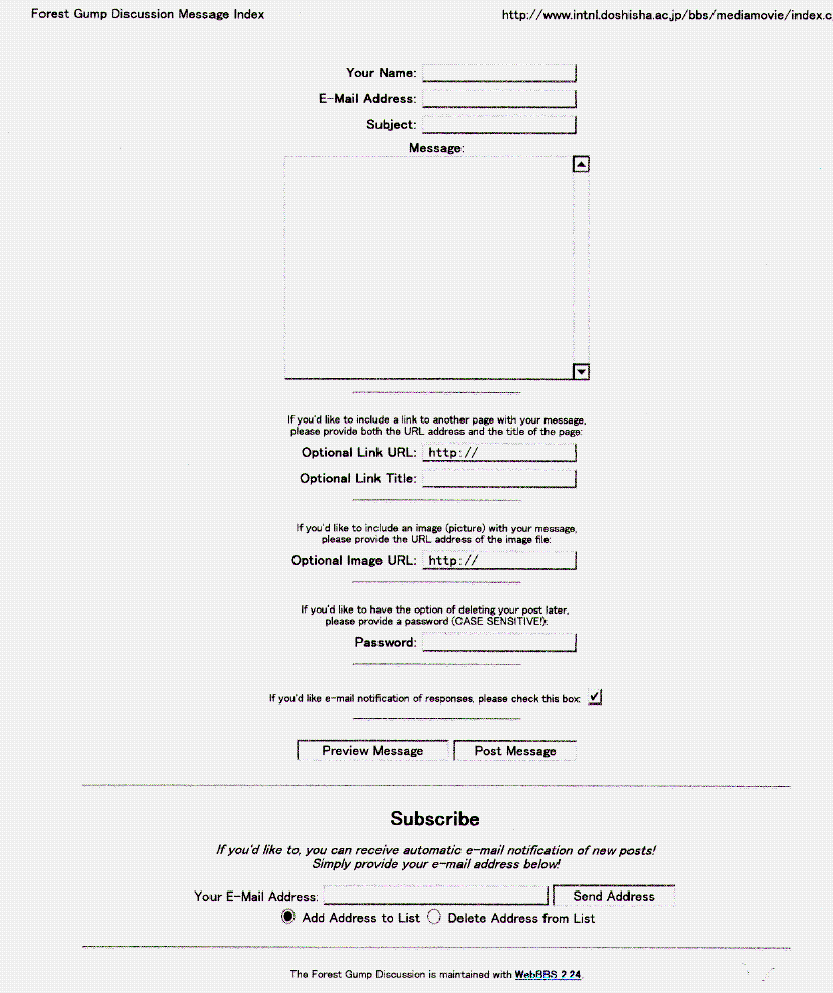2.3.5.評価と展望
2.3.5.1.Me and Mediaプロジェクト概観
Me and Media プロジェクトは、色々な意味で他の国際化プロジェクトと性質を異にしている。それは、このプロジェクトに参加する生徒たちが議論するテーマが「メディア」自身であることに起因している。このプロジェクトは「情報はメディアによって伝えられ、その意味は人間によって作り上げられたものであり、自分自身で作ることもできる」という広い意味でのメディア理解のための学習環境を提供している。
国内外の参加校、特に国外はESP (European
Schools Project) に参加している国々の生徒とのインターネットを通した意見交換を積極的に行い、メディアの様々な意味、メディアの重要性や創造性を追及し、メディアが自己形成に及ぼす影響などのテーマについて、現在でも議論を進めている。
新100校プロジェクトの国際化プロジェクトの教育内容は、国際理解教育として扱っている。嶺井(「新段階を迎える国際理解教育」『教育と情報』1999年1月号、第一法規出版)は、近年の国際交流教育について、その学習内容について実践例から以下の3つの学習内容に大別した。
(1)文化理解・国際交流・表現力
(2)地球課題・環境・開発
(3)人権・平和・異文化共生
また、これらの3つの学習内容と学習スタイルの関係も指摘し、
(1)は体験学習型、問題発見調査型、
(2)では問題提起型および問題発見調査研究型、
(3)では話し合い討議型の活動が多いとしている。
この嶺井の指摘からわかるように、国際理解教育では、知識習得型の個人的な活動はほとんどなく、協同学習型のオープンエンドな学習スタイルをとっていることがわかる。
Me and Mediaプロジェクトはメディアというテーマを通して、上述のような学習内容、学習スタイルをすべて包含する形として実践されている。このプロジェクトの根底には、生徒の自発的な探求を重視し、学習グループやメールでの討論を通じた相互作用のもとに「学習は社会的に構成されるもの」とする社会的構成主義の学習観がある。学習者がプロジェクト名であるMe
and Media、つまり自分とメディアの関係をもとに自分自身を問い直す場を提供し、結果として何かが成果として完成する、あるいは知識として身につくことを期待するのではなく、その学習の過程を重視するのである。
そこでここでは、このMe and Mediaプロジェクトの実現している学習環境の意義について掘り下げて考察する。
2.3.5.2.個人的な営みとしての「知識獲得」
これまでは教室には、教師と生徒だけが存在し、黒板の前に教師が立ち、標準的な教科書を使って生徒に対して一斉授業を行っていた。この背景には「学習」という人間の知的な営みを、「知識獲得の行為」としてとらえてきた学習観が存在する。人間の心を容器とみたて、そこに「知識」を注ぎ込んでいき、それをため込むことを学習とする。この知識獲得の概念はあくまでも注がれる容器は「個人」であり、その行為自体も個人的なもの、したがって学習という営みを個人的なものとしてとらえてきた。そしてその知識をため込むまでの行為だけを重視した上で、これらをいかに効率よく行うかが教育の目標とされ、上述のような学校の姿ができあがってきたのである。
問題解決能力の評価は、学校においては個人の頭の中にある記憶だけを頼りにしなければならず、さらに司法試験や公務員試験など、学校文化を背後に持つ特殊な出来事を「ものさし」として行われてきた。しかし、それらの試験に合格した人たちは、現実の場面では個人の頭の中にある記憶だけを頼りにしているわけではない。私たちの日常生活を見直してみると、頭の中にある「知識」だけでなく、ものや人を利用して上手に問題解決を行っている。何か問題に遭遇すると、他人に相談したり、本を調べたり、道具を利用したりと、様々な方法で情報を集めて解決しようする。問題解決においては、知識の獲得にとどまるだけではないことに注意を払う必要がある。人間の学習は、「知識獲得」という個人的な営みではなく、対話やコミュニケーションから生まれるものであり、そのときの状況や文脈とは切り離せないものでることが近年の認知心理学の研究成果からわかっている(美馬「ネットワークと学びの共同体」『教育』1999年3月号、国土社)。学習は個人の中だけで起こるものではなく、共同体との社会的な関わりや、その共同体の中に存在する様々なものとの相互作用を含めて生じる過程としてとらえるべきなのである。
以上のような思想的背景を持ったMe and Mediaプロジェクトが提供している学習環境として、プロジェクト型学習、協調的学習、ティーム・ティーチング、コミュニケーションスキルの学習、学習者の多様化がある。以下ではそれらについて説明する。
2.3.5.3.プロジェクト型学習
学校では特に、分野ごとに系統立てて教えることが最善あるいは必要とされてきた。しかしそのために、生徒にとって今学んでいることがどのようなことに将来結びつくのかがはっきりとせず、授業に出席すること、テストでよい点をとること自体が学習の目的になってしまっている。個々の学問分野には必ず、人間の社会的な活動が関連している。プロジェクト制学習とは、通常の学問分野ごとに整理された知識の提示を行う授業と異なり、その分野の「仕切り」を取り払う。その内容は人間の活動を体験するという意味を持ち、形式的にはいくつかの分野を統合した題材を扱うプロジェクトを単位としたカリキュラムによる学習である。このプロジェクト学習のデザインの背景には、人間は自分の生活あるいは社会的活動として意味のある活動の中でより多くを学ぶという事実がある。生徒は自分が参加するプロジェクト(Me and Mediaプロジェクトにおいては「テーマ」にあたる)に与えられた課題を解決するために、情報を収集したり、実験を行ったり、モデルを作ったり、シミュレーションを行ったりアイデアを創作したりという活動に従事することになる。
2.3.5.4.協調的学習とティーム・ティーチング
協調的学習とは、生徒が学習共同体を組織し、協調的に学ぶことを促進させる環境を提供することを意味する。それは新しい学習の方法と内容の両側面からの支援である。学習の場面に対し、協調的という用語を使用する背景には、「学習とは個人の中で起こるものではなく、そもそも共同的なものである」という学習観がある。できあがった知識を流し込むのではなく、問題や関心を共有し、解決しようとし、共通の言葉で話すことによって共同体が構築され、学び合いの場が生じるという考え方である。それを実現するために、個人の活動という「仕切り」を取り払い、各メンバーが相互作用しながら協調的に活動する場を提供する必要がある。これは社会の中で個々人が、それぞれ異なった役割を果たすということを意味している。言い換えれば、学習の場に参加する個人がそのプロジェクトの中での自己のアイデンティティを持つことである。この場においては、専門分野の異なる、または指導に対する視点の異なる複数の教師が共同で一つの授業あるいはプロジェクトに参加する。これは、ある課題についての学習内容を多視点的にとらえることのおもしろさを伝えることを目指している。このティーム・ティーチングにより、授業やプロジェクトの内容が豊かになり、また生徒に対する評価も多次元的になるという効果も期待される。Me and Mediaプロジェクトに参加したある高校では、社会科と英語の教師のティームが実際に組織された。
2.3.5.5.コミュニケーション・スキルの学習と学習者の多様化
自己の確立のためには他者との対話能力が、ある時点から非常に重要なものとなる。ここではコンピュータ・リテラシーと同様に、語学というものが「仕切られた」単独の学習の対象ではなく、表現の一手段として位置付けられている。コミュニケーション・スキルの学習の目的は、様々なメディア(映像、画像、音声、印刷物など)を利用して、様々な人々のために説明ができ、対話ができる有能で、自信を持ったコミュニケータを育てることである。コミュニケーションにおける自分自身の力を認識し、評価し、伸ばすことが要求される。学習内容としては、プレゼンテーション、メディア利用技術や、協調的な問題解決、プロジェクト運営などである。
通常学校では、学習活動の参加者が教師と生徒だけに限定されている。プロジェクト学習やコミュニケーション・スキルの学習を行っていく中で、この限定を取り払うことができる。プロジェクトの課題として、国内外の生徒との共同作業や討論する場面を設定することによって、構成員が多様化し、コミュニケーションのあり方がより現実世界に近いものとなっていく。ここに参加する生徒はもちろん、参加する教師たちもこのプロジェクトに参加することによって多くの学習の機会を与えられるのである。こうした開かれた学びの場としてMe
and Mediaプロジェクトが存在する。
2.3.5.6.展望
これまでの国際交流学習は、一方あるいは双方の生徒が国や学校を訪問したり、互いの文化を理解するための衣食住に関する情報交換、文通などを行うことが主であった。ここにインターネットという技術が加わったことで、即時的に、継続的に、文字ばかりでなく画像や映像もやりとりすることが可能になった。このことによって、イベント型の国際交流や表層的な文化の違いの理解にとどまることなく、テーマを定めて協同作業や討論を行っていくことが可能になった。様々な文化的背景を持つ参加者と協同作業や討論を行っていくことは、情報や意見を交換していくコミュニケーション・スキルを学び、さらにそこから他者との違いを認識し、それが自己への認識とつながっていく。その異文化の相手とは、異なる国、民族である必要はない。国内での実践でも、普通校と養護学校の生徒との討論や離れた地域の学校の交流、小学校と中学校という異年齢の交流、高校生と科学者集団との交流などがある。異なる文化的背景を持つものであれば、そこに上述の学習環境は提供される。したがって今後は、国際交流学習といわずに、異文化交流学習として大きな枠でとらえるべきなのかも知れない。
図1.Me and
Mediaプロジェクトのトップページ
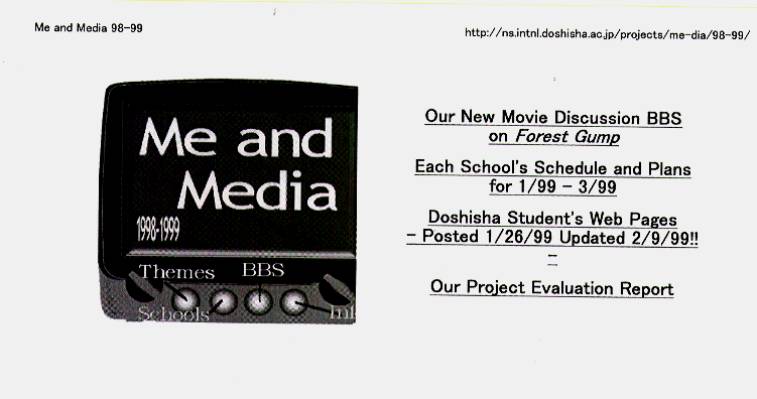
2.Me and Mediaプロジェクトの概要説明
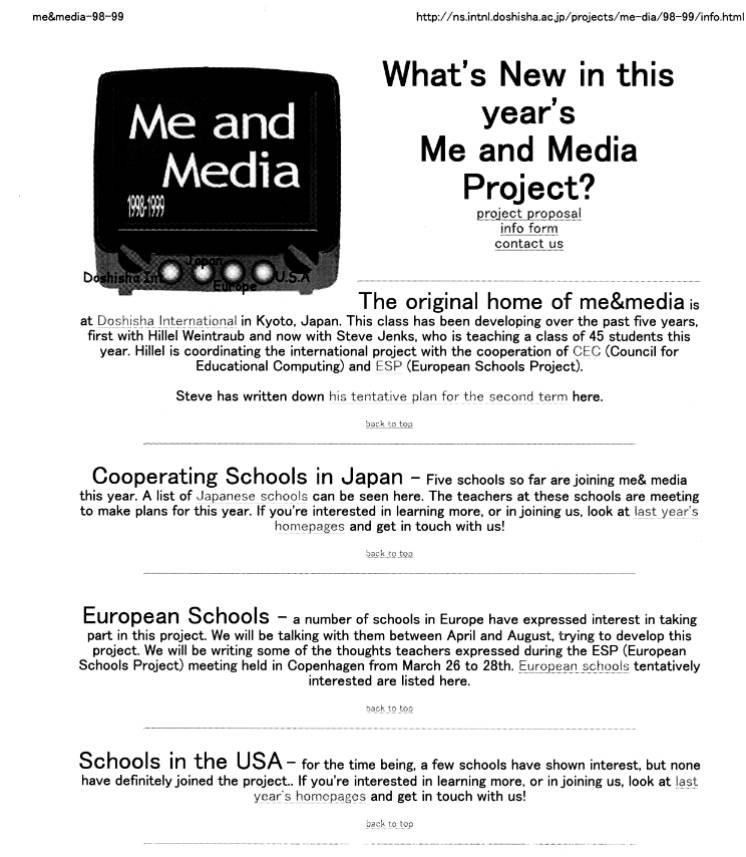
3.Forest
Gump Discussion の実例