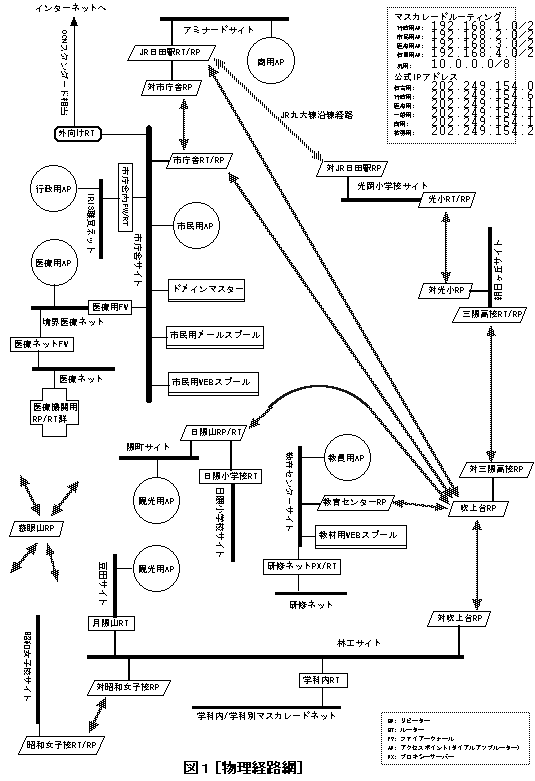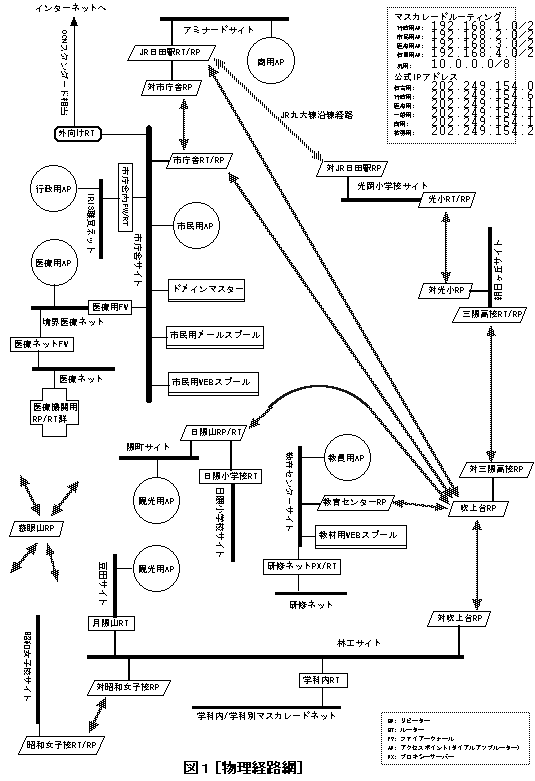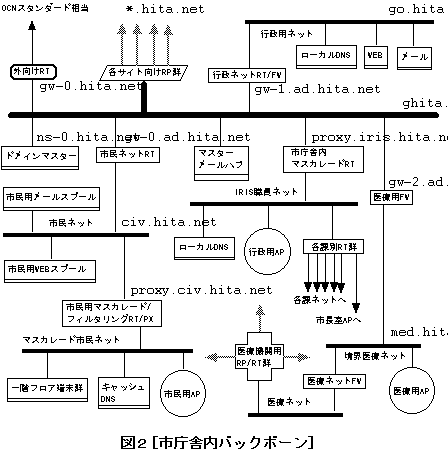3.3.1.5 今後の計画と課題
(1)日田地区地域ネットワーク
前述のように日田地域でインターネットを普及させる一つの要因として、「品質のよい、しかも高速な回線の誘致」がある。本地域にような大都市と離れた小規模地域においては大きなバックボーンを持つプロバイダのアクセスポイントの誘致は難しいこともあり、行政、教育、民間が一体となったシステム作りを進めなければならないことが公開シンポジュームの場でも確認された。この計画については、hita.or.jpの 山氏が中心となり具体的に立案し日田市に提案しているものである。
(2)システム計画案
a. 何が必要か
いうまでもなく、線と接続点が必要である。線とは、ほとんどの場合、常時通信できる専用線を指すが、通常の電話回線(ISDNを含む)を意味する場合もある。接続点とはそれらの回線を、バックボーンと呼ばれる基幹線へ接続する装置(ルーター)をいう。線について光ケーブルか電線かは重要な問題ではなく、最も重要視すべきは、その回線容量である。電線(メタルケーブル)よりも低速/小容量な光ケーブルは多く存在する。次に
IPアドレス群と必須要件ともいえるドメイン名も必要である。近年インターネットの大衆化によりこれらの接続点、回線、IPアドレス、ドメイン名を1つのパックにした商品が数社の電気通信事業者より発表された。それらの商品のうちで最もコストパフォーマンスの高い商品は
NTTのOCNであろう。このOCNという商品には利用可能な回線容量とIPアドレスに応じて
OCNエコノミー、OCNスタンダード、OCNエンタープライズ という3つの契約内容がある。従来の専用線接続については面倒な手続きと高額な費用が必要であったが
OCNはそれらの問題を割と納得のいく形で解決している。特に、回線料金と接続料金について、OCNの価格設定は意外なほどに安い。また回線の品質も、その利用料金を考えれば妥当であるように思える。その他数社にも同様の商品があるが、今後はこのOCNの回線容量、回線品質、利用料金を基準にした新商品が登場すると予想される。
OCNも含めてそれらの商品はまだ全国の各営業地域で等しく利用可能というわけではないが、次項からは、プロバイダ施設としては最も利用価値の高いOCNスタンダード相当の回線、接続点、IPアドレス群が利用できるという前提で進めることにする。
b.ネットワークの有効利用とは
ここで利用できる資源をまとめてみよう。 (見かけ上)インターネットと直結した1.5Mbpsの容量を持つ回線、その回線に対して
IPパケット通信を行う(対インターネット)ルーター
ドメイン名
クラスCのIPアドレス群
という具合だが、このくらいの規模になると、注意深く構成しないとひどく利用価値の低い活用しかできなくなる恐れがある。物理ローカルネットとしてイーサネットなどのブロードキャスト型ネットワークメディアを用いるとき、クラスCのIPネットワークを単一のネットワークにとして構成することは技術上の理由により避けるべきである。また設備の性能維持といった管理上のマシンパワー、マンパワー負荷分散のためにも、そのローカルネットワークを物理的に、あるいは論理的に分割したほうが好ましいことはいうまでもない。そこでサブネット、サブドメインという手法でそれぞれ物理ネットワーク、論理ネットワークを分割するわけであるが、技術上の理由によりまったく自由に分割できるわけではない。このためどのように分割するかはその技術仕様に従わざるを得ないのであるが、紙面の都合上、技術的に可能な分割例をすべて紹介することはできない。よって、技術的条件を満たす適切なネットワーク利用モデルを想定し、それに従った計画を提案することにする。なお、誤解を招きやすいことであるが、サブネットとサブドメインの間には必ずしも1対1の関係があるわけではない。ある1つのサブネットに多数のサブドメインが存在することもできるし、その逆もまた可能である。しかし無用の混乱を避けるため、しばらくの間、サブネットとサブドメインは1対1の関係にあるものとする。
c.ネットワーク利用モデルを考える
この利用モデルを想定するため、 まず以下のような用途別の要望があると仮定しよう。
教育用
行政用
医療用
非営利目的用
観光/商用
ネットワーク管理用
拡張用/実験用/緊急用
次にエンドユーザー(団体を含む)の希望する接続形態は以下のとおりとする。
端末型ダイアルアップ接続
LAN型ダイアルアップ接続
端末型専用線接続
LAN型専用線接続
また、各種サーバー、内部ルーター等の保安上の管理単位として 以下の4つの論理領域を考える。
ルーティングゾーン
公開ゾーン
非公開ゾーン
プロキシーゾーン
最初に断っておきたいが、これらの要件をすべて満たす理想的な解はない。それで各要件それぞれにある程度の冗長性を設定し、規模やそのネットワークに構築する機能にもよるが
実際に運用しながらカットアンドトライで整えていくほうが、一般に良い結果を得やすい。意外に思われるかもしれないが、完全性を求めるあまり、一切無駄がなく、きっちりと構築されたネットワークは間もなく破錠し、ほどなく、もう一度最初から構築しなおすことになるか、そうでなくとも不具合、故障が発生したときに、その復旧対策に往生することになる可能性が極めて高い。もちろん、きちんと構築しなければならないサブネットも存在するが、規模にかかわらず人間が管理するネットワークであることを常に念頭に置い等の保安上の管理単位として以下の3つの論理領域を考える。
公開ゾーン
非公開ゾーン
プロキシーゾーン
d.ネットワークの構成
前項までの議論の結果、図3.3−1 物理経路網を例として提案する。あくまでも合理性、利便性、将来性を鑑みた計画である。議論を具体的にするため便宜上トップドメインとしてhita.net、
利用可能なIPアドレスがクラスCのIPネットワーク
と仮定している。
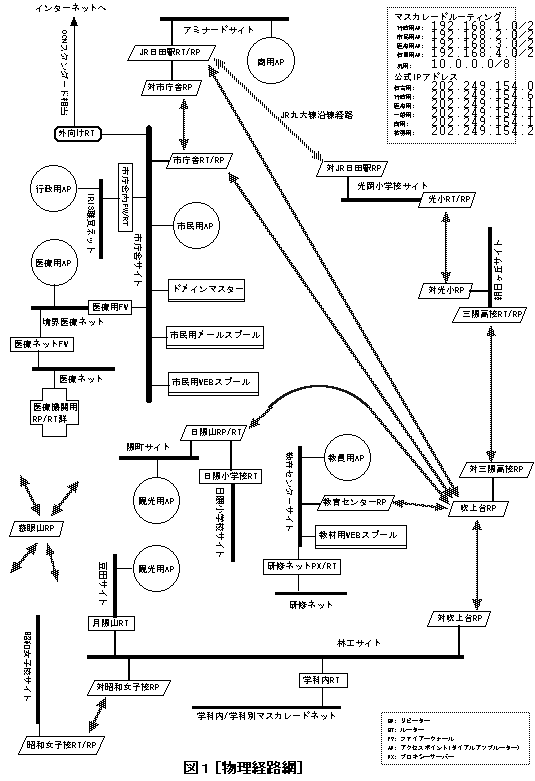
・ドメインマスター
図3.3−2 市庁舎内バックボーンのごとく、網計画の要となるプライマリDNSサーバーを設置しドメインhita.netの始点とする。このサイトの主たる目的は他経路、他サイトへのパケットルーティングと分割ゾーンの移譲である。そのため各方面向けへのルーター/リピーターが多数収容される。市庁舎内に設置されるサブネットについては市庁舎ルーターを含め、あとで議論する。これからは、あらゆる物理メディアが原理的に使用できることを考えていくべきである。近距離であれば赤外線ブリッジ、中距離であればスぺクトラム拡散方式無線モデム、遠距離であればレーザー光ブリッジがすでに実用化されている。それらを地理的、経済的条件の下で組み合わせればよいだろう。保守的ではあるが実績のあるNTTの専用線サービスを検討するのも、もちろんよい。
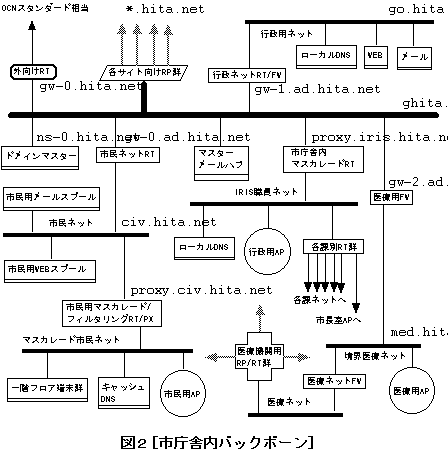
・月隈山/日隈山ルーター
市庁舎内バックボーンは月隈山ルーター、日隈山ルーター、慈眼山リピーター、 および吹上台リピーターにブリッジする。月隈山ルーターは豆田サイトと林工(日田林工高校)サイト、および昭和女子高校サイトの、日隈山ルーターは隈町サイトと日隈小学校サイトのデフォルトルートとなる。両ルーター内ではそれぞれに隈町ゾーン(kuma.hita.net)と
豆田ゾーン(mameda.hita.net)が定義されており、各々のゾーン管理者(サブドメインマスター)にそのゾーン構築権が委任されている。
・朝日ヶ丘サイト
市庁舎対吹上台ブリッジによって、見かけ上延長された市庁舎内バックボーンは、適切なリピーターによって三隈高校ルーターに接続される。この三隈高校ルーターは朝日ヶ丘サイトのデフォルトルートとして機能する。
・光小(てるしょう)サイト
吹上台リピーターは光小ルーターにも市庁舎内バックボーンを延長する。例によって、この光小ルーターは光岡小学校サイトを含む周辺のデフォルトルートとして機能する。
・アミナードサイト
市庁舎リピーターはJR日田駅に設置されたルーターにもブリッジする。この日田駅ルーターは、アミナード商店街、中央通り商店街、寿通り商店街などのデフォルトルートになる。
・市庁舎サイト
市政の中枢であることから慎重に構成すべきことはいうまでもない。そこで市庁舎ルーターをデフォルトルートとするサブネット内には
バックアップ用も含め内部ルーターを複数設置し、緊急事態発生時にも対応できるような構成にしたい。
・市民ネット civ.hita.net
この計画で最も大規模な市民用アクセスポイントをここに設置する。このサイトに期待する理想的サービスは、市民のインターネットに関する無制限利用である。加えて、市庁舎1階フロアにも一般利用可能な端末装置を配備すれば、初心者の素朴な好奇心にも答えられるのではないだろうか。
・IRIS職員ネット iris.hita.net
従来からあるIRISネット(BBS)は適切なゲートウェイを介して市庁舎LAN、すなわち市庁舎ルーターに接続する。これで現在の設備もそのまま利用できる。ここで「適切なゲートウェイ」とはTCP/IPルーティング機能を持ち、BBSホストコンピューターとパケット交換できるよう特別に設定されたルーターホストを意味する。そのようなフリーソフトウェアーは多く見かける。また、職員がその公務を迅速に執行する目的の行政用アクセスポイントもここに設置したい。もちろんこのサブネットは市長室にも直結しているものとする。
・医療ネット med.hita.net
IRIS職員ネットと同様、このサブネットもファイアーウォールを介して接続される。セキュリティ計画上の理由により詳しく紹介することを避けるが、
医療用アクセスポイントはこの層に設置する。
・医療機関ネット
医療ネットから更に厳重なファイアーウォールを介したあと、この層に接続する.この層は各医療機関とインターネットを介さない直接接続のため設けられる。
・商用観光ネット co.hita.net
これまでの各サブネットの構成と同様、商用ネット、観光ネットも設置されるべきであろう。ただし、近い将来一般化するであろう電子商取引にも対応すべく、このネットの管理者は前記の医療ネットと同等の保安条件を満足するよう計画を考えている。
・バックアップ用ネット ad.hita.net
各サイトへの経路上になんらかの障害が発生した場合、そのサイトとインターネットへの経路は簡単に使いものにならなくなる恐れがある。そのため断続的にでも市庁舎サイトへ接続できる補助回線と補助接続点が各サイトごとにぜひとも必要である。 また、将来インターネットとの間で、ダイナミックルーティング(動的経路変更)網を構築するためにも設置すべきであると考える。
・拡張計画について
紙面の都合上、その他のルーター設置点については省略するが、これまでの要領でおわかりのとおりバックボーン整備計画はそれほど難しいものではない。ルーティング設備の立地条件と適切なルート延長技術を用いれば、ランニングコストを最低限に抑えた
比較的良質な高速経路網が構築できると思われる。中継装置については赤外線ブリッジ、2.4GHz帯SS無線モデム、レーザー光ブリッジなど800Kbps〜300Mbpsの実効転送容量のものがすでに実用化されていることから、これにも着目したい。
実はこの計画に適当と思われる商用回線が昔から存在する。初期投資、運用経費ともに前述の無線系よりも高額であるのだが、それはNTTのフレームリレーと呼ばれる商品である。このフレームリレーの採用も冷静に検討すべきなのは当然であるが、
その前にここでユーザーは何を求めているかを掌握しておくべきだろう。
この文書の意味する計画のゴールは、前述の市民ネットの項でも著したが、市民のためのインターネットの開放である。将来的には「無償でユーザー各自が気軽に、また安全にバックボーンに接続できなければならない」と考えている。
以前、日田ネットメーリングリストにおいて、「インターネットは人と人とのつながりを意味するもの」という意見が出た。この意見はインターネットの本質を極めて直接的に表現していると思う。国境や人種などの物理的、文化的な障壁を意味するものはないのである。
このようなエンドユーザー利用環境をもくろみ、各方面において、それらが有する基礎設備環境を低コストで利用できるという理想的条件を仮定し、この計画は想起された。またいく度となく単位ネットワークでのシュミレーションを繰り返し、技術上可能な構成であると確認したことを付記しておく。
(3)運営体制
前述の4つのゾーンに関して、ルーティングゾーンを除く他の3つには各種のサーバーが接続される。それらのサーバーはいづれかのサブドメインに属することになっているので、次のような単位管理組織を各ドメインに置く。
a.一般利用者
1. 情報の提供。
2. 利用環境の調査/評価/報告。
b.経路維持班
・ ルーティング経路の監視
・ 経路装置/回線の点検
・ 経路装置内ルーティングテーブルのチェック
・ 不正パケットの監査
c.コンテンツ維持班
・ ローカル/パブリックの各領域に関して、Web係、メール係、ニュース係の担当者はスプール領域/コンテンツの監視を行う
d.企画班
・経路拡張計画、マルチキャストメディア(ビデオ会議等)、IPv6などの新技術の企画実験
・コンテンツ(Webページ、メーリングリスト、ローカルニュース等)の提案と評価
e.ドメインマスター
( WEBマスター、ポストマスター、USENET管理者、等を含む
)
・新アカウントの作成、旧アカウントの削除
・新サービスの作成、旧サービスの削除
・利用状況の評価/報告
・障害時の復旧対策
・不正パケットの監査
これらの管理については、日田市情報課が行うことが最も望ましいが人材や機器の設置場所の面から考えて市民ボラティアの力が必要になってくる。物理網が構築される前にネットワーク管理技術の研修の組織として「ネットワーク整備班」を編成する。 最初は全員この班に所属し有識者・業者、日田ネットの会員などのボランティア有志で構成する。ここで研修を受けたボランティアは分担し各サブドメインの管理を行っていく。インターネットも人が作りあげるものであるから、その各人が持つ特性や、最も得意とする技能が十二分に発揮できる体制、それらの人的資源(マンパワー)がうまく流用できる体制を目指している。
(4)今後の課題
a.機器の設置場所および管理体制(ボランティアグループの限界)
市庁舎内に機器を設置する場合、ボランティアグループの市庁舎内の自由な立ち入りについては問題がある。したがって、機器の管理およびボランティアグループの管理運営ということには限界があることから市内の民間プロバイダと第3セクタによる運営も考えなければならない。
b.人材の確保
地方都市における人材の確保については深刻な問題である。幸いにして本地域においては現在のところ確保されているが継続的な広がりのある人材の育成が必要になってくると思われる。日田林工高の役割も非常に重要になってくると思われる。
c.行政、教育関係(小中高との連携含む)、民間との協力体制
インターネットの性質上、地域内ネットワークの役割が非常に重要になってくる。特に義務教育と高校や地元大学、研究機関との関係を密接に保つ必要性があると思われる。しかしながら、管轄の異なる行政との連携は非常に難しいものがある。
d.地域教育情報のデータベース化(コンテンツの整備)
地域の連携により地域ネットワークが整備されたとしても、地域教育情報が蓄積され有効的な利用がなされなければ地域ネットワーク形成の意味は半減すると思われる。今後、積極的な地域教育情報のデータベース化を進めていかなければならない。