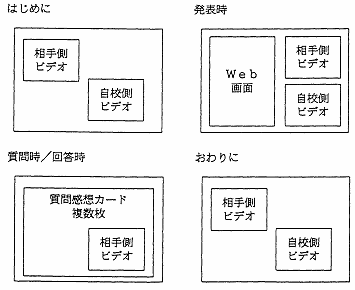
| 本実験は、 | |
| 実験参加校両校の児童がそれぞれの観点から調べ学習を行い、調べ学習からわかったことをお互いに発表/質問しあうといった形態で行うこととした。 | |
実験当日は、お互いに調べた自分たちの地域のまわりのことを発表し、質問/回答を行うことになるが、より授業を効果的なものにするためには、児童たちに「何故自分たちがこのような実験を行うのか」、その必然性を与えてやる必要があるといった意見が教師から出された。本実験のために児童たちは大変な準備をする必要があるため、その動機づけをする必要があるとのことである。そこで、以下のようなプロセスにより実験当日に至ることとした。
① お互いのホームページを閲覧し、交流相手を意識する。
②事務局で準備したメーリシグリストを通じて自己紹介、ホームページを見ての感想、質問などを行う。
③質問に対する回答を行うなどお互いの交流を深める。
このような形で相手の活動の理解/事前交流を行うことにより、児童の動機づけを行うとともに、実験当日の相手校の児童とのネットワークを通じた面会への期待感をふくらませることを試みた。
また、実験して終わりというのではなく、実験後も交流を行っていくぺきであろうとの意見も出された。
本実験では、発表/質問をお互いに行うということから、時問的に厳しいことが当初から予想された。短すきてはお互いに十分な発表/質問を行えないし、かといって長ずきても児童が飽きてしまうことが想定される。従って、学校で行われる連続授業を目安とし、90分構成で進めることとなった。具体的には、表1.2-1に示すタイムテーブルで授業を進めることと決定された。
基本的には、両校が全く同じことを行うわけだが、55分〜60分の間だけ特殊な時間帯となる。神応小学校側は、林間小学校側での質問の整理の様子を見ていることとなるわけだが、林間小学校側で神応小学校側の質問の整理の様子を見る場面はない。 本来であれば、55分から両校同時に相手校から送られた質問を整理しはじめられれぱよいのであるが、神応小学校の発表が終了したばかりであり、林間小学校からの質問がすべて送信されるまでには若干の時間を要することとなる。林間小学校側は、神応小学校が発表を行っている最中に、神応小学校からの質問/感想はすべて受け取ることができる。そこでこの時間は、既に相手校からの質問/感想を持つ林間小学校側で、教師が指揮をとってもらい、質問感想カードを整理する方法を説明するための時間とすることとした。
実験のイメージを明確にするため、各場面ごとの画面構成も事前に確定した。その結果を図1.2-1に示す。
表1.2-1 実験授業タイムテーブル| 時間(分) | 場面 | 内容 |
| O〜5 | はじめに | 授業担当の先生が本実験を開始するにあたっての挨拶を行う。 |
| 5〜30 | 林間小学校発表 | 林間小学校が発表を行う。 |
| 30〜55 | 神応小学校発表 | 神応小学校が発表を行う。 |
| 55〜60 | 林間小学校質問整理 | 神応小学校から送信された質問感想カードを整理する。神応小学校側は相手校の整理の様子を観察する。 |
| 60〜70 | 両校質問整理 | 両校とも相手校から送信された質問カードを整理する。 |
| 70〜78 | 林間小学校回答 | 整理された神応小学校からの質問に回答 する。 |
| 78〜86 | 神応小学校回答 | 整理された林間小学校からの質問に回答する。 |
| 86〜90 | おわりに | 授業担当の先生が本実験を終わっての挨 拶を行う。 |
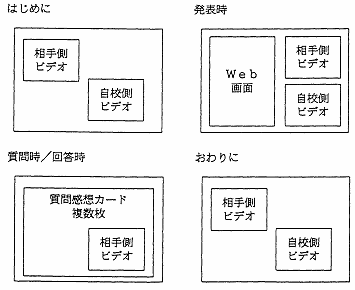 |
|
図1.2-1各場面における画面構成
|
これら検討された授業構成を実現すべく、システムの検討を行っていくこととした。