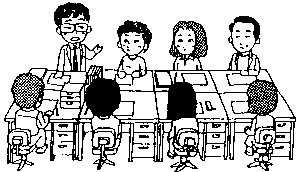第3章 活用実践例
1.教員研修での活用
①事前準備
1)打ち合わせ
担当の教員を決め、SEとの細かい打ち合わせを行う。
打ち合わせの内容としては、
・教員の技能レベル
・現在までの使用状況
・研修の持ち方と研修日程
・学校としての要望
2)資料作成
打ち合わせに基づいて、学校側が準備するもの、SEが準備するものに分けて、資料を作成する。
SEに資料作成を依頼するときの要望として、
・教員の技能レベルに応じて、用語や説明を変えてもらう。
・なるべく実際の環境に合わせて作成してもらう。(画面など)
・説明で使用する教材は、できるだけ実際の授業で使用するものと近いものにしてもらう。
②実践(当日)
1)研修前
打ち合わせ事項の最終確認と機器等の環境の確認を行う。
2)研修
導入時の研修例
・導入された環境のおおまかな構成
・電源の入れ方・切り方
・基本的な使い方
・データの保存の仕方
・使用上の注意点
ソフトウェアに関するの研修例(実際の授業を考慮しながら)
・使用する題材は、実際の授業に近いものにしてもらう。
・操作の説明には、生徒が間違えそうな点を盛り込んでもらう。
・操作だけでなく、全体的な運用も含め、研修のはじめから終わりまでを実際の授業とみたてながら進めてもらう。
研修の評価
・研修時の教員の様子を観察する。
・担当教員とSEとの話し合いを行う。
3)研修後
機器の環境などを変更した場合は、もとに戻してもらう。また、研修中に起きた問題や課題点について確認し、SEの指導を受けるとともに今後の対応を検討する。
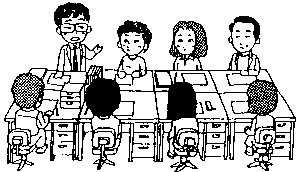
③事後処理
1)研修のまとめ
SEとの話し合いにより、研修の成果や今後の課題等について把握する。また、SEに対して研修報告書の作成を依頼する。
報告書の内容としては、
・参加人数
・研修内容
・研修の成果と今後の課題
2)研修後の対応
研修後に対応が必要なものに対して早急に対処する。また、SEによる対応が必要なものに関しては、SEとの協議により対処する。
2.授業補助での活用
①事前準備
1)打ち合わせ
授業者は授業の目標や進め方を明確にし、SEに対して補助、支援して欲しい内容を伝える。
補助の内容としては、
・授業中における児童生徒への技能指導
・児童生徒からの質問への対応
・困っている児童生徒への助言
・機器のトラブル等への対応
2)資料作成
授業で使用するデータやフォーマットの作成が必要な場合は、SEにその意図を伝え、事前の準備を進める。
SEに作成を依頼する場合は、
・授業者の意図を明確に伝える。
・授業前に授業者が確認を行う。
・SEの負担にならないよう注意する。
②実践(当日)
1)授業前
授業の進み具合により、本時の展開に変更がある場合には、SEとの打ち合わせを持ち、対応を依頼する。
2)授業(SEの役割)
児童生徒への技能指導例
・授業で活用するソフトウェアの操作方法について指導する場面で、教員に替わって指導する。
・授業用に作成されたデータやフォーマットの活用方法について、直接指導する。
児童生徒からの質問等への対応
・ソフトウェアの機能に関する質問等への対応
・ソフトウェア活用のアイデア等の助言
・自分だけでは操作できない児童生徒への支援
機器のトラブル等への対応
・操作ミスによる機能停止への対応
・機器そのものの故障等に対する対応
・ソフトウェアを活用している場面でのトラブルに関する対応
3)研修後
授業中に起こった機器のトラブルや児童生徒の様子等について記録する。また、機器の環境について直しておかなければならない部分があった場合はSEの指導を受け、必要に応じて修復をSEに依頼する。
③事後処理
1)授業後のまとめ
SEとの話し合いにより、授業中に起こった機器のトラブルや児童生徒の様子等について把握する。また、指導が必要な場合は早急に対応する。
SEに対して、実施報告書の作成を依頼する。
報告書の内容としては
・SEが行った指導内容
・児童生徒の反応や活動の様子
・授業補助を等しての課題
2)研修後の対応
SEによる授業補助の成果と課題をまとめ、今後の活用に生かすとともに、より有効な進め方について、教員間で話し合う。
目次に戻る | 前のページへ戻る | 次のページへ進む