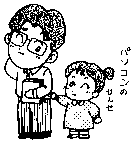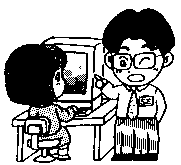第4章 実施における取り組み内容
1.教育委員会における取り組み内容
- ①SE派遣事業の周知
- 市町村教育委員会や学校にSE派遣事業の制度、内容を積極的に周知し、活用の拡大を図るとともに、操作研修のほか授業等における補助など、各学校の状況に応じたより効果的な利用を促す。
- ②計画立案
- 派遣方法は各自治体における活用目的により異なる。前年度までの状況や学校からの意見等を踏まえながら長期的な方針のもと、その年の派遣計画を決定する。
それに基づき学校の年間行事計画の策定時期、SE派遣を受け入れ可能な時期等に配慮しながら、派遣実施までの事務処理に関するスケジュールを立案し具体化を図る。
- ③委嘱企業の決定
- 学校現場からの派遣希望内容、設備環境等を考慮しながら、企業等を決定する。また、決定に際しては教育の場への参加と言う面にも配慮が必要である。 なお、SEを有する企業等の情報は財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC)から提供を受けることができる。
- ④企業への説明会実施
- 派遣を請け負う企業等に対して、説明会を開催するなどにより、事前打ち合わせの徹底等訪問の進め方、学校訪問に際しての必要な知識や留意事項、学校側の要望事項などを周知しSE側のスムーズな取りかかりを支援するとともに、適切な派遣体制の確保に努める。
- ⑤各学校とSEとの連絡
- 受け入れにあたっては、希望する派遣目的に則し、ソフト・ハードの設備面、教職員や児童・生徒のコンピュータに関する能力、実施に際しての要望等について、SE側との連絡を密にするよう学校に留意させる。
- ⑥実施状況の把握
- SE派遣による研修等が行われている学校を訪問するなどして、SE派遣事業の様子や各学校でのコンピュータ教育の実態をつかみ、今後の事業実施の参考とする。
- ⑦実施結果の集約
- 学校や企業から実施後の報告を受ける。これにより、実施結果と合わせ派遣計画に対する意見や問題点、新たな要望等を把握し、より良いSE活用方法の見直し検討を行う。
2.学校における取り組み内容
SEの派遣が決まった段階で、派遣事業が児童生徒にとっても教員にとってもより有効なものになるように、学校としての受け入れ態勢をどのようにつくるかが、重要となってくる。SE派遣の目的の徹底と受け入れ態勢をつくっていく上で特に大切なことは、その目的や内容を具体的に知らせるとともに、教員にコンピュータ活用の必要性や意義をどう持たせ、学校の組織上にどう位置づけるか、である。
- ①コンピュータ活用の必要性
- 1)新学習指導要領における「情報教育」の位置づけを知る。
平成10年12月に告示された小・中学校の新学習指導要領では、コンピュータや情報通信ネットワークを活用する学習指導が明確に位置づけられた。
| ・小学校「総則」: |
「各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習指導を充実する」 |
| ・小学校「社会」: |
「学校図書館や公共図書館、コンピュータなどを活用して、資料の収集・活用・整理などを行うようにする。」 |
| ・小学校「算数」: |
「コンピュータなどを有効に活用し、数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表やグラフを用いて表現する力を高めたりする」
|
| ・小学校「理科」: |
「観察、実験、栽培、飼育及びものづくりの指導については、指導内容に応じてコンピュータ、視聴覚機器など適切な機器を選ぶとともに、その扱いに慣れ、それらを活用できるようにする」 |
「総合的な学習の時間」でも、例示された課題等を学習する場合にコンピュータの活用が期待され、中学校の新学習指導要領でも総則や社会・数学・理科で小学校から一歩進んだ進展が期待されている。さらに、中学校では選択領域だった技術・家庭科の「情報基礎」が廃止され「情報とコンピュータ」が必須となっている。
2)ハード面の整備計画を知る。
・文部省のコンピュータ整備6カ年計画が、1994年度にスタートしている。1校当たりの整備目標は、小学校22台、中学校42台と設定されている。
・自治、文部両省では、学校をインターネットに接続する計画を98年度にスタートさせ、2001年度には小学校を含めた全国公立学校で完了することを目標にしている。
・文部、郵政両省は、99年度から先進的教育用ネットワークモデル地域事業として、全国1000校で高速回線によるネットワーク教育利用の研究開発を進める。
②校内組織上での位置づけ
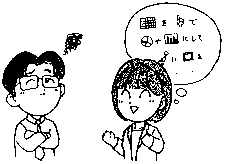 コンピュータ等を使って指導できる教員は2割程度(98年文部省情報教育実態調査)に留まっている現状がある。一部の熱心な教員以外はこれまで通りの伝統的な指導法から抜け出せない、また抜け出さないのが実態である。また、これまでの例では、熱心な教員が居る間はよく使われるが、転勤してしまうと使われなくなってしまう、というような傾向が見られた。教員の情報リテラシー向上に欠かせないのは、まず使おうとする教員を確保(使える教員を、あるいは研修の機会を与えて新たに)していくとともに、校務分掌と、教育課程に位置づけ、組織的に関わっていく場面を確保する事である。
コンピュータ等を使って指導できる教員は2割程度(98年文部省情報教育実態調査)に留まっている現状がある。一部の熱心な教員以外はこれまで通りの伝統的な指導法から抜け出せない、また抜け出さないのが実態である。また、これまでの例では、熱心な教員が居る間はよく使われるが、転勤してしまうと使われなくなってしまう、というような傾向が見られた。教員の情報リテラシー向上に欠かせないのは、まず使おうとする教員を確保(使える教員を、あるいは研修の機会を与えて新たに)していくとともに、校務分掌と、教育課程に位置づけ、組織的に関わっていく場面を確保する事である。
1)校務分掌への位置づけ
校内における研修や活用の実際場面での推進役は、管理職ではなく同じ立場の教員が望ましい。全校的に声をかけ研修等の時間を確保していくためにも、校務分掌にしっかりと位置づけ、役割を明確にしておくことが大切である。SEとの連絡の具体的な窓口もここになる。また、次の担当への引き継ぎができるようにすることが大切である。
2)教育課程への位置づけ
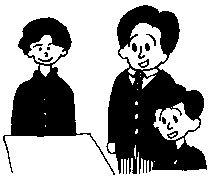 教員がコンピュータの操作・活用等について、習熟してから児童生徒に使わせるというのでは、彼らがコンピュータに慣れる機会は多くならないし、教員自身の技能の向上も多くは望めない。児童生徒とともに教員自身が学んでいくという形を組織的につくることが必要である。そのためには、情報教育について総合的な学習の時間を中心として、教科の学習でも意図的な形で取り上げるよう位置づけることが大切である。教務・教頭との連携のもとにその実を上げていくようにする。
教員がコンピュータの操作・活用等について、習熟してから児童生徒に使わせるというのでは、彼らがコンピュータに慣れる機会は多くならないし、教員自身の技能の向上も多くは望めない。児童生徒とともに教員自身が学んでいくという形を組織的につくることが必要である。そのためには、情報教育について総合的な学習の時間を中心として、教科の学習でも意図的な形で取り上げるよう位置づけることが大切である。教務・教頭との連携のもとにその実を上げていくようにする。
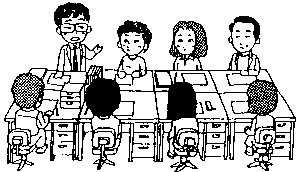
3.教員とSEとの連携
<教員研修における連携>
①教員研修のねらい(例)
1)コンピュータ操作の基礎・基本を身につける。
2)学校のコンピュータを授業またはクラブ活動で活かすことを可能にする。
3)インターネット操作の基礎・基本を身につける。
4)授業におけるインターネットの利用を可能にする。
②事前準備
1)教員の実態把握
・教員一人一人の技能とニーズをつかむ。
・技能とニーズをもとに、ねらいを設定する。
2)SEとの事前打ち合わせ
・ねらいをはっきりさせる。
・学校の実状を率直に伝える。(学校の様子、教員の意識・技能、施設・設備 等)
・実状をもとに、研修の進め方を話し合う。(内容、資料、グールプ、時間 等)
・SEの役割を確認する。(内容、範囲 等)
3)校内における準備
・打ち合わせ窓口を一本化し、研修体制を整備する。
・日程の調整及び時間の確保を行う。
・技能に応じたグループ分けを行う。
・SEの役割等をあらかじめ教員に伝えておく。
・研修通信等で教員の意識付けを行う。
③ 実施
1)時間厳守(開始、終了時刻)
2)雰囲気づくり。合図を決め、質問しやすく。
3)操作を中心にした研修。
④ 留意点
1)SEの与えようとしていることと、教員の求めていることがずれていることがあるので、事前の打ち合わせを入念に行う。
2)コンピュータ技能は個人差が大きい。説明図等、レベル差に応じる資料を用意できるとよい。(学校側 or SE側)
3)研修の効果を高める工夫が必要である。
4)SEは情報処理技術の専門家であっても、教育のことはよくわからず、戸惑うことがある。そこで、窓口になる研修リーダーが学校の実態をよく説明する必要がある。
<授業補助における連携>
① 事前の打ち合わせの前の準備
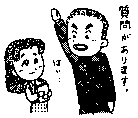 1)SEの授業補助について校内担当者を中心に、校内の共通理解を図る。
1)SEの授業補助について校内担当者を中心に、校内の共通理解を図る。
※教員の本務とSEの技術や知識を生かした授業補助の在り方を考える。
2)教員とSEが協力して、授業改善が行える指導計画を立てる。
※教科・領域のねらいと授業補助のねらいを明確にする。
3)SEと児童・生徒との関係を校内で共通理解し、指導しておく。
※例-SEを「○○先生」と呼びましょう。正しい話し方や態度の指導。
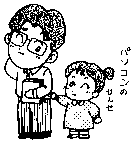
② 事前の打ち合わせ
1)指導計画をもとに、授業の目的(授業の目標)や学習の流れを知らせる。
※児童・生徒が、到達するべき目標や学習活動を共通理解しておく。
2)授業で使用する機器やソフトウェアについて確認する。
※授業の中でどのように、どの場面で活用されるのかを打ち合わせておく。
3)指導案をもとに、授業における教員とSEとの役割分担を明確にする。
※例-教員は全体への指導。SEは個別に技術指導。
4)授業に関わる教師と児童・生徒の実態についてSEに知らせる。
※教師の機器操作能力や個別指導を要する子、配慮を要する子などの情報を知らせる。
5)必要な機器の整備や資料(プリントや掲示)を作成をSEに依頼する。
※教員とSEで相談し、作業を分担する。
③ 授業の中での役割
1)児童・生徒に授業の初めにSEもも指導者であることを知らせる。
※事前にSEへの態度や話し方の指導を行っておく。
2)教員とSEが授業での役割を確認しながら、学習活動を協力して進める。
※主に指導する場面、個別に支援する場面等、指導計画をもとに、臨機応変に対応する。
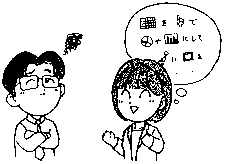
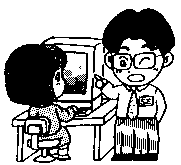
④ 授業後の打ち合わせ
1)授業の反省をSEと行う。
※目標への達成度から、授業の問題点(指導・機器・ソフトウェア・資料等)を探り、次回の課題を見つけ、対処する。
2)教員や児童・生徒からの疑問や残された課題を整理し、SEと検討する。
※その場で対応できないものは、次回までに対応できるようにする。
3)指導計画を基に、次回の授業の打ち合わせをおこなう。
※次回までに整備する機器・ソフトウェア等や準備すべき資料について考え、SEと次回の授業について打ち合わせる。
⑤ 留意点
1)役割の明確化
教員とSE双方がそれぞれの役割を十分理解し、その役割を果たすよう進めていくことが大切である。また、それぞれの持ち味を生かした授業になるよう計画することが必要である。
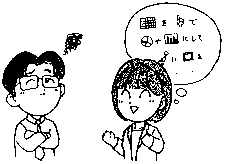 2)意志の疎通
2)意志の疎通
教員が立案した指導目標、計画が十分達成されるよう、両者の共通理解を十分図っておくことが必要である。
目次に戻る | 前のページへ戻る | 次のページへ進む
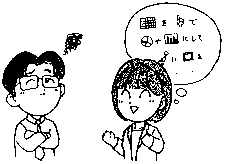 コンピュータ等を使って指導できる教員は2割程度(98年文部省情報教育実態調査)に留まっている現状がある。一部の熱心な教員以外はこれまで通りの伝統的な指導法から抜け出せない、また抜け出さないのが実態である。また、これまでの例では、熱心な教員が居る間はよく使われるが、転勤してしまうと使われなくなってしまう、というような傾向が見られた。教員の情報リテラシー向上に欠かせないのは、まず使おうとする教員を確保(使える教員を、あるいは研修の機会を与えて新たに)していくとともに、校務分掌と、教育課程に位置づけ、組織的に関わっていく場面を確保する事である。
コンピュータ等を使って指導できる教員は2割程度(98年文部省情報教育実態調査)に留まっている現状がある。一部の熱心な教員以外はこれまで通りの伝統的な指導法から抜け出せない、また抜け出さないのが実態である。また、これまでの例では、熱心な教員が居る間はよく使われるが、転勤してしまうと使われなくなってしまう、というような傾向が見られた。教員の情報リテラシー向上に欠かせないのは、まず使おうとする教員を確保(使える教員を、あるいは研修の機会を与えて新たに)していくとともに、校務分掌と、教育課程に位置づけ、組織的に関わっていく場面を確保する事である。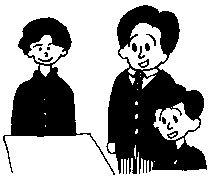 教員がコンピュータの操作・活用等について、習熟してから児童生徒に使わせるというのでは、彼らがコンピュータに慣れる機会は多くならないし、教員自身の技能の向上も多くは望めない。児童生徒とともに教員自身が学んでいくという形を組織的につくることが必要である。そのためには、情報教育について総合的な学習の時間を中心として、教科の学習でも意図的な形で取り上げるよう位置づけることが大切である。教務・教頭との連携のもとにその実を上げていくようにする。
教員がコンピュータの操作・活用等について、習熟してから児童生徒に使わせるというのでは、彼らがコンピュータに慣れる機会は多くならないし、教員自身の技能の向上も多くは望めない。児童生徒とともに教員自身が学んでいくという形を組織的につくることが必要である。そのためには、情報教育について総合的な学習の時間を中心として、教科の学習でも意図的な形で取り上げるよう位置づけることが大切である。教務・教頭との連携のもとにその実を上げていくようにする。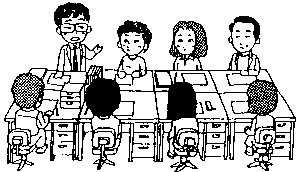
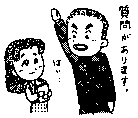 1)SEの授業補助について校内担当者を中心に、校内の共通理解を図る。
1)SEの授業補助について校内担当者を中心に、校内の共通理解を図る。