| 理論編 | 制作編 | 工作室ホーム | ||
|
||
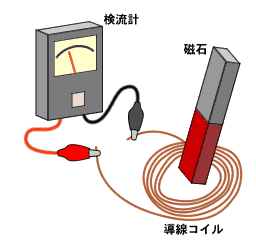 コイルを作り、検流計につなごう。そうしたら、棒磁石をコイルに入れたり出したりしてみましょう。わずかですが、検流計の針が振れます。 コイルを作り、検流計につなごう。そうしたら、棒磁石をコイルに入れたり出したりしてみましょう。わずかですが、検流計の針が振れます。つまり、電気が発生し、電流が流れたということです。しかし、この方法だけでは弱い電流しか流れません。 今度は、磁石の出し入れを速くしてみましょう。 さっきより検流計の針は大きく振れると思います。これは、コイルの中で磁石が動くことによって誘導電流という電気の流れができたからです。 磁石を固定して、コイルを動かしても同じです。 また、導線に電流を流すと、その回りに磁界ができ、例えば、方位磁石を近づけると針が揺れます。この性質を利用したものが電磁石で、モーターにも使われています。 |
||
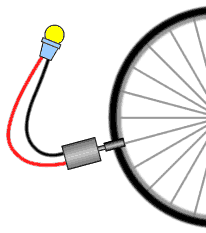 電磁石の逆をやると電気が起きるので、モーターを使って電気を起こせます。 電磁石の逆をやると電気が起きるので、モーターを使って電気を起こせます。模型用のモーターの軸にムシゴムをはめ、端子に豆電球をつけたソケットをつなぎます。 自転車のペダルを動かして後輪を回し、タイヤにモーターの軸を当ててモーターの軸を回転させます。すると豆電球が光ります(あまり速く車輪を回すとたくさんの電流が流れて豆電球が切れてしまうので気をつけましょう)。 模型用モーターの中は、まわりに磁石があり、まん中でコイルを巻いた鉄芯が回転します。普通の使い方では、電池をつなぐとコイルを巻いた鉄芯が回転しますが、発電機にした場合、コイルが回転したことによって電気が起きます。 |
||
|
|
||
| 理論編 | 制作編 | 工作室ホーム |
