不登校児童・生徒を対象にした
|
プロジェクトの各実施内容・問題点・評価内容等を示す。
インターネットカウンセリングシステムを設計するためのモデルとするため、文化観光省のもと韓国青年院が開設しているサイトを調査した。
韓国青年院 http://www.krci.or.kr
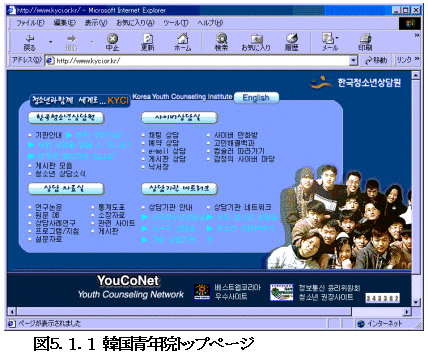
韓国青年院のサイト構成を図4.1.2に示す。
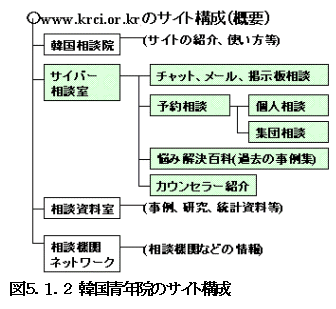
サイトの内容を表4.1.1に示す。
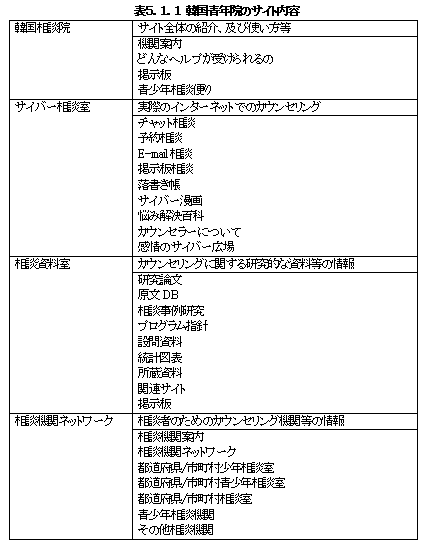
サイバー相談室の内容を表4.1.2に示す。
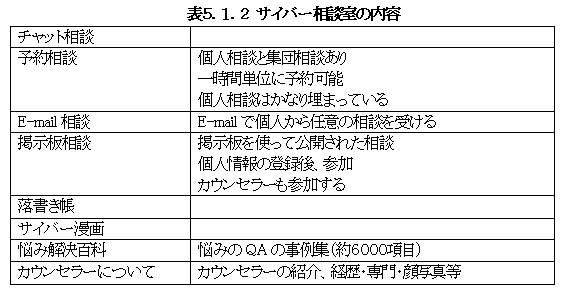
具体的な相談の流れを図4.1.3と図4.1.4に示す。
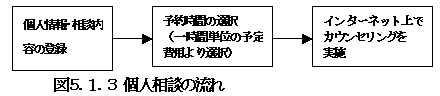
チャットもしくは掲示板形式。
人数は5-10名程度。
予め時間が決まっている(週一回複数回数実施)、対象・参加人数が決まっている。
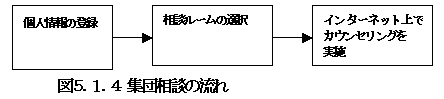
内容的には勉強方法など集団で行っても問題ないが多い。
勉強方法の改善
今後の進路について
効果的な勉強方法について
相談する前に、どんな悩みがあり、それに対する一般的な回答が見ることができる。表4.1.3に示すようなカテゴリーに分類され約6000件の想定質問と回答が整備されている。
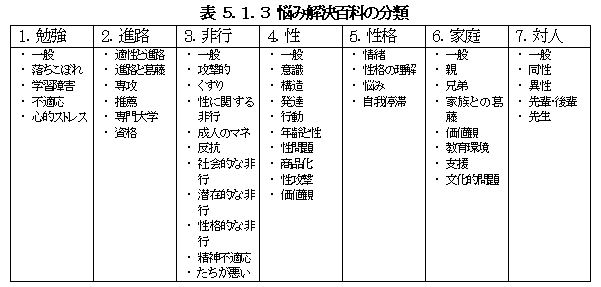
国内でのインターネットカウンセリングの状況等を以下に示す。
補足:内容の詳細及び参考文献については添付資料1.「国内のインターネットカウンセリング状況」を参照
電子メール相談・・・(小林、1999)、(林、1998)、(三鷹市、1997,1998)など
インターネットホンを併用した共有ホームページ(ウェブコラボレーション)・・・(三鷹市、1997,1998)
テレビ会議システムを用いた遠隔カウンセリング・・・(山下、1997)、(三鷹市、1997,1998)など
WWW上でのいじめ相談・・・(岡部ほか、1997)
ペンコンピュータとテレビモニター利用による描画・・・(森崎ほか、1997)
各地の教育委員会が適応指導教室や相談学級などを設置している。
各種病院や民間のクリニックにおいても専門的なカウンセリングを提供している。
フリースクールや通信制高等学校、大検予備校など。
そこでは、対面や電話による相談やカウンセリング、進路情報の提供などのガイダンス、学習保障などが行われてきた。
手紙・・・新聞、雑誌などの「人生相談」「法律相談」などのように、手紙によってその内容についての直接の回答を求めるタイプの相談。
電話・・・「命の電話」に代表されるもの。日本では1996年には電話相談学会も創設された(小林、1999)。
FAX・・・児童相談所でも少数だが使われている(林、2000)。
Sampton, et al.(1997)はマルチメディアを媒体としたカウンセリングの特徴として、「クライアントをカウンセリング場面に導きやすくすること、カウンセリング場面での課題や心理査定を援助しやすくすること、カウンセリング記録を簡便に記録、整理できること、カウンセリングを受ける場所を検索しやすくすること」などの利点を指摘している(小林、1999)。
Wilson & Lester(1998)は「電話は主として女性、ことに主婦層の利用頻度が高い」が「電子メールの場合は男性、ことに20代から30代の男性の利用頻度が高い」との特徴があると指摘している(小林、1999)。
保護者相談では父親の相談の多さが指摘できる(小林、1999)。
小林(1998)は「電子メールの最大の特徴は、他者の都合にあわせる必要がない点にある」という(小林、1999)。
不登校児本人に対する電子メール相談の意義
林(1998)は「あくまでも、対面的な関係を相談活動の中核に置きながらも、その周辺に、対面的でない相談活動をも、必要ならば面接関係への移行過程として設定することにも意味がある」としている。
不登校問題の回復では、生活空間を拡大することを目的とし、対人関係の幅を広げる対応が一番効果的である(小林ほか、1995)。すなわち、家族以外の他人との関係を回復すること自体が重要である。
電子メールという道具を媒介とすることで生活空間を拡大したり、人間関係の幅を広げるときの方法論が広がり、方法論そのものが人間関係の回復という目的を具体化していくといえる(小林、1999)。
不登校児の関係者へのコンサルテーション機能としての電子メール相談の意義
電子メールを送信する段階で、書記的な方法を用いるために、問題の整理や振り返りを自動的に行わせる効果がある(小林、1999)。
書記的な媒体で回答を得た場合、そこで得た情報がいつまでもクライアント側に存続する点である(小林、1999)。
誤解が生じやすい
自分の感情を投影しやすい
虚偽の情報が使用されやすい
対象の理解が容易ではない
これら4点の問題を回避するのは予想以上に難しい(小林、1999)。
誤解を回避するための工夫(小林、1999)
感情の投影への対処(小林、1999)
虚偽情報の使用への対処(小林、1999)
対象理解の的確化(小林、1999)
不登校支援システムの継続性の確保(小林、1999)
システムを日常的に円滑に支えていく人的資源を確保すると共に、その人的資源をさらに専門的に支える者や、全体に目配りをして人的資源を適切に配置するような管理者が常駐していない限り、装置があっても、現実には相談が機能しないという恐れが多分に出てくる。
新しくシステムを作ることよりも、そのシステムを継続・運営していくことの方がはるかに労力がかかり骨が折れることである。
不登校支援システムの範囲の拡大(小林、1999)
全国でインターネットを使った不登校支援システムを展開している教育委員会がネットワークを結ぶことで、巨大な相談ネットワークが自動的にできあがっていく。そのようになっていったとき、人的な資源の厚みも増し、サービスが全体として向上することが期待できる(小林、1999)。
韓国でインターネットカウンセリングシステムを開発した技術者と、システムの特徴、注意点、韓国での動向等の打合せを行った。以下に特出すべき内容を示す。
カウンセリング履歴の蓄積がシステムの特徴である。
カウンセリングデータの特殊性からセキュリティに留意する必要がある。
相談者自身が結果を確認できる心理テストの取り込みが進められている。
韓国の場合、BBSからシステムが始まったため、データをデータベースに蓄積していても
有効なデータの取り出し等が考慮されていないことが多い。今後、単にカウンセリングを実施するシステムではなく、カウンセリング履歴や結果をどう活用するかが検討されている。
カウンセリング結果の評価・判断の機能を組み込む傾向にある。
テレビ会議等の機能を拡張することを考慮している。
「システム基本仕様書」の作成にあたり、すでにメールでのインターネットカウンセリング経験のある所沢市立教育センターのカウンセラーとレビューによって仕様を確定していった。
以下特出すべき内容について示す。
メールについては、児童・生徒の年齢も考慮し、簡易的なWebメールの開発を考えていたが、過去のカウンセリング実績より、通常のメーラーで操作上問題がないとの指摘があり、このため通常のメーラーを使用することを前提にシステムを作ることとした。
韓国のシステムでは、チャット機能があるが、日本国内ではまだカウンセラーの要員確保の問題があり、非同期のメールとBBSを中心にすることとした。
メールでのカウンセリング履歴の取得については、あくまでカウンセラー側としては、通常のメーラーを使いたいとの希望があった。履歴取得機能を組み込んだメーラーの作成ではなく、メールの中間経路で履歴を取得する機能を組み込むこととした。
実運用上、相談者が増えた場合の管理機能を重視するように希望があった。
平成11年度の研究ではカウンセリング記録の整理の負荷が高かった。これらの記録分析の支援機能が必要ということで、各メールにコメント、タグによる分類機能を加えることとした。
単にカウンセラーと相談者だけの通信だけでなく、カウンセリング情報の共有も重視することにした。ただし発表などで、カウンセリングデータを使用する場合、公開できない情報もあるということで、特定データを別の文字に置き換える伏字機能を加えることとした。
不登校児童・生徒の状態を総合的に判断するため、所沢市立教育センターで使用している不登校状態のチェックリストを追加することとした。
前述したように、インターネットカウンセリングシステムではセキュリティが重視されるので、どのようなセキュリティを使用するかを検討した。今回採用した方法以外にも必要であればシステムに使用することは今後可能である。
尚、サーバへのログインやファイヤーウォール等の一般的なセキュリティは、検討から除外している。
インターネットカウンセリングシステムにおいては、個人の悩みを扱うということから他のシステム以上に個人プライバシーの保護が必要となる。その保護のための実装方式について調査を行う。
現在、多くのインターネットシステムにおいてセキュリティが重要視されているが、カウンセリングシステムの特異性について以下に示す。
カウンセリング情報については、担当カウンセラー及び相談者以外は内容(氏名・相談内容)を見ることはできない(システム運用者においてもカウンセリング記録を見ることはできない)。
カウンセリング研究者は、個々の相談内容について見ることはできないが、相談件数等の情報は扱うことができる。
電話相談のカウンセリングのように、広く一般の利用者を対象にすることも想定する。
メールを利用したカウンセリングまたはWebを利用したカウンセリングにおいて、以下のものを保護対象とする。
保護対象01 端末認証(相談者、カウンセラー)
保護対象02 利用者認証(相談者、カウンセラー)
保護対象03 メールデータの経路上での保護
保護対象04 蓄積されたメールデータの保護
保護対象05 Webデータの経路上での保護
保護対象06 蓄積されたWebデータの保護
保護対象07 ソースプログラムからカウンセリング内容が漏洩されるような手かがりを入手することの禁止
表4.4.1にセキュリティの実現方法と今回の実施範囲を示す。
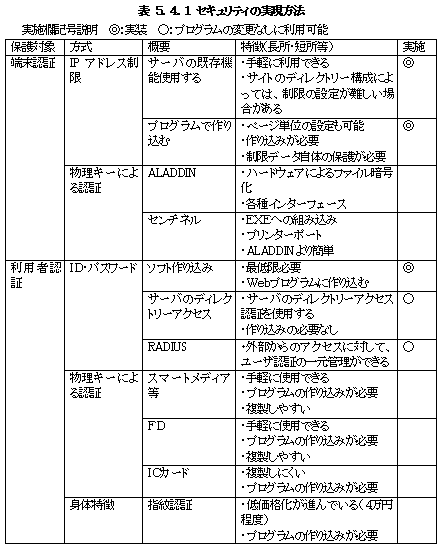
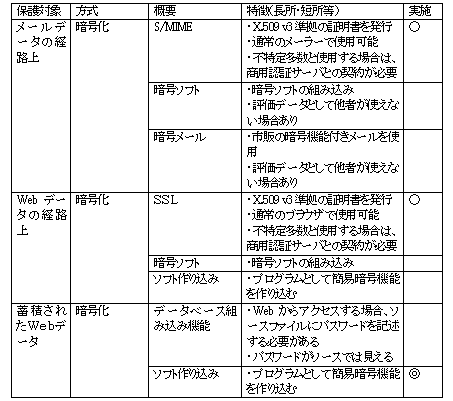
補足:内容の詳細については添付資料2.「システム基本仕様書」、添付資料3.「操作説明書」を参照
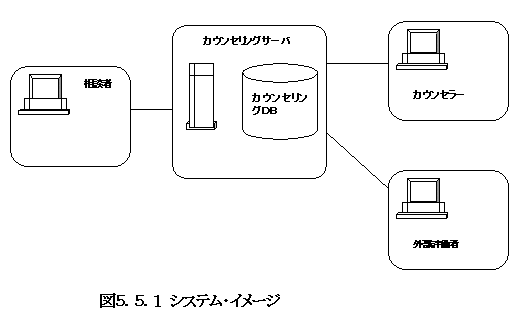
カウンセリングはカウンセリング・サーバを中心に実施される。
カウンセリングはメール及びWebを使用して行われる。
相談者は、メール又はBBSを使用して、個別又は集団でカウンセリングを受けることができる。
相談者はWebを通じてカウンセリングを申し込むことができる。
カウンセラーは自分で相談者の設定又は、申し込みのあった相談者のカウンセリングを実施できる。
カウンセラーはカウンセリング履歴の参照及び編集ができる。
外部の評価者は、カウンセリング履歴を見ることができる。この場合、内容は伏字などにより相談者が特定できないように変更できる。
表4.5.1に示すカウンセリングのタイプをサポートする。これは、「3.3システム概要」に示したプロジェクト開始時の想定システムを実運用に合わせて設計し直したものである。
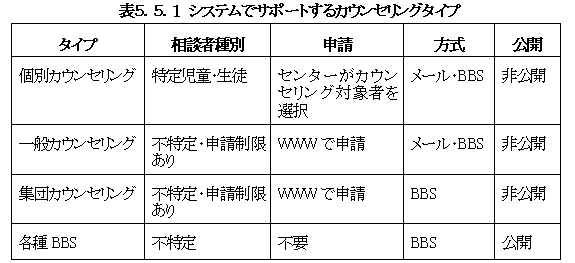
補足:個別カウンセリングと一般カウンセリングは、機能的には同一であり、カウンセラーが相談者に代わって相談者情報の登録及び申請を行う。
システムが持つ利用者区分を表4.5.2に示す。
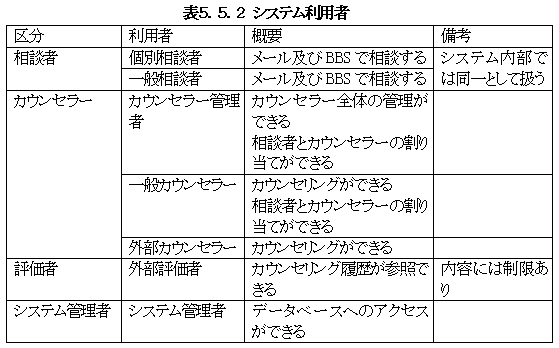
相談者用として表4.5.3の機能を持つ。
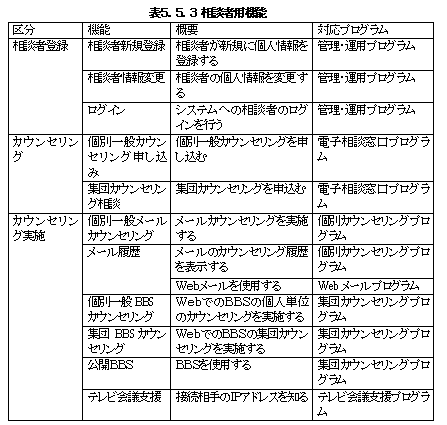
カウンセラー・評価者・システム管理者用に表4.5.4の機能を持つ。
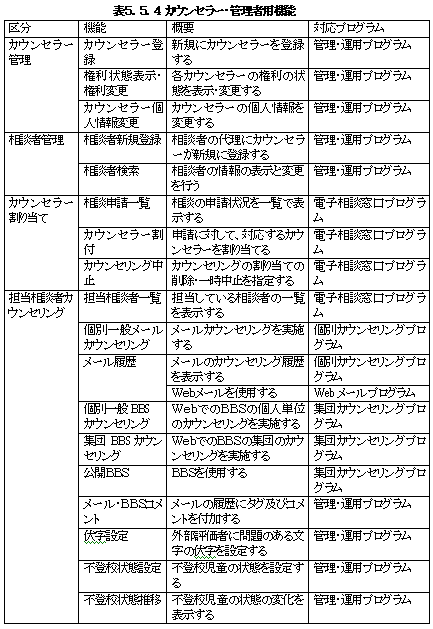
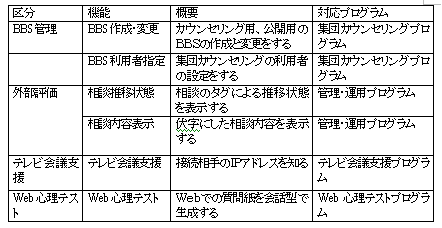
本システムでは、メールでのカウンセリングの履歴を管理するため、カウンセリングの中間メールアドレスを使うことにより、これを実現している。以下にその概要について説明する。
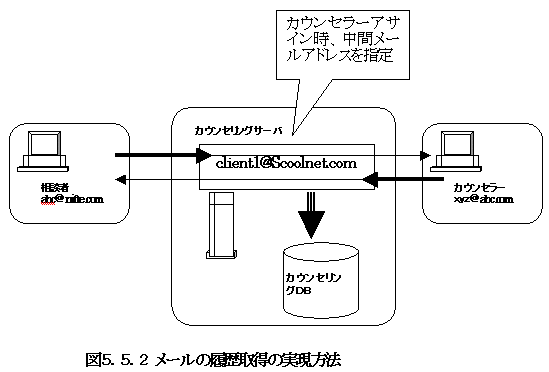
例:
前提条件
相談者のメールアドレス abc@nifte.com
カウンセラーのメールアドレス xyz@abc.com
動作
1)相談者の申請に対して、カウンセラーをアサインする時、メールを仲介する新規のメールアドレスを指定する。 例client1@Scoolnet.com
2)カウンセラーからは、このclient1@Scoolnet.comにメールを出すと、システムが仲介し、相談者のメールアドレスに転送する。
3)逆に相談者はこのclient1@Scoolnet.comにメールを出すと、システムが仲介し、カウンセラーのメールアドレスに転送する。
4)システムは、相談者とカウンセラー間のメールのやりとりをDBに記録する。
今回のシステムに関しては表.4.6.1のような運用形態を想定して作成した。
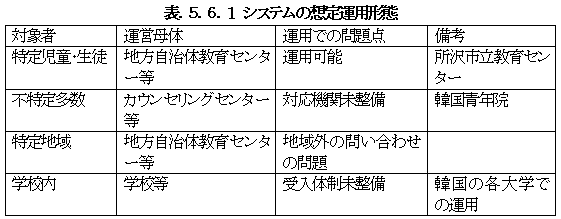
当初の所沢市立教育センター以外にプロジェクト期間中に導入の交渉・検討をおこなってきたが、短期間に運用開始することは、以下のような問題から困難であることがわかった。今回のプロジェクトの目的は「インターネットカウンセリング」システムを提供することにあったが、実際にシステムがあって、その導入を決定するまでには、各種手続きがある。また現状存在する問題点を運用上で解決していかなければならない。
日本国内で使用例がなく、教育委員会又は学校長レベルでは短期間で導入の可否の判断ができない。カウンセリングの実施に関しては、教育委員会や地方自治体の許可を受け、通常年度計画の中に正式に盛り込む必要がある。
学校等の導入において、学校側の担当カウンセラー等の配置が十分されていない。または、オフラインでのカウンセリング体制がまだ十分に確立していない。
カウンセラー自体が十分にインターネットを使えない場合もある。
インターネットカウンセリングについての対応方法などが確立していないため、問題が発生した場合の対応が十分にとれないという不安感がある。
例えば、「死にたい」、「運動会を中止しないと自殺する」等の相談が来た時に、対応方法がわからない等。
地方自治体においては、インターネットの特徴であるグローバル性から、行政地区内の問い合わせに限定することが難しい。
大学では留学生対象にカウンセリング相談を実施しているところもあるが、システムとしては日本語であるために使用できない。
尚、今年度の実施はできなかったが、特に市レベルの地方自体では、正式にインターネットカウンセリングを実施するための予算化が済んでいるところや、予算化を行っているところがあった。これらの市からは、他に国内で類似システムがないために、当プロジェクトの成果を平成13年度に利用したいという問い合わせもある。
昨年度までは、自治体レベルでこのような動向はほとんどなく、今年度に本プロジェクトで、モデルシステムを構築できたことは、今後の普及に大きな力になると思われる。
補足:内容の詳細については添付資料4.「韓国のインターネットカウンセリング状況」を参照
日本でのインターネットカウンセリングの運用の参考とするため、韓国青年院を訪問して韓国でのカウンセリング及びインターネットカウンセリングの状況について調査した。尚、韓国教員大学も訪問し、大学レベルでインターネットカウンセリングを開発・運用している教官にも状況を聞いた。
韓国内でのカウンセリングの状況、カウンセラーの育成、政府や国民のカウンセリングに対する考え方などオフラインのカウンセリング一般に関する調査を行う。
韓国内での電子メールや電子掲示板などインターネットを利用したカウンセリングの状況、カウンセラーの育成、資格について、オンラインのカウンセリングの利点や問題点などの調査を行う。さらに運用上の注意などオンラインのカウンセリングシステム一般に関する調査を行う。
大学: 1976年に大統領の命令により各大学に相談院を設置する。当時は学生運動が盛んであり、そのような状況での学生の悩みの相談を受けるのが目的であった。
その相談院が現在の大学におけるカウンセリングに続いている。
高校: すべての高校が相談室を設置しており、カウンセラーの資格を持つ教師が在室している。主な相談は、進学や暴力、性の問題である。
中学校: 一部の中学校でカウンセラーの資格を持つ教師が在校しており生徒の相談にあたっている。また、一年に2時間の相談の時間が設けられており単位システムに含まれている。主な相談は、進学の悩みである。
小学校: 相談室の設置はない。詳しいことは不明。
大学: 1997年度から本格的なe-counselシステムが導入された。1998年度からは青年院のようなサイバーカウンセリングがほとんどの大学で行なわれるようになった。大学ごとのe-counselシステムの組織名は「〜(大学名)大学ウェブ相談」である。
高校、中学校、小学校:公の運営(韓国の文化観光部がこのような問題を扱っている)のケースはない。行なわれているとしてもプライベートに教員が行うケースしかない。しかし、地方の教育センター(県レベル)では大体行なわれている。
大学: 実際2種類の相談方法が行われているので、大学においては連携が可能である。
高校、中学校、小学校 :地方の教育庁(県レベル)や青少年相談院のオンラインでの相談は多く用いられているが、オフラインでの相談は学校内であり、両者の連携はあまりない。
理想 :センターがすべてのデータを所有し、センター・学校間でカウンセリング情報を共有し連携することが必要である。しかし、韓国においては校長の力が非常に強く、このような連携を実施することに賛成する校長はまだ少ない。このため、校長の意識改革が必要である。
政府の関心: 政府からの指示、要望は多い。
家庭の関心: 家庭での関心も高く、個人的に運営しているカウンセラーへの相談もソウルや釜山(プサン)などの都市では多く利用されている。
不登校
韓国では不登校の子どもはあまりいない。例外として、子どもが家出した場合にその間学校に来られない、というぐらいである。また、高校1年生までは義務教育であり法律により、その間は学校をやめることはできない(落第という考えが無い)。しかし、万が一このような事態になった場合の責任は第1に教師に、第2に親にあるとされる。
いじめ
韓国ではいじめられているということで相談してくる子どもは少ない。ほとんどの場合、教師が解決している。韓国でのいじめは次のような道筋で解決される。いじめられている子どもは、いじめられていることを親には言わないが、毎朝、普通通りに家を出ても学校に行かないようになるので教師が気付く。そこで、教師はその当事者である子どもと話し合うことによって解決する場合がほとんどである。例外としてはいじめられていた子どもの転校ということもある。韓国においては教師に権威があり、子どもたちとの信頼関係も深いのでこのような解決が可能である。
相手が見えないのでたいへんである
礼儀がない
不満ばかりのデータである
雰囲気が悪い
上記のような状態が続き、韓国青年院のサイバーカウンセリングのサイトではチャットルームの作成等をカウンセラーしか行えない機能を追加した。
また、インターネットに簡単に入ることが可能なため相談内容は軽い物から重い物までさまざまである。ここで重要なのは重い内容の相談である。重い相談には早く気付くようにしてフェイストゥフェイスの相談に持っていく必要がある。オンラインの相談はカウンセリングに対する抵抗を取り除き、オフラインの相談に移行するためのプロセスであるという考えで行っている。また、以下のような特別なケースについての対応を示す。
オンラインにおいて「死にたい」というような内容の相談にはどう対応するのかについては、韓国青年院の場合、本気で死にたいという人はそのようなメールは送ってこない。もしほんとうにつらい内容の相談メールを送ってきたときには、「うん、うん」とうなずきながら、「どうして?」というようなやわらかい対応をしていくようにしている。
「運動会を中止しないと自殺する」というようなメールにはどう対応しているのか、韓国では事例が無くよくわからないが、何回も対応していくうちに得られたデータから戦略を立てるしかない、という答えであった。
管轄地域以外からの相談にはどう対応するのかについては、基本的にはすべての相談者の相談に対して対応している。
青年院発行「サイバー相談を通じてみた青少年の世界」より
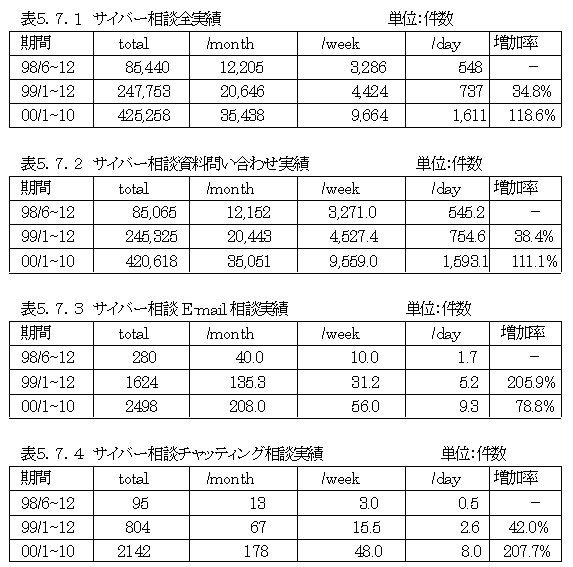
補足 表 4.7.1から4.7.4の増加率は98/6-12に対するものである。
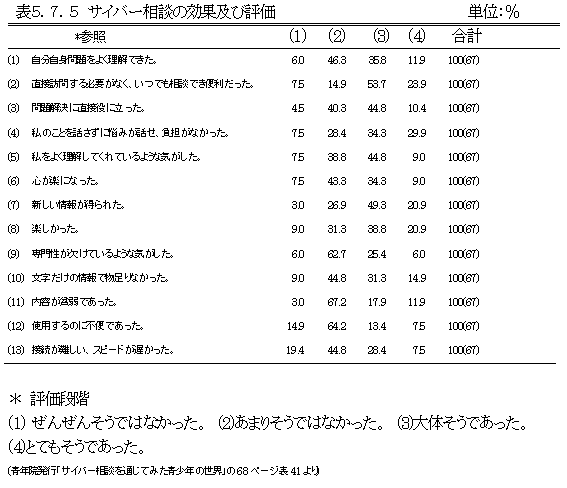
所沢市立教育センターでの実践方法について以下に示す。
(1)所沢市立教育センターでの不登校児に対するカウンセリングの総合的な対応方法所沢市立教育センターでは、図4.8.1に示すような6つの相談業務を実施している。
電話による申し込みにより、相談者の悩みに対して、直接会ってカウンセリングを行う。
保護者・教員に対し、電話を通して、カウンセリングを行う。また、そのなかで、直接面接を行った方がよいケースについては、面接相談をすすめ、面接相談の申し込みを受ける。初めから、面接相談を申し込まれる場合もある。
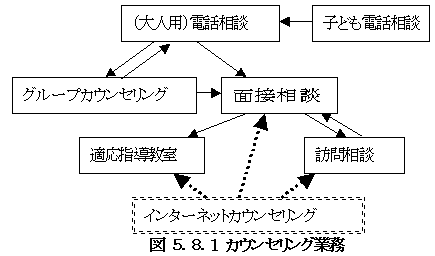
児童・生徒に対し、直接電話を通しカウンセリングや情報提供を行う。
非行や引きこもりがひどく学校との連携が取りにくい場合、保護者と学校からの申し込みにより直接家庭に相談員が訪問し、カウンセリングを保護者や子どもに対し行う。
情緒的不安傾向の不登校児童・生徒が自主学習やさまざまな体験活動を通し、学校復帰をめざす。センターに通える者は、保護者または本人に学校復帰をめざす意志があるかを確認し、面接相談を通してすすめる。最終的には、学校長からの申し込みによる。
広報「ところざわ」により募集し、不登校などに悩む保護者に集まってもらいグループカウンセリングを行う。
* 不登校に関わる相談の多くは、直接子どもが相談に来ることはない。その保護者が心配し、電話相談や面接相談やグループカウンセリングに申し込んでくる。保護者をサポートしつつ、その中で、子どもが動けそうな場合、保護者と子どもの両方に面接を行ったり、さらに、適応指導教室に興味をもてば、そこへの入級を進め、直接子どもへのサポートを行っていく。
また、引きこもっている場合については、訪問相談という形をとり、相談員との関係を作り、適応指導教室や学校へと結びつけるようにする。
(2) 上記の中でのインターネットカウンセリングの位置づけ等
インターネットカウンセリングの中で所沢市立教育センターでは、まずメールによるカウンセリングを導入する。 現在の不登校児童・生徒に対しPCを貸し出して行うメールによるカウンセリングは、適応指導教室や面接相談の補完的な意味合いが強い。
というのは、現在のメールによるカウンセリングは、既に面接相談を行っているケースのうちから対象者を選んでいるし、また一部、学校長にお願いし対象者を選ぼうとしているからである。何れにしても、センターと家庭との関係ができあがっているものについて実施することになるからである。
よって、不登校状況に合わせ、相談員や学校関係者とのやりとりを通し、子ども達が少しでも外に目を向け、行動や人間関係が広がるようにすることが、第一の目的となる。そしてPCを扱うことで、家庭でのコミュニケーションの広がりのきっかけともなる。また、PCを扱うことで、できないことができるようになる(メールの送受信、その他のソフトの操作、PCの操作等)ことで、自信を持つことが第二の目的となる。
(3) 所沢市立教育センターでのインターネットカウンセリングシステムの導入による改善
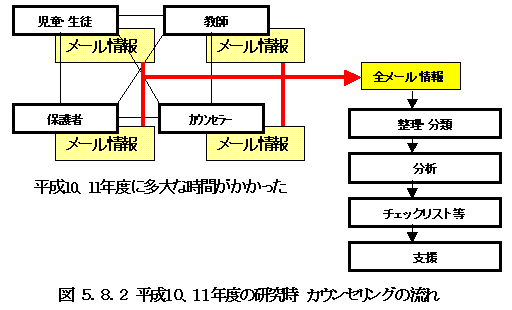
今回のシステムの想定運用のベースになった、所沢市立教育センターでの平成10、11年のメールカウンセリングの流れを図4.8.2に示す。
カウンセリングの作業としては次のようなことがある。
対象児童・生徒とのメールのやりとり
対象児童・生徒とカウンセラーおよび保護者、教師などの関連メールの収集(各家庭からメンテナンス時にFDにて収集)
各メールの整理、分析
(対象児童・生徒に対して適切なメールを頻繁に出すためにはこの整理・分析が必要)
このような個別対応において10、11年度の研究では、実際のメールのやりとりや、カウンセリング記録の分析に各カウンセラーが非常に時間をとられていた。そのため、実際少数の児童・生徒しか対応できなかった。
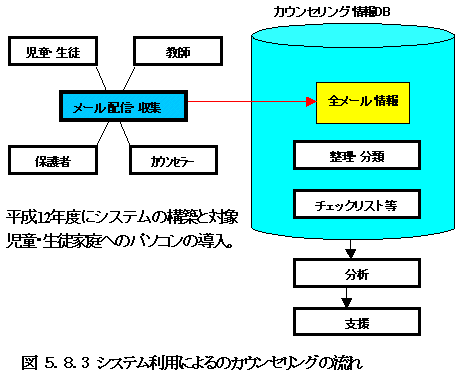
所沢市立教育センターは、インターネットを使用したカウンセリングを日常業務として実施するための支援システムとして、今回のシステムを位置付けている。システムを使用した場合のカウンセリングの流れを図4.8.3に示す。特に平成10、11年度にカウンセラーの負荷が高かったメールデータの収集および、データの整理・分類をシステム化することにより、より効率的、効果的にカウンセリングが実施できることが予想される。また、カウンセリング情報がデータベース化されているため、従来できなかった多方面の分析も可能である。
平成12年度において、システムの構築、システム機能の確認、および試使用が完了したため、平成13年度からは、従来の対面を主体としたカウンセリングに加えて、メールを使用したカウンセリングを正式業務として実施する予定である。
(4) メールを中心としたインターネットカウンセリングの実施手順
現在の貸し出し実施手順
1)面接相談あるいは適応指導教室のケースから候補を選出(一部学校長に依頼)
2)保護者に相談
3)保護者、本人の意思を確認
4)OKの場合は、家庭にセンター職員がPC設置に出向き、取り扱い方法などを説明
5)交信開始
6)学校に連絡し、学校のPCに対象児童・生徒のアドレスやフォルダをセット
学校とも交信開始
今回上記の確認やPCの貸し出しの確認書を作成した。
(5) 具体的な不登校児の選択、また、実施のための親や学校の許可等
子どもの情緒不安定感がやや強くさまざまなサポートを必要とするケース。(未実施)
消極的でなかなか話し言葉でコミュニケーションがつけずらいケース。(2件)
PCなどに興味をもっているケース。(2件)
引きこもってしまっているケース。(1件)
院内学級にいる生徒。(1件)
実施のための親や学校の許可
まず、保護者には、こちらから趣旨を説明し、実施してみたいという意思の確認をおこなう。確認ができたら確認書に記名・捺印をお願いし、貸し出しを行う。学校には、実施することを伝え、学校のPCにもアドレスとフォルダを作成に行き、趣旨を説明する。
(6) メールを中心としたインターネットカウンセリングの注意点
PCを通した文字情報だけなので、互いにその文字情報をどのように受け取るか不安がある(誤解を生む可能性もある)。
電話と違っていつでも見ることができ、いつでも返信を送ることができるよさがあるが、閲覧を忘れたり、時機を失ってしまったりということもありうる。今回はシステムの導入で単に直接の担当者以外もメールの更新状態をチェックすることが可能なため、どのような体制で今後行っていくか検討する必要がある。
メッセージの個人情報をどの程度守れるのか不安がある。たとえば、カウンセラー側のメールを、相談者が悪意をもって公開することも考えられる(現実にはまだないが)。
パソコンだけに埋没してしまう可能性も否定できない。
回数が多くなってくるとその変化などを分析するのが容易でないが、今回はシステムの導入により軽減されることが予想される。
(7) メールでのやりとりを増やすような工夫
特に意識的には行っていないが、行事や節目の時期にこちらからこまめにメッセージを送るようにしている。
こちらに送られてきた場合には、できるだけ早く的確に応答するようにしている。1週間に1度ぐらいはメールをみたり、出したりするように最初にお願いしてある。
今回のシステムでは、一人の児童・生徒に対して複数のカウンセラーがメールで対応してその情報を共有することも可能である。従来の1対1のカウンセリングから1対nのカウンセリングが可能になったことによる運用方法を検討していく。
メールがない場合は、操作上の問題があるときもあるので、電話確認をして、必要があれば家庭訪問を行う。
(8)教育実践活動における留意点、課題
所沢市立教育センターの実践と他の調査結果をもとに、今後のインターネット・カウンセリングの実践活動における留意点、課題を表4.8.1にまとめる。
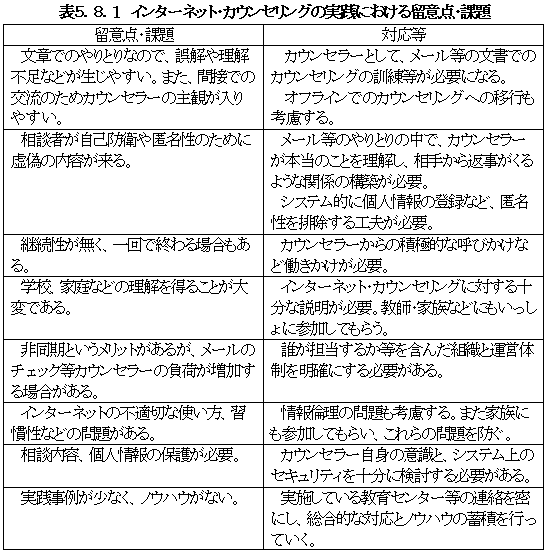
11月に中間報告会があり、委員より表4.9.1の指摘があり検討した。
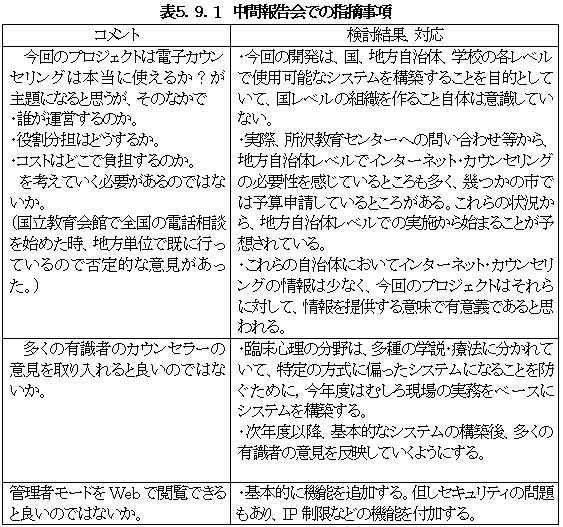
実運用に先立ち、システム機能について関係者内で動作確認を含み評価した。 以下、改良要求等について表4.9.2 に示す。
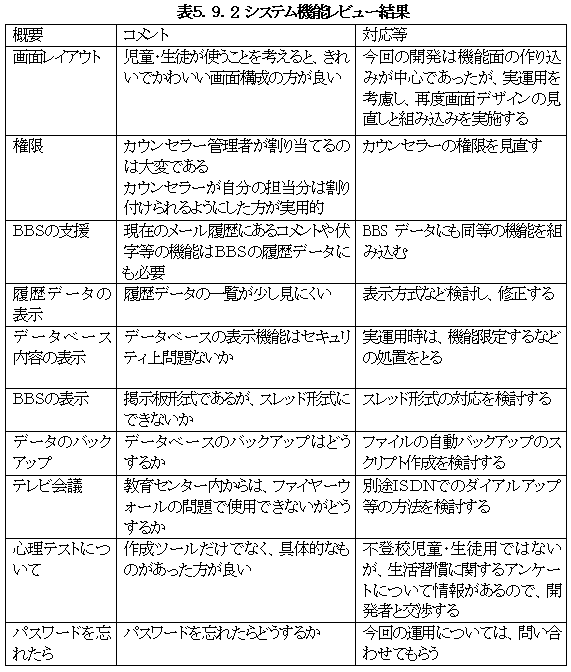
今回のプロジェクト開始時より、不登校児童・生徒などの状況の改善は長期的な判断が必要であり短期に結果はでないが、今回の実践の範囲における状況などを表4.9.3に示す。 尚、下記の判断は主に相談者とカウンセラー等のメールの分析結果にもとづく。
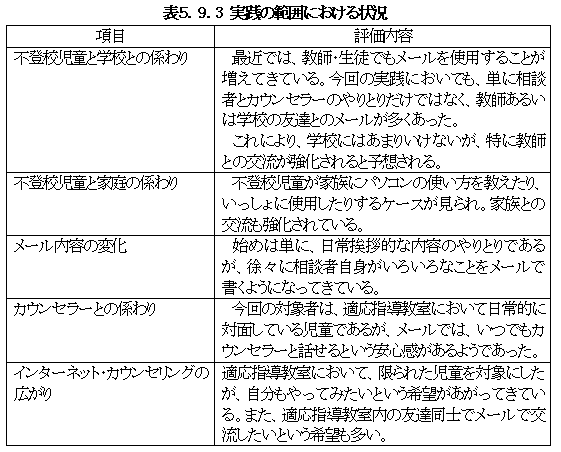
下記のサイトを開設し、プロジェクト内容、経過や成果を公開している。
「不登校児童・生徒を対象とした電子カウンセリング支援システムの構築」
尚、本サイトは以下のCECサイトよりリンクも張られている。
下記の目的を持った情報交換用メーリングリストを開設した。
児童・生徒の心をめぐる問題は広範で多様であり、その対応として、今後はインターネットを使用したカウンセリングが日本でも普及することが予想される。
本メーリングリストでは、平成12年度E2「先進的情報技術活用プロジェクト」の 「不登校児童・生徒を対象にした電子カウンセリング支援システムの構築」 をベースとして、今後の日本でのインターネットカウンセリングの方法、システム、問題点等を広く意見交換・検討する場とする。
尚、メーリングリストへの申込み方法は、上記サイトに説明がある。
今回のプロジェクトの成果は大きくシステムと、インターネット・カウンセリングに関する各種資料に分かれる
資料に関しては、主として上記サイトより入手可能である。
自治体や学校などでの、今後のインターネット・カウンセリング実施にあたっての検討資料
実際のインターネット・カウンセリングを行う場合の手順書・参考資料
インターネット・カウンセリング・システムを新規構築する場合の参考資料としての利用が可能である。
また、システムについては、システムのセキュリティ保護の問題により、プロジェクトチームに要求があった場合にプログラムを提供する。
システムを認知してもらうことと、今後、カウンセリングの有識者に活動に参加してもらえるように下記の学会などで成果を公表していく。
地方自治体の教育センターの連絡会
(所沢市立教育センターにはインータネット・カウンセリングの問い合わせが多く、教育センターレベルで公開、普及していくことが有効と思われる)
日本教育心理学会
日本教育工学会