国際交流支援システムの開発及び実証実験 |
本実証実験で使用したシステムの全体構成を以下に示す。
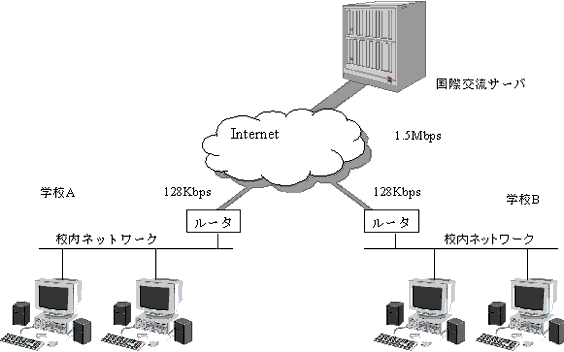
図 11 システム全体構成
以下に、上記システムを構成するサーバ環境、クライアント環境について記述する。
1) ハードウェア
以下のスペックのPC/AT互換機にLinuxをインストールして用いた。
|
CPU |
Celeron 500MHz |
|
メモリ |
64Mbyte |
|
ディスク |
約15Gbyte |
2) ソフトウェア
本システムにて開発したソフトウェアは以下の環境を用いている。
|
必要なソフト |
説明 |
|
Linuxカーネル2.0.35以上 |
OS |
|
Apache 1.3.9以上 |
Webサーバ |
|
Perl 5.6.0以上 |
本システムにて開発したCGIプログラム実行用のインタプリタ |
|
次のPerlモジュール
|
本システムにて開発したCGIプログラムが利用しているモジュール |
|
cgiwrap |
CGIプログラムを特定ユーザ権限で安全に実行するためのプログラム |
|
nkf |
日本語コード変換用プログラム |
|
enMime, deMime |
メール送受信時の添付ファイル取扱いプログラム |
|
sendmail |
メール送受信用プログラム |
|
procmail |
メール振分け用プログラム |
3) ネットワーク
1.5Mbpsの専用線に接続されている。
1) ハードウェア
NetscapeあるいはInternet Exploreが動作すれば、特にハードウェアは限定しない。本実証実験の際に、主たる学校で利用したハードウェアはPC/AT互換機である。
2) ソフトウェア
Netscape4.0以上あるいはInternet Explore4.0以上のWebブラウザのみインストールされていれば、メール作成他、本システムの主要部分は利用可能である。
コンテンツとして用意している動画ファイルを閲覧する場合には、ブラウザにプラグインとしてRealPlayer 8(Basic版は http://www.jp.real.com/products/player/ より無償ダウンロード可能)が組み込まれている必要がある。
3) ネットワーク
主たる評価校の環境は、10/100MbpsのLAN経由で、128Kbpsの回線で外部ネットワークに接続されている。
図 12に、実証実験を実施するための体制を示す。
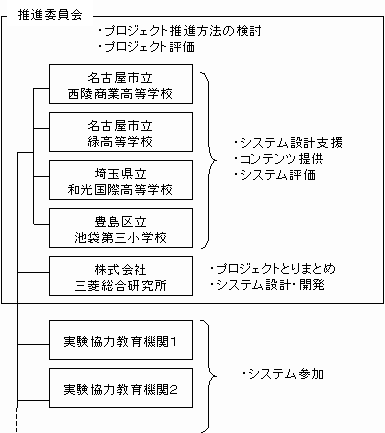
図 12 実施体制
推進委員会に属する学校・企業において、システム機能検討やコンテンツ収集、実証実験実施によるシステム評価等を行った。
実証実験は、教員および生徒が実際に本システムを使用して英文メールを作成し、国際交流場面へ適用することにより行った。実験後には、システムが国際交流実施に及ぼす影響とシステム使用感について教員および生徒にアンケートを実施すると共に、実際に授業を実施した観点からの知見を教員から収集した。
以下に、実験の概要と実験実施期間、実験参加者を示す。
1) 実施概要
実験参加校の実験環境を4.1において示したクライアント環境に基づいて整備した後、実際にシステムを用いて英語によるメール作成および送信を行った。
教員に対してシステムを利用した国際交流授業の指導案を提示し、授業イメージをつかんでもらった上で、それぞれの学校の特性に応じて、適切な教科、送信相手、メール内容を設定し、授業を実施した。
2) 実施期間
2000年12月〜2001年1月
3) 実験参加者
- 児童・生徒(小学校3年生から高校3年生まで)
- 指導教員(小学校、中学校、高等学校)
- 海外における日本語学習者
1) 実施概要
システムを利用した国際交流実施に参加した児童・生徒や教員を対象とし、Web上でアンケートを実施した。アンケートの内容は付録1、2に示す。
また、システムを利用した国際交流授業を実施した教員からは、指導内容や児童・生徒の様子、システムに対する所感等についての報告を収集した。
2) 実施期間
2000年12月〜2001年1月
3) 実験参加者
- システムを利用した児童・生徒(小学校3年生から高校3年生まで)
- システムを利用して授業を行った教員
- システムを試用した教員
アンケート調査を実施するに際しては、以下の観点から項目を作成して評価を行った。
1) 授業の満足度
- システムを利用した国際交流授業に参加した結果、授業内容や授業の進め方に対する生徒の満足度はどの程度であったかを評価する。
- システムを利用して国際交流授業を実施した結果、授業内容や授業の進め方、および授業の準備段階における教員の満足度はどの程度であったかを評価する。
2) 交流による達成感
- システムを利用した国際交流を実施した結果、国際交流の内容や結果に対する生徒の充実感と国際交流を継続していくことに対する意欲はどの程度であったかを評価する。
- システムを利用した国際交流を実施した結果、国際交流の内容や結果に対する教員の充実感と、国際交流授業を継続して行っていくことに対する意欲はどの程度であったかを評価する。
1) システムの操作性
- システムの反応速度は授業での国際交流実施に十分なものであったかを評価する。
- システムのコンテンツは実際の国際交流実施に十分な量および内容であったかを評価する。
2) インタフェース
- システムを国際交流授業で利用した結果、生徒が簡単に操作するのに十分なものであったか、教員にとっても操作性は十分であったかを評価する。
- ユーザインタフェースは生徒にとって十分使いやすいものであったか、教員にとっても十分なものであったかを評価する。