5.教材とサーバソフトの要件と試作
5.1 教材の要件
本節では、試作する教材の要件について検討を行った結果について述べる。 要件調査にあたっては、手書き入力に関する専門的技術をもつ富士通研究所の研究員、実践授業を行う三木市緑が丘東小学校の教員、教材開発や授業設計に関する指導助言を行う立場から三木市立教育センターの指導主事、教育工学を専門とする大学教員、実践環境の手配や構築を担当する富士通株式会社のSEらが協力して進めた。
具体的な検討手順として、実証実験の期間(2学期)や対象学年(5年生)での授業を前提に、教材内容の検討を行った。算数の計算問題や漢字の書き取り、見写(書き方)、地図への書き込み、絵画デザインなどの多くの内容を検討した。
これらの中から、開発期間や技術的な実現性も考慮して、今回の実践授業で利用する教材を決定した。対象教科としては、学習過程の中で「手書き」の比重が高く、反復学習が必要な、算数と国語を対象とすることにした。教材試作にあたっては
1-2の目的・狙い、であげた以下の5項目の機能目標の達成を目指した。
- 手書きによる解答入力・自動採点
- 書き方の判定と正しい書き方の提示機能の実現
- 自由な書き込みによる思考過程のサポート
- インターネットや家庭環境での利用
- 現場教師による自作・カスタマイズ
なお、教材検討にあたっては、児童ひとりが一台ずつタブレット PCを使用する環境を前提に検討した。
5.1.1 教材開発環境と教材構成
決定した教材の内容と、上記5項目の機能目標を実現するために、動きのある WEB コンテンツの作成環境として広く普及している Macromedia
Flash MX を教材開発環境として採用することにした。これによって、機能目標 D(インターネットからの利用)が解決でき、機能目標E(現場教師によるカスタマイズ)にも寄与すると考えた。
また、機能目標 A(手書き解答)、 B(正しい書き方判定)、 C(自由書き込み)を Macromedia Flash 教材で実現するため、別途富士通研究所で開発した、学習用手書き認識部品、および自由手書き部品
( Flash MX のライブラリ )を使用した。
実際の教材を開発するには、上記手書き部品を直接利用する形では教材構成が複雑になり、開発効率が悪いだけでなく、機能目標E (現場教師による教材作成)の達成が困難になる。このため、筆算や漢字書き取り等、特定の意味をもった教材構成要素を、上記部品を組み合わせる形で、
複合部品 として試作した。試作した複合部品には、小数割り算部品、分数計算部品、漢字書き取り部品、などが含まれる。これらの複合部品や基本部品、アニメーションなどの各種Flashコンポーネントを組み合わせて、教材の形に構成したものを
教材テンプレート と呼ぶ。この教材テンプレートに実際のコンテンツをセットすることで手書き電子教材が実現できるような形にした。
図 5-1に手書き電子教材の構成を示す。教材テンプレートに個々のコンテンツをセットすることは現場教師にも可能であり、このような教材構成とすることにより、機能目標E(現場教師による教材作成)の要件を満たすことが可能となった。
図5-1.手書き電子教材の構成
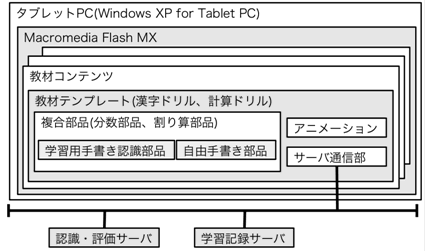 |
5.1.2 ログイン画面
教材を使用するにあたり児童の個人IDを入力するログイン画面での要件としては、
- 手書きできるタブレット PC の特性を活かすこと
- 不確定操作や時間を要する操作は入れないこと
を結論とした。
また、パスワードで保護する内容はほとんどないこと、パスワードを忘れる児童がいることを考えて、児童はパスワード設定なしでログインすることとした。
5.1.3 学習記録参照画面
児童が学習した状況を確認する学習記録参照画面での要件として、
- 担任教師が受け持ちクラスの児童の学習記録を参照できること
- 教師が受け持ち学年の児童の学習記録を参照できること
- 児童が教材を使用した履歴が参照できること
- 児童が教材を使用した結果が参照できること
を抽出した。
また、児童が自分自身の学習記録を参照するためには、児童のログイン時にパスワード設定をかけて、自分自身の学習記録だけを参照できるようにすることが必要となる。
5.1.4 一斉授業用教材
一斉授業で使用する教材としては、これまでノートや教師が用意した学習プリントの代わりになるもの(自由ノート教材)と漢字教材、算数教材の3種類について要件の検討を行った。
自由ノート教材の要件としては、
- 児童が画面上に自由に文字を書いたり絵を描いたりできること
- デジタルの良さを活かして、ペンの色を変えられること
- 塗りつぶしなどを容易にするための太いペンも用意すること
- 学習単元に応じて教師が作成した背景画がはめこめること
- 教材上に児童が描いた内容を児童の ID と対応づけて保存し、次回に同じ教材を開いた際にはその内容が表示されること
を抽出した。
また、一斉授業で使用する漢字教材については、以下を要件として抽出した。
- 必要量の問題が表示できることを前提として、解答枠が解答を記入するのに十分な大きさであるかどうかを検証してサイズを決定する
- 解答枠からのはみ出し記入にもある程度対応する
- 書くモードと消すモードを設け、ペン先のアイコン表示を変えるなどして現在のモードがどちらのモードかがわかるようにする
- 新出漢字を書いて覚える教材では、表示された手本をなぞって書けるようにする
- 手本をなぞる際には、手本文字の一画をなぞって入力すると手本文字の次の一画が表示され、正しい筆順で書けるようにする
- 文字の形と筆順の両方を評価した判定を行い、自動採点を行う
- 自動採点の結果、正解となった場合には解答の上に○を表示する
- 自動採点の結果、誤りと判定された場合には、形の間違いと筆順の間違いを区別して表示する
- 自動採点の結果、誤りと判定された場合には、その記入枠の隣にヒントボタンを表示し、ヒントボタン押下により書き順の手本が表示されるようにする
- 採点結果を保存し、教師が児童のIDと教材IDを対応づけた形で参照できるようにする
一斉授業で使用する算数教材については、以下を要件として抽出した。
- 必要量の問題が表示できることを前提として、解答枠が解答を記入するのに十分な大きさであるかどうかを検証してサイズを決定する
- 複数桁の数字を1つの解答枠内に書けるようにする
- 小数点記入用枠に小数点を書けるようにする
- 解答枠からのはみ出し記入にもある程度対応する
- 書くモードと消すモードを設け、ペン先のアイコン表示を変えるなどして現在のモードがどちらのモードかがわかるようにする
- 解答枠以外のところにも計算過程等を自由に記入できるようにする
- 解答枠に記入したものと、解答枠以外に記入したものはペンの色を変えるなどして区別して表示する
- 解答枠に書かれた数字を文字認識により自動採点を行う
- 最終解答だけでなく、筆算等の計算過程も採点対象とする
- 自動採点の結果、正解となった場合には解答の上に○を表示する
- 自動採点の結果、誤りと判定された箇所には誤り判定のマークを表示する
- 間違い直しボタン押下により、間違った箇所の筆跡がすべて消去されて書き直しできるようにする
- 採点結果を保存し、教師が児童のIDと教材IDを対応づけた形で参照できるようにする
5.1.5 自主学習用教材
自主学習で使用する教材としては、漢字教材、算数教材の2種類について要件の検討を行った。
自主学習で使用する漢字教材と算数教材については、一斉授業で使用する教材の要件に加えて以下の要件が必要であると考えた。
- 自動採点の結果、全問正解となった場合には花丸などの特別な表示を行う。
- 全問正解時の特別表示は、解答の上に透けて表示されるようにし、何らかのアクションがあるまでは表示されたままにしておく
- 解答するのに要した時間を測定できるようにする
5.2 サーバソフトの要件
本節では、サーバソフトの要件について検討を行った結果について述べる。
5.2.1 認識・評価サーバ
認識・評価サーバは、主として手書きされた解答を自動採点する機能を実現するものである。上述した教材を実現するために認識・評価サーバが満たすべき要件は以下である。
- 児童が丁寧に正しく書いた数字や文字は確実に認識できること
- ひとつの解答枠内に書かれた複数桁の数字を認識できること
- 文字の形と筆順の両方を評価した判定ができること
- 児童が間違って書いた文字は、形の間違いと筆順の間違いを区別して判定結果を返せること
- 児童が間違って書いた数字や文字を正解としてしまう誤認識や誤判定は最小限にすること
5.2.2 学習記録サーバ
学習記録サーバは、主として児童が学習した結果を記録するためのサーバである。上述した教材を実現するために学習記録サーバが満たすべき要件は以下である。
- 学年、組、出席番号の組み合わせから児童の名前と各児童に固有の UID を検索できること
- 指定された教材カテゴリに合致する使用可能な教材の一覧を各教材に固有の教材 ID とともに返せること
- U IDと教材IDを対応づけた形で、ドリル教材の採点結果を保存できること
- U IDと教材IDを対応づけた形で、自由ノート教材の筆跡情報を保存できること
- U IDと教材IDを指定して、その教材に対する児童の採点結果を読み出せること
- U IDと教材IDを指定して、その教材に対する筆跡情報を読み出せること
- 教材を使用するタブレット PC とインターネット接続されたサーバ上で上記の機能を実現できること

