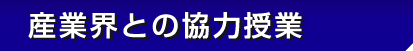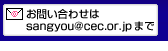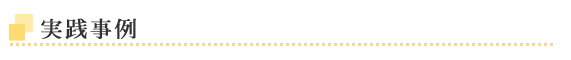|
■進行
飼育管理や解説員の経験をしている職員を講師とし、CD−ROM教材「水族館の仕事から学ぶ環境保護の大切さ」の画像を使いながら、体験談を交えて、水族館の多くの仕事が、動物たちの保護につながっていることを解説した。また、館からラッコの毛皮、イルカの調教道具、紙コップの糸電話などを持参し、道具を使った体験実験を行い、子どもたちの興味関心をひきつけた。さらに、授業の最後には質問の時間を設け、職員との対話も行った。
■内容
・サメの皮膚や歯の画像を使い、サメの本当の姿や生態、飼育する上での苦労話、県内各地の河川にいたヒナモロコが、今では限られた川にしか生息せず、その繁殖活動に水族館が取り組んでいることを解説した。子どもたちは、恐い生物と思っていたサメが危機に瀕している状況を知り、驚いた様子であった。
・また周辺の海岸にはイルカやクジラ類も漂着しており、死因の一つにゴミが影響していること、また水族館がイルカやクジラの保護活動をしていることも、PCやVTR映像などで説明した。
1年前の鹿児島でのクジラの漂着救助の映像では、危険を冒して保護活動に取り組む職員の責任感や勇気に感動していた。
・イルカのトレーニング過程を、イルカの着ぐるみを着た児童をイルカに見立て、調教体験を行った。イルカがどのようにしてジャンプを覚えるのか、自分の身をもって体験し理解がすすんだ。
・紙コップで作った糸電話では、イルカが顎の骨で音を聞く体感実験を行った。骨から音が伝わることを知り、感動していた。
・ラッコでは毛皮を用意し、防寒着として人の役に立ったことを体感させ、一方で乱獲され絶滅の危機にあること、さらに油流出事故で保護したラッコの様子を放映し、保護のために水族館などの飼育経験を持つ施設が役立っていること解説した。
水族館と言う飼育技術を持った施設にしかできない救助活動があることを学んだ様子であった。
・作成したCD−ROMでは、豊富な写真や動画を使いながら、水族館の様々な仕事の様子を紹介し、教育の仕事では自然や動物の大切さを伝える機能、研究の仕事では繁殖や病気の治療、リクレエーションの仕事では調教することで健康管理に役立つことを解説した。またどの仕事も動物や環境の保護につながっていることを解説し、水族館という産業が、遊びや楽しさを満足させる機能だけではないことを話し、職員の仕事が、野生動物と関わる責任とやりがいの有る仕事であることも伝えた。
・なおこの授業では、城南小学校が、事前にWebなどを使って絶滅に瀕している野生動物や、水族館との関わりなどを調べており、学習に入る前に班ごとに発表し、職員は感想を述べ質問にも答えた。子どもの中には、保護団体が運営するホームページで水族館や動物園の存在を否定するコメントを見つけ、どちらの意見が正しいのか悩んでいたが、当館職員のアドバイスにより、改めて水族館の役割を学んだ。
|

CD−ROM教材の映像を使い解説
(福岡市立三筑小学校)

CD−ROM教材の映像を使い解説
(福岡市立城南小学校)

イルカの調教を体験
(福岡市立城南小学校)
|