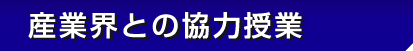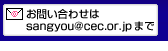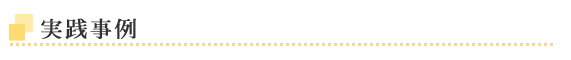���Ƃ͑�^�X�N���[����2���g���āA
PC�����ōs��

�@�@�����ł́A���ː��v����i�T�[�x�C���[�^�[�j������������ŁA�̌��I�Ɏ����ɕ�����₷�������������B

�@�@�s�̂̓����܂⎞�v�̕����ՂȂǂ���A�����̕��ː����o�Ă��邱�Ƃ��A���������ڑ��肳���Č�����B

�@�@�����S��d�r�ɂ�������ł́A�قȂ�����̓d�ʂ̈Ⴂ�𗘗p���āA���y��点��������s���B

�@�@����玝�����l�X�Ȗ��ʕ��ł����y���Ȃ邱�Ƃ�̌����A���̎�ނɂ���ĉ��ʂ��قȂ�Ƃ��납��A�Ȋw�I�Ɏ������ʂ��l�@���Ă݂�B

�@�@�u�t�́A�e�[�}���ƂɎ�������̎�����t����B����̓��e�́A���w���Ƃ͎v���Ȃ��悤�ȍ��x�Ȃ��̂��������B
|