


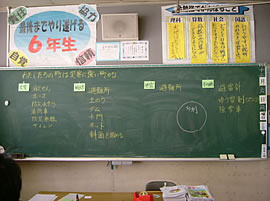



| 5.システムを活用した授業実践 |
5.3 第2分科会(地域の防災マップ)
1,ねらい
○地域防災に対して興味を持ち、災害に強い町にしていこうとする態度を育てる
○情報機器を有効に活用し、資料を作成するとともに考察できる能力を育てる
○複数の情報から自分の意見を持ち、相手に対してわかりやすく伝える能力を育てる
2,実践の概要
私たちの住んでいる町は、いつどのような災害にあう可能性があるかを考え、その可能性に対して町はどんな対策や予防策をとっているのかを調べる活動を通して、自分たちの町を見つめていくことをねらう。
まず、今までの経験から起こりうる可能性のある災害を出し合っていく。火災、水害、風害、地震などが取り上げられるであろう。それぞれの災害に対して、私たちの町はどんな対策や予防策をとってるかを予想し、実際にフィールドに出て調査する。校区地図上に調査したポイントと写真、および内容をつけていきながら、マップづくりをする。マップづくりにおいては、GPS携帯電話とGISを活用して自動作成していくことになる。出来上がったマップから、自分たちの町はどれぐらい災害に強いのかを検討し、分析するとともに、他校が同様に作成したマップと見比べたり、意見交流することによって、さまざまな視点から将来の町づくりについて一人一人が提案できることをねらう。
3,実施時期
12月6日〜12月17日
4,指導計画(全10時間)
| 時 | 学習活動 | 留意点・準備物 |
| 1 | 私たちの町はどんな災害にある可能性があるか考える | ・交流学習をすることを知らせておく ・過去の災害について調べておく |
| 2 | 災害に対して予防する設備や災害を最小限に抑える設備にはどんなものがあるか予想を立てる | |
| 3-6 | 実際に校区へ出ていって調査活動をする | ・GPS携帯電話 |
| 7 | 調査したデータを見直す(補正・修正) | |
| 8 | 他校の防災マップと見比べながら自校の出来上がったマップから自分の町がどれぐらい災害に強いか検討する | |
| 9 | 町が災害に強いかどうかについて他校と意見交流する | ・テレビ会議システム |
| 10 | 町についてわかったことと将来の提案を書きまとめとする |
○具体的な実践とガイド
| 【第1時】○わたしたちの町に起こりうる災害について理解する | |
 |
 |
| (写真1) | (写真2) |
| 【第2時】○災害別に分類し、それに対応した設備について予想する | |
 |
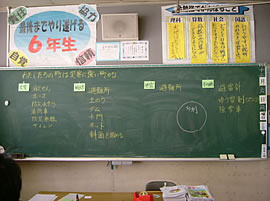 |
| (写真3) | (写真4) |
| 【第3時〜第6時】○地域の調査活動をおこない、災害対策の施設設備を分布地図を作る | |
 |
 |
| (写真5) | (写真6) |
| 【第7時】○災害別に調査地図を整理する | |
 |
|