

※紹介サイトを閲覧してイメージをつかむ。
○どんなマップを作り上げるのか、最終的なマップのイメージを作る
○調査計画を立てる(ワークシートの活用)。

※GPS機能付き携帯電話を活用して取材をする。
※時間や児童の興味関心等を勘案して「遊んでいる場所」にとどまらず「遊びたい場所」「遊んでいた場所」へと取材の網を広げることも可。
○写真をアップする際に、最低限の情報も同時に記録する。
○写真の構図を工夫する。
※実際に遊んでいる場面が撮れるとよい。

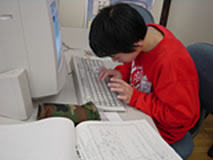
○最初にイメージしたマップに近づくようにする。

○「遊び場や遊び方への質問や感想」「新しい遊び方の提案」「互いの遊びを比較して気づいたこと」等々を自由に述べ合う。
○野外活動の専門家等のアドバイスが得られれば写真を見てアドバイスをいただく。
○完成したマップをどのように活用するか考える。
○場合によって、保護者も交えた授業参観等で、マップの活用について考えたり、世代間の交流を行ったりする。