地域活動に関する実践研究の総括 |
|
宮城勤労総合福祉センター 蔵王ハイツ |
|
教育と地域の情報化を考えるシンポジウム実行委員会 |
|
宮城教育大学 環境教育実践研究センター |
|
宮城県教育委員会 |
|
アライドテレシス株式会社 |
|
主に,東北地方を中心とした初・中・高等教育を担当される先生方,教育委員会の方々。さらに,教育現場や地域の情報化を支える方々や,ネットワーク関係者を対象とする。 |
|
眞壁豊 仙台幼児保育専門学校 |
安江正治 宮城教育大学 |
名越幸生 東北学院中学高等学校 |
|||
|
|
渡辺景子 いわき明星大学 |
高橋洋充 仙台市立太白小学校 |
|
||
去る2000/11/11(土)、宮城県・蔵王ハイツにおいて「教育と地域の情報化を考えるシンポジウムin宮城(略称:SPER2000 in MIYAGI)」が開催され、東北地方を中心に120名を越す教育関係者、地域活動者、そしてネットワーク事業関係者が参集した。このシンポジウムの実施内容及び開催に至る組織・準備内容などについて報告する。
2000年11月11日(土)、宮城県・蔵王において「教育と地域の情報化を考えるシンポジウムin宮城」が、同シンポジウム実行委員会、東北学術研究インターネットコミュニティ(TOPIC[1])、及び郵政省東北電気通信監理局(現:総務省 東北総合通信局)の主催により開催された。
このシンポジウムでは、1つの基調講演と、東北各県の初中高等教育機関所属者や、各地域で活躍されている方々より9名の事例発表がなされ、120名を越す教育関係者や地域活動者、及びネットワーク事業関係者が参集した。本稿ではシンポジウム開催に至る組織・準備内容及び実施内容等について報告する。
なお、2001年1月現在公開されている「SPER2000 in MIYAGI」WebサイトURLは、以下の通りである。
参考資料1に、「教育と地域の情報化を考えるシンポジウムin宮城(SPER in MIYAGI)」(以下、“本シンポジウム”)の開催要項を示す。
本シンポジウムは、1999年3月に福島市・飯坂温泉において「教育と地域の情報化を考えるシンポジウム」(主催:TOPIC、あぶくま地域展開ネットワーク研究会、福島県インターネットワーキング技術研究会)が開催されたことに端を発している。
この「飯坂シンポジウム」の開催によって培われた福島県内の人的ネットワークの構築を、東北広域圏へ広げようとの意図から、約半年に1回という間隔で、東北各地で本シンポジウムが開かれており、岩手県・花巻、秋田県・田沢湖に続く、第4回に相当するのが、今回の「SPER2000 in MIYGAI」である。
2000年4月下旬、仙台で定例のTOPIC総会・研修会時に、同年6月に開催が迫っていた、秋田県・田沢湖での開催に向けての会議の席で、次回開催を宮城で行う旨の打診を受けた。そこで、この打診を受けて宮城サイドは5月より、開催に向けて準備を進めることとなった。
準備開始当初は、数名という規模で個人メール(あるいは数名に対するメール)という形である程度行ってきた。しかし準備に関わる人数が増え、徐々に準備段階が具体的な事項に及ぶにあたり、6月はじめに本シンポジウムのメーリングリストが成立することとなった。このメーリングリストが、事実上、他に仕事を抱える人々が本シンポジウムの開催成功のために集う、実行委員会の議論の場となり、同時に、このメーリングリスト参加者が、本シンポジウムの実行委員となった。
開催までの間、東北各県からさまざまな協力者(ボランティア)が、このメーリングリスト(=実行委員会)に名を連ねることとなり、最終的には40名以上を越える実行委員会となった。
本シンポジウム開催に向けての準備を大きく分けると、いくつかの要素に分かれていた。以下では、それぞれの要素で経てきた準備内容を見ていくことにする。
本シンポジウムでは先にも述べたように、半年に1回東北各県から集まるということもあり、可能な限り参加しやすく、また一方では長時間にわたって納得のいく議論ができる場所の設定を行わなければならないと考えた。
そこで基本的には、以下の要件に見合う場所を探すことになった。
夜23〜24時くらいまで使用可能な100人(以上の)規模の会議室があること。
宿泊施設があること。
交通の便が良いこと。
開催日は11月の第2あるいは第4土曜日であること。
開催日を決定するにあたり、11月第4土曜日は、仙台市科学館で別のコンピュータ関連のイベント「仙台市ソフトウェア作品展」開催が既に予定されてあったので、事実上第2土曜日を、本シンポジウムの開催日とした。
開催場所は3カ所ほど候補に挙がっていたのだが、上記の条件すべてに見合う場所は「蔵王ハイツ」だった。予約を申請したのは、開催日から約5ヶ月前の2000年6月2日となった。これは会場となる「蔵王ハイツ」の11月分の予約受付開始日が6月からだったためである。この時点での予約内容は、
100人規模の会議室を、1日借りる。
宿泊数は、岩手県・花巻の例では89名だったこともあり、約90名とし、追って双方で調節することにする。
といった、簡単な内容であった。
先の開催日時、場所が正式に決定したのとほぼ同じタイミングで、宮城県内の主要な実行委員のメールアドレスを集め、本シンポジウム実行委員会メーリングリストの設置が行われた。ただ、本格的にこのメーリングリストが活用されはじめたのは、秋田県・田沢湖でのシンポジウムが終了した6月下旬からであった。
参加メンバーも、メーリングリスト作成当初は宮城県内のみで構成されていた。しかし、これまでのシンポジウムで実行委員として活躍されてきた方々や、東北圏内の人的ネットワークのつながりによって、まもなく東北各所から実行委員が参加することとなった。結果的に、実行委員会メーリングリストに参加した人数は40名を越えることとなった。
いっぽう、実行委員会内の各分担の作業が徐々に活発になってくるに従い、実行委員会メーリングリスト1つのみで運用していくにあたり、次のような問題が生じた。
あまりにも各分担に関する議論や活動内容が、1つのメーリングリストに集中されるため、1日あたりの投稿量が爆発的に多くなってしまった。
まだ確定段階まで進んでいない議論を話し合うための場がない。
そこで、予算・金銭関係など、実行委員会の中でも特に大事に扱わなければならない話題に関するメーリングリスト「m-sper-ac」(2000年10月5日作成)を皮切りに、さまざまな分担別メーリングリストが立ち上がることになった。最終的に本シンポジウム開催時点では、以下のメーリングリストが立ち上がっていた。
m-sper
実行委員会メーリングリスト。以下の各分担からの決定事項の報告などを行う。ここに投稿すれば、実行委員会メンバー全員に配信される。
m-sper-ac
比較的大事に扱う話題を議論する。特に全体の意志決定が要求される場面では、まずここで議論される場合が多い。シンポジウム実行委員の中で、特に行動力が要求される主要メンバーで構成。
m-sper-co
展示ブースを設置する企業と、実行委員会との間で、展示に関する各種準備や打ち合わせに使用。
m-sper-panel
パネルディスカッションに参加するパネリスト(今回は、事例発表者)とコーディネータとの間で、当日の進行に関する準備などを行う。
m-sper-pc
他の分担の状況を確認しながら、当日のプログラムの構成を、ここで議論する。
m-sper-tech
意見回収システム、会場内イントラネットを実現させるための、技術的な議論を行うためのメーリングリスト。
m-sper-ml
本シンポジウムの「参加者」メーリングリスト。上に掲げたメーリングリストとは少々趣が違うが、交通(バス)の案内などといった、参加者全員に対するアナウンスが可能。
実行委員会開催日
2000年 7/4 7/24 8/21 9/19 10/17 11/1
(いずれも場所は東北学院中学高等学校、時間は6:30〜9:00)
実際にオフラインで実行委員会が行われたのはたった6回のみで、おおよそ月に1回のペースであった。主な議論や作業は、メーリングリストなどといったネットワーク(オンライン)上で充分行え、実際に行われていたのである。
しかし、参加できる実行委員は限られることになるが、シンポジウム全体の方向性や、会場設営に関する議論を、さまざまな現地の資料を広げながら議論するためには、どうしてもこのような1つの場所で話し合っておく必要がある。
もちろん、このオフラインで話し合った議論の内容が、すぐに本シンポジウムの決定事項になるのではなく、上記m-sperメーリングリストに報告することで、実行委員会内全体での共通認識を確認し、オンラインでの議論がより進むのである。
本シンポジウムでは、企業展示ブースの設置や、以下に述べる意見回収システムの開発など、これまでにはないさまざまな試みを行ってきた。しかしその準備段階は、メーリングリストの分化がはじまった開催約1ヶ月前の10月上旬までは、あまりエンジンがかかっていなかった状態は否めない。
ぜひとも次回以降の準備では、このような各分担における議論の「場」と、それらをまとめる「場」を、ネットワーク上で早めに設け、スムーズなシンポジウム開催準備を進められるように働きかけたいところである。
本シンポジウムにおいて、予稿集を編集・発行した。予稿集担当係として実行委員会より福島県いわき市立泉北小学校の根本省治委員、宮城県仙台市立連坊小路小学校の米谷年法委員、福島県いわき明星大学の渡辺景子委員がそのとりまとめに当たった。花巻、秋田でのシンポジウムと同様、印刷にかかる経費は主催・共催団体からの支援により賄われた。
原稿の執筆は、基調講演および1部・2部の発表者全員とそれぞれの部で行うパネルディスカッションのコーディネータ、さらに3部のパネルディスカッションのコーディネータ、および5名のパネリスト全員、さらに主催2団体(TOPIC、電監)の総勢20名に依頼した。また、それとは別に、今回の新しい試みとして企業からの寄稿も募った。
以下に、予稿集編纂の経緯を示す。なお、これらのやりとりは主にメーリングリスト上や個別のメールで行われ、実際に顔を合わせての打ち合わせは行わなかった。
8.中 予稿集扉絵・題字の内定
予稿集の表紙の扉絵として宮城県白石市教育委員会の中村敏弘氏に「蔵王のスケッチ」を借用することの快諾をいただく。なお、題字は、秋田シンポ時に秋田県立六郷高等学校の竹村美範氏により作成された物を流用させていただくことを、既に了解いただいていた。
10.05 予稿集表紙装丁担当者決定
予稿集表紙のレイアウトをあぶくま地域展開ネットワーク研究会の佐々木昇氏に依頼。快諾いただき、早速作業開始。
10.09 予稿集係根本委員よりページ割についての提案
10.12 予稿集原稿執筆要綱1.0 公布
締切10月24日。
原稿は所定のアプリケーション(MS-Word、一太郎等約10種類)で電子化したものをメールに添付し、原稿受付専用アドレスに送付する。
この時点で秋田県からの発表者はまだ決まっていなかった。
※対象は基調講演、1部・2部の発表者、パネルディスカッションコーディネータ、主催2団体のみ。
10.16 企業へ予稿集への寄稿を募る
広告でも構わないが、本シンポジウムにふさわしいもの。
広告掲載料はいただかない。
締切10月24日。
10.24 原稿締切
集まった物を予稿集係がpdf形式に変換し、Webサーバにアップ。執筆者はそれを確認。
印刷業者にここから確認済みの原稿をダウンロードしてもらう。
10.24 3部コーディネータ・パネリストへ原稿執筆依頼
いくつかの項目に対してメールに平文で記入。体裁は予稿集係で整える。
締切10月25日。
10.24 表紙・裏表紙の装丁完成
装丁担当の佐々木氏が直接印刷業者に原稿ファイルをMOで持ち込み入稿完了。
10.25 3部パネルディスカション予稿締切
ほぼ締切通りに全員の原稿が揃う。
11.02 予稿集係による最終調整終了
全原稿を印刷業者(針生印刷)に渡す。(Webよりダウンロードしてもらう)
仕上がりは11月10日(シンポ前日)。
11.10 夕方、東北学院中高に300冊納品。
本シンポジウムには、実行委員会メンバー約40名を含め、124名が参加した。この参加者のほぼ全員が、前述の「m-sper-ml」メーリングリストに参加したことになる。
シンポジウムの告知及び参加の呼びかけは、実行委員会メンバーによる各種メーリングリストへの開催要項の投稿、口コミ及びマスメディアへの働きかけ、各種教育機関への配布などを行った。参加申し込みはWebページ上のフォーム入力、電子メール、ファックス、以上3つの方法を設けたが、ほとんどの参加者がWebフォームによる参加申し込みだった。
以下に参加者の職業別、県別内訳を示す。
| 表5.1 県別参加者内訳 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 表5.2 職業別参加者内訳 | ||||||||||||||||
|
| 表5.3 校種別参加者内訳 | ||||||||||||||||
|
本シンポジウムも含め、「教育と地域の情報化を考えるシンポジウム」の持つ特徴として、会場内にイントラネットの敷設を行っており、これを生かしながらシンポジウム作りを行っている点が挙げられる。
特に本シンポジウムにおいて特筆すべき点は、後に述べる意見回収システム用のサーバ、ダイアルアップルータと可搬型端末50数台からなるネットワークを敷設し、質疑応答をWeb化したことである。
外部には、DDIポケットの無線回線(64Kx2又は32Kx4)でインターネット接続した。サーバ機の4枚のnicを介して、
ユーザ用のHUBポート(総計80ポート)のための会場内イーサネット
会場内の無線LAN
協賛企業の展示機器向けのLAN
アップリンク
の4種の回線サービスを実現した。(図6.1)
このサービスは、地域ネットワークや企業の技術者、現職教員、学生達からなる技術グループを実行委員会の中に組織することで実現されたもので、文字どおり地域ネットワークのこれまで蓄積してきたノウハウを総合した結果と言える。特に、ドメインを設定し、DDIポケットの無線回線からのインターネット接続に際して、あぶくま地域展開ネットワーク研究会の資源を利用させていただいた。
参加者の持参の端末をLANに接続することも可能であったが、それでも端末台数が参加者の半分程度しか用意できなかったため、参加者の中には、座る場所によって生ずる情報格差の問題点や、講演者やコーディネータに対する負担が多くなりはしないかなどの反省点が指摘された(図6.2)。今後の課題は、シンポジウムの成果を各地域や組織に持ち帰り、周りに広め、教育研究に有効な活用へと展開して行くことである。
| 図6.1 会場内におけるネットワーク |
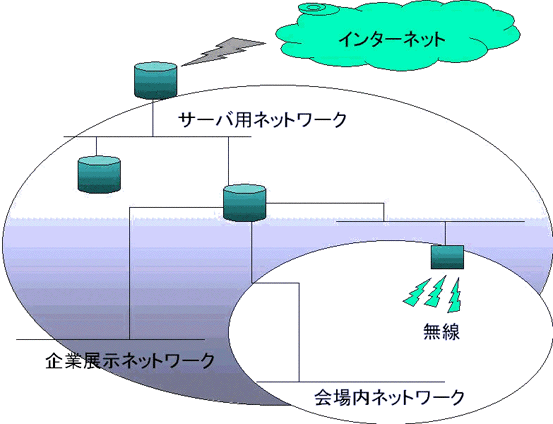 |
| 図6.2 会場の様子 |
 |
本シンポジウムで設置・運営した、イントラネットを用いた意見収集システムは、2つの側面を担うものとして検討された。
本シンポジウムのプログラムを検討しはじめたときに「宮城県の方々に事例を発表してもらい、それに対して、各県からお集まりの方々に、多くの質問・意見を寄せてもらう形で、教育と地域の情報化を考えるきっかけとなるシンポジウムにできないだろうか」という方向性が考えられた。
この案に対して、「各県の発表があるべきではないか。宮城県の発表が多いということは、他県から来る方々を軽んじているのではないか」という意見が寄せられた。
宮城県の準備委員はそれを受け止め、検討した際に、「決して他県から来られる方々を軽んじているわけではなく、逆に、会場からどんどんと意見を寄せてもらって、シンポジウムを形作っていただきたい」ということを考えた。
「教育と地域の情報化を考えるシンポジウム」は毎回、会場にネットワークを敷設されている。ところが、シンポジウム自体には、これを前面に出して用いている場面は少なかった。そこで、会場内にあるLANをシンポジウム自体が活用する試みとして、意見回収システムを構築して試用してみることとした。
既存のシンポジウムにおける質疑応答の時間は、会場内の質問や意見を吸い上げるのには効率が悪いと考えられる。まず、質問する人は、会場内で挙手をした人であり、あらかじめ主催者側が想定した人ではない。よって、主催者側の意図を越える、内容の深い質問が出される場合もあれば、会の趣旨から外れるような質問や意見に、貴重な時間を消費されてしまう場合もある。また、他人に遠慮して質問が出なかったり、逆に、発表者に気を使って、無理に質問をしたりするようなことも見かけられる。コーディネータが、質疑応答に気を使い、自ら質問することなども見られる。
以上述べたようなデメリットを、会場内のイントラネットを用いたシステムで解消できないだろうかと考えた。
まず、イントラネットを用いたシステムであるので、質問をしても、シンポジウムの時間を消費することはない。また会場や時間を気にすることなく、ダイレクトに聞きたい内容を質問できる。よって、複数の人が同時に質問を寄せることができるのである。
このように、できる限り多くの質問を寄せてもらうことによって、「参加者主体のシンポジウム」、つまり、発表者はいわゆる“発題”であって、意見交換のきっかけをつくってもらうものとなり、シンポジウムの真髄となる、多くの意見交換やコミュニケーションは、会場に来てくださった参加者が形成する、という状態が実現するのではないかと予想した。
初期の段階で意見回収システムは、下記のように考えられた。
会場内のサーバにBBSボードを設置し、そこに質疑を寄せてもらう。
BBSボード上で議論となり、意見交換が継続されても構わない。
会場内でネットワーク機器を利用できない方々のために、質問用紙を用いた質疑の回収も同時に行う。
寄せられた質疑は、パネル討論会で取り上げ、シンポジウムにフィードバックさせる。
意見回収システムの開発のために、10月23日、30日、11月6日の3日間、ミーティングが持たれた。
初日のミーティングでは、掲示板システムの完成度次第で、シンポジウム内でこのイントラネットによる意見回収システムの活用の度合が左右されることが予想された。また、BBSシステムに慣れない方々も多く参加することも予想された。
しかしながら、今後の教育現場や地域の情報化を考える参加者に対して、ネットワーク活用の一形態として、イントラネットを用いた意見回収システムを提示し、実際に活用してもらうこと自体が、このシンポジウムの意義に適っていると判断し、「シンポジウムにおける試験的な試み」として、参加者にアプローチするという方針を固めた。
開発にあたっては、パネルディスカッションへのフィードバックを見越して、キーワードごとに意見を収集する掲示板を用意することも考えたが、シンポジウム自体が必要とする質疑応答に支障をきたさないことを最優先とし、BBSシステムになれていない方からも質疑・意見をスムーズに回収できる画面形式を開発し、採択することとした。
準備を進めている間に、「発表最中におけるキーボード入力は、発表者に失礼ではないか」という意見が出た。しかし、最近ではノートパソコンでメモを取る人もいる、ということなどを考慮した結果、次のようなアナウンスをすることにした。
(アナウンスの内容)
今回はイントラネットを使用し、効率的に意見や質問を吸いあげるシステムを取り入れました。
発表中にコンピュータをメモ代わりにご使用なさるのはかまいませんが、夢中になりすぎて発表者の失礼にあたるような行為はご遠慮してくださいますようお願い申しあげます。
なお、書き込みは発表者の交代時間に効率よく行っていただけますよう、重ねてお願い申しあげます。
また、ネットワーク端末がない参加者を想定して、イントラネットによる意見回収システムの入力画面と同じ項目で構成された意見回収用紙を準備し、発表の合間に係が回収し、それを担当が掲示板に入力する、ということも準備した。
それでもなお、口頭で質問を寄せたい、という方も考えられたが、そういった方の要望は、パネルディスカッションにおいて、会場内の方々にはたらきかける、ということで補うことを確認した。
まず最初に、会場に集っている方々の書き込みであるにもかかわらず、多少好ましくない雰囲気の書き込みが見られたため、ハンドル名による書き込みをご遠慮いただいた。その後、本名とともに寄せられた書き込みは、非常に有意義なものが多かったと評価する。
実際に運用して、一般的な口頭での質疑応答とは違ったものとなった。ここで、シンポジウム後に議論に挙がったメリットとデメリットをまとめる。
口頭での質疑応答の時間には質問しにくい、小さな質問をすることができる。また、それに対する答えも簡単であるため、発表者がコメントをすることで、十分に回答となった。これにより、質疑応答の時間の浪費が回避できることが分かった。
より幅広い方々からの質問が寄せられるため、発表する側としては、普通の質疑応答以上の反応を、会場から得ることができた。普通の質疑応答では質問して頂けないような方々と発表者を繋ぐはたらきを示した。
発表時間内に表現できなかった内容にまで突っ込んで、会場との意見のやり取りが可能となった。発表を補完するはたらきも担えることが分かった。
「デジタルデバイド」の存在である。
質問用紙で質問した人には、発表者からのリアクションは、シンポジウムの時間内には、会場内で得られない。
ネットワーク端末を持っていない人は、掲示板上に、どのような質問が寄せられているか分からない。また、掲示板上で継続されている議論を閲覧することもできない。
本来の口頭での質疑応答であれば、手をあげて、その人が直接声を出し、質問をする。そのことによって、人間的な繋がりが形成されるはずであったが、ネットワークが介在することによって、その人間的な繋がりが形成される機会が奪われてしまった。
やはり、掲示板を利用して質疑応答をする人は、ネットワークコミュニケーションに慣れている一部の人達に偏っているようであった。すなわち、参加者に占める掲示板の利用者は、こちらの想定していた予想より高いものではなかった。(これについては、普通の口頭での質疑応答によって発言する人の割合との比較が終了していないことを付しておく)
大人数が同時に利用することによって、システムの不具合が多く見つかったが、担当技術者の努力により、その場で改善がなされた。
最も重要と感じたのは、シンポジウム全体を熟考した運営の重要性である。
まず、「デジタルデバイド」の存在について、主催側・企画側がいかに配慮をすることができるのかが問われる。それは、これから教育現場にネットワークを導入しようと試みる多くの場合に、同様の問題が発生することが考えられる。
次に、時間配分と運用との兼ね合いである。前述したとおり、イントラネットを用いた質疑回収システムは、今までに見られない幾つかのメリットを生じさせるが、そのメリットをシンポジウムの場でリアルタイムに活かすためには、やり取りや取りまとめのための十分な時間が必要である。時間があれば、各発表者とのやり取りによって、それぞれの発表が参加者一人一人に深められる。一方で、パネルディスカッションのように、リアルタイムなやり取りによって内容を多くの参加者で深めていくものには、不適切であった。
最後に、各発言の扱いや、掲示板システム自体の著作権等の問題も残っている。
今回の意見回収システムを試験運用してみて、上記のような問題が浮き彫りになったわけだが、これらの問題がクリアされれば、参加者にとっても発表者にとっても、シンポジウムが始まる前から発表内容に関する予備的な議論を行うことができ、また当日の発表や議論がより実りのあるものにすることができるのではないだろうか。
質疑応答用のBBSシステムを準備することには、今回以上に、シンポジウムの成果を高める可能性があることを、ここに明記しておきたい。
会場は、蔵王ハイツの大ホールを使用し、そのうち前方2/3を事例発表やパネルディスカッションなどを進める本会場に、そして後方1/3を、展示スペースとして用いた。
今回は、第1部から第3部までそれぞれにテーマを設け、最後には必ずパネルディスカッションを行うという構成にした。その間には、展示スペースを観覧するための休憩時間をはさむようにした。
以下に、発表者と演題を含む当日のプログラムを示す。
| 13:00 | 開会宣言 主催者代表挨拶1 主催者代表挨拶2 事務局連絡 |
| 13:20〜15:00 第1部 「学校の情報化について」 | |
| 沼尾敏彦(八戸工業大学第一高等学校) 生徒重視型ネットワークを目指して 佐々木常雄(秋田和洋女子高等学校) 学校におけるネットワーク環境の整備について 鈴木一生(仙台市立沖野東小学校) 沖野東小学校の情報化環境と実践 山口 晋(盛岡市立北松園中学校) 実技教科(書道科)におけるビデオ資料の活用 山田 徹(富岡町立富岡第一小学校) 校内ネットワークに無線LANを導入しよう ―――(休憩) 第1部パネルディスカッション コーディネータ:酒井 創(福島学院短期大学) ―――(休憩) |
|
| 16:05〜17:15 基調講演 釘田寿一(フリーライター) | |
| 「学校と地域の連携は可能か? ――取材の現場から見た学校情報化の様相」 ―――(休憩・夕食) |
|
| 19:40〜22:15 第2部 「地域・社会の情報化について」 | |
| 土田 伸(西川町役場) 西川町における情報化の取り組み 及川 敏(盛岡市子ども科学館) 総合的な学習での利用を目指した教育用ソフトの開発と 社会教育施設を利用した小学校総合的な学習の実践 岩渕成紀(仙台市科学館) 双方向性インターネット調査システムを利用した環境調査 庄子平弥(仙台シニアネットクラブ) シニアパソコン教室受講者による地域情報化への支援活動 (企業発表) ―――(休憩) 第2部パネルディスカッション コーディネータ:新田展弘(郡山市立三代小学校) ―――(休憩) |
|
| 22:35〜23:45 第3部 「教育と地域のIT革命 光と影」 | |
| 総合パネルディスカッション「教育と地域のIT革命光と影」 コーディネータ:岩本正敏(東北学院大学) パネリスト 吉田等明(岩手大学情報処理センター) 渡辺昌邦(福島県教育庁・あぶくま地域展開ネットワーク研究会) 竹村美範(秋田県立六郷高等学校) 渡邉孝之(JIP・あぶくま地域展開ネットワーク研究会) 齋藤武夫(SE、社会人博士課程学生、 あぶくま地域展開ネットワーク研究会) |
|
| 23:45 閉会イベント | |
| 23:50 終了(尽きぬ話題は、泊まり部屋へ持ち越し) | |
このシンポジウムは今回で4回目を迎え、このたび、宮城県の蔵王に教育と地域の情報化に献身的な働きをしてこられた多くの方々がつどい、人を育て、人を生かす情報ネットワークのビジョンを語り合う機会を持てたことは、私たち実行委員にとって、大きな喜びである。
この開催に到るには、宮城県ばかりでなく近隣の多くの方々に実行委員の役を担っていただいた。
これは、安易な生き方をするための道具として情報化を進めるのではなく、これまでにない新しい教育の場と互いに支え合う社会を築くために、ネットワークという道具が、強力な道具たりえるものであるということではないだろうか。特に「あぶくま地域展開ネットワーク研究会」の方々は、本シンポジウムを含めた「教育と地域の情報化を考えるシンポジウム」の、まさに原動力となっている。
今後も更なる人的ネットワークの形成と次回以降への活動へ進展させる為に、継続して参加者メーリングリストの運営を行っていく予定である。MLでのディスカッションを行っていく中で、より大きなネットワークへと広げていき、今回の成果や反省点を生かした形の次回イベント開催を念頭に入れつつ、地域の活性化を行っていきたい、と考える。
この研究会の、東北という地域性を生かしたネットワーク上でのコミュニケーションと実行力を無駄にすることのないよう本シンポジウムを契機として、宮城県内、東北圏内の人的ネットワークの形成を支え続けていきたい。
[1]Tohoku OPen Internet Communityの略称.http://www.topic.ad.jp/
「教育と地域の情報化を考えるシンポジウム in 宮城(SPER2000 in MIYAGI)」
Symposium on Practical Education and Regional Community of Information
|
【日時】 |
2000年11月11日(土) 13:00〜23:50 (第1部:13:00〜17:15 第2部:19:40〜22:15 第3部:22:25〜23:50)
|
|
【会場】 |
宮城勤労総合福祉センター 蔵王ハイツ 住所:〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉 TEL:0224-34-2311
|
|
【主催】 |
教育と地域の情報化を考えるシンポジウム実行委員会 東北学術研究インターネットコミュニティ(TOPIC) 東北電気通信監理局
|
|
【共催】 |
宮城教育大学 環境教育実践研究センター 宮城教育大学 情報処理センター 財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC)
|
|
【後援】 |
宮城県教育委員会 仙台市教育委員会 白石市教育委員会 蔵王町教育委員会
|
|
【協賛】 |
アライドテレシス(株) (株)内田洋行 DDIポケット(株) (株)日立製作所 日本電気(株) (株)ジェプロ 日本電子計算(株)(JIP) (株)APC Japan シャープシステムプロダクト(株)
|
|
【対象】 |
主に、東北地方を中心とした初中高等教育を担当する先生方、及び教育委員会の方々。さらに教育現場や地域の情報化を支えるネットワーク関係者を対象とする。 |