2.4.3.交流の実践
2.4.3.1.KIDLINKの概要
1.はじめに
KIDLINKは、ノルウェーのオッド氏が、1990年5月に始めた国際的な草の根のネットワークである。「世界の15才までの子どもたちが、KIDLINKというネットワークを使って、お互いに対話を通して学びあっていこう」というものである。主な活動の場は、メーリングリストである各会議で、現在、66のメーリングリストが動いている。これまでに延べ、125,000人の子ども達が、世界125ヶ国から参加して活動をしてきた。
また、「子どもたちが普段使っている自分の国の言葉で、世界の友達と交流してほしい」という願いもあって、KIDLINKは多言語サポートを重視している。1996年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれたKIDLINKの世界大会で、この多言語サポートの問題が具体的に話し合われた。現在では、英語だけでなく、デンマーク語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、アイスランド語、イタリア語、日本語、マケドニア語、ノルウェー語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、スカンジナビア語等、それぞれの国の言葉でKIDLINKの活動が進められている。そして、更に多くの国の言葉でのKIDLINKの活動も展開されようとしている。この中のトルコ語とヘブライ語以外は、それぞれの国の言葉でホームページが作られていて、その国の言葉でKIDLINKの情報を手に入れる事が出来るようになっている。
多言語と同時に、多文化もKIDLINKの重要な課題の一つである。文化の違いに着目し、そこからお互いが学び合おうとしている。
2.KIDLINKの各活動
KIDLINKに参加できるのは、世界の15才までの子どもたちと親や教師、そしてボランティアの大人である。活動の場は、国際郵便やファックスでの参加、あるいはテレビ会議、アマチュア無線での参加等、色々な形態があるが、主にメーリングリストである。
子どもたちが直接活動するのが、KIDCAFEと言われるメーリングリストである。大人は、KIDLEADERというメーリングリストに参加して、子どもたちの活動をサポートしている。
学校から教育の一環として参加するケースが増えてきたため、KIDCAFEも、その後、様々なバリエーションを持って動いている。また、KIDPROJという長期に亘るプロジェクトと取り組むメーリングリストもある。KIDFORUMという会議は、二ヶ月単位で一つの話題を集中的に話し合っていこうというものである。
メーリングリストの他にも、オンラインチャットと言って、同時につないでの交流にも取り組んでいる。また、KIDARTと言って、美術作品を作りあう場所もある。
KHOUSE(KIDLINK HOUSE)と言って、恵まれない子どもたちにもインターネットでの学習をしてもらおうという取り組みも、1996年以来ブラジルを中心に続けられている。
1990年、オッド氏の個人的な活動として始められたKIDLINKも、1993年には、 The Kidlink Societyという組織母体を持つようになり、また1997年には、KIDLINK
INSTITUTEも開設されて、発展を続けている。1998年には、ノルウェーのオスロにThe KIDLINK MUSEUMも出来、名実ともに世界的なネットワークに成長してきた。
3.KIDLINKの活動に参加するには
KIDLINKに参加したい15才までの子どもたちは、KIDLINKの4つの質問に答えて、その回答をKIDLINKに送らなければならない。KIDLINKの4つの質問とKIDLINKはどんなものか。
の日本語のホームページには次のような文書で紹介している。
キッドリンク参加のための4つの質問
(1)「わたしは、どんな人なのか」
私の名前(なまえ)は? (フルネームを書いて下さい)
私は、何歳(なんさい)?
男の子?、それとも女の子?
どこに住んでいるの?(市町村の名前、そして国の名前を書いて下さい)
私の通っている学校の名前は?
そして、あなたの好きなこととか、趣味(しゅみ)のこととか、関心(かんしん)を
もっていることなど、色々書いてください。
その他にも、ぜひ世界のお友達に知らせておきたいあなた自身のことを、書いて
ください。
(2)「私が大きくなったら、何になりたいか?」について
大きくなったら、何になりたいのか? 職業(しょくぎょう)とか、将来(しょうら
い)、どんな学校に行きたいとか、その他色々書いてください。
(3) 「私が大きくなったとき、この世界がどんなによくなっていてほしいか。」
お互いの環境を、お互いの関係を、どんな風によくしたいですか。
(4)「3番の願いを実現させるために、今、私にできる事は、何なのか」
3番に書いた願いを一歩一歩実現させていくために、今、私にできることは、な
んだろうか?
注意として、次のようなことがある。
<注意>あなたの名前、住んでいる所、学校の名前、そして国の名前は、英語で書
いてください。その他の答えは、あなたの好きな言葉で書けばいいのです。
この回答は、 RESPONSE@listserv.nodak.edu宛に送ると、レスポンスというメーリングリストで紹介されることになっています。
(http://www.kidlink.org/japanese/general/response.html)
4.KIDLINKのホームページ
Listserveによるメーリングリストで始められたKIDLINKの活動であるが、現在ではそのほとんどがホームページで見られるようになっている。メインページは、http://www.kidlink.org/ で、
そこから各国語のオフィシャルなページに飛べるようになっている。例えば、日本語は、http://www.kidlink.org/japanese/general/ である。
オッド氏自身が英語版のホームページで文書を作ると、各国語もそれにならって、オフィシャルなページを作っていくことになる。オフィシャルなページの他にも、各国語の担当者が各国の状況をみながらそれぞれその国独自のページ作りをしている部分もある。KIDLINKのホームページのデザイン、作り方等も世界会議の重要な議題であり、各国のマネージャー、ホームページの担当者が参加して話し合われている。
(1)「KIDLINKについての理解が難しい」
9月早々にこんなメッセージが流れてきた。
「 Drop out from Kidlink」、彼の学校の子どもたちがインターネットを使っての授業計画を立てたという。そして、KIDLINKに案内を出したが、どこからも返事が来ないから、KIDLINKから抜けるというのだ。この間のやりとりは、本プロジェクトのメーリングリストである100kid-tとKIDLEADER-JAPANESEというKIDLINKのメーリングリストで行わた。
一つには、「KIDLINKが難解に過ぎる」という話は、1998年のペルーでの世界会議で、各国のマネージャーが一様に持っていた話題であった。その昔、創設の頃は、子ども用のkidcafeと大人用のkidleaderしかなかった。それが、子ども達の参加が増え、とても一つのメーリングリストでは処理しきれなくなって、kidcafeが色々に分化され、細分化されて行った。
また、別の観点であるマルチ言語サポートも本格的に動き出した。英語しかなかったKIDLINKの活動も、1993年には、スペイン語、ポルトガル語、そして日本語でも出来るようになった。これらの言葉で大人用と子ども用のメーリングリストが動き出した。
例えば、日本語に関して言えば、子ども用が、KIDCAFE-JAPANESE、大人用がKIDLEADER-JAPANESEというように、それぞれの国の言葉で大人用と子ども用のメーリングリストが動き出したのだ。
そして更に驚くことに、現在では、17ヶ国の国の言葉が使われている。まさしく世界にたった一つのネットワークなのである。
参考<KIDLINK日本語版のトップページ>
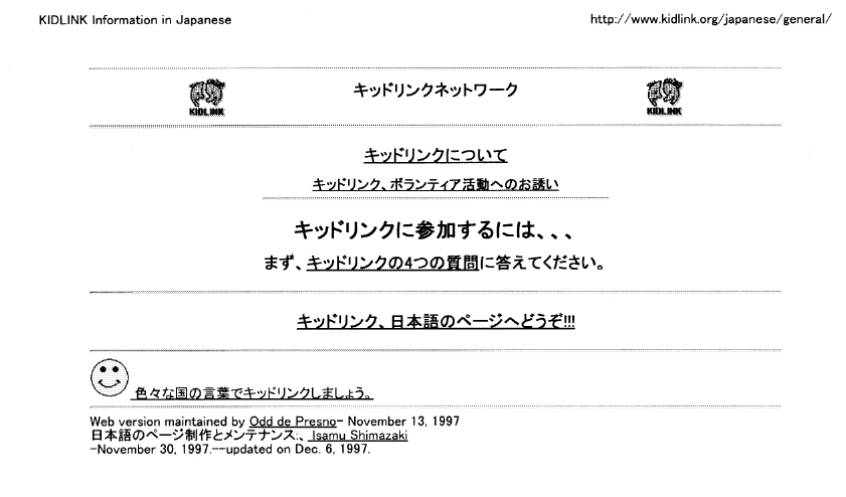
2.4.3.2.幹事校としての取り組みと役割 林間小学校 島崎 勇
1.はじめに
1992年、私は、初めて海外旅行を体験した。ニュージーランドに行ったのであるが、そこの小学校を二つ見学する事ができた。その時、ちょうどスペインでオリンピックをやっていた。彼らは、そのオリンピックを題材に、一年生から六年生までそれぞれの学年で一ヶ月かけて授業を作っていた。
私は、その時、「夢にまで見た教育がここにはある」と驚いたものだった。
それからしばらく後、幸いにして、1995年、画期的な「100校プロジェクト」が始まった。それまでの日本の学校教育では取り組みたくても、「コンピュータがない」「コンピュータをつなぐ電話回線がない」「カリキュラムがない」「英語が分からない」と、ないないづくしであった。「100校プロジェクト」がパイロットプロジェクトであったおかげで色々と新しい取り組みの可能性も見る事が出来るようになってきた。
2.KIDLINKのプロジェクト
KIDLINKのプロジェクトは、KIDPROJという会議で取り組まれている。その代表者がパッティー先生で、このパッティー先生とは、1995年以来、色々と交流を続けている。
このKIDPROJの中で、私とパッティー先生が、「言葉の壁に橋をかける」というプロジェクトを提案している。そして交流の場所として掲示板を作ってもらった。このKIDLINKの掲示板は、英語のものが1998年7月4日に始まり、日本語版は、少し遅れて、1998年10月19日から始まった。
KIDLINKのサーバー上で、英語版が、
http://www.kidlink.org/KIDPROJ/Bridges/wwwboard/
日本語版が、
http://www.kidlink.org/KIDPROJ/Bridges/japan/wwwboard/
で展開されている。
1996年8月、ブラジルのリオデジャネイロで世界大会があったとき、オッドさんは、KIDLINK
is a community.と言った。私はすかさず、KIDLINK is a family.と言い返した。ブラジルの人たちがすごくこの言葉を気に入ってくれて、それ以後、「KIDLINKは家族のようなもの」が、私たちの合い言葉になった。
つまり、KIDLINKにはKIDLINKのやり方があることを、私は言いたい。1990年5月から始まったKIDLINKの活動にも、KIDLINKの歴史があるのだ。その流れを抜きにして突然に割り込んでも、うまく行かないのは当たり前ではないだろううか。参加者も増える一方であった。事務的になってしまった部分もあるだろうが、しかし、KIDLINKに参加する一人ひとりに「KIDLINKは家族だよ」ということの意味を体験して欲しいと思っている。
3.具体的にKIDLINKでどんな活動があるのか。
KIDLINKのKIDPROJで、「言葉の壁に橋をかける」というプロジェクトが動き出した。これは、私とアメリカのパッティー先生が、1995年以来取り組んできた課題である。
当時、KIDLINKは、10才から15才という年齢制限が厳然とあり、私たちは、KIDLINKのマネージャーとしての活動と並行して、色々な取り組みをした。主なテーマが、「絵」を使って交流すれば、お互いの言葉が分からなくても、お互いの理解には役立つのではないのかというものだ。そこで、「絵」や「写真」を使って、お互いの日常生活、学校生活の話題を伝えあってきた。それなりの成果もあった。また、KIDLINKの年齢制限も、上限「15才まで」というのは残ったものの、下限がなくなったことから、私たち二人のプロジェクトもやっとKIDLINKの表舞台のプロジェクトに成長させることができた。それが1998年、昨年のことだ。4年かかった。
4.「KIDLINKへの参加」プロジェクトへの提案
今年度せっかく参加表明をしている学校も交流にはずみがつかない状態からなかなか抜けきれないようなので、12月26日の研究会で、次のように提案をした。
Date: Sat,
26 Dec 1998 07:47:24 +0900
To: 100kid-t
From: Isamu
Shimazaki <simazaki@rinkan-es.yamato.kanagawa.jp>
Subject: 12月26日(提案)国際掲示板を使った情報交換・共同学習
目的1:
国内外の学校とウェッブ掲示板を使って交流し、その中からテーマを見つけて、小プロジェクトを作り共同学習と取り組む。そして何らかの形で公表していく。
(例)
1.世界お天気しらべ
毎日の気温を報告しあう。
2.校庭の様子を写真で知らせ合い、子どもたちがどんな遊びをしているのか、報告しあう。
3.各学校で行われている行事を写真と手紙で紹介しあう。
目的2:
今後の新しい授業づくりにおける情報活用、インターネット活用の実例を作る。
(例)
1.国際理解教育におけるインターネット活用
2.国際掲示板を使った共同学習
方法1:
各学校はインターネットに接続して国際掲示板に書き込み、そこで情報交換をする。その時、メーリングリストも活用していく。
メーリングリストは、100kid-t、100kids、KIDCAFE-JAPANESE、KIDLEADER-JAPANESE等、日本語、英語で行い、プロジェクト参加校、また一般参加校とも、それぞれのルートで話題にしていくが、なんらかの形でそれらをリンクしていく。
方法2:
言葉の問題は、事務局の翻訳ボランティアに依頼するか、各学校でPTA等地域に働きかけて、支援を受ける。また、事務局は、この件の支援体制について研究し、参加校への支援体制を強化していく。
この件に対して、参加校の実例があれば、教え合い、各学校の支援体制の強化に役立てる。
実際1:
期間は、1999年1月から、とりあえず、3月までこの三ヶ月間の成果をまとめる方向で取り組む。
そのためには、各学校の綿密な計画作りが必要である。どこから交流にかける時間を確保するのか、常に計画を作って実施していく。
実際2:
プロジェクトを進めるについての支援は、上記掲示板、メーリングリスト等で日常的に行っていく。また、個別の相談があれば、事務局に電話連絡をする。
基本的には、合意を得たということで、具体的な活動を待つまでとなった。
5.KIDLINKの掲示板での共同学習
(イ)「カブトガニを知っていますか」
1998年12月26日、山口の秋穂中から日本語の掲示板にメッセージが寄せられた。
それを英語の掲示板で秋穂中のホームページにあった一枚の写真をリンクして紹介文を書いた。それが12月31日の夜だった。そしたら、30分するかしないうちに、アメリカのパッティー先生から、「カブトガニなら自分の所のホームページにもあるよ」と海岸にうじゃうじゃといるカブトガニの写真をリンクして返事を書いてくれた。また、秋穂中からも英語でメッセージが寄せらた。そして翌年、1月4日、学校が始まったデルマーの子どもたちからもメッセージが寄せられ、交流も活発に展開されて行った。この共同学習には、その後、広島の子供英語の子ども達、林間小の国際教室の子ども達も参加してきた。
カブトガニは「生きた化石」と言われ、二億年前とも三億年前とも言われる前から地球上に生きていたと言う。しかも、このカブトガニ、世界で4カ所にしか生息していないとも言う。(1)北アメリカの東海岸---デルマー小から車で30分の海岸にアメリカカブトガニが住んでいる。(2)日本の山口県秋穂中、そして残りの二つが、(3)(4)東南アジアに住んでいると言う。
またアメリカのデルマー小の学区には、大西洋の海岸に住む動物についての本を書いた作者が住んでいるとデルマーの一年生が書いて来た。
----------------------------------------------------
We have a book called “Ribbons of Sand” and it tells us about
animals on the beaches near where we live. The man who wrote the book, Mr.
Larry Points, lives in our town of Delmar! He knows all about horseshoe crabs.
We will ask
him to tell us more about these crabs.
Can you see his book in our picture?
We are in the first grade. We have seen horseshoe crabs
on the beach at Assateague Island.
Your friends at Delmar,
Stacey, Tyler, Charles, Joshua and Rakeem
----------------------------------------------------
その後、この作者であるMr. Larry Pointsにデルマーの子どもたちはメールを書き、返事をもらって感激した。そのほかにも、デラウェア大学の海洋研究所のDr.Hallも参加してくれて、私たちの質問にも答えてくれた。アメリカでは、こうしてその道の専門家を自分たちの学習に巻き込むのがとてもうまい。後に、「カブトガニの模型」がアメリカから送られてきた。それは、切り抜いて、糊で貼っていくと立体的なカブトガニの模型になるというものである。出来上がった模型は掲示板で紹介していった。
そして東南アジアのカブトガニの様子が知りたいと思って、NGPという日本人学校メーリングリストにて質問をしてみた。すると、東南アジアにある日本人学校の先生から、色々と情報が送られてきた。東南アジアでは、カブトガニが食用にされているというのである。また、マーケットでカブトガニが売られていると、市場の台の上のカブトガニの写真もそのホームページから見つける事ができた。何でも、一匹、70円位だと言う。日本では、その生息地が天然記念の指定がされているかと思うと、食用にしている所もある。みんな口々に、「同じカブトガニでも地域によってこんなにも違うものなんだなあ」と感心したものであった。
(ロ)気温しらべプロジェクト
毎朝の気温調べは、デルマー小と林間小とアルゼンチンの三つの学校間で、一学期に始めていた。この時には、お互いが不定期に気温を知らせあって一覧表を作った。
掲示板を使っての交流が順調になってきたので、この気温調べも、掲示板にて案内を出し、参加者を募った。アメリカ、日本、オーストラリア、ベルギー、イタリア、ギリシャ、南アフリカ、イギリス等からデータが送られ、デルマー小の5年生は、そのデータを元にしてグラフを作り、掲示板に送ってくれた。
デルマー小で毎日のように気温のデータを送ってくれるのが、二年生のShawn君でした。彼は、タイトル1というパッティー先生のクラスで、コンピュータを使った授業に参加している子どもの一人である。毎日だと彼の他の学習に支障が出ると考えて、気温のデータは、一週間分をまとめて送るようにした。そのおかげで、Shawn君が他のメッセージも書けるようになったと、パッティー先生も喜んでくれた。
途中、アメリカはテキサスとかアラスカからも気温のデータが寄せられるようになった。アラスカの幼稚園の先生のMrs.Reederも熱心に書いてくれた。デルマーの子どもたちもアラスカに興味を持ち、メッセージを書いた。その一つひとつのメッセージに対してMrs.Reederは答えていた。私もオーロラについて聞いてみた。
The
skies need to be dark and clear so winter is the only time we can see
them here. We can see them any time from November through February or so. It is
always cold and clear when they are visible. No two sights are the same. They
are truely a sight to see. Most of the time they are a light green with broad
streaks across the sky but sometimes they are different colors and ripple or “dance” across the sky.
どうも、オーロラの見物は、冬がいいようだ。
(ハ)最新の取り組み、「私の住んでいるお家」
「あなたはどんなお家に住んでいるの」「あなたの住んでいる街はどんなですか」、こんな質問を新しくしてみた。そろそろ新しいテーマが必要かと思っての提案であった。いつものように、さっそくデルマーの子どもたちが「自分の家」の紹介を始めてくれた。
サンプルとして、最初、私の家の四畳半の畳の部屋を紹介した。すると、テレビは無いのかとか、ベッドはどこにあるのか、、、色々と質問が寄せられた。次にその答えになればと、テレビのある部屋の写真を紹介した。また、近くで家を建て始めたので、その紹介も定期的に始めた。
今回は、日本からは、広島の子供英語の子どもたちが真っ先に返事を書いてくれて、交流が活発になっていった。子供英語は、英語を教える放課後の教室であるが、積極的にKIDLINKと関わってくれている。そこの先生がKIDCAFE-JAPANESEのマネージャーをしてくれている。彼らは、英語と日本語でメッセージを書き、日本語の掲示板に書き込んでくれる。その英語のメッセージの方を、私が英語の掲示板に転載している。そしてデルマーの子どもたちの英語の返事が英語の掲示板に書かれる。それを私が日本語にして、英語と日本語の両方を、日本語の掲示板に紹介する事にしている。
日本語と英語の掲示板の橋渡しをする事は、このプロジェクトの柱の一つだと思ってきた。これがうまく行けば、今度は、英語とスペイン語、英語とポルトガル語、英語とフランス語等など、各国語の掲示板が一つの話題で同時進行するようになる。まさしく、地球に一つの掲示板作りである。KIDLINKのマルチ言語サポートが、世界でもまれな取り組みである証拠だと思っている。
6.色々な交流の形
KIDLINKのメインの活動の場は、メールによるメーリングリストであった。しかし、今回のプロジェクトの様に、写真や絵を使って、お互いの理解をより深めようとする交流も活発になってきた。日本ではまでそれほど教育の世界で利用されていないが、IRCというチャットもアメリカやヨーロッパでは一般的な交流の形である。
KIDLINKのアメリカのマネージャーのポニーさんは、このIRCにホームページを組み合わせて、c2dというシステムをKIDLINKに導入しようと実験をしている。このシステムを使うと、チャットと同時に、バーチャルトリップが出来たり、百科事典が使えたり、楽しみが倍増するしかけが組み込まれている。
もう一つが、テレビ会議である。KIDLINKではCUSee-Meを使ってのテレビ会議も時々案内されて、参加者を募っている。このテレビ会議もチャットも、アメリカとヨーロッパ間では盛んであるが、日本の場合には、時差の関係であまり有効には使えない。しかし、今後、ハワイとかニュージーランド、オーストラリアからの参加者が増えてくれば、日本とのテレビ会議もまんざら夢の話ではなくなる。
いずれにしても、技術の進歩により、教育の世界でもそれらを有効に使っての活動も出来るようになってきたということである。
参加各学校は、個別にもメール交換を続けているであろう。その報告は、各学校からなされると思うので、ここでは省略する。