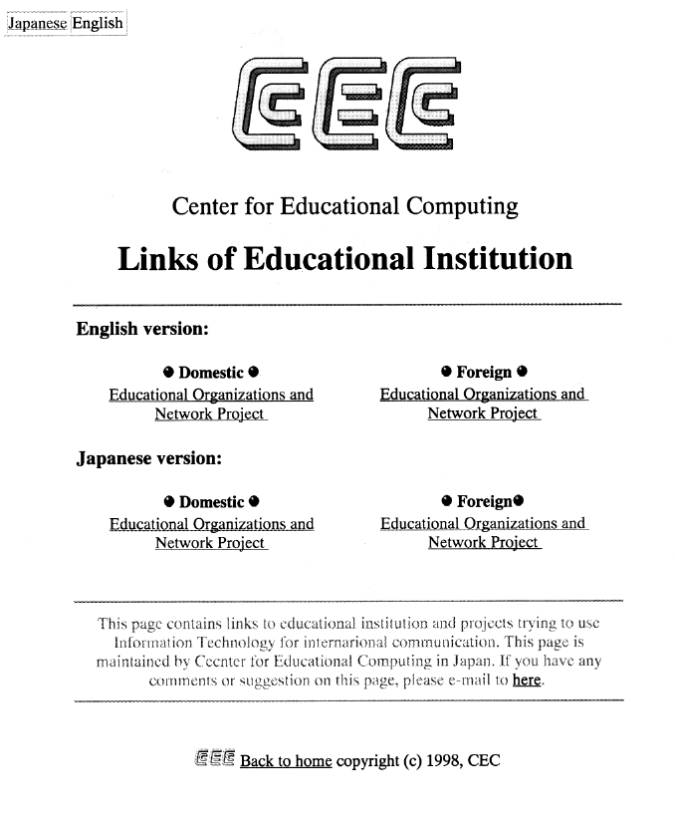2.6.URL集の作成
2.6.1.目的
昨年度の事業として、以下のような目的でリンク集を作成した。
日本の学校が海外の学校と交流を開始しようと考えても、交流の相手先を探すのが困難であり、また海外の学校が日本の学校と交流を希望しようとする場合も同様である。双方ともに、交流を行おうとしても窓口機関がなく、海外および日本へのアプローチが困難な状況にある。
これらを解決すべく、双方の橋渡しの役割を果たすという目標を掲げ、その手始めとして、以下の3つの基準、
(1)国内外でネットワークを利用した国際交流プロジェクトを組織して活動している団体・機関
(2)国内外の教育関連団体・機関
(3)国内外の組織で教育に参考となるような団体・機関
を調査して、その結果を学校で使えるリンク集として、200の教育関連機関を、財団法人コンピュータ教育開発センターのホームページに掲載した。
URL http://www.cec.or.jp/CEC/
平成10年度は前年度の実績を踏まえ、以下の目的でリンク集の充実を図り改訂版を作成した。
(1)新たに100教育関連機関を追加してリンクする。
(2)昨年度作成のリンク集の見直しする。
2.6.2.作成方法
2.6.2.1.新規100機関の追加
(1)候補リストの作成
選定基準としては、2.6.1の3つの基準を基に、次の3点から得られたURLをリストアップし、213の機関を候補とした。
①新100校プロジェクト事業のシンポジウム、国際交流プロジェトなどから得られた情報
②教育関係の新聞、雑誌、教育関連機関発行の出版物より得られた情報
③サーチエンジンで検索して得られた情報
(2)絞り込み
上でノミネートされリストアップした機関を、更に選定のキーワードとして、①国際化 ②国際交流 ③国際理解教育 ④共同学習 の4つの観点で見直しを図り、111の機関に絞り込んだ。
(3)リンク許可願い
111の機関に対して、リンク許可願いを、日本の機関に対しては日本語で、海外の機関に対しては英語で申請した。
(4)コメント作成
リンク集に掲載する情報としては、そのページのURLだけでなく、ホームページで取り扱っている主題を簡潔に表現したタイトルやコメントが必要と考えた。内外の教育関係者に見てもらうために、日本語と英語の両方を用意した。
2.6.2.2.昨年度作成のリンク集の見直し
上記の新規100の教育関連機関の追加以外の、昨年度作成のリンク集の変更の視点は以下の通りである。
①URLアドレスが移動したものを更新する。
②URLが消滅したか、変わってしまって分からないものについては削除する。
③ホームページを見て、掲載願いや変更依頼をしてきたものは、意向に沿うように更新する。
④新たに英語のホームページができたものについては、英語版には、その英語のURLアドレスを貼り直す。
2.6.3.構成内容
昨年度は、国内の教育関連機関、海外の教育関連機関、国内のネットワークプロジェクト、海外のネットワークプロジェクトの4つに分けたが、ネットワークプロジェクトの組織も教育関連機関であるという指摘を受けたことと、教育関連機関とネットワークプロジェクトのどちらに分類したらよいのか迷う機関もあるので、2つを一緒にして教育関連機関としてまとめ、国内の教育関連機関、海外の教育関連機関の2つに分類し直した。
①URLの下には、2~3行程度の注釈を付け利用者に分かり易いようにした。
②国内外の利用者のために、日本語と英語の注釈を付け、日本語版と英語版の双方を用意した。
③昨年度は、海外の機関を国別に分類していたが、国籍が不明のものも結構あるため、国内と海外の2つに分類し直した。
④利用者からの指摘もあり、目の弱い人のために基調の色を若草色からオーシャンブルーに変更した。
⑤新規100教育関連機関を追加したものと、昨年度作成のリンク集の見直しをしたものを一緒にしてまとめて改訂版とした。
2.6.4.まとめ
昨年度と今年度で合計300を越える教育関連機関をリンクしたが、対象URLの選定やその更新、メンテナンスに予想以上に時間をとられ、大変な作業であるが、学校或いは教職員に有用かつ良質な情報だけを提供しているホームページは少なくて、トップページではなく、その下層のページにあるメニュー項目の中の1つが、我々が目的とした情報、例えば国際交流という例が多い。リンクをトップページに貼ると、利用者には情報の所在がなかなか分からず、かといってリンクを直接その国際交流のページに貼ることにより、情報提供者の名前が分かり難いというリンク先の問題がある。
今回のリンク集では、この問題に対しては、リンクをトップページに貼ってコメントでカバーしたり、リンクを直接下層の項目に貼ったりして、コメントで情報提供者をカバーしたりしている。
信頼性の高い、有用なリンク集を作成し維持していくためには、利用者の視点に立ったホームページの収集、評価、情報付加が必要であるが、ホームページの移動や消滅、内容変更等々への対応といった作業が不可欠である。
この2年間に、日本の学校に急速にインターネットが導入され、いろいろな工夫を凝らして使われるようになってきた。教育の現場でも、新100校プロジェクトなどで、共同学習、作品発表、意見交換、国際交流等々いくつかのインターネット教育活用の実践が積み上げられてきた。学校へのインターネットの導入が、単なる教育改革ではなく、21世紀を目指す国策として取り上げられている今日、教育現場、教育委員会等教育関係者の参考となれば幸いである。
参考1 教育関連機関リンク集のページ(日本語版)
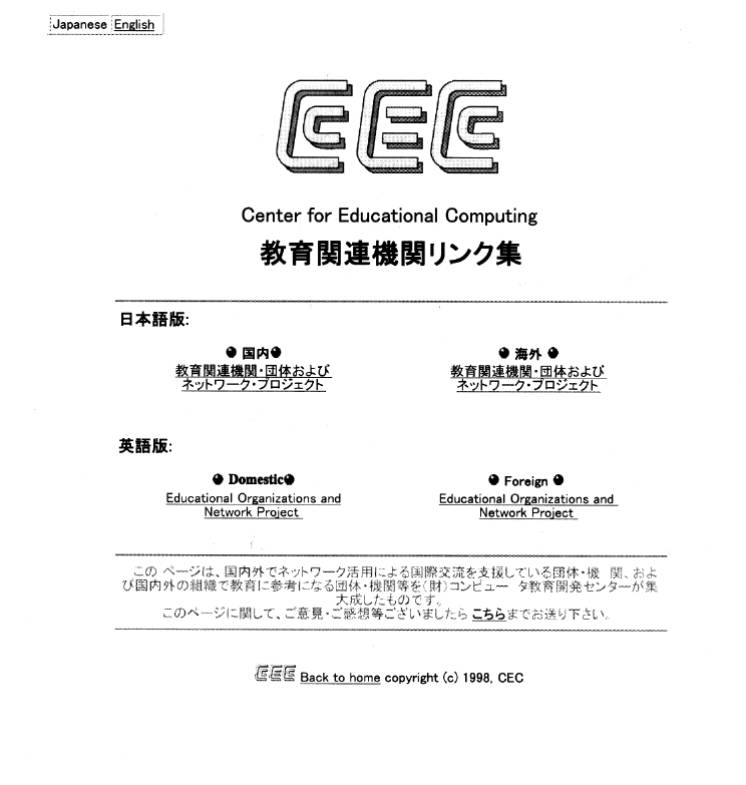
参考2 教育関連機関リンク集のページ(英語版)