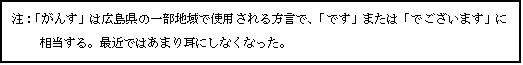4.広島地域における初等中等教育インターネット利用研究プロジェクト
4.1 はじめに
文部省は2001年までにすべての学校をインターネット接続する方針を打ち出している。その多くはISDNを利用したダイアルアップが想定されているようであるが,潜在的利用者の多数いる学校を組織として接続するには,技術的に安定した専用線で接続し,各種ネットワークサーバを設置することが最低条件と考えられる。100校プロジェクトにおいて初期の頃から指摘されていたことであるが,学校においてインターネットを有効活用するには,少なくとも接続回線の安定性が強く要求される。また,学校現場の教職員がネットワーク環境に慣れ親しみ,日常業務に活用することも極めて重要な要素である。現在,既に幾つかのプロジェクトにより初等中等教育におけるインターネットの利用が試みられているが,その多くはダイアルアップ接続の形態であり,自組織のサーバ管理,利用者管理の方法等について本格的な検討が進んでいない。
本章では,広島地域(広島市および呉市)で小中高校約10校を専用線にてインターネット接続し,各学校にネットワークサーバを設置する「ネットdeがんす」プロジェクトの試みを紹介する。本プロジェクトは,学術系地域ネットワークである中国・四国インターネット協議会(CSI)が中心となって進めている研究プロジェクトである。CSIは1995年にスタートしたネットワーク利用環境提供事業(以下100校プロジェクト)において中国・四国地域11校のインターネット接続を担当したが,それをきっかけとして初等中等教育関係の活動を支援するとともに,関連するシンポジウムを開催してきた。従来CSIは大学や研究機関の研究者を中心としたインターネットの普及,啓発活動を行ってきたが,100校プロジェクトを契機として,既にインターネットが導入されている大学等のネットワーク管理者と今後インターネットを導入する初等中等教育現場の教職員が直接交流し,情報交換することのできる場が生まれた。100校プロジェクトの成果を踏まえた種々の議論の結果,今後多数の学校がネットワークを導入しインターネットを有効活用するには,解決しなければならない問題が多数存在することが分かった。
特に,学校において本格的にネットワークを導入した場合,その運用・管理等をどのように行うべきかは大きな問題となる。単に納入業者および現場の教職員の責任とするだけで,健全な定着が図れるかは疑問である。これまで大学等での導入経験では,組織内外の多くの人達のボランティア的貢献が大きく寄与しており,それらを効果的に活用できる枠組みが必要である。また,導入するネットワーク環境に関しても,専用線接続およびネットワークサーバの独自管理が必要となるであろうことは容易に想像がつく。100校プロジェクトは,上記の問題を正面から捉え,解決を試みたプロジェクトとして高く評価できるが,予算上の制約や開始当初の技術的制約のため,その効果が十分伝わらなかったのではなかろうか。具体的には,多くの学校接続にアナログ専用線を用いたため,回線障害が頻発したことや,技術的に十分洗練されていないPC
UNIXが多用されたことで,その管理に過大な手間を必要とした。すべての学校がディジタル専用線を利用でき,現在の技術水準のPC UNIXサーバが利用できたとすれば,インターネットに対する印象は大幅に違ったであろう。また,100校プロジェクト参加校は各県あたり1〜2校であり,担当者間の日常的な相互協力や情報交換を考えるとこの数は十分とは言えない。
これらのことから,広島市およびその周辺地域で10校程度をディジタル専用線にて接続し,低価格で技術的に安定しているPC UNIXによるネットワークサーバを設置し,種々の実証実験を実施する必要性を痛感し,本プロジェクトを開始した。本プロジェクトでは以下に挙げるテーマについて研究を行い,全国全ての学校がインターネットに専用線接続されることを想定して実践的な検証を行っている。
(1)インターネット教育利用の実践的研究
・インターネット導入に伴う問題点の掌握
・導入および使用に関する支援モデルの研究
(2)利用者環境支援システムの開発
・教員自身が管理すべき情報等の明確化
・管理支援システムの開発と評価
(3)初等中等教育における情報倫理の研究
・問題点等事例の蓄積
このうち,本報告では主に(1)について述べる。(2)および(3)は現在推進中であり,機会を改めて報告することにする。