4.4 支援モデル
4.4.1 本プロジェクトで行われた支援の実際
今回のプロジェクトに参加した教育センターや学校の担当者のほとんどは,パーソナルコンピュータを日常的に使いこなしているもののUNIXについては初心者である。そこで,ネットワークサーバ管理経験者2名の教員と工学部学生1名からなるサポートグループを組織し各担当者を支援した。一般的な疑問やトラブルについてはサポートグループが対応し,専門的な内容については,さらに3名の大学ネットワーク管理者からのアドバイスを得ながら支援が行われた。
サポートグループが行った支援のほとんどは,ネットワークサーバ構築に関すること,校内LANの構築に関するものなど技術的な内容が多かった。また,職員研修や授業での活用については担当者間の情報交換による相互支援の形で発展していった。
○ ネットワークサーバ構築に対する支援
 今回のプロジェクトでは,光ファイバーによるIP接続で研究協力校をインターネットに接続した。ネットワークサーバのOSには研究機関やISP(Internet
Service Provider)での稼動実績があるFreeBSDを採用した。PC UNIXをインストールしたパーソナルコンピュータがインターネットサーバとして十分な性能を持っていることは,ここ1〜2年で広く認知されるようになってきた。本プロジェクトで用意したネットワークサーバ用のコンピュータもいわゆるパソコンである。UNIXシステムは遠隔地から操作することが可能であり,リモートメンテナンスすることができる。また,ソースコードが無料で公開されていることで世界中のユーザが開発に参加しており,セキュリティホール対策も迅速である。
今回のプロジェクトでは,光ファイバーによるIP接続で研究協力校をインターネットに接続した。ネットワークサーバのOSには研究機関やISP(Internet
Service Provider)での稼動実績があるFreeBSDを採用した。PC UNIXをインストールしたパーソナルコンピュータがインターネットサーバとして十分な性能を持っていることは,ここ1〜2年で広く認知されるようになってきた。本プロジェクトで用意したネットワークサーバ用のコンピュータもいわゆるパソコンである。UNIXシステムは遠隔地から操作することが可能であり,リモートメンテナンスすることができる。また,ソースコードが無料で公開されていることで世界中のユーザが開発に参加しており,セキュリティホール対策も迅速である。
ネットワークサーバへのOSインストールと各種設定作業はサポートグループの支援のもとに,各学校の担当者自身が行った。自らが作業することで,UNIXシステムやネットワークについて理解を深めることができた。同時に支援ソフトを用い,各種サーバアプリケーションソフトのインストールを自動的に行い手間を軽減した。この支援ソフトを使うことで,日常業務(ユーザアカウントの登録や削除,ネットワーク内ホストのネームサーバ登録や抹消,メーリングリスト作成,システムのバックアップ等)をWebブラウザから行うことができ,UNIXコマンドによる操作を極力少なくすることができた。
UNIX講習会も行った。内容はネットワークサーバOSや各種ソフトのインストールと設定,ファイルシステムの研修,基本コマンドの実技講習,ネットワーク管理の基礎的な実技講習等であった。
○ ネットワーク稼動後の支援
ネットワークサーバの設定が終了した後は,「ネットdeがんすプロジェクトメーリングリスト」(以下メーリングリスト)で日常的に電子メールを交換しながら,技術的な問題についての質問とアドバイス,授業実践,児童・教職員の研修内容など広範囲の話題について情報交換を行った。
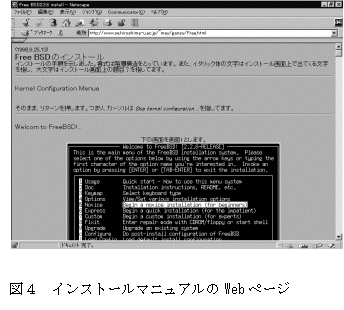 また,各組織のネットワークサーバの立ち上げ作業を支援のためのWebページを開設した。Webページには,OSのインストールからネットワークサーバ構築までの手順を詳細に記述したため,UNIX初心者でもインストールを行うことができた。各種の設定ファイルも公開され,設定のポイントはメーリングリストを通して担当者に知らされた。これらの情報を参考にして各担当者によって作業が行われ,問題が発生した場合にはさらにメーリングリスト上で情報交換しその結果をWebページに反映させるといった作業を繰り返した。
また,各組織のネットワークサーバの立ち上げ作業を支援のためのWebページを開設した。Webページには,OSのインストールからネットワークサーバ構築までの手順を詳細に記述したため,UNIX初心者でもインストールを行うことができた。各種の設定ファイルも公開され,設定のポイントはメーリングリストを通して担当者に知らされた。これらの情報を参考にして各担当者によって作業が行われ,問題が発生した場合にはさらにメーリングリスト上で情報交換しその結果をWebページに反映させるといった作業を繰り返した。
メーリングリストでの情報交換だけでは解決できない問題が発生したときには,サポートグループが直接訪問して支援した。
授業実践へのインターネットの活用が始まってからはクライアント不足に悩む学校に対してコンピュータの貸し出しもおこなった。ほとんどの研究協力校では,クライアントコンピュータが不足しており,メーリングリストで希望を調整しながらコンピュータを巡回させた。コンピュータの貸し出しを受けた学校では担当者が協力しながら設定や操作法のマニュアルを作り,必要な場合には修理等を行った。
4.4.2 支援においての明らかになった成果と問題点
○ 支援による成果
ネットワークサーバは,予期せぬ停電のために再起動後画面表示にエラーが出た事例が1つあっただけで,非常に安定して稼動している。パーソナルコンピュータにPC
UNIXをインストールしたコンピュータは,ネットワークサーバとして十分な性能を持っているということが明らかになった。しかし,一般にネットワークサーバは停電や雷等の電気的な事故に弱い。最悪の場合にはハードディスク上の全てのデータを失うことになる。万一に備え無停電電源装置やデータバックアップ装置が整備されることが望ましい。
今回のプロジェクトで使用したサーバ管理支援ソフトは非常に優れており,サーバソフトのインストールやDNS,DHCP等の起動も,支援ソフト用の簡単な設定ファイルを作成するだけで可能であった。この支援ソフトはブラウザを利用した日常管理の機能も持ち,重要ファイルのデータバックアップの機能ももっている。
校内LAN敷設支援では,クライアントの配置やケーブル敷設の工夫など,実践的なノウハウが得られた。また,「ネットデイ」の実施により学校の雰囲気を盛り上げることができた研究協力校もあった。
サポートグループの直接訪問による支援は問題のすばやい解決だけでなく,担当者がネットワークへの理解を深める上でも有効であった。つまり直面している問題点が最高の研修材料となり,それが解決できることが最高の研修機会になったのである。しかしながら,サポートグループのメンバーも本来の仕事の合間をぬってサポートを行っていたため各組織を頻繁に訪問できなかったことが残念である。
メーリングリストでは,参加者それぞれの得意な分野で相互に支援を行った。貸し出されたクライアントのトラブル(故障・日本語入力・アプリケーションの使用方法)はメーリングリストでのその機種に詳しい担当者のアドバイスによって解決することができた。独自にパスワード自動生成マクロを作成し,教職員全員のアカウント発行に利用した学校もあった。もちろんこのマクロは他の学校でも活用された。
○ 問題点
UNIX基本操作についての講習とOSインストール作業が同時に進行したため,UNIX初心者の担当者には大きな負担がかかった。特にネットワークサーバの設定作業では,担当者自身が今何の設定をしているかわからなくなっていることもあった。したがって,各種設定に先立って,その手順だけでなく機能や使用方法の説明を行い,作業後には設定がうまく行っているのかどうかを確かめる方法を提示することが必要であった。特にネームサーバに関する事項はインターネットにとってかなり重要度の高いものなので,十分に時間をかけて理解してもらうべき内容であった。しかしながら,今回のプロジェクトではどうしても時間の確保ができなかった。
サポートグループよりネットワークサーバの設定ミスがあると連絡されたにもかかわらず,時間が確保できず修正が行われないといった事例があった。特に,ネットワークが順調に稼動した後には,操作を加えて調子を悪くさせた場合,その復旧にさらに時間がとられると考え,ネットワークサーバの設定変更をできるだけ避けようとするのである。これら問題の背景には,コンピュータ管理が学校の業務として認知されていないという実態がある。
また,自分が実際に経験していない問題についての電子メールの内容は,読んでもあまり印象に残らないということも明らかになった。そのため,後に自分が同じ問題に直面してもそれがすでにメーリングリストで話題になった事柄だと気づかずに,再度同じ質問がメーリングリストに投稿されるということが起こった。電子メールを利用したコミュニケーションには電話や手紙とは異なった特性があり,それをよく理解した上で活用する必要がある。また,サポートグループの反省として,トラブルシューティングに当たってどういう手順でサポートグループの支援を得るべきかを明確に示すべきであったという点がある。しかしながら,これらの課題を検討しネットワークを通したコミュニケーションのノウハウを蓄積すれば,ネットワークを通じて効率的に研修を行う制度が実現する可能性がある。
メーリングリストで報告されたトラブルのほとんどはネットワークサーバ構築とLANの敷設に関するものであった。主なものは次の通りである。
サーバコンピュータ構築に関する問題
・ インストール時のエラー
・ ネットワークカードの不調(ハードエラー,kernelの再構築の不調,/etc/rc.confの記述ミス)
・ DNSの設定(resolverの指定)
・ ルーティングの不調
・ WWWサーバの起動
・ メールの不正中継対策(sendmail.cfの記述)
・ セキュリティ対策(tcp_wrapperの設定,APOP)
・ X Window Systemの設定
・ ファイルサーバの設定と使用方法(samba,NETATALK)
サーバコンピュータ日常管理に関する問題
・ WWWサーバのアクセス制限
・ セキュリティ対策(sendmailのバージョンアップ)
・ トラフィックの監視
・ ディレクトリやファイルのパーミッション設定
・ サーバ管理ソフトの使用方法(メーリングリスト作成,ホストの登録)
・ ユーザアカウントの発行のあり方
・ 日常管理業務(logの読み方,不要ファイルの選別,ファイルシステムの管理等)
・ 突発事故による障害
クライアントコンピュータに関する問題
・ ハードウェアのトラブル(内蔵電池の不良,マウスの不調など)
・ ブラウザの設定(proxyの設定,ヘルパーアプリ)
・ 日本語入力のノウハウ
・ メールソフトの設定
LANの敷設
・ 校内LANの設計(配線方法,HUBの配置)
・ ネットワークケーブルの作り方
職場研修・授業実践
・ 職員研修の内容や進め方
・ 授業実践報告
・ 共同学習
4.4.3 支援モデル
プロジェクト実施中に発生した問題とそれに対して行った支援から「担当者に期待する業務」と「外部機関からの支援が可能な業務」とに分類・考察してみる。支援において主に関わるのは,教育委員会,教育センター・情報センター等専門機関,関連業者である。
各学校の担当者に期待する業務
ネットワークサーバおよびネットワークの管理
アカウントの発行
マシンの登録や抹消
logファイルのチェック
接続回線の監視
データのバックアップ
職員へのアドバイス
校内研修計画の立案
教育委員会に期待する業務
ネットワーク利用環境導入のための仕様作成
支援体制の統括
担当者養成長期研修の実施
教育センター・情報センター等専門機関に期待する業務
ネットワーク担当者の研修講座の実施
教職員の研修講座の実施
各種共同学習のコーディネート
問題発生時の相談窓口
関連業者に期待する業務
機材の初期設定と設定データの保存
機器の点検や修理
セキュリティホール対策のためのバージョンアップ
各学校の担当者に期待する業務
まず,各学校には必ず情報教育担当者が置かれなければならない。担当者は日常的なコンピュータの保守点検やデータ等の管理をしたりネットワークを活用した教育実践について助言したりする。また,何らかの問題が起こった場合,関連機関へのレポートを行い,学校側の窓口となる。校内の現状をよく把握して職員のニーズに対応した校内研修を企画運営することも大切である。担当者に必要と思われる技術や能力は次の通りである。
・
インターネットを適切に使いこなす能力
(コンピュータ基本操作や,情報倫理に関する事項も含む)
・ 機材に関する問題を的確に把握し,関連機関に適切に報告できる能力
・ インターネット利用者の質問等に適切に受け答えできる能力
などが挙げられる。特にネットワークやサーバの管理人として,すべての情報を掌握する権限を得ることになるので,公平で冷静な担当者としての適性は重要である。
教育委員会に期待する業務
コンピュータを含むインターネット関連機器は製品開発競争が激しい分野である。また,回線料金の低価格化も予想できない速度で進んでいる。このことを踏まえ,教育委員会から学校に導入する機器については,後の柔軟な対応が可能な機材構成や予算措置をする必要がある。
また,学校の情報教育をリードし,校内LAN等のインターネット利用環境を管理していくことができる教職員は十分な数ではなく,その業務も校務として位置付けられていないことから,教育委員会は人材育成に努めつつネットワーク管理に関する業務を校務に位置付ける必要がある。たとえば大学等の専門機関に教職員を派遣し,ネットワークの専門的な技術と知識を習得した人材を育成するといった研修制度が必要である。研修終了の後は,受講者自らが講師となり,習得した知識・技術を伝達するための講習会を行い,インターネットに関する技術・能力の育成に努めるのである。たとえば,アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ教育委員会では,各学校で校長が推薦し,代表教員を教員研修センターに派遣し,コンピュータ教育に関する専門研修を実施している。研修はのべ150時間にもおよび,研修終了後,所属の学校に戻り,各校の教員に対して60時間の研修を行うといった制度を設けている(1998年米国インターネット教育視察団報告書)。
教育センター・情報センター等専門機関に期待する業務
教育センターでは,担当者向けや一般教員向けの研修講座を実施しネットワークを利用した教育実践を支援する必要がある。ネットワークを活用することで各勤務地で効率的に研修を進めることも可能である。たとえば,初回の講座は教育センターで実施し基本的なコンピュータ操作や電子メールソフトの使い方を実習する。その後,勤務地からメーリングリストやCGIによる電子掲示板を活用しながら課題に取り組み研修を進めるのである。この研修はコンピュータやインターネットに関する研修内容だけでなく,いろいろな分野の研修に応用することができる。
学校で発生したトラブルについての相談窓口も必要である。比較的解決しやすいトラブルについては適切な助言を行い,解決が困難なものについては業者に連絡し早期解決をはかるシステムを確立するのである。
また,インターネットを活用した学習指導について研究を進めることも重要である。特に交流型の学習を実施しようとするときには,交流を希望する学校を紹介したりスケジュールを調整したりすることが必要である。こういったコーディネーションも教育センターの重要な業務である。
関連業者へ期待する業務
インターネットに接続された校内LANが稼動した後には,学校の事情に精通した技術者の配置が必要となる。その技術者を「学校SE」と呼ぶことにする。「学校SE」は各校に1名配置され,ネットワークサーバの管理業務や教員の要求による各種設定が即座に行われることが理想である。先にあげた各学校での担当者がそのまま高いレベルの技術をもつことができれば理想である。せめて数校に1名程度,定期的にまたは要請に応じて学校に出向き,サポートを行う技術者を配置するといった制度を業者に委託などして実現して欲しい。なぜならば,本プロジェクトで出張サポートが不可欠であったように,実際のネットワークに関するトラブルはその原因を切り分けるのが非常に困難であり,現地での支援が必要となるためである。
ここで,大きな問題がある。情報関連事業に多くの予算がつぎ込まれているとおり,これは今後の発展が最も期待されている分野の一つである。また,情報通信はまだまだ歴史の浅い分野であり,ここ数年の爆発的普及もあいまって技術者が慢性的に不足しているというのが実状である。全国4万あまりの学校が一斉にインターネットに接続された場合,たとえそれが端末型のダイヤルアップ接続だったとしてもサポート体制が後手後手になるのは必至である。
そこで業者だけに依存するのではなく,学校ネットワーク運用の支援活動を行ったり,他機関との連携をコーディネートする枠組みが必要となる。例えば,国家的プロジェクトとして支援センターを設立することが実現するかもしれない。あるいは適切な規模の地区ごとにNPO(民間非営利組織)を設立し,そこからボランティアベースの人材派遣を行うという方法も考えられる。学校へのネットワーク導入を地域コミュニティの核の整備ととらえ,地域のインターネットに関する技術をもつ協力者を募ることも可能である。この場合,生涯教育を見据えた社会教育の場として地域社会へ積極的にネットワーク環境を提供することで地域と学校との連携を実現し,公共サービスの充実をはかることもできる。ただし,安直な外部依存は児童生徒の個人情報保護や学校内の運営に大きな不安や負担をもたらす危険性もある。制度の慎重な運用が必要である。