3.地域展開企画の活動
山梨県総合教育センターでは,情報ネットワークの環境を整備し,教育に役立つ情報の交流を盛んにすることで,山梨の教育の活性化を行うことを目指して平成5年度から取り組んできた。平成7年度にはインターネットを導入し,学校を接続する試みも開始した。平成9年度には新100校プロジェクトの教育センターを核とした地域展開の指定を受けた。学校にネットワークを利用しうる環境を提供し,教育での有効活用を推進する取り組みも開始した。
3.1.1.2では山梨県総合教育センターを核とした教育情報ネットワークシステムのこれまでについて,3.1.1.3では地域展開のためのネットワークシステムのあり方,山梨で導入しつつあるネットワークシステムについて報告する。3.1.1.4では本年度山梨での地域展開で総合教育センターが実施した環境整備,ネットワーク研修,自主的参加の研修組織「山梨スクールネット研究会」の活動と,総合教育センターとこの研究会を中心に開発した地域に根ざしたWeb教材の内容について報告する。
3.1.1.2 山梨県教育情報ネットワークシステム「Hi-Use
Net」
(1)ハイユースプランと「Hi-Use Net」
山梨県教育委員会は,平成2年に「山梨県情報教育推進基本計画(ハイユースプラン)」を策定した。この中で公立学校のコンピュータ等の設備基準を明らかにする一方,近い将来の情報教育推進のための構想を明らかにした。この中で,「山梨県教育情報ネットワークシステム」を構築し,教育関係者の情報交流を行えるようにすることや,教育に役に立つ情報を提供することを提起した。このハイユースプランに基づき,平成4年度に山梨県総合教育センター内に情報教育センターが開設された。
平成5年度には情報教育センターにホストコンピュータを置くパソコン通信の「Hi-Use
Net」がスタートした。「教育情報ネットワークシステム」と呼ぶにはやや非力ではあったが,安価な設備で情報交流を行える基盤を構築できた点では有効であった。このパソコン通信の機能の概略は次のとおりである。
・電子メール
・電子掲示板
・電子会議室
・オンラインソフトライブラリ
・オンライントーク
・教育情報検索システム
・研修情報システム
・電話回線数 アナログ6回線
・通信速度 9600bps
当初から公務で活用されることを目指したので,県内のすべての公立学校及び教育委員会などのIDはあらかじめ登録して配付した。個人会員は本人の申請で登録した。オンラインソフトの充実と会議室の活用を中心に運用し,最盛期には毎月2000アクセスを越えた。個人ユーザーも次第に増え,現在では900人を越えている。このパソコン通信を教育センターと学校との連絡を中心に次のような公務でも活用した。
・総合教育センターの研修の申し込み
・研究発表会の参加申し込み
・高校入試処理に関する担当者との事務連絡
・入試処理結果の統計資料収集
・情報教育センターが開発した教育用ソフトの更新情報及びファイルの配布
開設して2年ほどは活発に活用されてきたが,次第に会議室等への情報提供者が減り,メールなどの個人的な使用と,公務での使用に限られるようになってきた。これはある程度開設当初すでに先駆的なネットワークからは報告されていたことであるが,パソコン通信のように限られたユーザーだけで構成するネットワークは次第に情報が枯れて消滅していく傾向がある。活発な情報交流を維持していくためには,常に新たな情報を提供する大勢の運営者が必要である。また,ネットワークの情報の幅を拡大する上でも,他のネットワークとの相互乗り入れ等が必要となる。
「Hi-Use
Net」開設後すぐに他県の教育センターで運用しているパソコン通信と相互乗り入れを検討したが,それぞれのシステムが異なり,技術的に困難であることと,県外の人をユーザーにできない規約がほとんどにあることなどのため実現できなかった。
(2)アイオワプロジェクト
インターネットが大学などを中心に活用されはじめ,山梨でも地域ネットワーク設立の動きが平成5年に開始された。パソコン通信の限界を超えるネットワークとして非常に有効であると感じられたので,総合教育センターにインターネットを導入する予算要求を平成5年度から開始した。教育委員会でも当初はインターネットという言葉すら知られておらず,時期尚早ということで見送られた。
平成6年度末になると状況は一変した。商用プロバイダーが誕生し,インターネットも日常のニュース等にも登場するようになった。知事がアイオワ州との姉妹州県締結35周年を記念して渡米することになり,教育レベルでの交流をインターネットを利用して行う国際交流事業を開始することをプランとして持っていくことになった。将来に備えて,総合教育センターをネットワーク拠点として整備し,ここに実験校を接続してインターネットと結ぶこととした。
インターネットを活用した国際交流事業(略称アイオワプロジェクト)の概要は次のとおりである。
・平成8年度から3年間の実験事業とし,その後も継続事業とする予定。
・山梨,アイオワ双方で実験校5校(中学2,高校3)を指定する。
・インターネットを活用し相互交流を行う。
・山梨県総合教育センターを山梨大学経由で学術ネットのTRAINに接続し,実験校は総合教育センターにLAN型のダイアルアップ接続をする。
・事業費は県独自の負担,中学校は県から半額補助し,他は町村の負担する。
本年度中間報告が行われ,現在もメーリングリストの活用を中心として交流が進められている。
3.1.1.3 地域展開のためのシステム構成
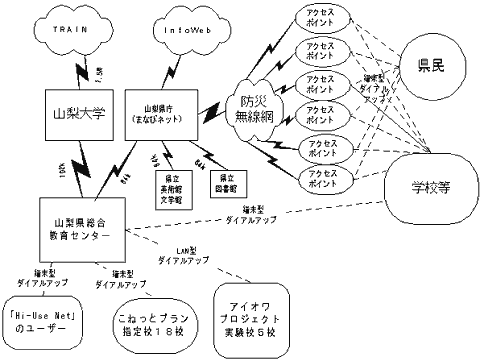
山梨県総合教育センターに導入されたインターネットシステムは,アイオワプロジェクトで導入されたシステムを所内のネットワーク機器の更新で一部変更して使用している。現在のネットワークの構成の概念図は次のとおりである。
総合教育センターの上位回線は山梨大学経由のTRAINと県庁経由のInfoWebである。県庁ルートではこねっとプランの指定校18校をインターネットに接続し,山梨大学ルートではアイオワプロジェクトの実験校と,総合教育センターをインターネットに接続している。
一般の学校及び「Hi-Use
Net」のユーザーは総合教育センターに接続すると,県庁のサーバー及びまなびネットに接続しているサーバーまでアクセスできる。また,まなびネットのアクセスポイントに接続すると,まなびネットに接続しているサーバーの他,総合教育センターのサーバーまでアクセス可能である。この場合,県庁からも総合教育センターからもインターネットには出られない。
(1)イントラネット版「Hi-Use Net」
「Hi-Use
Net」はパソコン通信としてスタートしたが,総合教育センターが平成7年7月にインターネットに接続したのを機会に,まずインターネットからTelnetによる接続を可能にした。これにより,インターネットから「Hi-Use
Net」のパソコン通信に接続することが可能になった。ゲストのアカウントでの利用制限を大幅にへらし,県外の方との交流も可能とした。これとともに「Hi-Use
Net」の電子メールもインターネットと交信可能とした。今までの「Hi-Use Net」のIDにドメイン名をつけるだけでインターネットからメールを受け取れるようになった。
パソコン通信の大きな欠点は,画像や音声,動画などが簡単に扱えないことであるが,インターネットの通信方式を「Hi-Use
Net」のユーザーにも利用可能にすることで,この欠点を克服可能とした。平成8年10月より,インターネットの接続手順で総合教育センターにダイアルアップ接続して,総合教育センターのWWWサーバーにアクセスできるようになった。これにより山梨県内のインターネットの通信方式によるネットワーク(イントラネット)が実現された。この接続はパソコン通信のIDパスワードがそのまま利用可能なので,改めてユーザー登録する必要はない。
現在「Hi-Use
Net」のユーザーはインターネットには経路制御により接続できなくしてある。これは,上位回線との契約に予め登録した特定ユーザー以外は接続しないことが定められているからであるが,今後上位回線を民間プロバイダーに切り替えた後も,民間の業者の保護のため,学校以外はインターネットには繋がない予定である。
(2)一局集中型からクラスター型へ
総合教育センターでは,インターネットを導入した当初から,将来は県内のすべての公立学校を総合教育センター経由でインターネットに接続するプランを持っていた。ところが実験プロジェクトとして事業が始まったこと,学術ネットの特別会員として上位回線の利用が認められたため,契約上一般の学校をインターネットに接続できない状況となった。しかし,この間に学校のインターネットを活用する意欲は非常に強く,独自に民間プロバイダーと契約して導入する学校が急激に増加しつつある。本年度総合教育センターで行った調査によると,県内の学校のうち146校が平成9年度末までにはインターネットに接続する。これは県内の公立学校のうち約40%にあたる学校数である。このうち総合教育センターに接続している学校は23校であるので大部分はいろいろな民間プロバイダーと接続していることになる。
a.教育センター集中接続の利点と欠点
総合教育センターに学校が直接接続することの利点は次のような点が考えられる。
・教育センターのサーバーへのアクセス経路が複雑でないので,一定の通信速度が確保でき,教育センターからの情報利用が容易である。
・他の経路を通過しないので外部への情報漏れの可能性が少く,公的な情報の通信にも利用しやすい。
・有害情報のフィルタリングを教育センターで一括処理できる。
・インターネット接続のための学校の費用負担や労力負担を軽減できる。
一方欠点と考えられることは次のとおりである。
・一極集中することで,利用の集中する時間が重なり,インターネットへの接続速度が遅くなる。
・教育センターとの距離により,通信にかかる費用に学校間格差が生じる。
・学校がサーバーを持たない場合,教育センターの負担が増大する。
・教育センターに障害が発生すると,全学校の通信が停止してしまう。
このように,学校がインターネットを活用するために,環境を整備し,技術的な支援や回線の負担を行い,容易に利用しうるようにする事は大切なことであるが,現在のように沢山の民間プロバイダーが存在し,県下にいくつものアクセスポイントを持つ業者も存在する状況では,すべて教育センターに直接つなぐことが必ずしもベストであるとはいえない。
b.Y−NIXとYCN
平成9年の12月に山梨では,県の働きかけで,県内にアクセスポイントを持っている主なプロバイダーが参加して相互接続機構(Y−NIX)を設立した。今までに一地方の県が相互接続機構を設立した例はなく,画期的な取り組みである。今までは学校から教育センターに接続する場合でも,民間プロバイダーに接続している学校は東京の相互接続機構経由でなければ接続できなかった。県内にY−NIXができたことにより,県内間の通信はY−NIX経由で行われるため,非常に混んでいる東京の相互接続機構を遠回りして通る必要がなくなり,県内の通信は快適になった。学校教育ネットワークからみたY−NIXの効用は,県内の学校がすべて同一の上位ネットワークに直接接続していなくても,県内のいずれかのネットワークに接続するすべての学校の間がネットワーク上で近距離で通信できる仮想ネットワークの運用が可能になることである.このようなネットワークを利用して,学校間で文字テキストの情報のみならず,画像や音声を実時間で双方向に伝送することが可能になり,このような機能を利用して,互いに離れた学校の間で交流授業やテレビ電話のような情報交換も可能になる.また,Y−NIXを経由して,学校と地域の色々なネットワークに接続する組織や家庭とり間の通信も迅速になり,この経路を通じて,学校と家庭,学校と地域の間の日常的な情報交流が可能になる.
また,山梨県では平成10年度から「シームレス通信実験事業」をスタートさせる。県域の防災無線網やCATV,インターネット,衛星回線等を相互に継ぎ目なく接続する「山梨コミュニケーションズネットワーク(YCN)」を構築し行政の情報化や県民参加のモデル実験を行う計画である。教育の分野でもサテライトスクール実験が計画されている。学校教育ネットワークからみたYCNの効用は,生涯学習ネットワークや地域共同体の情報ネットワークと学校教育ネットワークを相互に接続することにより,児童・生徒と地域の大人の情報交換,情報サーバの共有,共同利用が可能になることである.
このように山梨の通信ネットワークは急速に整備されつつある。今後は,それぞれの地域で最も有効で活用しやすいネットワークに接続し,それらの相互接続により,全体として教育で有効に活用できるネットワークとなっていくものと考えられる。今後は他県でもこのようなクラスター型のネットワーク形態が導入されていくのではないだろうか。それに伴い,教育センターの果たす役割も,インフラの整備から教育で活用できる情報の整備やWeb教材の整備,インターネットの活用研修,技術支援などのソフト的な内容に重点を置いたものになる必要があると思われる。
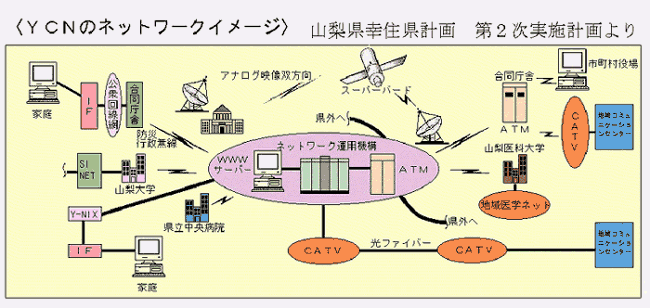
(3)県立学校に導入するシステム
山梨県教育委員会は,平成10年度に「総合教育センターを核としたインターネット網の整備」を行う計画を立て,「山梨幸住県計画」の「第2次実施計画」に組み込むとともに,予算要求を行った。要求の主な点は次のとおりである。
・総合教育センターの上位回線を学術ネットから民間プロバイダーに移行し,回線容量も増強する。
・総合教育センターのダイアルアップ受信用の回線を増強する。
・総合教育センターのインターネットサーバーを増強する。
・県立学校にインターネット接続用のINS64回線を設置する。
・県立学校にLAN型ダイアルアップに対応したルーター及び端末用コンピュータ1台を設置する。
・新設のパソコン教室を設置済みの学校及び10年度設置予定の学校にはインターネットサーバーを設置する。
・谷村工業高校を総合教育センターに専用線で接続し,ここを周辺の学校の接続拠点とする。
まだ,現時点では予算が要求通りとおるかどうか分からないが,今後学校に導入を考えているシステムの構想が伺える。
・学校を総合教育センター経由でインターネットに接続する。
・接続形態は基本的にLAN型ダイアルアップで行う。
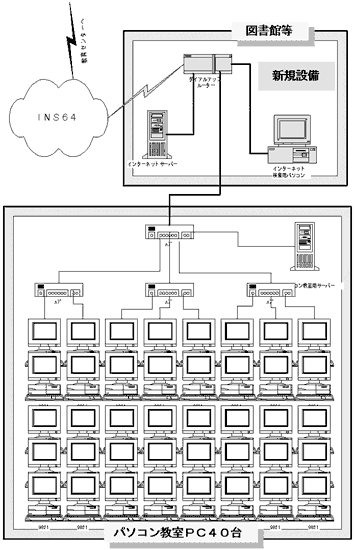
・当面は端末1台を設置するが,パソコン教室の更新とともにインターネットサーバーを設置する。
学校施設課が昨年度から開始した普通高校のパソコン教室の更新と連動して,パソコン教室の40台のコンピュータがインターネットと接続される。これにより生徒が授業などでインターネットを活用することができるようになる。
また,学校にサーバーが設置されることにより,ダイアルアップではあるが,校内でメールアドレスを発行でき,職員や生徒の使用を可能にできる。
WWWサーバーの機能もあるので,校内での情報交流や生徒の情報発信の実習にも活用できる。このWebページはこのままでは外部に公開できないが,総合教育センターのサーバーにこれらのミラーを置くことによりインターネットにも公開可能となる。このサーバーを核に順次校内のLANを拡張していくことも可能である。将来通信量が増加した場合専用線に切り替えて運用することも容易である。このシステムは県立学校のためのものであるが,小中学校でも類似のシステムとしていくことが良いのではないかと考える。このシステムが学校のインテリジェント化の核となってくれることが期待される。
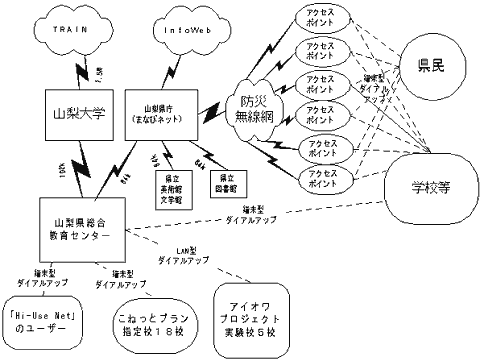
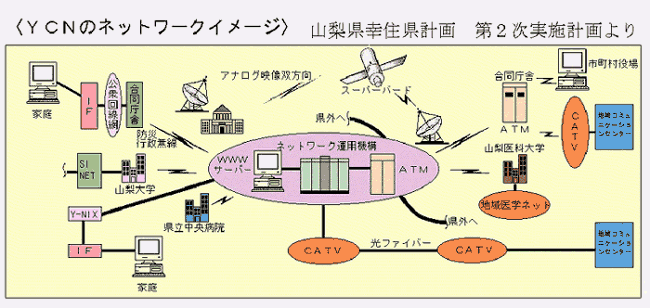
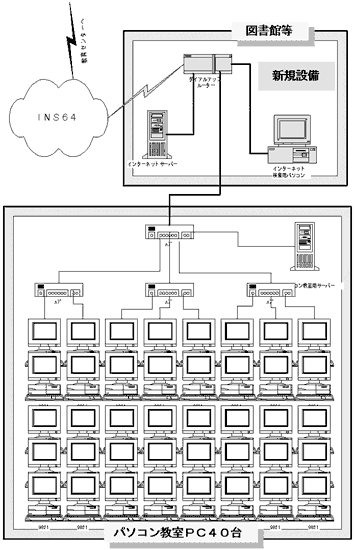 ・当面は端末1台を設置するが,パソコン教室の更新とともにインターネットサーバーを設置する。
・当面は端末1台を設置するが,パソコン教室の更新とともにインターネットサーバーを設置する。