俁丏侾丏俀丂嵅夑導嫵堢僙儞僞乕偵偍偗傞妶摦
丂嫵堳偺抭宐偺岎棳傪栚揑偲偟偰暯惉俇擭侾侾寧傛傝僷僜僐儞捠怣傪拞怱偵塣梡偑奐巒偝傟偨乽嵅夑導嫵堢忣曬僔僗僥儉乬俤俢倀亅俻倀俙俲俬俤偝偑乭乿傕丄杮擭搙偐傜偼乽僀儞僞乕僱僢僩妶梡嫵堢悇恑帠嬈乿偲偟偰僀儞僞乕僱僢僩偺杮奿塣梡傪巒傔偨丅乬俤俢倀乕俻倀俙俲俤偝偑乭偺塣梡忬嫷偲崱屻偺寁夋摍偵偮偄偰曬崘偡傞丅
丂
俁丏侾丏俀丏俀丂嵅夑導嫵堢忣曬僔僗僥儉乬俤俢倀乕俻倀俙俲俤偝偑乭偺塣梡忬嫷偵偮偄偰
丂乮侾乯宱堒
丂丂丂暯惉俁擭侾侾寧偵嵅夑導嫵堢忣曬僔僗僥儉専摙埾堳夛傪愝抲偟丄杮導嫵堢挿偐傜嫵堢忣曬僔僗僥儉偺嵼傝曽偵偮偄偰帎栤偑側偝傟丄暯惉係擭侾俀寧偵摎怽偑弌偝傟傞丅暯惉俆擭搙偼挷嵏尋媶傪峴偄丄暯惉俇擭侾侾寧偵僷僜僐儞捠怣傪拞怱偲偡傞乽嵅夑導嫵堢忣曬僔僗僥儉乬俤俢倀亅俻倀俙俲俤偝偑乭乿偺塣梡傪奐巒偡傞丅僀儞僞乕僱僢僩偵偮偄偰偼挷嵏尋媶偲偟偰丄暯惉俈擭係寧偵俤亅倣倎倝倢偺僒乕價僗傪巒傔丄暯惉俈擭侾侽寧偵嫵堢僙儞僞乕偺儂乕儉儁乕僕傪棫偪忋偘傞偲偲傕偵僟僀儎儖傾僢僾俬俹愙懕偺僒乕價僗偺帋峴傕奐巒偟偨丅暯惉俋擭搙偵偼乽僀儞僞乕僱僢僩妶梡嫵堢悇恑帠嬈乿偲偟偰杮奿塣梡傪奐巒偟丄侾侽寧偵僔僗僥儉峏怴傪峴偆丅
丂
丂乮俀乯僀儞僞乕僱僢僩妶梡嫵堢悇恑帠嬈偺栚揑
丂丂丂導撪偺彫丒拞丒導棫妛峑偲慡崙丒悽奅偺妛峑丄尋媶婡娭摍傪僀儞僞乕僱僢僩偱寢傃丄僀儞僞乕僱僢僩傪妶梡偟偨嫵堢偺悇恑媦傃嫵堢忣曬偺岎棳偺廩幚傪恾傝丄丂丂杮導偺嫵堢偺廩幚敪揥偵帒偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞傕偺偱丄師偺傛偆側帠崁傪巟墖偡傞丅
丂丂丂丂丒懡條偱朙偐側妛廗娐嫬偺採嫙
丂丂丂丂丒嫵巘偺宱尡揑抦幆偺拁愊丒棳捠
丂丂丂丂丒嫵堢尋媶婡娭摍偲偺岎棳偺懀恑
丂丂丂丂丒嫵嵽摍偺拁愊丒棳捠偺懀恑
丂丂丂丂丒嫵堢峴惌摍偺忣曬偺拁愊丒棳捠偺岠棪壔
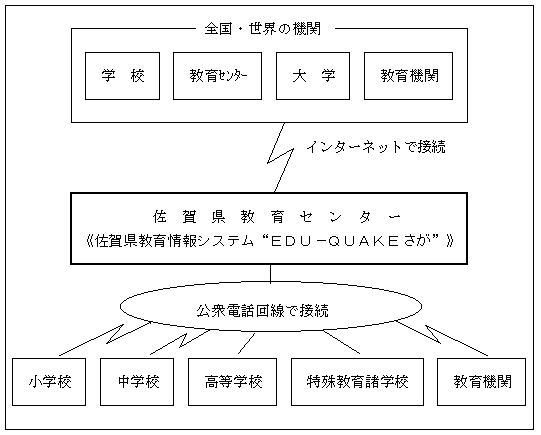
丂
丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾丂乬俤俢倀亅俻倀俙俲俤偝偑乭僀儊乕僕恾丂
丂
丂乮俁乯悇恑懱惂
丂丂丂杮僔僗僥儉偺僗儉乕僘側塣梡偲妶梡傪恾傞偨傔偵師偺傛偆側懱惂傪庢偭偨丅
丂
丂倎丏嵅夑導嫵堢忣曬僔僗僥儉塣塩嫤媍夛乮暯惉俇擭搙乣暯惉俉擭搙乯
丂丂丂丂丂杮僔僗僥儉偺塣塩偵偮偄偰嫤媍傪峴偆偨傔偵暯惉俇擭傛傝暯惉俉擭傑偱擭娫俀夞幚巤偟偨丅嫤媍撪梕偼丄嘆杮導偺妛峑嫵堢偵偍偗傞嫵堢忣曬僔僗僥儉偺塣塩偺峔憐偵娭偡傞偙偲嘇嫵堢忣曬僨乕僞儀乕僗偵娭偡傞偙偲嘊嫵堢忣曬僱僢僩儚乕僋偵娭偡傞偙偲摍偱偁傞丅傑偨丄嫤媍夛偺埾堳偼嘆妛幆宱尡幰乮庡偵戝妛娭學幰乯嘇嫵堢峴惌娭學幰乮妛峑嫵堢壽丄惗奤妛廗壽乯丄嘊妛峑嫵堢娭學幰嘋儚乕僋僔儑僢僾戙昞幰偱偁傞丅
丂丂丂丂丂暯惉侾侽擭搙偱偼僔僗僥儉妶梡悇恑嫤媍夛傪奐嵜偡傞梊掕偱偁傞丅
丂
丂倐丏嫵堢忣曬僔僗僥儉扴摉幰偺愝抲偲尋廋夛
丂丂丂丂丂妛峑撪偺棙梡幰傪巟墖偡傞偨傔丄妛峑偺峑柋暘彾偵嫵堢忣曬僔僗僥儉扴摉幰偺愝抲傪梫惪偡傞丅扴摉幰偼丄杮僔僗僥儉偺庢埖偺島廗傗憡択丄奺庬挷嵏側偳妛峑偵偍偗傞忣曬嫵堢偺梫偲側傞嬈柋傪峴偆丅嫵堢僙儞僞乕偐傜杮僔僗僥儉偵學傢傞撪梕偺楢棈丒捠抦偼扴摉幰傪捠偟偰偍偙側偆丅
丂丂丂丂丂嫵堢忣曬僔僗僥儉扴摉幰尋廋夛偼丄扴摉幰偲偟偰偺栶妱偵偮偄偰擣幆傪怺傔丄杮僔僗僥儉偺棙梡媄弍偺岦忋偲嫵堢妶梡傪悇恑偡傞偺偵昁梫側帒幙偺岦忋傪栚揑偲偟偰丄暯惉俇擭搙偐傜幚巤偡傞丅
丂丂丂丂丂尋廋夛偱偼丄杮僔僗僥儉偺愢柧傗嫵堢棙梡偵偮偄偰偺島媊偺懠偵丄妛峑儂乕儉儁乕僕偺嶌惉丄儊乕儖偺棙梡丄僱僢僩僒乕僼傿儞側偳偺幚廗傪庢傝擖傟偰偄傞丅杮擭搙偼丄僔僗僥儉偺峏怴傪峴偭偨偙偲傕偁傝丄僔僗僥儉棙梡偱偺曄峏揰傗愝掕偺曄峏曽朄媦傃丄僀儞僞乕僱僢僩傪嫵堢妶梡偟偰偄傞愭惗曽偺幚慔敪昞傪尋廋撪梕偲偟偨丅
丂
丂們丏嫵堢僙儞僞乕偺島嵗
丂丂丂丂丂杮擭搙偺忣曬偵學傢傞尋廋偱偼丄峑撪尋廋巜摫幰傪堢惉偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰師偺撪梕偵庡娽傪偍偄偨島嵗傪奐愝偟偨丅嘆僐儞僺儏乕僞儕僥儔僔乕偵偮偄偰嘇僐儞僺儏乕僞偺庼嬈妶梡偵偮偄偰嘊忣曬捠怣僱僢僩儚乕僋偵偮偄偰丅偙傟傜慡偰偺島嵗偵偍偄偰丄僀儞僞乕僱僢僩偵娭傢傞撪梕傪幚巤偟偨丅
傑偨丄忣曬埲奜偺嫵壢暿島嵗偵偍偄偰傕丄僀儞僞乕僱僢僩偺嫵壢棙梡傪偦偺撪梕偵惙傝崬傫偩丅
丂
丂倓丏嫵堢忣曬偩傛傝偺攝晍丂
丂丂丂丂丂杮僔僗僥儉偺塣梡忬嫷偵偮偄偰峀偔棟夝偟丄妶梡偟偄偨偩偔偨傔偵丄暯惉俇擭搙偐傜暯惉俉擭搙傑偱俇夞嶌惉偟丄奺妛峑偵攝晍傪峴偭偨丅
丂
丂乮係乯塣梡忬嫷乮僀儞僞乕僱僢僩偺傒乯
丂倎丏導壓偺妛峑偺愙懕忬嫷
丂丂丂丂丂嫵堢僙儞僞乕偲奺妛峑偲偺愙懕忬嫷偼丄杮擭搙俋寧枛偺挷嵏偱彫妛峑俇俀亾丄拞妛峑俇俋亾丄導棫妛峑俉俋亾丄慡懱偱俇俉亾偱偁傞丅導棫妛峑傊偼暯惉俇擭搙偺僷僜僐儞捠怣奐愝帪偵儌僨儉偲揹榖夞慄傪攝晍偟偰偄傞偙偲傕偁傝愙懕棪偼崅偄丅
丂
丂丂 昞俁丏侾丏俀亅侾丂僀儞僞乕僱僢僩愙懕忬嫷
| 丂丂 |
暯惉俉擭俋寧 |
暯惉俋擭俁寧 |
暯惉俋擭俋寧 |
| 彫妛峑乮侾俈俈峑拞乯 |
係俆
|
俆俉
|
侾侾侽
|
| 拞妛峑丂乮俋俆峑拞乯 |
俁係
|
俁俈
|
俇俇
|
| 導棫妛峑乮係係峑拞乯 |
俀係
|
俁侾
|
俁俋
|
丂
丂倐丏俬俢偺敪媼忬嫷
丂丂丂丂丂奺妛峑丄嫵堢帠柋強摍偺嫵堢婡娭傊偺俬俢偺敪媼偺懠偵丄導撪偺嫵堢娭學婡娭偵懏偡傞婓朷幰偵俬俢偺敪媼傪峴偭偰偄傞丅僀儞僞乕僱僢僩偺俬俢敪媼悢偼丄侾俀寧枛偱俀丆俈侽俈丅僷僜僐儞捠怣偺敪媼悢傪崌傢偣傞偲俆丆侽俁侾偱偁傝丄彫丒拞丒導棫妛峑偵嬑柋偡傞嫵怑堳偺栺俇侽亾偑乬俤俢倀亅俻倀俙俲俤偝偑乭偺俬俢傪帩偮偙偲偵側傞丅
丂
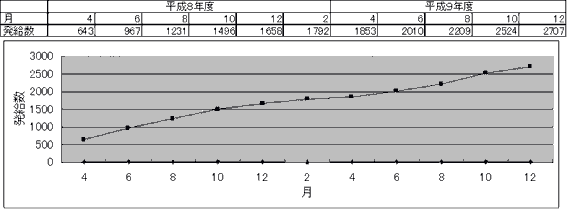
丂恾俁丏侾丏俀亅俀丂僀儞僞乕僱僢僩俬俢敪媼悢
丂
丂們丏傾僋僙僗忬嫷
丂丂丂丂丂寧偛偲偵傾僋僙僗悢偼偺傃偰偄傞丅偲偔偵暯惉俋擭侾侽寧偺怢傃偼媫寖偱偁傝丄慜寧偺栺侾丏俉攞偵側偭偰偄傞丅偙傟偼婡婍峏怴偺嵺丄揹榖夞慄傪憹傗偡側偳偺夵慞偵傛傞傕偺偱偁傞丅
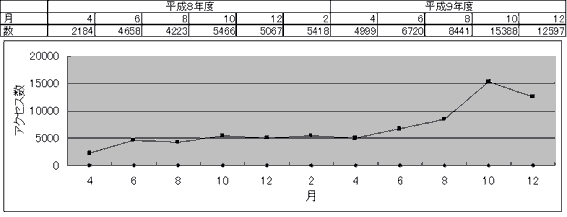
丂恾俁丏侾丏俀亅俁丂僀儞僞乕僱僢僩傾僋僙僗忬嫷
丂
丂倓丏儂乕儉儁乕僕偐傜揮憲偝傟偨僼傽僀儖悢
丂丂丂丂丂乬俤俢倀亅俻倀俙俲俤偝偑乭偺儂乕儉儁乕僕偐傜揮憲偝傟偨僼傽僀儖悢傕婡婍偺峏怴偲偲傕偵儂乕儉儁乕僕傪峏怴偟偨偙偲傕偁傝媫寖偵怢傃偨丅
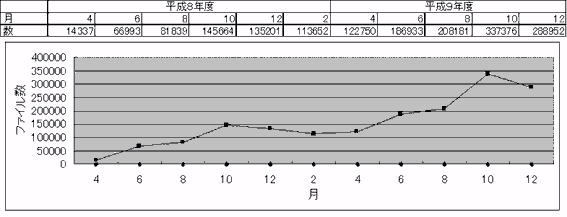 丂丂丂丂
丂丂丂丂
丂丂恾俁丏侾丏俀亅係丂儂乕儉儁乕僕偐傜揮憲偝傟傞僼傽僀儖悢
丂
丂倕丏妛峑偺儂乕儉儁乕僕奐愝悢
丂丂丂丂丂妛峑偺儂乕儉儁乕僕奐愝悢偼丄彫丒拞丒導棫妛峑偁傢偣偰俇俇偱妛峑愝抲悢偺栺俀侾亾偵偁偨傞丅
丂
昞俁丏侾丏俀亅俀丂妛峑偺儂乕儉儁乕僕悢
| 彫 妛 峑乮侾俈俈峑拞乯 |
丂俀俉 |
| 拞 妛 峑乮丂俋俆峑拞乯 |
丂侾俈 |
| 導棫妛峑乮丂係係峑拞乯 |
丂俀侾 |
| 崌丂丂寁乮俁俀俇峑拞乯 |
丂俇俇 |
丂
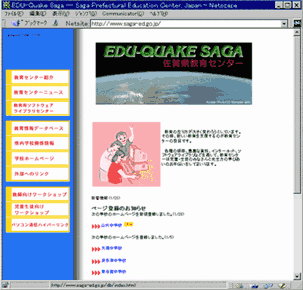
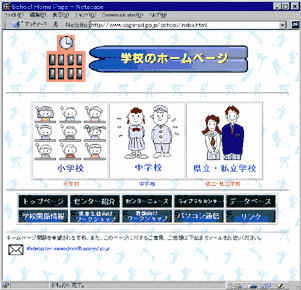
丂丂
恾俁丏侾丏俀亅俆丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅俇
乬俤俢倀亅俻倀俙俲俤偝偑乭偺儂乕儉儁乕僕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂妛峑偺儂乕儉儁乕僕
丂http://www.saga-ed.go.jp/

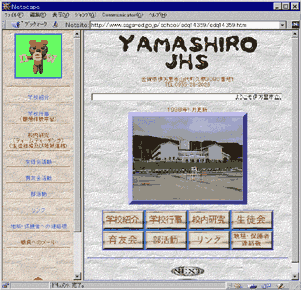
恾俁丏侾丏俀亅俈丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅俉
懢椙挰棫懡椙彫妛峑偺儂乕儉儁乕僕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埳枩棦巗棫嶳戙拞妛峑偺儂乕儉儁乕僕
丂倖丏儚乕僋僔僢僾
丂丂丂丂丂儚乕僋僔儑僢僾偲偼丄摿掕偺僥乕儅偺傕偲偱榖偟崌偄傗妶摦傪峴偆僌儖乕僾偺偙偲偱丄乽抦宐偺僱僢僩儚乕僋乬俤俢倀亅俻倀俙俲俤偝偑乭乿偵偍偗傞丄抦宐傪惗嶻偡傞僱僢僩儚乕僋忋偺尋媶僌儖乕僾偱偁傞丅嫵堢偵娭偡傞條乆側忣曬乮嫵嵽丄巜摫埬丄帒椏摍乯偺拁愊丄嫟桳丄岎姺傪栚揑偲偡傞帺庡揑尋媶妶摦偺応偱偁傞丅
丂丂丂丂丂嫵巘岦偗偲帣摱惗搆岦偗偺偁傢偣偰侾俁偺儚乕僋僔儑僢僾傪奐愝偟偰偄傞丅堦椺傪嫇偘傞偲乽娐嫬栤戣偺晹壆乿乮恾俁丏侾丏俀亅侾侽乯丄乽偨傫偗傫嵅夑乿丄乽帇妎忈奞幰巟墖俽倵倎値乿乮恾俁丏侾丏俀亅侾侾乯丄乽嫵堢忣曬曮扵偟乿乮恾俁丏侾丏俀亅侾俀乯側偳偑偁傞丅僷僜僐儞捠怣偵偍偄偰傕俉侾偺儚乕僋僔儑僢僾傪奐愝偟偰偄傞偑丄僀儞僞乕僱僢僩傊偺堏怉傪恑傔偰偄傞丅
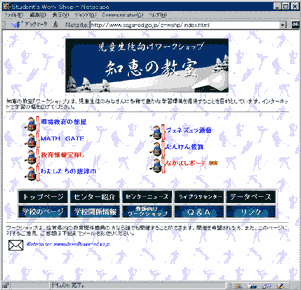
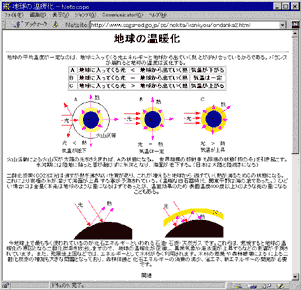 丂
恾俁丏侾丏俀亅俋儚乕僋僔儑僢僾偺儁乕僕丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾侽
丂
恾俁丏侾丏俀亅俋儚乕僋僔儑僢僾偺儁乕僕丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾侽
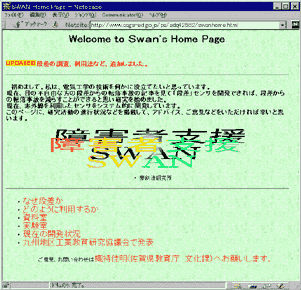
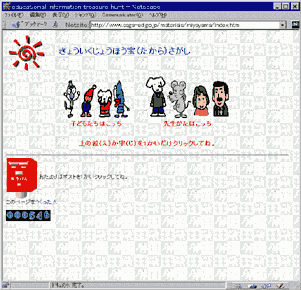
恾俁丏侾丏俀亅侾侾丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾俀
倗丏嫵堢梡忣曬僨乕僞儀乕僗乮恾俁丏侾丏俀亅侾俁乯
丂丂丂丂丂乬俤俢倀亅俻倀俙俲俬俤偝偑乭偺儂乕儉儁乕僕偵奐愝偟偰偄傞僨乕僞儀乕僗偵偼師偺傕偺偑偁傞丅
丂丂丂丂丒僜僼僩僂僃傾儔僀僽儔儕僙儞僞乕強桳偺僜僼僩僂僃傾専嶕偺儁乕僕
丂丂丂丂丂乮恾俁丏侾丏俀亅侾係乯
丂丂丂丂丒嵅夑導嫵堢僙儞僞乕恾彂専嶕偺儁乕僕
丂丂丂丂丒嵅夑導嫵堢僙儞僞乕挿婜尋廋曬崘彂乮梫栺)
丂丂丂丂丒嵅夑導嫵怑堳撪抧棷妛榑暥偺梫栺
丂丂丂丂丒嫵堢僙儞僞乕強桳尋媶婭梫専嶕偺儁乕僕乮恾俁丏侾丏俀亅侾俆乯
丂丂丂丂丒幚慔帠椺専嶕偺儁乕僕乮恾俁丏侾丏俀亅侾俇乯
丂丂丂丂丂僨乕僞儀乕僗偲偼尵偭偰傕傑偩僨乕僞検偑彮側偄傕偺傕偁傝丄崱屻偦偺廂廤偲搊榐曽朄偵夵慞偑媮傔傜傟傞丅
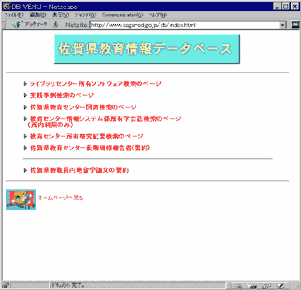
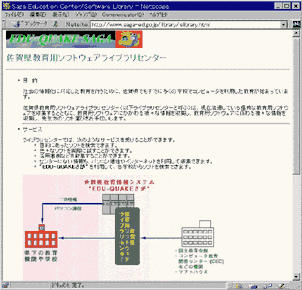
恾俁丏侾丏俀亅侾俁丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾係
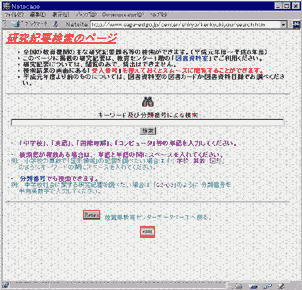
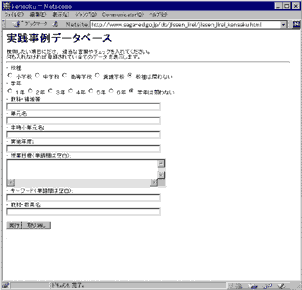
恾俁丏侾丏俀亅侾俆丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾俇
丂丂倛丏嵅夑導撪妛峑娭學忣曬偺儁乕僕乮恾俁丏侾丏俀亅侾俈乯
丂 丂丂丂妛峑嫵堢壽偐傜妛峑傗惗搆丒曐岇幰岦偗偵奐愝偟偨儁乕僕偵偼師偺傕偺偑偁傞丅
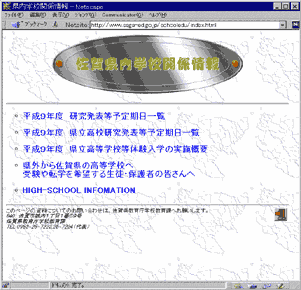 丂
丂
丂
丂 丒導棫妛峑懱尡擖妛偺幚巤奣梫
丂 丒尋媶敪昞梊掕婜擔堦棗
丂 丒導奜偐傜嵅夑導偺崅摍妛峑傊庴尡揮妛傪婓朷偡傞惗搆丒曐岇幰偺奆偝傫傊
丂 丒崅峑恑妛偺偨傔偺 HIGH-SHOOL INFOMATION
丂
丂
丂
恾俁丏侾丏俀亅侾俈
丂
丂 丂倝丏嫵堢棙梡乮幚慔帠椺乯
丂丂丂丂丂僀儞僞乕僱僢僩偺嫵堢棙梡傊偺庢傝慻傒忬嫷偵偮偄偰偄偔傜偐帠椺傪偁偘偰傒傞丅
丂丂丂丂丒抧堟偺娐嫬挷嵏傪峴偄丄偦偺惉壥傪娐嫬忣曬偲偟偰敪怣丅
丂丂丂丂丂乮恾俁丏侾丏俀亅侾俉乯
丂丂丂丂丒傠偆妛峑偺惗搆偺儊乕儖傪巊偭偰偺岎棳妶摦乮恾俁丏侾丏俀亅侾俋乯
丂丂丂丂丒傊偒抧丒彮恖悢妛媺偺帣摱偨偪偑崙岅偺妛廗傪捠偟偰偺岎棳妛廗
丂丂丂丂丂乮恾俁丏侾丏俀亅俀侽乯
丂丂丂丂丒奜崙偺惗搆偲儊乕儖傪巊偭偰偺塸岅妛廗
丂丂丂丂丒壽戣尋媶偱妛峑偺儂乕儉儁乕僕傪嶌惉乮恾俁丏侾丏俀亅俀侾乯
丂丂丂丂丒俠倀亅俽倕倕俵倕傪巊偭偨崌摨妛廗乮恾俁丏侾丏俀亅俀俀乯
丂丂丂丂偦偺懠丄挷傋妛廗傊偺妶梡側偳僀儞僞乕僱僢僩傪巊偭偰偺妛廗妶摦偑惙傫偵峴傢傟傞傛偆偵側偭偨丅

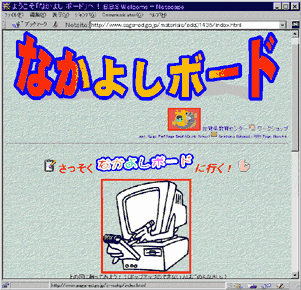
恾俁丏侾丏俀亅侾俉丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾俋
搨捗巗棫婼捤彫妛峑偺傒偠偐側娐嫬挷傋丂丂丂丂丂丂丂丂丂導棫傠偆妛峑偺側偐傛偟儃乕僪
丂
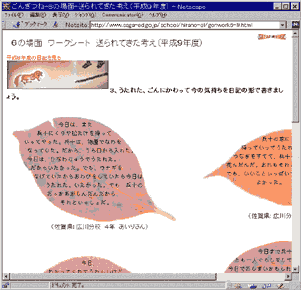

恾俁丏侾丏俀亅俀侽丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅俀侾
尩栘挰棫尩栘彫妛峑暯擵暘峑偺崙岅偺傊傗丂丂丂丂丂丂丂導棫懡媣岺嬈崅峑偺儂乕儉儁乕僕
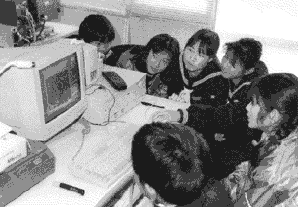 恾俁丏侾丏俀亅俀俀
恾俁丏侾丏俀亅俀俀
桳柧挰棫桳柧拞妛峑偲晲梇巗棫晲梇
杒拞妛峑偺俠倀亅俽倕倕俵倕傪巊偭偨崌摨妛廗
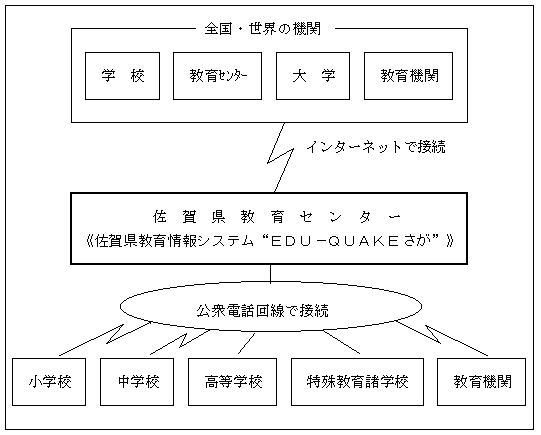 丂
丂 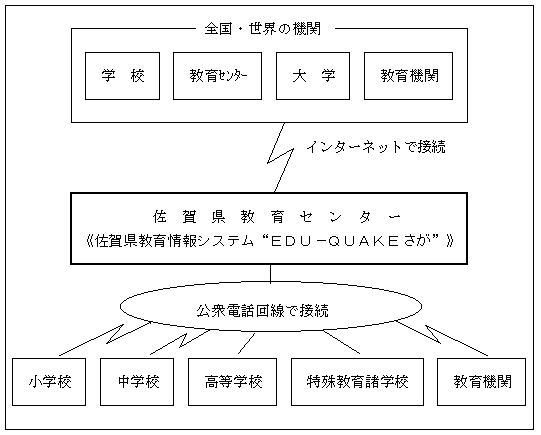 丂
丂 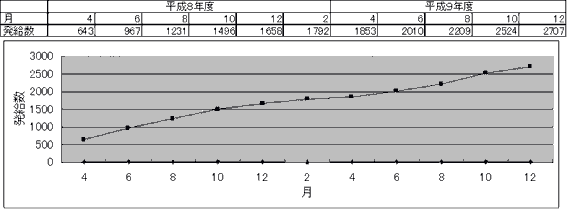
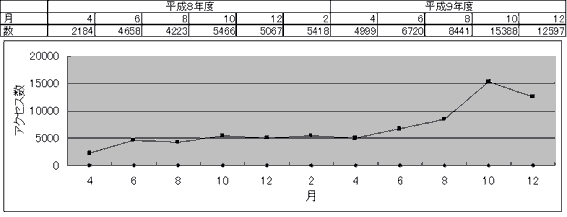
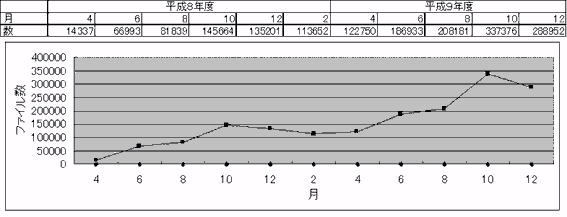 丂丂丂丂
丂丂丂丂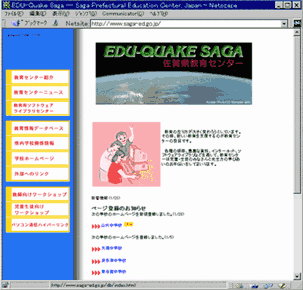
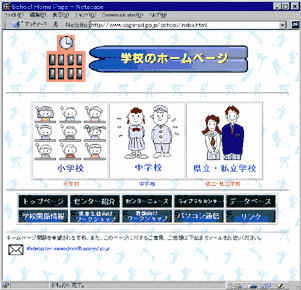

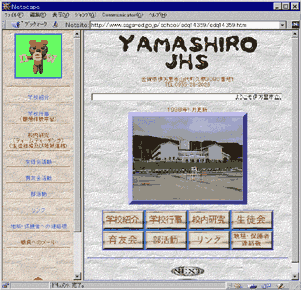
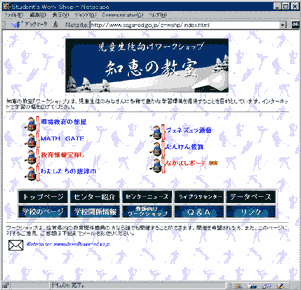
丂 恾俁丏侾丏俀亅俋儚乕僋僔儑僢僾偺儁乕僕丂丂丂丂丂恾俁丏侾丏俀亅侾侽
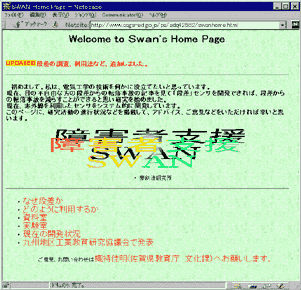
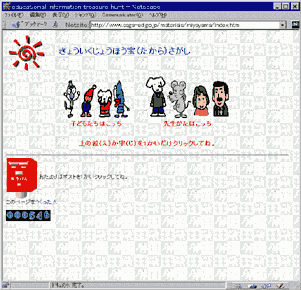
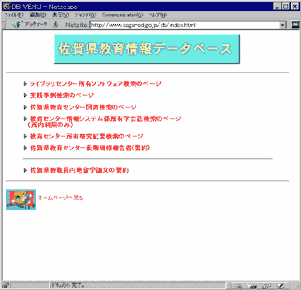
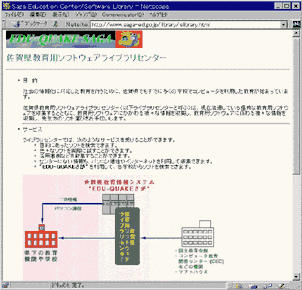
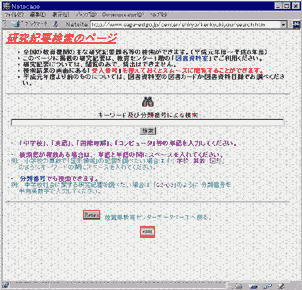
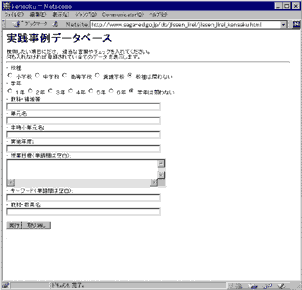
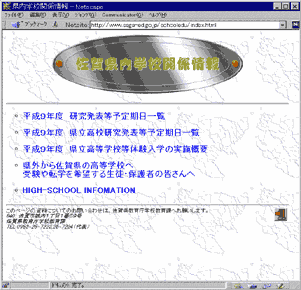 丂
丂 
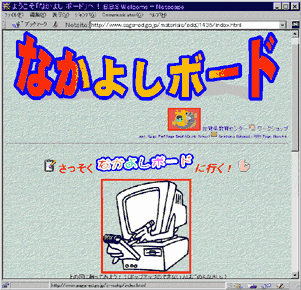
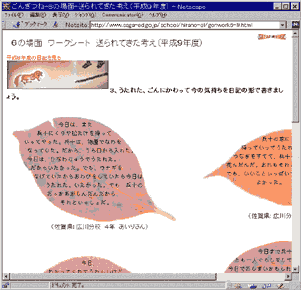

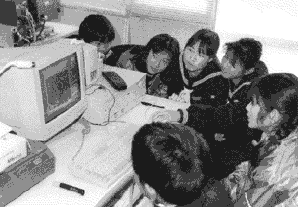 恾俁丏侾丏俀亅俀俀
恾俁丏侾丏俀亅俀俀