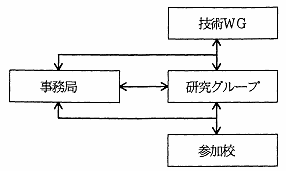
技術WG:企画の検討
研究グループ:実験システムの検討、授業内容の設計、実験結果の分析
参加校:教育用素材の提供、高速回線を利用した授業の実施
(1) 企画の目的
我が国の情報化社会の本格的到来により、通信回線の高速化が急速に高まっている。
教育の現場においても、動画等のデータ量の大きな教育用素材をインターネット上で操作できる環境の整備に対する期待が高まっている。
このため、将来予想される高速回線を用いた動画や音声等を活用可能な共同作業支援ツールを使用した授業実践を行い、インターネットの教育利用における高速回線の活用方法について調査する。
(2)企画の概要
昨年度のインターネット上での共同作業支援ツール、学習用プレゼンテーションシステム(以下「Plessui」という)を用いた活用実証実験の結果をふまえて、インターネットの教育への活用を試みることとした。昨年度の実証実験で低速回線ゆえに問題となったこと、低速回線ゆえに実現できなかったことが、高速回線を用いることにより、それらをどこまで克服することができるかを念頭におき、さらに、教育利用の効果と課題を明らかにすることを目的とし、実験を行うこととした。
具体的には、1.5Mbps程度の高速回線を用いた共同学習の実験(以下、実験という)を行い、高速回線利用の課題の抽出および教育的効果の評価を行い、高速回線の活用方法について考察することとした。
(3)高速回線の確保
本実験では、当初学校間に新しく回線を引くことも考えたが、コスト面から既設回線を利用することとした。また、教育現場との便益性を考え、情報処理振興事業協会の本部(以下、IPAという)と情報基盤センター(以下、CIIという)問の1.
5Mbpsの専用回線を使用することとした。
(4)参加校
IPAとCIIに児童・生徒が移動可能で、校種が同じ学校を調査し、参加の理解を得られた次の2校で授業実践を行うこととした。
・港区立神応小学校:IPAに児童が移動して授業に参加
・大和市立林間小学校:CIIに児童が移動して授業に参加
(1)実施体制
CECでは、高度化技術ワーキンググループ(以下、技術WGという)を設置し、この実験の実施に関して審議を重ねた。技術WGの下に「高速回線を用いた共同学習実験研究グループ」(以下、研究グループという)を設置し、実験実施上の課題検討や実施結果の評価のための体制を検討し、図1.1-1の体制とした。
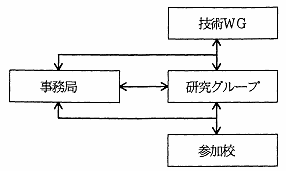 |
| 事務局(CEC):研究グループの運用、参加校への支援、報告書のとりまとめ 技術WG:企画の検討 研究グループ:実験システムの検討、授業内容の設計、実験結果の分析 参加校:教育用素材の提供、高速回線を利用した授業の実施 |
|
図1.1-1企画実施の体制
|
(2)技術WG
| 1)委員構成 | ||
| 主査 | 苗村憲司 | (慶応義塾大学環境情報学部教授) |
| 委員 | 国分明男 | (財団法人ニューメディア開発協会理事) |
| 委員 | 高橋邦夫 | (東金女子高等学校総務部長) |
2)技術WGの活動
・第1回技術WG会議(平成9年5月30日)
「高速回線を用いた共同学習実験」を高度化技術のテーマの候補として検討した。
・第2、3回技術WG会議(平成9年6月12日、7月3日)
企画内容及ぴ進め方を検討した。
・第4回、5回技術WG会議(平成9年7月30日、9月2日)
実施計画を検討した。
| 1)委員構成 | ||
| 委員 | 苅宿俊文 | (港区立神応小学校教諭) |
| 委員 | 浅野智子 | (大和市立林間小学校教諭) |
|
表1.1-1研究グループの活動スケジュール
|
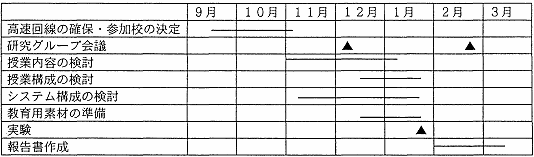 |
3)研究グループ会議
・第1回(平成9年12月4日):
共同学習実験の内容、学習環境、スケジュールおよび進め方について討議した。また、実際に授業を行う神応小学校および林間小学校の担任の教師と事務局による参加校会議を別途持ち、授業内容の構成、授業構成の検討および教育用素材の準備を検討することとした。
・第2回(平成10年2月26日)
実験に参加した児童が記入したアンケートを分析し、高速回線利用の課題と教育的効果、及び高速回線の活用方法について討議し、報告書に記述することとした。
(4)メーリングリスト
メーリシグリスト(kousoku97@cec.or.jp)を開設し、参加校、研究グループの委員、事務局をメンバーとし、各々からの実験に関する情報提供および情報交換を行った。また、参加校に対する技術支援もこのメーリシグリストで行った。