インターネット電子地図を利用した
|
インターネット電子地図を利用した協働学習環境の構築プロジェクトに参加した組織は以下のとおりである。
九州工業大学情報工学部硴崎研究室
粕屋町の教育委員会および小中学校
住商エレクトロニクス(株)
エリアス
また,参加者氏名を表 1に示す。プロジェクトの総括は,九州工業大学の硴崎賢一が担当した。各小中学校の参加者は,指導案の整備,実証授業の実施などを担当した。住商エレクトロニクスは,情報システムの設置運営に関する支援を,エリアスはGIS技術やWWW技術に関する支援を行った。
表 1 プロジェクトメンバー
|
所 属 |
氏 名 |
専門分野 |
|
|
九州工業大学 |
情報工学部 |
硴崎賢一 |
情報工学 |
|
粕屋町小学校 |
粕屋中央小学校 |
寺本正治 |
教諭,教務主任 |
|
野中慎治 |
教諭,社会科担当 |
||
|
竹本学 |
教諭,情報教育担当 |
||
|
粕屋西小学校 |
佐藤和宣 |
教諭,教務主任,社会科担当 |
|
|
中尾裕二 |
教諭,社会科担当 |
||
|
大川小学校 |
御手洗昭夫 |
教諭,教務主任 |
|
|
仲原小学校 |
橋本洋 |
教頭 |
|
|
関光治 |
教諭,情報教育担当 |
||
|
粕屋町中学校 |
粕屋中学校 |
坂井和彦 |
教諭,技術家庭担当 |
|
興津吉英 |
教諭,社会科担当 |
||
|
粕屋東中学校 |
今長谷寛 |
教諭,情報教育コンピュータ担当 |
|
|
住商エレクトロニクス(株) |
大塚誠也 |
||
|
上野裕治 |
情報システム担当 |
||
|
エリアス |
大津俊英 |
GIS技術支援担当 |
|
本プロジェクトを遂行するために,以下のような業務を実施した。
プロジェクト実施委員会の開催
サーバーの構築
小中学校の環境整備
授業実施内容の検討
実証授業の実施
実証授業の検討
成果の取りまとめ
来年度以降への準備
プロジェクトのスケジュール実績を表 2に示す。
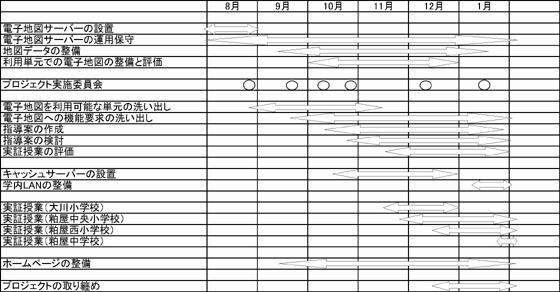
プロジェクトの実施と成果の公開を円滑に行うために,以下のようなサーバー群の整備を行った。
インターネット電子地図サーバーは,本プロジェクトの中核システムとなるもので,九州工業大学情報工学部の硴崎研究室内に設置している。既存の機材と,CECの予算により導入した機材によって,多数の教育機関に安定したサービスをできることを目標としてサーバーを構築した。また,学外との接続は,当面は5Mbps程度の帯域をめどとして,安定したネットワークラインが確保できるように,情報科学センターに協力をいただいている。
www.edumap.netとwww.kasuya-kids.netは,それぞれレンタルサーバーを確保した。
www.edumap.netは,インターネット電子地図の表玄関として利用し,分かり易く短い文字数で指定できるURLを付与した。このサーバーでは,プロジェクトの紹介などの静的なページのサービスに重点をおき,動的なページ生成や大容量のデータを必要とするインターネット電子地図の中核のサービスは,硴崎研究室に設置したサーバーによって行う。
現状では,粕屋町の小中学校はホームページを持たず,また,その整備の具体的なスケジュールが教育委員会で上がっていないという問題があった。また,各学校は,電子メイルアドレスを1つしか持たず,プロジェクトの連絡を教師単位で電子的に行うことが非常に困難であるという問題があった。
www.kasuya-kids.net は,小中学校が本プロジェクトの成果を公開したり,各学校のその他の情報を発信していくために利用できるように確保した。また,このサーバーを利用して,プロジェクトに参加されている小中学校の先生方に電子メイルのアカウントを提供し,連絡業務を円滑に行うための支援を行っている。
プロジェクトに参加する小中学校に対して,以下のような環境整備を行った。
3.4.1 キャッシュサーバーの設置によるインターネット環境の整備
3.4.2 デジカメ,ソフトウェアなどの配布
3.4.3 粕屋中央小学校の職員室ネットワークの整備
粕屋町の小学校は22台,中学校は42台のPCを設置するコンピュータルームを持っており,それぞれ64KbpsのISDN一回線を使用して,インターネット接続が可能な状態にある。しかしながら現在では,数台のPCしかない家庭単位でもISDNを利用していることからわかるように,22台から42台のPCで64KbpsのISDN回線を共有して利用することは,通信能力的に非常に厳しいものがある。現実に粕屋町の小中学校では,インターネットを利用して調べ学習をさせることはこれまで困難であり,授業でインターネットを積極的に利用することができない状態であった。
インターネット電子地図を利用する本プロジェクトでは,インターネットを通じて地図や写真といった比較的大容量のデータをやり取りするため,インターネット接続が高速に行えることが非常に重要となる。たとえば,70Kバイト程度の地図あるいは画像を参照する場合,64KbpsのISDN回線では,画像の転送が完了するまでに10秒程度を要する。このため,22台のPCから独立して参照した場合には,すべてのPCで画像が表示されるまでに3分以上必要になり,限られた時間で行わなければならない授業の円滑な進行の大きな妨げになる。現在では,ADSLなどの低コストで高速なインターネット接続サービスも開始されているが,粕屋町をはじめとする多くの地域では,当面そのサービスを受けることができないという問題がある。
本プロジェクトでは,このような問題を解決するために,小中学校にWWWキャッシュサーバーを設置することで対処した。WWWキャッシュサーバーは,一度参照された画像やHTMLファイルを利用者側に設置された装置に記録しておき,利用者から再度要求があった場合には,インターネット上から改めて取得することはせず,装置に記録されていた画像やHTMLファイルを提供する機能を持っている。これにより,必要となるネットワークの太さを低く抑えることができるという利点があるだけでなく,利用者の要求に高速に応えられるという利点がある。
WWWキャッシュサーバーの設置には,以下のような利点がある。
1台のPCの設置で済むため,コストが安い
インターネット接続の帯域が太くない他の多くの学校でも現実的な解である
インターネットを利用する教育全般に効果がある
本プロジェクトでは,WWWキャッシュサーバーは,低コストのPCにLinuxを組み込み,Squidと呼ばれるWWWキャッシュソフトウェアを導入することにより構成した。
複数のグループに分かれて取材するためには,取材のために多数のデジカメが必要となる。また,取材後には電子地図に記録するために画像を加工するソフトウェアやホームページを作成するためのソフトウェアが必要となる。これらの機材やソフトウェアが不足していたため,不足分を導入し,児童生徒がそれぞれの目的を持ち,取材場所を分担して自主的に取材と取りまとめを行えるように配慮した。また,デジカメは,動画像も取れるものを導入し,インターネット電子地図のデータとして将来的には動画像も記録することができるように配慮した。
児童生徒に適切な指導を行うためには,教師が指導のための十分な準備と訓練を行っておかなければならない。このためには,インターネット電子地図を職員室で利用し,指導案の作成や,指導手順の具体的な確認を行える環境が必要である。しかしながら,粕屋町の小中学校では,職員室にほとんどパソコンはなく,また,インターネットを利用できる環境がないという問題があった。粕屋中央小学校をモデルケースとして,この様な問題を解決し,教育のための準備や訓練が充分に行えるようにするために,職員室や会議室でもインターネット電子地図を利用できるように, LANの敷設を行った。
また,児童がインターネット電子地図を利用した学習成果を多くの児童の前で発表できるように,発表会などで利用する多目的ホールにもLANの敷設を行った。
プロジェクトを円滑に実施していくために,プロジェクトに参加する教師の全員参加を基本として,プロジェクト実施委員会を6回ほど開催した。さらに,プロジェクト実施委員会とは別に,個別の実証授業の準備や,小中学校の環境整備を行うために,硴崎と各小中学校の教師とで,個別の打ち合わせを多数実施した。
開催日:8月30日(水)13:00〜16:00
開催場所:粕谷中央小学校コンピュータ教室
参加者:硴崎賢一,寺本正治,野中慎治,竹本学,佐藤和宣,中尾裕二,御手洗昭夫,橋本洋,関光治,坂井和彦
議題:
プロジェクトの内容と経緯説明
プロジェクト参加メンバの確認
インターネット電子地図の説明とデモンストレーション
質疑応答
硴崎から本プロジェクトの内容と,申請から実施にいたる経緯の説明が行われた。また,インターネット電子地図がどのようなものであるか,具体的に理解してもらうために,既存の(教育用に特化されていない)インターネット電子地図のデモンストレーションが行われた。
次回の委員会までに,インターネット電子地図を利活用可能な単元の洗い出しを行うことを宿題として終了した。
開催日:9月22日(金) 15:30〜17:00
開催場所:粕谷中央小学校コンピュータ教室
参加者:硴崎賢一,野中慎治,竹本学,佐藤和宣,中尾裕二,橋本洋,関光治,坂井和彦,興津吉英,今長谷寛
講師:原田静男氏(CEC)
議題:
Eスクエアプロジェクトにおける本プロジェクトの位置付け(CEC:原田静男氏)
教育用のインターネット電子地図のデモンストレーション
実施可能単元の報告と検討
必要な機材の確認
CECの原田氏から,Eスクエアプロジェクトにおける本プロジェクトの位置付けについてお話いただいた。また,教育用途を想定して試作されたインターネット電子地図の機能のデモンストレーションが行われた。
宿題となっていた,インターネット電子地図の利用可能単元について,報告と意見交換が行われた。インターネット電子地図を活用可能であると考えられる単元をに表 3〜表 6に示す。
表 3 小学3年生のインターネット電子地図利用可能単元
|
単 元 名 |
活 動 内 容 |
|
4月 「学校のまわり」 |
校区の様子を観察する 道の探検を計画する 道の探検をし,地図に整理する お互いの地図を比較しながら見やすくするための工夫をする |
|
5月 「みんなでつくる町」 |
地域の人々が住みよい環境づくりのために協力している活動を調べる 公共施設を見学しまとめる |
|
6月 「町内たんけん」 |
町内の地図(土地利用図)を見て,自分達の町の地形・土地利用・交通の様子などに関心を持つ 自分の町の地図と他の町の地図を比較し違う点にきづかせる。 |
|
11月「わたし達のくらしとものを作る仕事」 |
町の工場分布や農業の特色について調べ,町にある工場や農家を見学し,まとめる。 |
|
12月「農家でつくられるもの」 |
町の中で農業の盛んな地域を地図をもとに概観する。 |
|
1月「かわってきた人々のくらし」 |
昔からのまつりや行事について話し合う |
表 4 小学4年生のインターネット電子地図利用可能単元
|
単 元 名 |
活 動 内 容 |
|
4月「くらしをささえる水」 |
水の利用の仕方や送水ルートに目を向け資源としての水を意識したり,浄水までの過程を進んでしらべたりしようとしている【町の浄水場】 |
|
5月「ゴミとすみよいくらし」 |
ゴミの処理に目を向け,ゴミやその処理のしかたを進んで調べようとしている【町のゴミ焼却場】 |
|
6月「火事からくらしを守る」 |
学校や地域の消防施設に関心を持ち,その種類や仕組み,役割などを進んで調べようとしている【消防署・消防団・消火栓】 |
|
7月「交通事故から命をまもる」 |
交通事故の発生場所や件数など地図や表にまとめる |
|
9月 わたし達の県福岡県「 自然と人々のくらし」 |
人工衛生からの写真や立体模型地図をもとに,県全体の地形や様子について話し合い学習問題をつくる 福岡県の地形,土地利用、農産物、人口分布を白地図に書きこみ,特徴を話し合う |
|
3月「国土の自然とくらし」 |
が国の位置や地球の様子に関心を持ち,地図などを進んで活用し,意欲的に学習に取り組むことができる。 |
表 5 小学5年生のインターネット電子地図利用可能単元
|
単 元 名 |
活 動 内 容 |
|
4月「米づくりのさかんな○○」 |
米づくりについて話し合い,米屋調べの視点づくりをする 町の米づくりの様子を調べ,農家の人の悩みや願いについて考える |
|
5月「野菜づくり」 |
農家や農協の施設を見学し,野菜作りの工夫について調べる |
|
7月「伝統的な技術を生かした工業」 |
わが国の伝統工業や地域にある伝統工業の盛んな地域について調べる |
|
10月「これからの工業と環境」 |
地域を流れる川を調査し,汚れの原因や問題点について調べる |
|
11月「わたしたちの生活と運輸」 |
ものを送る方法について調べ,町内の流通センター等について話し合う |
|
2月 「緑の地球を守る」 |
地域の森林について調べ,森林についての役割や問題点について話し合う |
表 6 小学6年生のインターネット電子地図利用可能単元
|
単 元 名 |
活 動 内 容 |
|
4月「わたし達の町の歴史探検」 |
身近な地域に残っている行事や遺跡・文化財を調べ,地図や年表にまとめる |
|
11月「みんなの願いを実現する政治」 |
身の回りにあり,さかんに利用されている公共施設やその設立の経緯,災害復旧の様子を調べる |
|
3月 発展 |
インターネットを使って他の地域や学校と地球環境や平和について話し合う |
次回の委員会までに,インターネット電子地図に望まれる機能の洗い出しを行うことを宿題として終了した。
開催日:10月7日(土) 11:00〜12:30
開催場所:粕谷中央小学校コンピュータ教室
参加者:硴崎賢一,寺本正治,竹本学,佐藤和宣,中尾裕二,橋本洋,関光治,坂井和彦,興津吉英
議題:
修正された電子地図について
電子地図を活用できる単元について
機能性の要求
今後の取り組みについて
インターネット電子地図を利用できる単元について引き続き議論が行われた。
インターネット電子地図への機能要求として,以下のようなものが出された。
《書き込み関係》
写真や文章などの埋め込み機能
建物など自由に書き込める機能
地図上に線を引く機能(新しい道,通学路)
書き込みに使える地図記号(スタンプ)
書き込みと表示のウィンドウのレイアウトを自由にできるようにならないか。
《表示関係》
シームレスなスクロール機能。無段階の拡大縮小機能。
分類ごとに表示できる機能。
入力者の名前だけを地図上に表示できるようにしては。
学校,班,クラスごとの表示
《画面構成》
縮尺が大きい地図を「メイン画面」とすべきでは。
縮尺の小さい地図で道路が太すぎでは。
開催日:10月27日(金)16:00〜18:00
開催場所:粕谷中央小学校コンピュータ教室
参加者:硴崎賢一,寺本正治,野中慎治,竹本学,中尾裕二,御手洗昭夫,橋本洋,関光治,坂井和彦,興津吉英
議題:
インターネット電子地図を利用できる単元と,インターネット電子地図に要求される機能について引き続き議論が行われた。
以下に示す実証授業の実施計画が出された。
小学校
大川小学校 第6学年 総合 単元「森と地球環境」
粕屋中央小学校 第3学年 社会科 単元「わたしたちのくらしと物をつくるしごと」
粕屋西小学校 第5学年 社会科 単元「これからの工業と環境」
中学校
粕屋中学校 第1学年 社会科 「身近な地域」
開催日:12月11日(月) 16:00〜17:00
開催場所:粕谷中央小学校コンピュータ教室
参加者:寺本正治,野中慎治,佐藤和宣,中尾裕二,御手洗昭夫,関光治,坂井和彦,興津吉英
議題:
実証授業の報告
今後の予定
実施された実証授業の様子や成果について報告された。また,これから実施する実証授業について報告が行われた。
開催日:1月15日(月)15:00〜17:00
開催場所:粕谷町町役場会議室
参加者:硴崎賢一,寺本正治,野中慎治,佐藤和宣,中尾裕二,御手洗昭夫,関光治,坂井和彦,興津吉英,今長谷寛
粕屋町教育委員会,粕屋町小中校長会
議題:
プロジェクトの経過報告
実践事例の報告
粕屋町の来年度の取り組みについて
粕屋町の校長会および教育委員会に対して,硴崎と寺本より,本プロジェクトの経過報告が行われた。また,各実証授業の実施校から,インターネット電子地図を利用した実証授業に関する成果報告が行われた。
インターネット電子地図が教育に効果的に活用可能であるとの結論が出され,来年度以降は,さらに積極的にインターネット電子地図を利用していくことが確認された。