|
(1)集計グラフ
|
| 質問 インターネット利用により,児童・生徒の学習テーマへの興味・関心が向上しましたか?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小学校(14校)
|
中学校(4校)
|
高校(4校)
|
盲学校(1校)
|
|
(2)教師の感想・意見 |
| 質問 なぜそう思われたか感想・ご意見などを記入してください。特に子どもたちの授業での様子について具体的にお願いします。
|
|
|
a.小学校教師の意見(全員の意見を記す)
- 本企画では,協力校とともに,調べ学習した成果をまとめ,リンクさせ合って百科事典をつくっている。ホームページを公開した後では,子どもたちは,父母に自分のページを自慢げに見せていた。他校のリンクを見た後では,自分の学校にない良い点を,みとめていた。ページをもとに交流をはじめると,コンピュータのむこう側にいる人間に対して,興味を持ったようである。自分達が出したメールの返信を,まだかまだかと待つようになった。
- 新奇性もあるのかもしれませんが,情報が「ザクザク」と出て来ることに素直に感激してました。放課後,休み時間にも学習に取り組むなど向上した姿が見られました。逆に言えばインターネットなくして放課後などの自主的な取り組みはなかったと考えます。
- 図書資料や学習シート等のメディアを用いた学習では積極性が今ひとつだった子供が,積極的かつ真剣に学習に取り組んでいた。・コンピュータネットワークの有効性や価値を実感した子供が多かった。・「もっとインターネットを活用する授業を多くやってほしい!」ということを話す子供が増えてきた。
- 毎朝のメールチェックは当番の仕事を時々忘れる児童ですらおこたらなかった。「交流校のお友達はどう思うかな」といいつつ自ら進んでメールをうち,送信している姿。
調べ学習でいっしょうけんめいHPをさがしている姿。 などから。
- 子ども達は,それぞれに自分の思いや願いを達成するために活動に励んでいった。そのため研究内容を他に発信したり,情報を収集したいと強く要望するようになった。そこで,日常的にインターネットを使える環境を整えることによって,子ども達の要望にこたえた。
- (1)顔も知らない人が,自分の作った俳句を読んで感想を送ってくれたことを,とても喜んでいた。また次も,作って読んでもらいたいという意欲がみられた。(2)メディアキッズ(掲示板)にアクセスできるよう整備されているコンピュータが2台だったため,やりたいと思った時できないことがあり意欲をそぐこともあった。(2)より(1)の児童が多くみられたので「少し向上した」に「V」をした。
- 子供たちが「次の時間はいつありますか」など楽しみにしている様子がみられた。
- 何か行事があったあとに,「メールを書こう」という声が子どもから出された。交流会に取り組む前にあらかじめ,メールがあることで,交流会を心待ちにする気持ちが強いようである
- ライントレーサの製作という子ども自身が興味を持っている教材であり,授業で使用したプレゼンテーションデータが授業終了後にWebページになっており前回の復習が容易にできた。また授業中のわからなかったことの回答も同Webページに掲載したため質問の共有ができた。
- 「町の現状を知りたい」という意識が,休日の仲間をつのっての調査や,日々の中での会話にでている。また,教科学習の中で,環境についての部分になると,「川の汚れがひどいのでなんとかしたい」という発言がある。学習の中で,わからないことがあると,教科書中心に調べるが,その後インターネットを見ることがふえた。
- 子ども達の学習フィールドが広がった。その事により学校の外からいろいろな資料や意見を集める事ができ自分が活躍しているという満足感が得られる。
- 子どもが直接感想を言ってくれる。休憩時間でも学習の続きをしたりしている。
- 自分の目的とするものが見つかると,喜んで担任に報告にくる。まわりの子どもも「わぁ」といった感じで集まってくる。そして,画面を見ながら,「これについても調べてみたいな」などと発展してくることがある。
- 相手側にわかりやすく伝えるために,どんな工夫をすればよいか文や画像などの中で,自分なりの工夫をする姿が見られた。ホームページ作成等でもどのような文をかくことで相手にわかりやすく自分の考えを伝えられるかを常に意識して取り組んでいた。
b.中学校教師の意見(全員の意見を記す)
- これまでにない新しい活動に加え,発見や驚きがあり,意欲的に活動しながら課題を解決しようとする姿が多々見られた。情報をいち早く収集することができ,その量も豊富であることから生徒の関心が向上したと考えられる。
- 以前には興味を示さなかった内容まで,手軽に最新の情報が視覚に飛び込んでくるおかげで,自主的に調べようとする態度が見られたから。
- 自己の調査結果に対する,異なる調査結果にふれたことにより,自己の中で次の課題を見出し,解決しようとする姿勢が多く感じられた。
- 授業を終えて生徒のボランティア,視覚障害者に対する意識が高まったことはまちがいありません。しかしそれが点訳データをネット上にのせた(インターネット利用)が原因かどうかというところについては確信がありません。
c.高等学校教師の意見(全員の意見を記す)
- 調べるテーマをしっかりと自分の物にしている生徒は,インターネットを利用すると,さらに幅が広くなり内容も深まった。一方テーマ設定がなかなかすす(?)まない者にとっては,インターネットを介しても「調べたい」というモチベーションが低かった。
- インターネット利用は,学習行動に対して,レスポンスが速く,次の行動のきっかけを多く生みだすことができ,興味,関心を持続させる効果があると考えられる。また,教材内容を事前にチェックするなどしておくと安全も確保できるし,鮮度の良い教材も利用することができる。
- 教室で黒板に向かって授業を受けるスタイルに限界が見られる。集中力にかける生徒が多い。パソコンに向かって自ら主体的に取り組まなけれがならない環境づくりが重要でないか。受身の姿勢では何もできないし,教科書に書かれていないことを学ぶので集中して聞かなければついていけなくなるし,どんなことをするのだろうかという興味関心もある どの生徒も熱心に学習に取りくんでいた→操作面で問題を感じなくなるよう指導しておくことが必要である。普段ボッと聞いていたり退屈そうにしている生徒が黙々と取りくみ,熱心に聞いている生徒が悪戦苦闘し,投げやりになっていた姿が印象的であった。
d.盲学校教師の意見
- 視覚障害のディスアビリティゆえに情報の入手や交換が困難であったのでIT化により,これらのバリアーが低くなり,その量が前に比べて多くなった。少人数化により,同じ発達段階の生徒が減少し意見交換などが,少なくなっていたが,ITにより広い地域の同じ障害を持つ同じ年齢層の同じ発達段階の生徒との意見交流が可能となったので,授業への反応がより活発になってきた。
|
(3)教師への「興味・関心の向上」要素の集計結果 |
| 教師への質問 「向上した」,「少し向上した」と思われた要素を以下に挙げました。該当する項目にチェックをお願いします。(複数チェックも可)
|
|
|
| 回答 項目別にチェック率を%表示する。 |
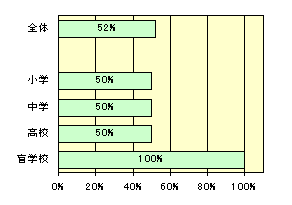 (1)意見交換や質問が多かった。 (1)意見交換や質問が多かった。 |
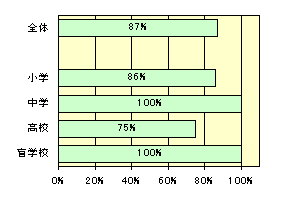 (2)学習活動を楽しんでいた。 (2)学習活動を楽しんでいた。 |
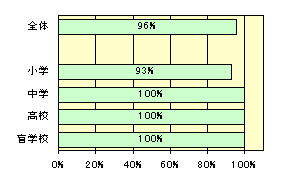 (3)積極的に学習する態度が見られた。 (3)積極的に学習する態度が見られた。 |
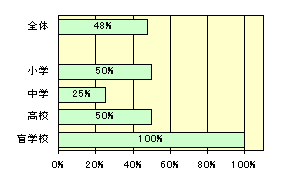 (4)教室に活気があった。 (4)教室に活気があった。 |
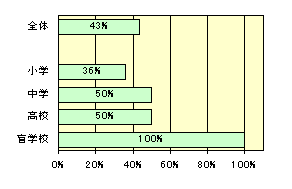 (5)課題をより深く追求する場面が見られた。 (5)課題をより深く追求する場面が見られた。 |
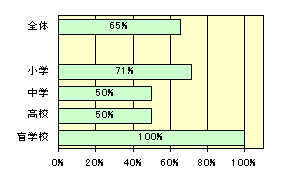 (6)驚きや発見を教師に伝える生徒がみられた。 (6)驚きや発見を教師に伝える生徒がみられた。 |
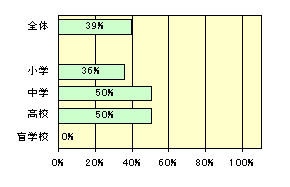 (7)学習活動の中で感動する場面が見られた。 (7)学習活動の中で感動する場面が見られた。 |
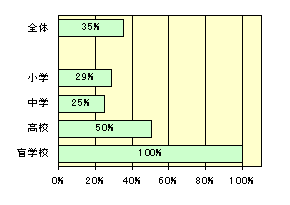 (8)新しい課題へ積極的にチャレンジする様子が見えた。 (8)新しい課題へ積極的にチャレンジする様子が見えた。 |
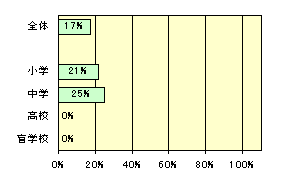 (9)相手への思いやりやより深く相手を理解しようとする様子が見えた。 (9)相手への思いやりやより深く相手を理解しようとする様子が見えた。 |
(4)教師への「興味・関心の向上」で否定要素の感想・意見 |
| 教師への質問 「少し低下した」,「低下した」とした場合,その要因を記入してください。
|
|
|
a.小学校,中学校,高等学校教師の記入
記載無し
b.盲学校 教師の記入
教員との会話の量(IT利用時に聞くことが慣れるに従って少なくなった。) |
  |




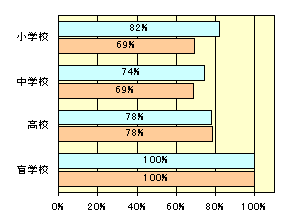 (2)インターネットを使った授業をもっとしたい。
(2)インターネットを使った授業をもっとしたい。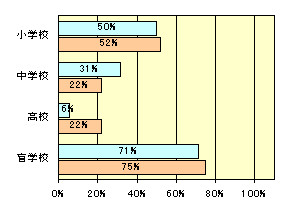 (3)インターネットを使うと,クラス(学校)外の人たちと交流ができて楽しい。
(3)インターネットを使うと,クラス(学校)外の人たちと交流ができて楽しい。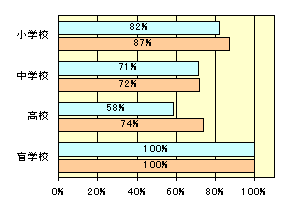 (4)インターネットを使うと,いろいろなことを広く,深く,調べられるので便利。
(4)インターネットを使うと,いろいろなことを広く,深く,調べられるので便利。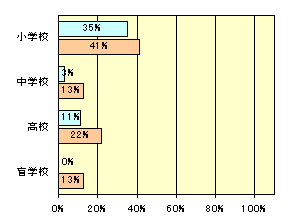 (5)インターネットを使うと,自分の作品や考えを人に伝えやすい。
(5)インターネットを使うと,自分の作品や考えを人に伝えやすい。