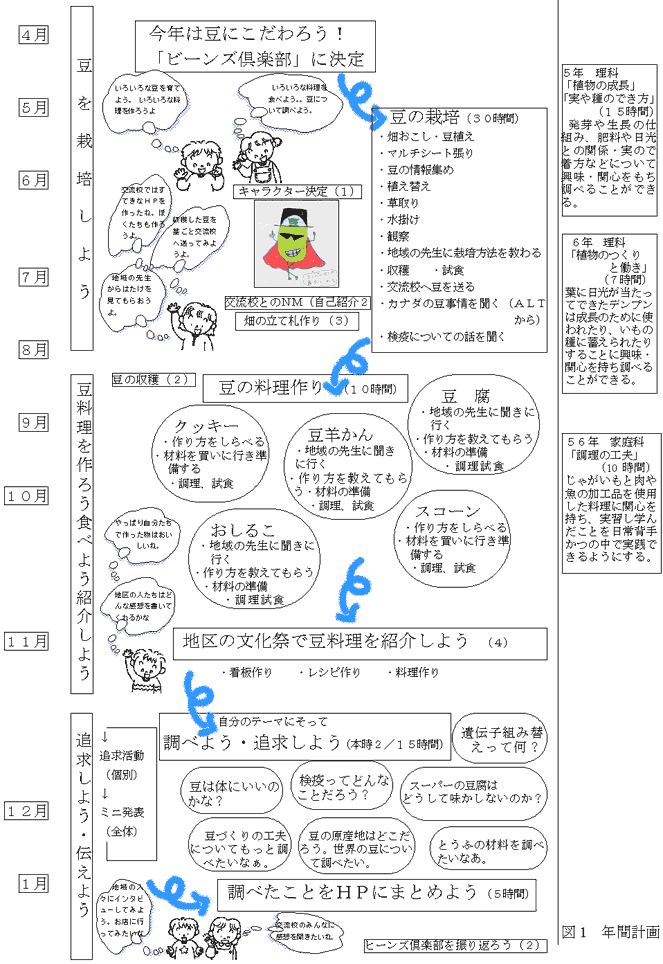|
「そばウガリプロジェクト」から「コ−ンプロジェクト」,「POTATO ROAD2000」,「Beans School」と実践を重ねてきたことによって以下の様な成果と課題が明らかになった。
 |
|
写真4 NetMeeting
|
4.1 成果
(1) 児童の課題を解決するための場を学校だけでなく地域,交流校と広げながら活動することによってさらなる課題への深まり,人的ネットワ−クの広がりがみられ充実した学習へ発展することができた。
(2) 交流学習においては,初期の段階では学校対学校の交流でしかなかったが,次第に学級対学級,個人対個人のように相手の顔が見える交流に発展してきた。また,自校や交流校という単位で課題を解決するのではなく,学校の枠を取り払ったグル−プによっての課題を解決する場面が見られるようになり,遠隔地を意識させない協働学習が成立した。
(3) 交流の手段はインタ−ネットに主軸をおいてきたが,それのみにたよらず,場に応じた交流手段を選択する児童が見られた。複数の手段で相手と関わることができるようになった。
(4) 毎日のメ−ルチェックなどにみられるようにコンピュ−タの操作だけでなく,自主的に情報機器や情報に接しようとする態度が児童に定着してきた。
(5) 交流学習を進めるにあたり,自校の教師だけでなく他校の教師との授業のための話し合いや情報交換を必要な時,必要なだけ行うことができた。本来なら出会うことがない交流学校の教師と協働でプロジェクトを進めた体験は今後のIT技術の進歩の中でも貴重な経験となった。
4.2 課題
(1) 多量の児童のポ−トフォリオから活動の評価などを行う手法を深めていく必要がある。
(2) 回線の容量などインフラの整備について学校間に格差がでてきた。
 |
|
写真5 地域の方に豆栽培を教わる
|
ワンポイントアドバイス
・地域の現状に応じた素材や人材を探す。<写真5>
・交流学習は互いに信頼できる学校をつくることから始める。
・NetMeeting<写真4参照>などのオンラインで使用するソフトは事前テストを十分に行い,仮に本時でうまくいかない時を考えてバックアップ体制を用意しておく。
・最良の方法が準備できなくても最善の手を尽くす。
|