|
協力校と行う「Hokkaido Web High School」プロジェクトの中で,本校ではインターネットを活用した授業として,「北海道Web文化祭プロジェクト」と「テーマ別課題研究」の2つの授業を行った。これらの活動を協力校と円滑に行うために,教員用,生徒用のメーリングリストを別々に構築し,情報交換を行った。この際,生徒には電子メールのマナーについて徹底させ交流を行わせた。
生徒用クライアントコンピュータのインターネット接続は,プロキシサーバを経由させ,本校が発行しているメールアドレスのみしか,送受信できないような設定にしており,本校から発信していることが特定しにくい,生徒個人が所有する電子メールやフリーメールなどを使った電子メールの送受信は出来ないような設定としている。
3.1 「北海道Web文化祭プロジェクト」(6時間)
「北海道Web文化祭プロジェクト」はインターネットを使った授業実践の共同プロジェクトの1つとして企画されたもので,これは,北海道各地のプロジェクト参加校(協力校)で行われた文化祭(学校祭)の様子を,生徒が中心となり共同でWebページを制作・公開していくものである。
(1) プロジェクトの特徴
インターネットを使った授業実践を共同で行う場合,現在の各学校で生徒にインターネットを利用させる環境が異なっている現状では,長期間のプロジェクトを企画しても,学校事情によっては参加できない学校も出てくる可能性がある。したがってこのプロジェクトは短期間のプロジェクトとし,より多くの学校が参加できるような環境を作っている。またプロジェクトのテーマは,各学校の特色を出しやすいテーマの設定をし,高校生活において身近な話題である,文化祭(学校祭)を取り上げている。
(2) 本校の取り組み
学校祭紹介のウェブページのコンテンツを決定し,それを分担して制作したページには,製作者名を生徒の合意のもとに公開している(個人を特定できる画像は用いていない)。Webページ制作は1年次において学習しておりスムーズに制作ができた。また,静止画データだけではなく学校祭の様子をビデオカメラで撮影し,動画などのマルチメディアデータも積極的に取り込んだ。
生徒は他校の生徒が製作したWebページと自らが作成したページを見比べ,他校の生徒の作品の高い完成度と,行事内容の新鮮さに刺激を受けていた。また他校の生徒が製作したWebページを見ることにより,自分たちが発信するWebページのコンテンツがインターネット上で他校の生徒に見られているということを意識させ,コンテンツをより充実させ,著作権問題などにも配慮したウェブページを製作するように指導した。
なお,授業でのWebページ製作にあたっては,校内のイントラネット上のWWWサーバ,DNSサーバを利用し,インターネット環境を利用しなくても,ファイル転送や,各生徒が製作したページのリンクを確かめるなど,校内でインターネットでの表示シュミレーションをしながら作業を行った。
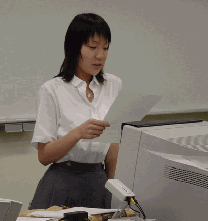 |
|
図2 プレゼンテーション
|
3.2 「テーマ別課題研究」
(1) 授業の特徴
生徒自ら研究課題を設定,積極的にインターネットを使用し,ウェブページでの情報収集や,メーリングリストなどを活用した,他校の生徒と交流を積極的に行うことによって研究を行い,プレゼンテーションソフトやウェブページでプレゼンテーションを作成していく授業である。今年度は北海道内の協力校とメーリングリストを構築し共同授業を行った。
(2) 本校の取り組み
生徒がいくつかの班を作り,それぞれ設定したテーマについての研究を行った。主なテーマは以下のようなものがあった。
1) 高校生の携帯電話についての調査
2) 電話と電子メールの違い
3) インターネットを利用したディペートのメリット・デメリット
その中で,ウェブページから情報を得たり,メーリングリストを活用し他校からの高校生の意見や情報を得たり,アンケートを行うことにより,より研究内容を深めることができた。最後にそれらの取り組みをまとめプレゼンテーションを行った(図2)。
「高校生の携帯電話についての調査」では,担当生徒が携帯電話についてのアンケートを作成し,これらを聞き取り調査により集計を行った。さらにメーリングリストを通じて,他校の生徒にも呼びかけ,他校の調査結果も参考にしながら考察を行った。
|



