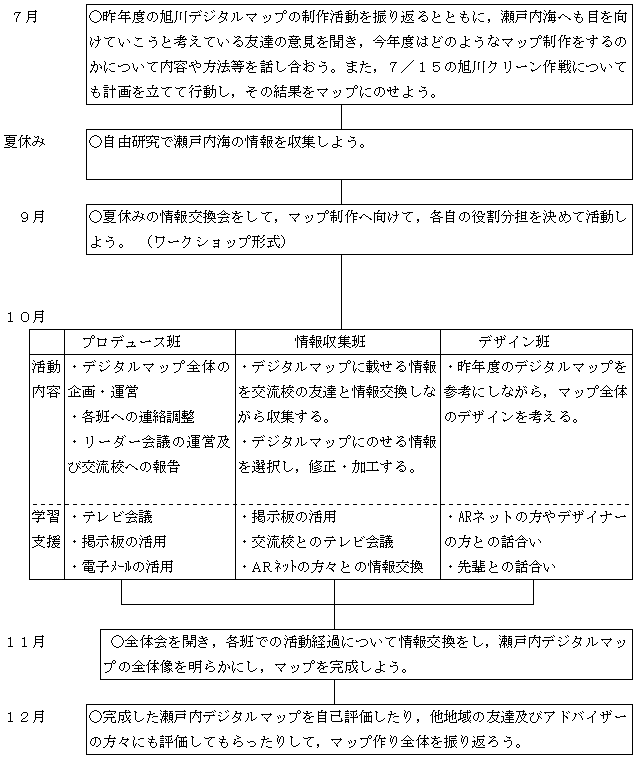|
(1) ねらい
5,6年の合同学習における環境学習では,1学期は体験活動を重視し,身近な自然「旭川」を調査・研究の舞台として個々の興味・関心・問題意識のもとに追究活動を展開し,水にかかわる様々な問題点を浮き彫りにしていった。その学習を通して,「水を大切にする思いをもっと多くの人たちに伝えるために自分にできることを考え,行動していかなければならないのでは・・」という思いが子どもたちの心のなかにわき上がってきたのである。特に,今年度の子どもたちは,旭川から瀬戸内海へと視野を広げ,瀬戸内海の実態に興味・関心をもつとともに,旭川や瀬戸内海の実態を地域や瀬戸内海に面した人々に知ってもらい,ともに身近な環境について考え,少しでも改善できるように行動していくことを提案したいと考えていた。
そこで,同じ瀬戸内海に面した学校である富来小学校の子どもたちとの交流を支援し,子どもたちの思いや願いの多くの人たちに伝える手段として,デジタルマップを製作し,発信していくという単元を構想し,実践に取り組んだ。
|
|
|
(図1 旭川の球体パノラマ画像)
|
|
|
|
(図2 FCISの電子掲示板)
|
|
|
|
(図3 校内のコンピュータ環境)
|
(2) 指導目標
● 瀬戸内海の自然・歴史・文化等の様々な視点から見つめ直したり,川と海のつながりに目を向けたりして,未来の瀬戸内海のあるべき姿について,自分なりの考えをもち,自分たちが身近な環境にどのようにかかわっていけばいいかについて仲間とともに考え,思いや願いをもって行動することができる。
● 瀬戸内デジタルマップの共同制作活動において,電子掲示板(ネットワーク広 場),インターネットメール及びテレビ会議等を利用して,他校の友達と情報交換しながら情報を集めたり,整理したり,自分にとって必要な情報を選んだり,マップを作って発信したりする力を身につけることができる。
(3) 利用場面
課題設定場面において,まず身近な環境の球体パノラマ画像(図1)をみて,個々の気づきをその画像のなかに埋め込んでいく。そして,交流校と画像を交換し,相手校の画像や気づきをみることによって,双方の環境を比較し,様々な疑問点を見つけだし,テーマを設定した。その後,インターネットによる交流学習を開始し,共通の課題ごとに会議室を立ち上げ,追究活動に取り組んだ。
(4) 利用環境
他校との交流については,FCIS(学校間交流支援ソフト)の電子掲示板を活用した。瀬戸内海に面した学校の子どもたちが参加しているネットワークである「瀬戸内キッズ」に参加し,そのなかの富来小学校の子どもたちとの交流を軸に学習を展開した。
そして,各会議室のメンバーの顔を会議室内に貼り付け,子どもたち同士が互いを身近に意識しあえる工夫を試みた。
(5) 稼働環境
64KBのISDN回線で接続
●情報通信インフラ
〈校内サーバ〉
WindousNT server 4.0
〈クライアント〉
Windous95
デスクトップ型(22台)
ノートブック型(3台)
※LANシステムを構築
Peer to Peer 型
〈プリンタ〉
〈デジタルカメラ〉
23台(35万画素)
6台(230万画素)
|