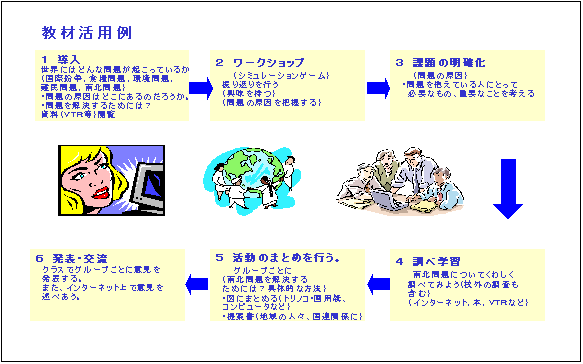|
(1) 成果
生徒がゲームに取り組んでいるとき,興味ある場面を見かけた。自己中心的傾向の強い生徒Aが,自分が思ったことを成し遂げようとしても,立場が違う者からは相手にされないことによって感情的になる。
A「これだけ条件を良くしても,○○が買いたいのに,ほかの人がいっこうに売ってくれないな〜。」
B「ほかに条件がいいところに売ろうと思う。」
C「これを売ってしまったら,僕のほうは生産できなくなるよ。」
生徒Aはさまざまな会話を通して,一時の感情に走るのではなく,それぞれの立場を客観的に理解できるようになった。このあと他のものと楽しく続けていたようだが,ゲームという限られた仮想的な場面ではあっても,お互いの立場を考えることによって,プラス思考で日ごろの生活を見直すきっかけになったようである。現段階では,ほんの小さなことしか教育効果としては現れてないが,いろいろな活用を通してこれから可能性を見い出していけると確信する。以下に成果をまとめて載せる。
○ソフト開発から得られたこと
・人権教育のための効果的な教材の開発,教育用ゲームの可能性
(興味関心がわく,ロールプレイングの要素をとりいれたもの)
・担当者の経験の蓄積,総合的な学習等への応用等,教育活動への波及効果
・さまざまな必要性や重要性の認識
・さらなるソフト開発の継続,発展の可能性
○教材活用から得られたこと
・子どもの人権意識の向上
・指導計画,指導案,指導方法の蓄積(人権教育,総合的な学習,社会科など)
・新しいスタイルの人権教育の可能性
・人権教育のみならず,総合的な学習等,広範囲に利用できる可能性
(2) 課題
・効果的な活用法の蓄積,広い範囲での教材の配布
・さまざまな評価による,さらなる改良,新しい要素を入れた発展
(インターネット上での利用,発達段階に応じた教材への改良など)
・評価法の工夫(具体的な内容にし,開発につなげる必要性がある)
・企画担当者としての留意点
(調査協力者への調査の具体的な説明,開発者のための具体的な青写真つくり)
ワンポイントアドバイス(プロジェクトをよりよく推進するために)
○活動目的をしっかりと持ち,それにもとづいてしっかりとした企画を立てること
○教材開発にのみ精力をかたむけるのではなく,いかに効果をあげ広めるかを考える
○企画担当者がコーディネーターとして仕事をとらえること(専門性を持った人とそうでない人のギャップをいかにうめるか,いかに広範囲の人に対して啓発していくか)
○教員自身が自ら考えていくこと,活動における柔軟な組織をつくること
|