

 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
植物の栽培・育成・観測企画,特に全国発芽マップのような参加校が広く全国にわたる企画の場合,全国共通の植物を栽培することを通して観測データの共有を図ることができ,栽培活動や観察活動が活性化されるものと考える。 ************************************************************************************** ************************************************************************************** さて,本年度育てる植物についてですが,みなさんのご意見を伺いたいと思います。昨年度はケナフでした。また,種まきの期日についてもご意見ありましたらお知らせください。(ちなみに昨年は第1回目が5月20日で,第2回目が6月17日でした。) ************************************************************************************** いよいよですね。なんとなくわくわくしてきます。 1 育てる植物( ケナフ ) 昨年は,はじめての参加で教えていただくだけでした。 このメールからこれまでの参加校の方々の中には5年間続いた共同栽培植物である「ケナフ」の教育現場での有効性を認識しながらも,新しい植物の栽培の挑戦をしていこうとする参加者の主体的な意識の現れでもあると考える。また,インターネットを活用した協働学習の推進力としてより相応しい植物という点で今後,全国発芽マップのシステムの在り方にも関係する重要な部分である。 全国発芽マップの目的として,「同日,同時刻に一斉に全国各地で種子をまき,その成育の様子や子どもたちの活動を電子メールやホームページ等で情報交換し交流を図る。」がある。それは,1つには同日,同時刻に一斉に播種するということで,参加意識や活動の共有感が高まること,2つは植物の栽培・育成・観測企画ということで,気候,地域による成育の状況の違いを明確にするためである。 2001年度は2000年度と同じくケナフを共同で栽培することが決定したため,2000年5月2日(火)に,ケナフの種子の有無についても参加校に以下のような電子メールをメーリングリストを通して流した。 発芽マップメーリングリストのみなさん。 ************ 全体の部 ************ この種子の送付に関しては,幹事校から送付するだけではない。これまでの実践校から送付される場合もあれば,地域のボランティア団体に問い合わせて種子を入手する場合も考えられる。つまり,種子の入手に関してもネットワーク上のつながりで交流が生まれるのである。 |
||||||||||
|
全国発芽マップの昨年度までの課題として「児童・生徒の直接対話を通した協働学習」「全国190校を超える参加校の増加による活動の沈滞化」「共通して栽培する植物の多様な希望」が挙げられる。そこで,これらの課題を解決するために,全国発芽マップ2001の始動にあたって,メーリングリストを通して次のようなスモールプロジェクトに関する方針を伝えた。 先にも述べたが,全国発芽マップでは,幹事校のみが活動を推進していくプロジェクトではない。参加者が自ら企画立案して全体に提案して全体を動かしていく文化を守り続けている。2001年度のスモールプロジェクトについても同じことが言え,主体的に全国発芽マップの活動を支えていく人材が多く存在している。それは参加校の教師もいれば,学校の保護者でもある。 全国発芽マップにおける支援者,協力者はあくまでもボランティアである。この活動の主旨に賛同し,自主的に活動をしてくださる方々を中心に協力をお願いしている。ただ,インターネットなどバーチャルなつながりだけでなく,全国発芽マップの集い等でface to faceの発表会において話し合いをしたり,協議をしたりして参加校同士,及び全国発芽マップ事務局と支援者,協力者との関係構築と維持を行ってきた。この関係構築と維持については,常時,掲示板やMLにおいて人間関係の醸成を行ってきている。 |
||||||||||
|
2001年度からWeb掲示板と平行して植物の観察・成長記録システムの活用を始めた。この成長記録システムは,幹事校への登録申請をすればブラウザ上で観察した結果等を記録できるものである。2001年度は以下の21校が登録をし活用を進めてきた。
|
||||||||||
|
本企画を実施する上では,ケナフが一年草ということもあり一年間の大まかなスケジュールをつかんでおく必要がある。ケナフを栽培したときの一年間の節目は,全国一斉播種,発芽,成長の観察,開花,災害,収穫及び紙すき等の流れである。この一連の流れの中でメーリングリスト,ホームページ,掲示板等で全国の子どもたちの活動や教師の活動が広がってきたのである。また,それぞれの地域の立場や状況でケナフや全国発芽マップに対する思いが見えてくる。このことは全国発芽マップのメーリングリストの数からも明確になっている。 全国発芽マップの教育実践の準備はほとんどないと言ってよい。というのもこのプロジェクトは,植物の種子さえあれば実施・参加できるからである。つまり,教育実践をはじめるにあたっては,まずインターネットの環境を整備してあることと,植物の種子と栽培を行う場所を確保すれば実施できるという訳である。このことは初めてインターネットを活用した教育実践を行う学校等にも参加しやすく,汎用性のあるプロジェクトであると考える。 |
||||||||||
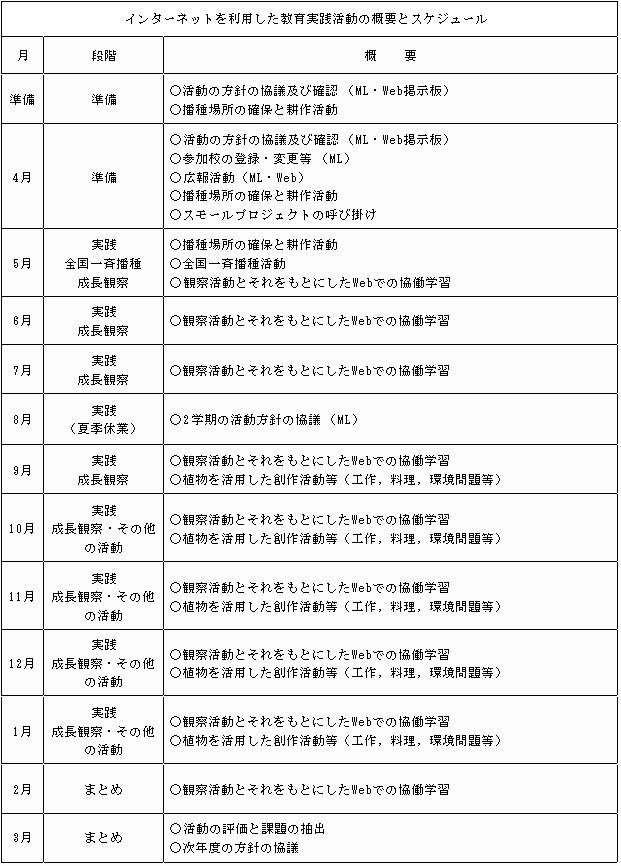 |
||||||||||
|
2001年5月19日(土)午前10時,北は北海道から南は鹿児島の全国約200校の学校の子どもたちと一緒に「5・4・3・2・1!」の掛け声のもと全国一斉にケナフの種子を播いた。すべてはこの種まきから始まりまる。この時にはインターネットの存在は薄く,そこに大きく存在するのは,全国の仲間とその瞬間を共にしているという共有感とこれからの植物の成長に対する期待である。 北海道から教師の報告: このような子どもたちの思いや活動の様子をインターネットのWeb掲示板を通して報告していく。全国の参加校の友達や教師と,同じ日に同じ時刻に共通の種子を播くことで相手意識が生まれてくる。インターネットの威力が発揮されるとともに,相互の交流が始まっていくのである。 2001年度は,早いところで2日後に発芽し,全国発芽マップのメーリングリストにおいてもぞくぞくと発芽の一報が寄せられた。 ************************************************************************************** ほとんどの参加校が5月21日から5月23日にかけて発芽報告がなされた。それに伴って,各地で発芽の状況を各学校のホームページにアップする活動やWeb掲示板で報告をやりとりする様子も盛んになってきた。 静岡県の参加校の子どもの掲示板での報告************************************************************************************** ケナフは数カ月で3メートルから4メートルにまで,急速に成長する植物である。そのため子どもたちにもその成長ぶりに驚きや感動がある。このことは継続観察していく上でもポイントとなることである。また,成長する過程において葉の形が変わったり,7月から10月にかけては台風も数多く接近することでも数多くの交流や活動が生まれる。 ************************************************************************************** それに対して参加校の教師から以下のような返事があった。 ************************************************************************************** このような児童・生徒,教師の直接対話を促すためにも観察活動を促す必要がある。そこで,MLを通して以下のように観察活動推進のための全国一斉観察日を設定した。 ************************************************************************************** この後,参加校からぞくぞくと全国各地の成長の報告がなされた。 ケナフは大抵の場合,9月から10月にかけて開花する。クリーム色をしたハイビスカスに似た花である。 ************************************************************************************** また,このメールに呼応して, http://www.fes.miyazaki-u.ac.jp/HomePage/kyoudoupuro/hatuga12/isei/kaika/kaika.html 昨年はこの時期にすでに1メートル50センチ程度になっていたのですが,今年は若干育ちが悪いようです。なぜでしょうか?(鵜飼さんも以前そのようにおっしゃっていましたね。) その開花の報告に連動する形で,宮崎大学教育文化学部附属小学校の保護者の方が,全国開花マップを作成してくださった。 10月頃からは,収穫の段階に入る。収穫といっても紙すきをするために茎を用いたり,工作をするために茎や葉を用いたり,ケナフを使っての料理をするための収穫である。ケナフは素材的にも捨てる部分がなく,ほとんど全てを使うことができる。茎は紙の原料や工作の素材,葉は料理の材料,手作り葉書の飾り,花はジュースの材料,押し花など使い方次第で様々な活動を行うことができる。 |
||||||||||
|
○ 参加校に対する種子の提供及び送付 ○ 全国発芽マップのメーリングリストの使い方の共通理解 昨年度までの取組からいくつかの「とりきめ」がありましたので,お知らせします。
このようにある程度のメーリングリストの使い方を共通理解しておくことで,参加校のそれぞれの環境にも対応できるとともに,事務処理の手間を省くことができた。 ○ 観察結果の共有化(Web化) ○ 観察活動の推進 2.2.5.2 参加校の活動(スモールプロジェクトを中心に) 2001年度は,2000年度までの課題を解決するために,スモールプロジェクトを募り,以下のプロジェクトが参加校から立ち上がってきた。 「ケナフクラフトバザール」(ケナフを用いた工作等) それぞれのスモールプロジェクトの活動の様子については,全国発芽マップの集い2001の論文集に掲載されているため,ここでは割愛する。 1 理科においての実践 |
||||||||||
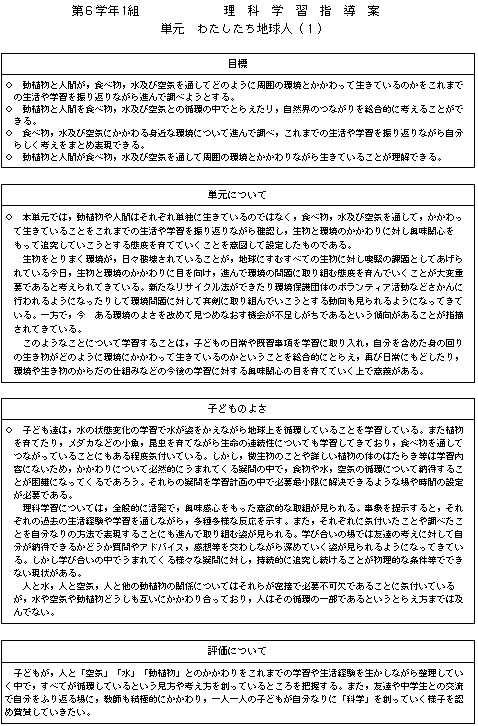 |
||||||||||
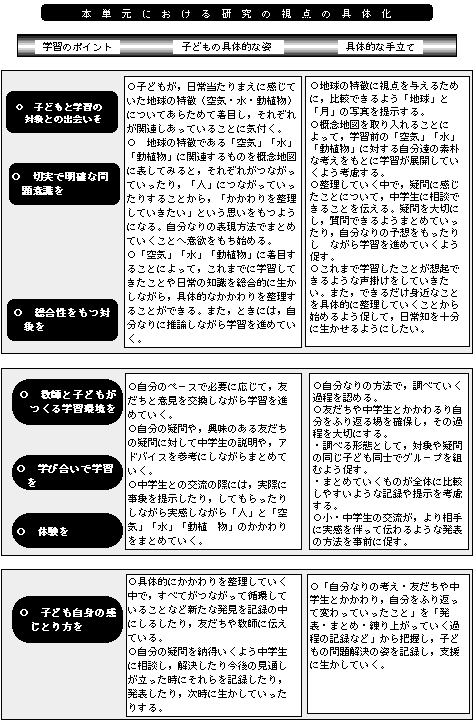 |
||||||||||
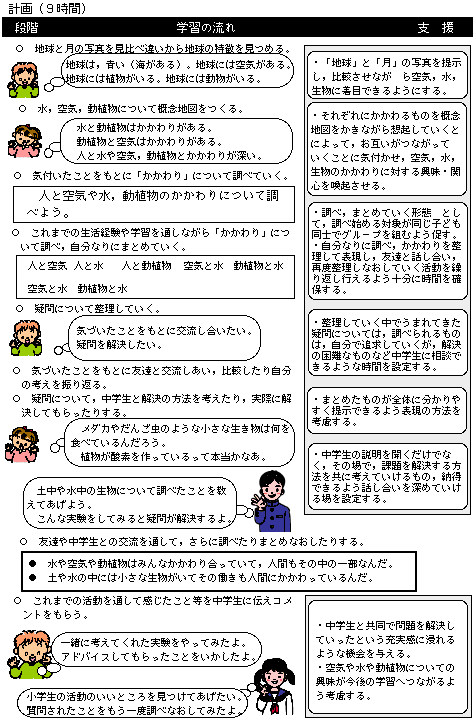 |
||||||||||
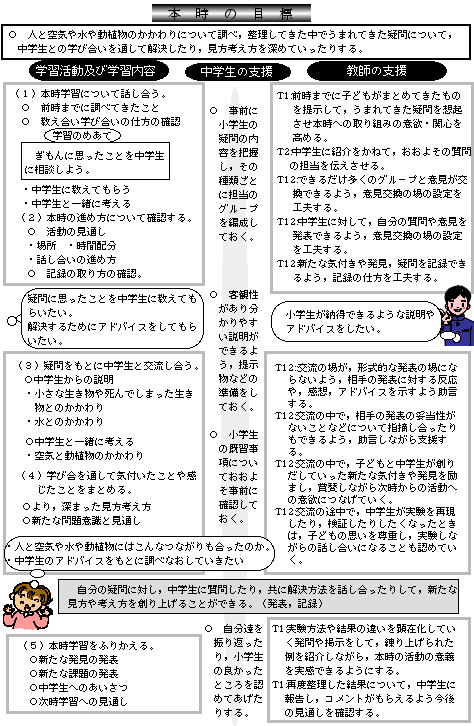 |
||||||||||
| 2. 総合的な学習の時間においての実践 | ||||||||||
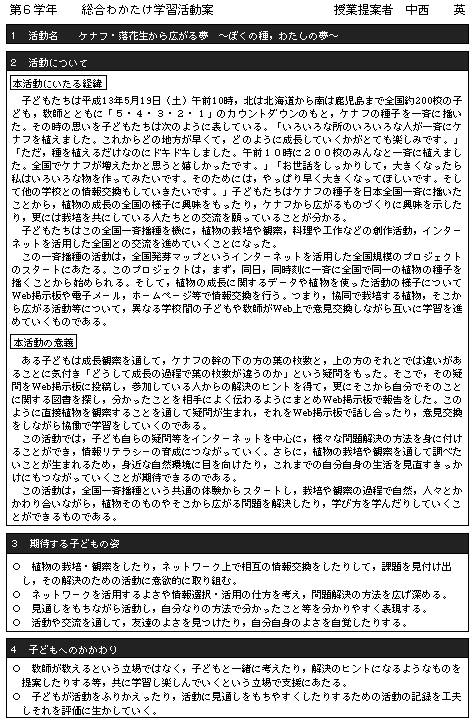 |
||||||||||
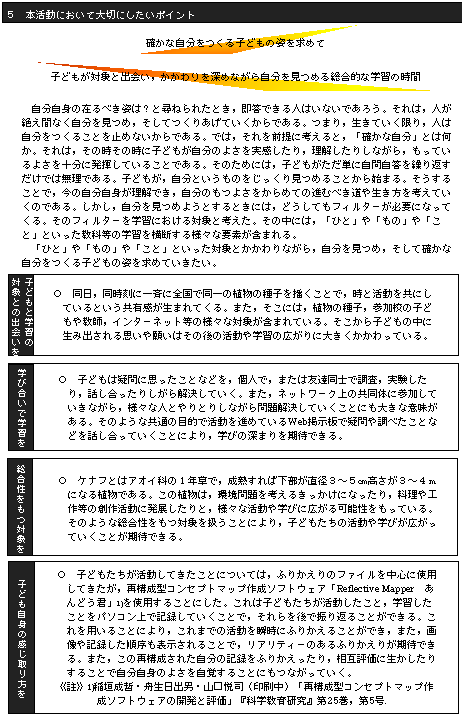 |
||||||||||
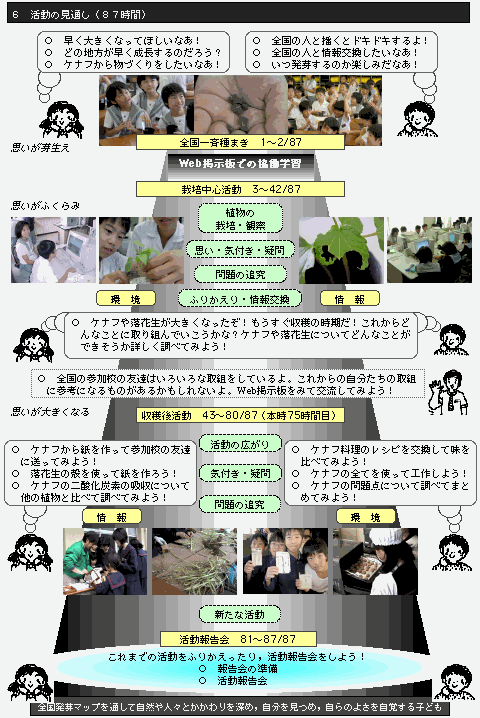 |
||||||||||
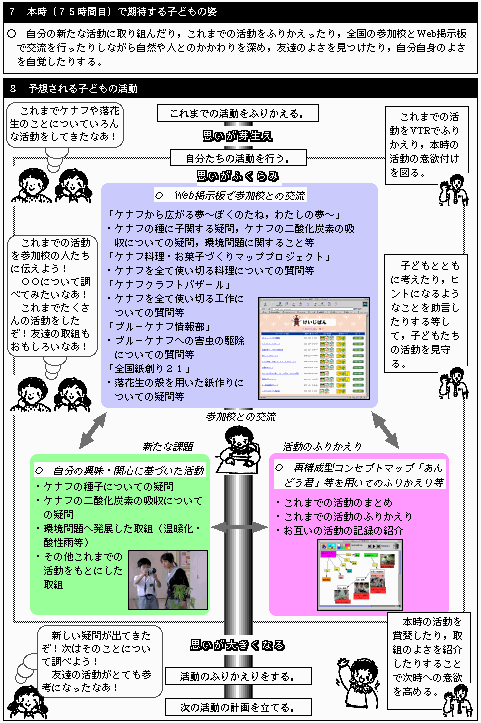 |
||||||||||
|
全国一斉にケナフの種子を播き,育て,観察し,そこから生まれる活動に主体的に取り組む児童の姿を見ることができた。これらの活動の中に子どもたちの学び方を学ぶ姿を見い出すことができる。全国発芽マップは教科の目標を達成するだけでなく,総合的な学習で期待されている学ぶ力の育成,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育てる可能性を大いに秘めていると考える。 |
||||||||||
|
|
|
「全国発芽マップの集い2001」をプロジェクト委員会で,以下のように計画・実施した。 |
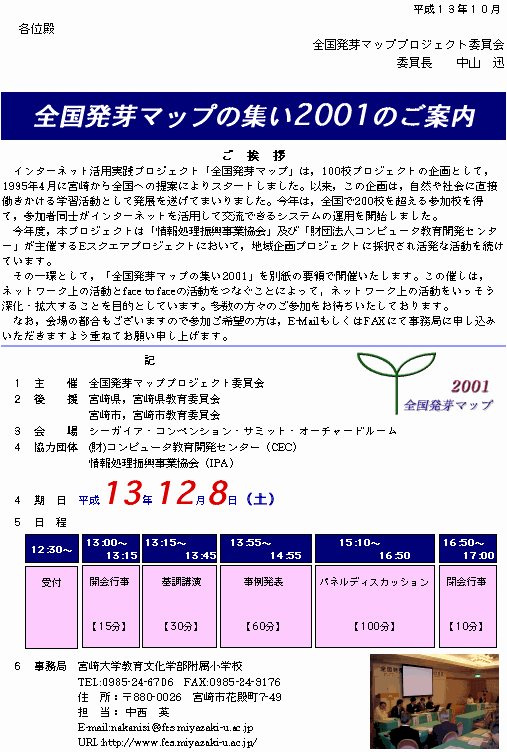 |
|
|
| (4)プレゼンテーション 当日のプレゼンテーションは,原則的にプロジェクタにパソコンを接続して行うことにした。そのため,あらかじめ発表者からファイルを送ってもらい,会場用ののパソコンにインストールして動作確認をした。 (5)配付資料 「全国発芽マップ2001の集い発表論文集」を作成した。これには,当日のプログラムの他,講演,事例発表,パネルディスカッションのパネラからの原稿を掲載した。 |
|
当日のプログラムは,前掲の通りで,祝辞,講演,事例発表,パネルディスカッション,及び,全国発芽マップ宣言から構成される。 ************************************************************************************************ ごあいさつ 21世紀を迎え,全国発芽マップも節目の年となりました。今年度は,新たに次のようなことを始めました。 全国発芽マップ2001プロジェクト委員長
宮崎大学教育文化学部 教授 中山 迅 ************************************************************************************************
「全国発芽マップの集い」 (Eスクエアプロジェクト 協働実践企画) ■開催日 2001年12月8日(土) 【プログラム】12月8日(土) 13:00〜13:15 開会行事 13:15〜13:45 基調講演 13:55〜14:55 事例発表 15:10〜16:50 パネルディスカッション 16:50〜17:00 閉会行事 ************************************************************************************************ 全国発芽マップとは… 1. プロジェクトの目的 2. プロジェクトの実施内容 2.2. 年間スケジュール(予定) 3. 参加条件 4. 主な実践内容 5. 事務局の支援内容 6. 実施体制 7. 応募方法 8. 募集期間 9. プロジェクトの期間 10. 参加申し込みに関する問い合わせ先 11. 実施内容に関する問い合わせ先 12. 2001年度の試み 〜電子掲示板〜 『ケナフクラフトバザール』 管理者名 河畑南美子 (かわばたなみこ) なお,本プロジェクトは「情報処理振興事業協会(IPA)」及び「財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC)」が主催するEスクエアプロジェクトにおいて,協働実践企画プロジェクトに採択され,支援を受けて実施されてきたものです。 情報処理振興事業協会(IPA) ************************************************************************************************ |
|
|
|
今年度の活動に関し,対外的に公開・普及するために,下記の活動を行った。 |
|
今年度の成果物に関しては,下記のURLにて公開し,利用を希望する学校にはWebからの申し込みで利用できるようした。 http://www.fes.miyazaki-u.ac.jp/HomePage/kyoudoupuro/hatuga13/hatuga13.html |
|
|
|
|