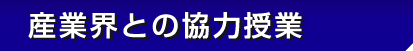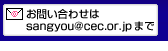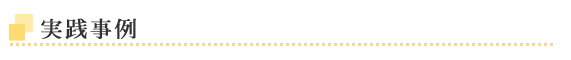|
|
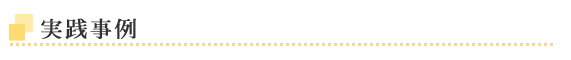

| �w�N |
�N���X |
���k�� |
���{�� |
���v���Ǝ��� |
| ��1�w�N |
1�N���X |
40�� |
����15�N10��16���A23���A11��6�� |
420�� |

| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�����@����Љ� |
(1) ����ɐ����鎄�����̉ۑ� |
| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�ƒ�@�ƒ��b |
(3) ������Ɗ� |
| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�ƒ�@�ƒ둍�� |
(5) ������Ǝ����A�� |
| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�ƒ�@�����Z�p |
(2) ������Ɗ� |
| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�w�Z�ݒ苳�ȁ@�Y�ƎЉ�Ɛl�� |
��Љ�ƎY�� |

 |
----- |

 |
�@�������̓��퐶���͗l�X�ȑf�ނɈ͂܂�Ă���B���̒��̂ЂƂA�g�߂ŕs���ȁu�K���X�v�Ƃ����f�ށB����̎��Ƃł́A�K���X�Y�ƂƂ��̐��i�A�����ă��T�C�N���ɂ��Ċw�K����B����I�Ɏg�p���Ă���K���X���i�̐����ߒ��Ɗ����ׂ̊W�𗝉�����ƂƂ��ɁA��Ƃ̍l����u�����\�Ȑ��Y�v�ɂ����ڂ���B�����IT�����i�m�e�N�m���W�[�Ƃ̗Z���Ŋ���K���X���i�Ɍ��y���A�K���X�Y�Ƃ�ʂ��āu���Ɩ����v���w�сA�Y�ƎЉ�Ɛl�ԂƂ̊ւ����l���A���\���邱�Ƃ��˂炢�Ƃ���B
�@���Ƃ́A�����w�ȂłP�N���ɕK�{�́u�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁv�𒆐S�ɁA�u����Љ�v�ň����u��Ɗ����Ɗ��v�A�u�ƒ�v�ň����u������Ɗ��v�Ƀ����N������̂Ƃ��A����Y�ƊE�ƍ����w�Z�̌𗬎��ƂɗL�p�Ȏ��Ɠ��e����тh�s���ނ��\�z����B
�@�����w�Z�̎��Ǝ��{�ɂ��ẮA�K���X�Y�ƘA����̎����ǂ����e�ɉ����Đl�I���A�h���v�������P���̊e�c�̋y�т��̍\����Ƃ̎Љ�l�u�t���s���B�E�ƈӎ�����ޏ����i�K�ŎY�ƊE�̍u�t�ɂ����Ƃ��A���̎Y�Ƃ̌�������w���邱�ƂŁA�Y�ƂƊ��ɂ��Ď���l���A���肠��E�Ɗς��m������ꏕ�Ƃ������B
|

 |
�E �F�m�I�ڕW�F���Ƃ����������ɁA�K���X�f�ނ�i�ɂ�鍡��̊����ւ̉e����Y�Ƃւ̖�����F�����邱�Ƃ��ł���B
�E ��ӓI�ڕW�F�g�̉��ɂ���K���X���i��K���X�f�ނɑ��鋻���S��[�߁A���̓�����T�C�N���̈Ӗ��A�n�����̑���𗝉����A���퐶���̒��ōs���Ɍ��т��Ă������Ƃ��ł���B
�E �Z�p�I�ڕW�F�ړI�ɂ������e�[�}��I�����A�e���̖ڕW������Ɋ֘A���鎑����{��C���^�[�l�b�g���g���Ď��W�����\���ł���ƂƂ��ɁA���҂̔��\��ϋɓI�ɗ�������悤�w�߂�B
|

| ���{�P�� |
�e�[�} |
| 1��� |
�K���X�̑g���E�����E��Ƃ̊��ւ̎��g�݁A��[�Z�p |
| ���{�ꏊ |
�}�g��w������ˍ��Z
�R���s���[�^�� |
���{���� |
135�� |
| �u�t |
�K���X�Y�ƘA���� ���c�Lj�
�i���{�R���Ɏq������Ёj |
�g�p���� |
Microsoft(R)PowerPoint(R), VHS�r�f�I, Web�R���e���c, ���[�N�V�[�g |
| ���Ƃ̐i�s�E���e |
���Ƃ̗l�q |
���i�s
�g�߂ɑ��݂��邪�̂ɉ��߂Ėڂ������邱�Ƃ̏��Ȃ��u�K���X�v�Ƃ����f�ނɊS�������邽�߁A��P��ڂ̎��Ƃɐ旧���A�h����o���B�K���X���̂��̂ւ̗�����[�߂����ƁA�K���X�Y�Ƃ��Ƃ̊��ւ̎��g�݁A���ʂ����҂̖����A�����ւ̓W�]�ƁA�e�[�}���g���Ă������B
�u�`�̕⊮�Ƃ��āA�p���[�|�C���g��r�f�I�AWeb�ւ̃A�N�Z�X�ȂǗ����𑣂��c�[�����g�p�B
�l�X�ȃK���X���i�⌴���A�J���b�g�Ȃǎ��������������ɓW�����A���k�ɐG���Ď������Ă��炦����������B
�����e
���O�ɏo�����h��F
�@�@�@ ����ɂ���K���X���i�̎�ނƂ��̐��������o���Ă݂悤�B
�@�@�A �h��P�ȊO�ŁA�m���Ă���K���X���i�������o���Ă݂悤�B
�ɂ��A�K���X�ɂ��Ēm���Ă��邱�Ƃ̔��������߂��B���̓����܂��ăK���X�����p����Ă��镪����Љ�����Ƃ����B
���ɂ��Ă̍��ڂł́A���c�u�t�̋߂�K���X�т��Ђ���������גጸ�ɔz���������i�������Ȃ���A�J���Ҏ��g�ł���u�t���炻�̊J����b�������B
|


|
| ���{�P�� |
�e�[�} |
| 2��� |
�K���X��������у��T�C�N���H���̌��w |
| ���{�ꏊ |
���{�R���Ɏq������Г����H��i���͌��s�j
|
���{���� |
150���i���ړ����ԁj |
| �u�t |
�K���X�Y�ƘA���� ���˖M�G
(���{�R���Ɏq������Г����H��)�@ |
�g�p���� |
���[�N�V�[�g(A4�Łj |
| ���Ƃ̐i�s�E���e |
���Ƃ̗l�q |
���i�s
�K���X�̐����A���T�C�N���H��݂����H��̌���S���҂��A�K���X�̐����A���T�C�N���̂Ȃ��������B�����H�ꌩ�w�ɍۂ��ẮA���ۂ̔M��������������Ă��炤���߁A�����Ȃǂ͂����Ɍ��w�B��������ł��邽�߁A�ٕ������h�~�̔z���Ƃ��ĉו��͎������A�R��A�w�����b�g�A�r�j�[���C������z�z���A���i�̕i����ۂ��߂̏��i�Ǘ��̓O��ɂ��Ă��u�`�B�v���Ƃ��Ă̌������ƏA�J�ӎ��ɂ��Ă��u�`�B
�����e
�w�Z�ł̎��ƏI����A�o�X�ŃK���X�H��Ɉړ��B
�o�X�̒��ł��A�K���X�Ɋ֘A����r�f�I���������A�K���X�ւ̊S������ɐ[�߂Ă��炤�B
�H��ł́A�H�ꌩ�w�̍ۂɎg�p���Ă���p���[�|�C���g�ɂ��A�H��̊T�v�A�K���X�̐����H���A�H�ꂪ�s�����T�C�N���̗�����u�`�B
�H�ꌩ�w�̐S���ƒ��ӂ̂��ƁA�w�����b�g�Ȃǂ𒅗p���H������ցB�͂��߂Ƀ��T�C�N���H���Ƃ��āA���T�C�N���Ɏg�p��������т[�h�A�K���X���������w�B���T�C�N���̂��߂ɕK�v�ȑI�ʍ�ƂƂ��āA�@�B��l��ōs����ٕ��̑I�ʍH���ł��̎��ۂ����w�B�����H���ł́A�����ŗn�����K���X���u���Ɉړ����K���X�̌^�ɗ������܂�錻���A�ł�������̃K���X�̕s�Ǖi�Ƃ̑I�ʁA�@�B�ɂ��s���郉�x���\��A�q�ɂɈړ������S���������ꂽ���i�̔��o�̌�������w�B�S�Ẳӏ��ɐ�������z���A�H���̏ڂ�����������B
�z�z���ꂽ�����F��Јē��A�����A�����H��T�v�A�H��ē��A�������w���V���A�K���X�Y�ƘA����[�t���b�g
|


|
| ���{�P�� |
�e�[�} |
| 4��� |
�O���[�v���Ƃ̔��\�Ƒ��ݕ]���A�u�t�̍u�] |
| ���{�ꏊ |
�}�g��w������ˍ��Z
|
���{���� |
135�� |
| �u�t |
�K���X�Y�ƘA���� ���c�Lj�
�i���{�R���Ɏq������Ёj |
�g�p���� |
���[�N�V�[�g(A4��) |
| ���Ƃ̐i�s�E���e |
���Ƃ̗l�q |
���i�s
�P��ڂ̎Љ�l�u�t�ɂ��u�`�A�Q��ڂ̍H�ꌩ�w�܂��ăO���[�v���Ƃɒ��w�K���s���A�p���[�|�C���g�ł܂Ƃ߂��c�[�������p���Ȃ���O���[�v���Ƃɔ��\���s���B���Ƃ����{�����}�g��w������ˍ��Z�́A���˂Ă��u�Y�Ɨ����v�̒P���̂��ƁA�O���[�v���ƂɒS������Y�Ƃ�^�����A�S���Y�Ƃ̊�Ƃ��o�c����Ƃ������Ƃ��s���Ă��邽�߁A������e�O���[�v�̒S������Y�ƂƃK���X�̊ւ����������\�e�[�}�Ƃ����B
�����e
�����̃O���[�v���S�������ƂƃK���X�̂������̒�����e�[�}��ݒ肵�A���\���e���܂Ƃ߂��p���[�|�C���g��p���ăv���[���e�[�V�����������B
�P�D���ʐM�Fkaji-kaji communication
�@�@�@�@�u�ʐM and �K���X�@�`���ʐM�`�v
�Q�D���݁F�L�b�R�[�}������
�@�@�@�@�u���ǂ���炵�����߂āv
�R�D��s�F��e��s
�@�@�@�@�u���Ɏ��g�ފ�ƂƋ�s�̊ւ��v
�S�D�����FSST�}�[�g
�@�@�u�K���X���i����鏤�i�̃C���[�W
�@�@�@�@�@�`�y�b�g�{�g���ƃK���X�̈Ⴂ�`�v
�T�D���i�F�^���[����
�@�@�@�@�u�K���X�Ƃ̊ւ��v
�U�D�A���@��F�}�⎩����
�@�@�@�@�u�ԂɎg����K���X�ɂ��āv
�V�D�H�i�F���v�`�j�`�a�`
�@�@�@�@�u���i���̂���H��ɂ��āv
�W�D�d�C�@��F����G���^�[�e�C�������g
�@�@�@�@�u�d�C�ƃK���X�̃R���{�ɒ���v
���\��A���k����̎��^�����E���z������A�Љ�l�u�t����u�]���������B�u�]�́A�u�t�̐�啪��ł���K���X���i��Y�Ƃ݂̂ɂƂǂ܂炸�A�v���[���e�[�V�����Ɋւ��Ă��A�悩�����_�A�H�v���K�v�Ǝv����_�A�u�t����̒�ĂȂǁA�S�ʂɂ킽��u�]�������������B
|

�p�\�R�������ł̃f�[�^�̎�荞�ݍ�ƕ��i

|

 |
�E �K���X�f�ނ�i�̓����A�Y�Ƃɂ��ė���
�K���X�Y�ƂƂ��̐��i�A���T�C�N���A����ɏ]���̘g���ĐV��������Ői����������K���X�̖����ւ̓W�]�ɂ��Ċw�K���A����I�Ɏg�p���Ă���K���X���i�̐����ߒ��Ɗ����ׂ̊W�𗝉�����ƂƂ��ɁA�Y�ƊE�̋�̓I�Ȋ��ւ̎�g�݂̗�����[�߂��B
�ƒ���̃K���X���i����n���K�͂̊����ɖڂ������A���������̖L���Ȑ����Ɗ����ׂ̊ւ��ɒ��ڂ����B
�E ���������ɖ��ڂɊW���Ă�������ւ̔F���ƍs���ł���ӎ��̏���
���ݖ��A�n�����g���A���z�������ȂǁA�����Ɗ֘A�����Ȃ���K���X�̗D�ʐ��𗝉����A�����Ɩ��ڂɂȂ�����Ƃ��āA����l���s���������҂Ƃ��Ă̈ӎ������N�����B
�E �h�s�Ȃǂ����p�����v���[���e�[�V�����\�͂̌���
�}�g��w������ˍ��Z�ł́A�P�N���̔N�x�n�߂̎��ȏЉ���p���[�|�C���g�ōs���Ă��邱�Ƃ���A�Ō�̎��Ƃ̌������\�́A�O���[�v���Ƃɂ킩��ăp���[�|�C���g�ɂ�蔭�\���邱�ƂƂ����B�p���[�|�C���g�ł̃e�L�X�g�ł����݁A�摜�̌f�ځA�A�j���[�V�����@�\�̊��p�ȂǁA�h�s�@��̗��p�ɂ����Ċ�b�ɂȂ郊�e���V�[�̌����啝�ɐ}�邱�Ƃ��ł����B�܂��A�Z�p�ʂ����łȂ��A���C�A�E�g��w�i��A�z�F�ȂǁA���₷���Ƃ��Ă̍H�v���Â炵�����o�����Ă���A���҈ȏ�̐��ʂ��������B
|
 |
���\����
<1�NA�g�̐��k�ɂ��p���[�|�C���g���>
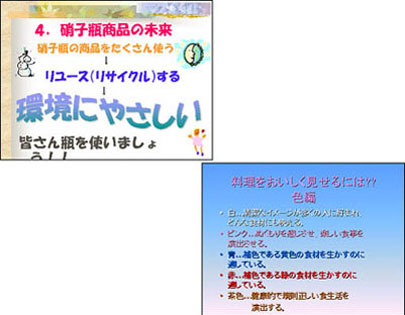
|

| ���{�ꏊ |
�}�g��w������ˍ��Z�@�R���s���[�^�������1�NA�g����
���{�R���Ɏq�����H�� |
| �g�p�����@�� |
�f�X�N�g�b�v�o�b�A�v���W�F�N�^�[�A�r�f�I�f�b�L�A�X�N���[�� |

| ���ރ^�C�g�� |
�K���X�Y�Ƃ���݂���Ɩ��� |
| ���ގd�l |
Microsoft(R)PowerPoint(R) 37���
|
| ���ފT�v |
�g�߂ȑf�ނł���u�K���X�v�ɂ��āA���̑g���E�����A�K���X�Y�Ƃ̐��ڂ��Ƃ̊����גጸ�̂��߂̋Z�p�J����T�C�N���̎��g�݂Ȃǂɂ��āA�T�̍��ڂœW�J�B�摜��O���t�C���X�g�̃��B�W���A�������Ƃ��ču�`�̕⊮�����A���ꂼ��̃X���C�h�ɂ̓m�[�g�������A�u�`�̃|�C���g���L�ځB
|
| ���ރ^�C�g�� |
������K���X�Y�Ɓ`�K���X�̐�[�Z�p�` |
| ���ގd�l |
VHS �r�f�I�@��10�� |
| ���ފT�v |
�����镪��Ŋ��p����A�J�����������鍂�@�\���K���X�ƁA�i�m�e�N�m���W�[�Ƃ̗Z���ɂ��]���̘g���Đi�����Â���K���X�������ւ̓W�]���Љ�B
|
| ���ރ^�C�g�� |
�K���X�̊��T��c |
| ���ގd�l |
HTML�f�[�^�@5��� |
| ���ފT�v |
�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɂ���K���X���v���x����R���e���c�B�����ƃK���X�̊ւ��A�ƒ�Ŏg�p���Ă���K���X�̊����ׂ̓x�����̖ڈ�������A�����ł���R���e���c�B
|
| ���ރ^�C�g�� |
�K���X�̉摜�W |
| ���ގd�l |
HTML�f�[�^�@90��� |
| ���ފT�v |
�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɍ\�z���ꂽ�K���X�֘A�摜�W�B�P�Q�̃W�������ɕʂ�A���ꂼ�ꕡ�������[�B
|

| ���@�� |
���@�� |
���Ƃł̐��� |
�K���X�Y�ƘA����
�i���{�R���Ɏq�j |
���c�Lj�
|
�u�t |
�K���X�Y�ƘA����
�i���{�R���Ɏq�j |
���˖M�G
|
�H�ꌩ�w�S�� |
| �K���X�Y�ƘA���� |
�{�{��q
|
IT���p�w�� |
| �������NHK�\�t�g�E�F�A |
���]�r��
|
IT���p�w�� |
| �������NHK�\�t�g�E�F�A |
������
|
IT���p�w���A���ƒ��� |

�����Ǝ��{��
�@�i�Y�ƊE�u�t�j���� |
- ����A�u�Y�Ɨ����v�Ɋւ�����Ƃ����Z�ōs���Ă��邱�Ƃ�m�����B����͎����A�H�ꌩ�w�̎���A�u�t�h���ȂǁA�Y�ƊE���ϋɓI�ɍs���Ă�����Ɨǂ��B
|
| ���S�C���� |
- ���k�����ɁA�w�Z�ɂ�����w�K�Ǝ��Љ�����т��ăC���[�W���Ă��炤���Ƃ��d�v�ł���A���̂��߂ɂ͎Y�w�A�g�͂���߂ėL�Ӌ`�ł���Ǝv���B
- �Y�w�̘A�g�͏d�v�ł���A�C���^�[�l�b�g���Ȃǂ𗘗p���āA�A���𖧂ɂ��Ă�����Ɨǂ��B
- ������w�Z�̓��������ł͂Ȃ��A�L���Љ�̎h����������Ă��������B���k�ɂ����Ƃ����łȂ��A���낢��Ȓm����o����ς�ŗ~�����B
- �w�Z����ɂ����Ƃ�Ƃ肪����A��Ƃ�����ɂ����Ɩ�˂��J���A�A�g���Ă�����Ɨǂ��B
- �N���X�P�ʂł͂Ȃ��A���l���̃O���[�v�P�ʂōs����Ƃ����ʓI�ł���B
- �Y�ƊE�̐V�����Z�p������A����̕��̘b����̂͋M�d�ȑ̌��������B
|
| �����k���� |
- ���܂ł̓K���X�Ƃ������̂����܂�ɐg�߂����āA���̂����������������ǁA����̎��Ƃ��āA�����̈����̂̓����Ă����r�����ǂ�ȃr���Ȃ̂������Ă݂��肷��悤�ɂȂ����B�@�f�M�ނȂǁA�����Ȃ��Ƃ���ɂ�����Ă������Ƃ��m�邱�Ƃ��ł����B
- ���H�A�A�X�t�@���g�ɃK���X������̂�������悤�ɂȂ����B
- �K���X�т�̍�������ԋ߂Ō��ꂽ�B�K���X�̎�ށi�����E�F�C�r���Ȃǁj���킩�����B
- �v��ʏ��ɃK���X�������Ă��ċ������B�Ⴆ�Ό��t�@�C�o�[�Ȃ͕��������Ƃ����Ȃ����������ۂɎc�����B
- ���^�[�i���r���̘b���������̂ŁA���T�C�N���ɐϋɓI�ɋ��͂��Ă��������Ǝv���܂��B�r���̂ӂ���x�����͂�������ƁA�ׂ������ɂ��C��t�������ł��B
- �����[�X����B�����ӎ�����B���ߗ��Ēn�������邢�������������ł������~�߂邽�߁A�K���X�ɒ��ڂ��Ă݂�B
- �����ƃK���X�̂��ƂׂāA�ǂ�Ȃ��Ƃ���������̂��߂ɂȂ�̂��Ƃ��A�����ƒm�������邱�Ƃ���n�߁A���ꂩ��A�������ǂ�����ׂ������l�������Ǝv���B�K���X�͊��ɂ悢�Ƃ����悤�ɁA���ɂ����ɂ₳�������̂͂�������͂��Ȃ̂ŁA�������@�����̐����ɂ������Ȃ��琶���Ă��������B
|
| ������W�̗��ꂩ�� |
- ����]��ӎ����Ȃ��Ŏg���Ă���u�K���X�v�Ƃ������̂ɖڂ������Ă��炤�ǂ����������ɂȂ����Ǝv���B
- �Z���ԂŐ��ʂ����߂��A�p�����Ă������Ƃ��d�v���Ǝv���B
- �����̂��̂�^������Љ�̒��ŁA�����A����Ȃǂ̋@��𑝂₵�A���̌���n��̊y�������o�����Ă����ė~�����B
|


|