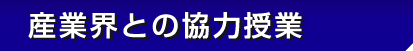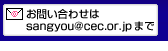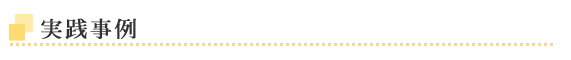|
|
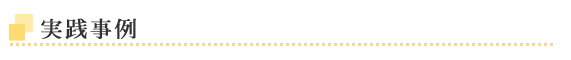

| �w�N |
�N���X |
���k�� |
���{�� |
���v���Ǝ��� |
| ��1�w�N |
2�N���X |
44�� |
����15�N12��5���A10���A12�� |
200�� |

| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�Z�p�ƒ�@�Z�p����A |
�u�Z�p�Ƃ��̂Â���v(1)�C�Z�p���E�G�l���M�[�A�����̊W |
| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�Z�p�ƒ�@�ƒ땪��a |
�u�Ƒ��Ɖƒ됶���v(4)�C�����̐��������ɗ^����e�� |
| �w�N |
���Ȗ� |
�P�� |
| ��1�w�N |
�Љ�@���� |
(2)�@�A�������̐����ƌo�� |

 |
----- |

 |
�@�@�������̓��퐶���͗l�X�ȑf�ނɈ͂܂�Ă���B���̒��̂ЂƂA�g�߂ŕs���ȁu�K���X�v�Ƃ����f�ށB����̎��Ƃł́A�K���X�Y�ƂƂ��̐��i�A�����ă��T�C�N���ɂ��Ċw�K����B����I�Ɏg�p���Ă���K���X���i�̐����ߒ��Ɗ����ׂ̊W�𗝉�����ƂƂ��ɁA��Ƃ̍l����u�����\�Ȑ��Y�v�ɂ����ڂ���B���Ƃ́A�Z�p�ƒ�Z�p����`�u�Z�p�Ƃ��̂Â���v(1)�C�Z�p�Ɗ��E�G�l���M�[�A�����̊W�^�Z�p�ƒ�ƒ땪��a�u�Ƒ��Ɖƒ됶���v(4)�C�����̐��������ɗ^����e���^�Љ����(2)�A�������̐����ƌo�ςɃ����N������̂Ƃ��A����Y�ƊE�ƒ��w�Z�̌𗬎��ƂɗL�p�Ȏ��Ɠ��e����тh�s���ނ��\�z����B
�@�@����ɁA�K���X�т�̃��T�C�N���֘A�ɂ��Ė⍇���̑������w�Z�ɂ��ėp�����L���邽�߁A���w�Z��P�w�N��ΏۂɁA���ʂɔ�d��u������蕽�ՂȃJ���L�������������Ď��{����B
�@�@�K���X�̐����y�у��T�C�N���ɂ��āA���Ƃ����k�Ɍ����Ă킩��₷��������A�ƒ���̃K���X���i����n���K�͂̊����ɖڂ������A���������̖L���Ȑ����Ɗ����ׂ̊ւ����w�K����B����ɃK���X�H�|��̌����Ȃ���K���X�ɐG��邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��K���X�Ƃ����f�ނɂ��ė�����[�߂Ă����B
�@�@�K���X�Y�ƘA����̎����ǂ����e�ɉ����Đl�I���A�h���v�������P���̊e�c�̋y�т��̍\����Ƃ̎Љ�l�u�t���s���B�E�ƈӎ�����ޏ����i�K�ŎY�ƊE�̍u�t�ɂ����Ƃ��邱�ƂŁA�Y�ƂƊ��ɂ��Ď���l���A���肠��E�Ɗς��m������ꏕ�Ƃ������B
|

 |
�E �F�m�I�ڕW�F���Ƃ����������ɁA�K���X�f�ނ�i�A�����ɂ��ĊS�������A���ƂɎ�g�ނ��Ƃ��ł���B
�E ��ӓI�ڕW�F�K���X�f�ނ̓�����T�C�N���A�n�����̑���𗝉����A���퐶���̒��ōs���Ɍ��т��邱�Ƃ��ł���B
�E �Z�p�I�ڕW�F�u�t�̐E�ƂɊW�����M���}������̉��H���ł���B
|

| ���{�P�� |
�e�[�} |
| 1��� |
�K���X�̑g���E�����E��Ƃ̊��ւ̎��g�� |
| ���{�ꏊ |
�V�h�旧��v�ے��w�Z
�R���s���[�^�� |
���{���� |
100�� |
| �u�t |
�K���X�Y�ƘA����@������o�C
�i���{�Ɏq������Ёj |
�g�p���� |
Microsoft(R)PowerPoint(R), VHS�r�f�I, Web�R���e���c, ���[�N�V�[�g |
| ���Ƃ̐i�s�E���e |
���Ƃ̗l�q |
���i�s
�g�߂ɑ��݂��邪�̂ɉ��߂Ėڂ������邱�Ƃ̏��Ȃ��u�K���X�v�Ƃ����f�ނɊS�������邽�߁A��P��ڂ̎��Ƃɐ旧���A�h����o���B�K���X���̂��̂ւ̗�����[�߂����ƁA�Y�Ƃ���ւ̎��g�݁A���ʂ����҂̖����ƁA�e�[�}���g���Ă������B
�u�`�̕⊮�Ƃ��āA�p���[�|�C���g��r�f�I�AWeb�ւ̃A�N�Z�X�ɂ�藝���𑣂��c�[�������p�B
�l�X�ȃK���X���i�⌴���A�J���b�g�Ȃǎ��������������ɓW�����A���k�Ɏ����ɐG��A�����ł�����������B
�����e
���O�ɏo�����h��F
�@�@�@ ����ɂ���K���X���i�̎�ނƂ��̐��������o���Ă݂悤�B
�@�@�A �h��P�ȊO�ŁA�m���Ă���K���X���i�������o���Ă݂悤�B
�ɂ��A�K���X�ɂ��Ēm���Ă��邱�Ƃ̔��������߂��B���̓����܂��ăK���X�����p����Ă��镪����Љ�B
�u�t�̐����̍ۂɂ́A�摜��O���t�A�����ݐ}�Ȃǂ̃r�W���A�������������Ȃ��痝���𑣂����B�܂��A�̌������Ƃ��ċ����K���X�̏ォ��S���𗎂Ƃ����x�����A�h�ƃK���X�����ƂŒ@������j������A�d���̂n�m�A�n�e�e�ŃK���X���s�����ɂȂ钲���K���X�̏u���ω��A�b�n�Q�r�o�}���ɍv�����镡�w�K���X��^��K���X�̒f�M���ʑ̊��Ȃǂk�Ƌ��ɍs���A�u�`�Ƒ̊������A�r�f�I�̎�����D�荞�݂Ȃ���i�s�����B
|


|
| ���{�P�� |
�e�[�} |
| 2��� |
�M���}������̌� |
| ���{�ꏊ |
�V�h�旧��v�ے��w�Z
|
���{���� |
100�� |
| �u�t |
�K���X�Y�ƘA����
�㏼�q�� |
�g�p���� |
���[�N�V�[�g(A4�Łj |
| ���Ƃ̐i�s�E���e |
���Ƃ̗l�q |
���i�s
�@�@�P��ڂ̎��ƂŃK���X�ɂ��Ă̒m���ƊS��[�߁A�Q��ڂł̓K���X�H�|��̌����Ȃ���K���X�ɐG��邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��K���X�Ƃ����f�ނɂ��ė�����[�߂Ă����B
�����e
�K���X�Y�ƊE�ɒ����]�����A����K���X�̔����فi���ݕ��j�ő����̐l�ɃM���}��������w�����Ă����u�t���A���܂ł̌o���������Ď��ȏЉ�B
�P��ڂ̎��Ƃ̍u�`�̒�����A���Ƀ��T�C�N���ɂ��ĐU��Ԃ�����A�H�|����ł��K���X�����T�C�N�����Ċ��p����Ă����������������Ȃ������B
�M���}������̌��ɐ旧���A���O�̗R����e���܂�Ă������j�A�H��i���[�^�[�j�̂����݂Ǝg�����A������{���ۂ̒��ӎ���������B
�܂��A���[�^�[�Ɋ���邽�߁A���K�p�̔K���X���g���Ď���������s���A��i����ɂƂ肩����B
�f�U�C���̕`���N�����A�܂��̓T���v���f�U�C������`���N�����A���M�܂��͔K���X�ɗ��ʂ��璤����J�n�B���ʃK���X�́A���ʂ���̒���ƂȂ邽�߁A�t�łŒ��邪�A�ԈႦ�ĕ\�̂܂ܒ����Ă��܂������k���������A���܂���������ďC������ȂǁA�l�X�ȍH�v���Â炵�Ȃ���d�グ�Ă����B���ʂ��̂ւ̌@�肪��������A�p�т�A�v���Y���A�~�j�{�g���ȂǁA�p�ӂ��ꂽ�K���X�f�ނ���D���Ȃ��̂�I�э�i��B�Q���Ԃ̎��Ԃ̒��ŁA�قƂ�ǂ̐��k���x�ݎ��Ԃ��Ƃ炸�ɐ���Ɏ��g�B
|


|

 |
�E �K���X�f�ނ�i�̓����𗝉�
�@�@�K���X�Y�ƂƂ��̐��i�A���T�C�N���ɂ��Ċw�K���A����I�Ɏg�p���Ă���K���X���i�̐����ߒ��Ɗ����ׂ̊W�𗝉�����ƂƂ��ɁA�Y�ƊE�̋�̓I�Ȋ��ւ̎�g�݂̗�����[�߂��B
�@�@�ƒ���̃K���X���i����n���K�͂̊����ɖڂ������A���������̖L���Ȑ����Ɗ����ׂ̊ւ��ɒ��ڂ����B
�E ���������ɖ��ڂɊW���Ă�������ւ̔F���ƍs���ł���ӎ��̏���
�@�@���ݖ��A�n�����g���A���z�������ȂǃG�l���M�[�ɂ����������𗝉�������ŁA�����Ɩ��ڂɂȂ�������₻�̑�Ȃǂ��w�B
�E �h�s�����p���A�C���^�[�l�b�g�Ɋ����
�@�@�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɍ\�z����Web�R���e���c�փA�N�Z�X���A�ƒ�Ŏg���Ă���K���X�ƃ��T�C�N���ɂ��Ă̍s���肷��ł����݂��������A�z�[���y�[�W�ւ̃A�N�Z�X��ł����݂̃��e���V�[�����コ����_�ŁA�\�͂̌��オ�}��ꂽ�B
�E �K���X�H�|��ʂ��ăK���X�f�ނɐe����
�@�@�K���X�H�|��̌����Ȃ���K���X�ɐG��邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��K���X�Ƃ����f�ނɂ��āA������[�߂��B�M���}������̌��ɐ旧���A�u�t����H�|����ł̃K���X�̃��T�C�N���̉���ɁA�P��ڂ̎��ƂŊw�K�����s���A��Ɗ����ł̃��T�C�N���̂����݂Ƃ͕ʂɁA�H�|����ł����p����郊�T�C�N���ɂ��Ă������̕����L�����B�M���}���̖��O�̗R���A�M���}������̍�i�̊ӏ܁A�H��g�p�̒��ӂ̂��Ƃɍs�����M���}������̌��ł́A�f�U�C�����璤��̍H�����A���Ԃ̔z�����l���Ȃ���A�H�v���Đ��E�Ɉ�����̍�i���������������Ƃɖ������o�������k���ڗ������B
|
 |
���\����
<1�NA�g�̐��k�̍�i>
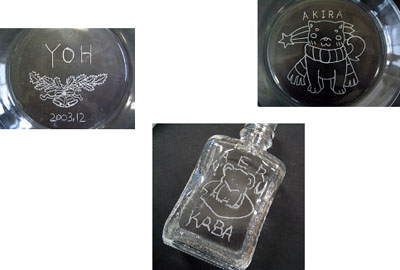
|

| ���{�ꏊ |
�V�h�旧��v�ے��w�Z�@�R���s���[�^�[������і؍H��
|
| �g�p�����@�� |
�E�f�X�N�g�b�vPC�@�E�v���W�F�N�^�[�@�E�r�f�I�f�b�L�@�E�X�N���[�� |

| ���ރ^�C�g�� |
�K���X�Y�Ƃ���݂���Ɩ��� |
| ���ގd�l |
Microsoft(R)PowerPoint(R) 23���
|
| ���ފT�v |
�g�߂ȑf�ނł���u�K���X�v�ɂ��āA���̑g���E�����A�K���X�Y�Ƃ̐��ڂ��Ƃ̊����גጸ�̂��߂̋Z�p�J����T�C�N���̎��g�݂Ȃǂɂ��āA�T�̍��ڂœW�J�B�摜��O���t�C���X�g�̃��B�W���A�������Ƃ��ču�`�̕⊮�����A���ꂼ��̃X���C�h�ɂ̓m�[�g�������A�u�`�̃|�C���g���L�ځB
|
| ���ރ^�C�g�� |
�K���X�̊��T��c |
| ���ގd�l |
HTML�f�[�^�@5��� |
| ���ފT�v |
�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɂ���K���X���v���x����R���e���c�B�����ƃK���X�̊ւ��A�ƒ�Ŏg�p���Ă���K���X�̊����ׂ̓x�����̖ڈ�������A�����ł���R���e���c�B
|
| ���ރ^�C�g�� |
�K���X�̉摜�W |
| ���ގd�l |
HTML�f�[�^�@90��� |
| ���ފT�v |
�K���X�Y�ƘA����z�[���y�[�W���ɍ\�z���ꂽ�K���X�֘A�摜�W�B�P�Q�̃W�������ɕʂ�A���ꂼ�ꕡ�������[�B
|

| ���@�� |
���@�� |
���Ƃł̐��� |
�K���X�Y�ƘA����
�i���{�Ɏq������Ёj |
������o�C
|
�u�t |
| �K���X�Y�ƘA���� |
�㏼�q��
|
�u�t |
| �K���X�Y�ƘA���� |
�{�{��q
|
IT���p�w�� |
| �������NHK�\�t�g�E�F�A |
���]�r��
|
IT���p�w�� |
| �������NHK�\�t�g�E�F�A |
������
|
IT���p�w���A���ƒ��� |

�����Ǝ��{��
�@�i�Y�ƊE�u�t�j���� |
- �����ƂƊw�Z�Ƃ̘A�g�����P���邽�߂ɂ́A���ۂ̎��Ƃ��d�˂Ă����ʂ��đ��݂ɗ�����[�߂Ă����B
- �����K���X�A�h�ƃK���X�A�^��K���X�A�����i�t���j�K���X�Ȃǂ̎����������A���\��̊������邱�Ƃ��ł����B
- ��ƂƊw�Z�̒��ړI�𗬂͗e�Ղł͂Ȃ��B�Ⴆ�H�ꌩ�w�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�P�Ɍ��Ă��炤�����ł͎v�����`���Ȃ��ꍇ�������B����̃v���W�F�N�g�̂悤�ɁA���Ƃ̃R���e���c�ɂ��āA���O�ɑō������d�˂邱�ƂŁA�`�������_�A�`���ė~�����_���N���A�ɂȂ�A���������Ӗ��ł̓R�|�f�B�l�[�^�[�̑��݂��d�v�B
|
| ���S�C���� |
- �h�ƃK���X�⋭���K���X�A�K���X�@�ۂł����Ă���f�M�ނȂǂ����ۂɌ����Ȃ���A�K���X�͂��낢��ȏꏊ�Ɏg���Ă��邱�Ƃ�A�����̉��x�������艷�x�ɕۂ��Ƃ��ł���Ƃ������ƁB
- �F�ʂɕ����ĉ�����ꂽ�K���X�т��T�C�N�������H�������邱��
����āA�K���X�̍ė��p�̑������Ƃ�m�������ƁB
- �M���}������̗R���̐����������āA�S�������Ƃ��ł����B
- �M���}��������s���ۂ̏����ӂ�����A���S�ʂł̎w�����������B
- �f�U�C���T���v�����L�x�ɂ���A���k���ӗ~�I�Ɋw�K���鏀�����ł��Ă����B
- ��Ƃ���̍u�t�����ꂽ���Ƃɂ��ẮA�N�Ԏw���v��ɓ���Ď��{�������ƍl���Ă��邪�A�w�Z���Ɗ�Ƒ��Ƃ̎��Ԓ��������ɓ���̂Ŏ��{�ł��Ȃ��Ǝv���Ă���B
|
| �����k���� |
�q�u�`�r
- �K���X�Ƃ����Ă������Ȏ�ނ������ĂƂĂ��������납�����B
- �K���X�̌����͍��Ƃ����̂��A���߂Ēm�����B
- �K���X�������ƒf�M�ł���K���X���������̂ŁA�r�b�N�����܂����B
- ����Ȃ����M�Ɗۂ��傫�ȓS�̋ʂ��K���X�ɗ��Ƃ����̂̓r�b�N�������I
- �Ȏ����E�ȃG�l���M�[�E�b�n�Q�̍팸�A�R�q�i���f���[�X�E�����[�X�E���T�C�N���j�̐��i�A�S�~���o���Ȃ��悤�ɂ���B���ɁA�u�S�~���o���Ȃ��v�悤�ɋC������I
�q�M���}������r
- �e�N�j�b�N��莩���ōŏ�����Ō�܂ł���Ƃ����S������Ƃ������Ƃ��킩�����B
- ������Ƃ����g�̎���ɂ���K���X�ŁA�����ȁA���������̂������Ƃ킩�������ƁB
- �K���X�ɂ́A�_�C�������h�ŊȒP�ɃL�Y�������Ƃ��킩�����B
- �v���Y���̔��˂��ʔ����B�M���}�����肪�ł���悤�ɂȂ����B
- �M���}������̃f�U�C����A������A�K���X�ɂ͊y���ݕ����������邱�ƃK���X�H�|�̂������낢�Ƃ���B
- ���i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ȃK���X�ł��A���͎g�������������邱�ƁB
|
| ������W�̗��ꂩ�� |
- �K���X�Ɗ��Ƃ����ڌ��т��C���[�W�͒ʏ펝���ɂ������Ǝv���܂����A�u�s�q�A�u�t�̐����ł�����x�̗����͂ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- �K���X�т�̉���Ȃǂɓw�߂�Ί��ɂ��ǂ��Ƃ������Ƃ��A���k�����͔F�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ȏ�ɐ��ʂ������邽�߂ɂ́A���퐶���̒��ł̃��T�C�N���i�S�~�̕��ʂƓ��l�ɂт�K���X�����܂Ŏ̂ĂĂ������̂����T�C�N���ɏo���悤�ɂ���Ȃǁj���s���Ă������ƁB
- �F�m�I�ڕW�ɑ��āA�̌��A������ʂ��Ĉ�ۂÂ����Ǝv���B�𑝂₹����Ȃ��ǂ��B
|


|