 |
 |
||||||
 |
 |
 |
 |
||||
第11回:わかば賞
 |
自然だ〜い好き千葉県 柏市立酒井根小学校 3年 |
 |
|---|

児童の素材をそのまま見ることができるので、子どもたちの興味のポイントが良く分かります。次のステップは、調べたことや興味のわいた事柄を人に伝える工夫に磨きを掛ければ、さらに良いものに発展するでしょう。
受賞者の声
「記事を書くということが初めてだったので最初は面倒くさかったけど(笑)、だんだん楽しくなってきました。大変だったのは蝶の性格や食べ物などを調べたこと。だけど実際に蝶を飼ってみたことは大きかったです。実際3カ月間しかやってなかったので、3年生で勉強したことを今度は4年生で生かしたいと思います。もっと色々な種類の蝶を飼ってみたいな」(生徒たち談)。
「107人ほどいる生徒たちが全員、蝶を一匹ずつ持ち帰って育てました。目の前で羽化の瞬間を見たりなど、勉強になったのでは」(西林千津加先生談)
 |
田井小学校 ホームページ茨城県 つくば市立田井小学校 |
 |
|---|

地域への情報、地域からの情報発信がバランスよく組み込まれ、自然の豊かな地域の様子がよく伝わる学校のホームページです。今後は、足跡を残せる作品づくりに期待します。
受賞者の声
「泥の中に手をつっこんで田植えをしたり、ひこばえの観察をしたり…たくさんの自然と触れ合えて楽しかった」(代表児童談)
「ホームページでは授業の内容を紹介しているので子どもたち自身、受賞の実感があまりないようです。来年はぜひ自分たちで企画したテーマで頑張ってここに来よう!今回はそんな目的意識を持てたのではないかと思います」(中村泰先生談)
 |
わくチャレ2004高知県 須崎市立須崎小学校 5年生 |
 |
|---|
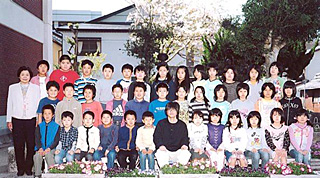
地域で展開される仕事を通して、その街の特色や様子をうかがうことができます。毎年、調べたことを受け継ぎながら、着々と進化しています。体験を通して、地域の活性化につながる活動を期待します。
受賞者の声
「高知県からですし、生徒たちは40人近くいるので今日の授賞式は一人で来させてもらいましたが、受賞の報告は帰ったらすぐに。“わかば賞”は一度しかもらえない新人賞に当たるような賞だと思いますので、いただけて嬉しいです。ありがとうございます。生徒たちが町で働くという体験学習は毎年5・6年生が行っておりますが、来年のホームページ作りは今年と違う形のものをと考えております」(松坂正夫先生談)
 |
トリビア in 登米宮城県 仙台市立郡山中学校 第1学年 |
 |
|---|

ブログの特性を活かした興味ある作品です。意見交換ができるようになっており、とてもライブ感のある内容になっています。作品を生み出すプロセスでこの点の活用をもう一歩進めれば、より見やすい作品に進化するでしょう。
受賞者の声
「郷土の誇れる文化財を調査するなかで驚いたことの一つに、建物の構造が挙げられます。例えば旧登米高等尋常小学校は現在教育資料館になっていますが、地震・災害に対する耐久力にとても優れているんです。作品のなかで一番工夫した点は“トリビア”として最後の見せ場でもあるまとめ方。印象に残る言葉選びをテーマにビシッと決めたつもりです」(大沼良介先生談)


